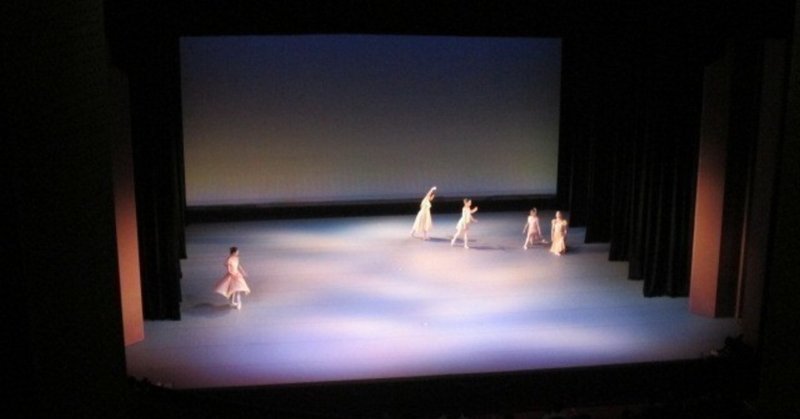
厳しい指導には先にやる気スイッチを押すことが大切
学芸会は無事に終わったが・・・
小学4年生ボイ実と小学1年生シー子の学芸会が
無事に終わりました!!
ボイ美は本番の出来に不満を持っているようですが、
シー子は会場の笑いも取れたので満足しているようです。
しかし、どうしても引っかかることがあります。
それは、先生のコンセプトと指導方法です。
noteでも書いたのですが、まずオーディションが尖っていました。
この時は、熱心な先生!
それに今の時代がアウトプットが必要
だと問題なく感じていました。
しかし、演劇の練習が進むにつれ、問題が見えてきました。
児童劇団のような舞台にしたいという先生の想い
先生の想いは、
「目標は児童劇団並の舞台にしたい!」
この目標のため、先生からは厳しい叱咤が生徒たちに飛んだようです。
しかし、ここは、「学校」です。
演劇をやりたい、得意な子もいれば、人前で何かをすることが苦手な子もいます。
一方、児童劇団は、やる気にみなぎった子どもたちの集団です。
案の定、人前で何かをすることが苦手な子達は先生の叱咤に耐えきれず
学校に行きたくないと漏らす子もいたそうです。
学校の行事ですから、子どもたちがそう思ってしまうのは
非常に残念です。
私なりに、どういった指導が良かったのか考えてみました。
やる気スイッチを押してからの厳しい指導が大切
「厳しい指導」
これは先生に限らず、親もやりがちです。
「なんでできないんだ」
「やる気ないなら、習い事辞めちゃいな」
「お前に奥義は教えられない、出て行け」
このような厳しい指導を行う場合は、
厳しい指導に心が耐えられるよう
最初の段階でやる気スイッチをポチッとな、することが大切です。
また、きちんと「どうやったら出来るか?」という技術面も教えることも大切です。
今回の先生の指導の中には「声が小さい!」
という事を多くの生徒が言われてそうです。
しかし、腹式呼吸など発声法についての指導は皆無だったと。。
左足の踏み込みを教えてもらわずに
天翔龍閃を打て!
と言われているようなものです。
やる気スイッチを自分で押す場合もある
ピアノのコンクールに出たい!
という目標を自ら掲げたシー子の場合は、
自分でやる気スイッチを押しました。
(またに親が再度スイッチを押しますが・・・)
この場合は、厳しい指導を受けても
モチベーションが下がりません。
何度か先生との個別レッスンを見ていますが、
先生の圧力は、すごく・・・
私なら10分後には泣いているかもしれません。
今回の学芸会にしても、
なぜ、この劇をやるのか?
みんなで演劇をやる事で得られるものは何か?
ゴール設定を行うなどモチベーションUPの事前準備が必要だったと思います。
年齢を重ねてくると、「指導」という場面に出会します。
その際に、厳しい指導をしてしまいそうな時は、
ふと立ち止まり、相手のやる気スイッチは押されているのか?
先にやる気スイッチを押した方がいいのかもしれないと
考えてみてはいかがでしょうか?
サポートして頂けると嬉しいです。 毎日の音声発信の励みになります!
