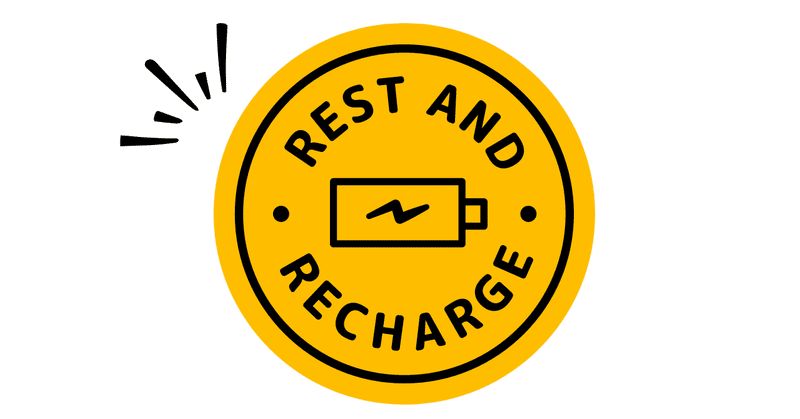
攻めの休養
昨日、書店で見つけて買った「休養学」という本。
内容が気になり、昨日と今日で読破。
冒頭にあった日本人の8割は疲れている!というアンケート結果に少し驚いた。
ただ冷静に考えると、いかにも日本人らしいな…とも思う。
ストレスは適度に、腹八分目が良い、生活リズムを整えよう、朝に日光を浴びよう…といったことは、これまでにもきいたことがあったので割愛。
本書の中で、新たな学びとなったのが「休養」の種類について。
休養と聞くと、「寝ること・体を休めること」というイメージが強い。
これらは筆者にいわせると守りの休養。
しかし休養には、「体を動かすことや外出すること」も含まれる。
これらは、攻めの休養である筆者はいう。
本書によると、休養は大きく3つに分けることができる。
①生理的休養(休息・運動・栄養)
②心理的休養(親交・娯楽・造形/想像)
③社会的休養(転換)*周りの環境を変えること。
ここでポイントなのが、どんな休養であっても、自らの意思で選択して行うべきだということ。
例えば、運動嫌いな人が、休日に無理やり先輩にランニングに付き合わされても、これは休息にならない。むしろ疲労がたまる。自ら「今日は体を動かすぞ」という思いをもって運動を行うことで、リフレッシュできたり達成感を味わえたりする。これは心理的な部分が大きく作用しているといえる。
この休養の概念は、自身のことだけでなく学校や家庭でも活用できそう。
例えば、学校の休み時間。みんなでドッジボールを行うとなった時、それが楽しいと思う人もいれば、そうでない人もいる。だから、みんな遊びは希望制にしたり、中と外の遊びを交互に行ったりするなど、いろいろな工夫が考えられる。
他に例として挙げられるのは、まさに今の自分の状況。
2人目が生まれて、10年ほど続けていた週1回のフットサルに行けなくなってしまった。これは自分にとって、中々の大きな出来事。
このフットサルは地元の友だちや職場の後輩と一緒にやっているので、生理的休養(運動)だけでなく、心理的休養(親交・娯楽)であり、場所もいつもと異なるので社会的休養(転換)でもある。つまりパーフェクトなのである。
はあ…やっぱり行きたいなフットサル…
妻にどう伝えたら実現できるかな…
これは今の自分にとって最重要課題。
今回の学びONEスライド

