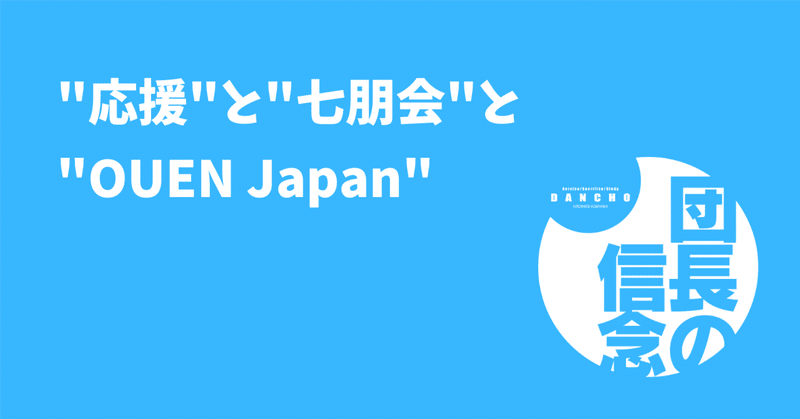
"応援"と"七朋会"と"OUEN Japan"
人生71年間を振り返る時、私の人生は、"応援"という言葉がキーワードであったと思う。
[応援]
1.味方となって励まし、また、助けること。また、その者。加勢。
2.競技などで、拍手をし、歌をうたい、声をかけるなどして、味方やひいきの選手を元気づけること。
[たすける]
助ける/扶ける/援ける/佐ける
1.力を貸して、危険な状態から逃れさせる。救助する。
2.経済的に困っている人などに金品を与えて苦しみ・負担を軽くする。救済する。
3.不十分なところを補い、物事がうまく運ぶように手助けする。助力する。補佐する。
4.ある働きがより好ましい状態になるようにする。促進させる。促す。
5.倒れたり傾きそうになるのを支える。
私が"応援"に関わったのは高校時代が最初だ。
私が、通っていた金沢大学附属高校は戦後創設された金沢大学教育学部の附属高校だが、旧制第四高校の流れを汲んでいたところがある。
毎年夏には校庭でファイヤーストームが開催された。ファイヤーストームは、全学年が火を囲み、旧制高校の寮歌(主にナンバースクールの寮歌)を肩組みながら歌うイベントだ。そのため、5月頃から、昼休みに校舎の屋上で3年生を中心に寮歌の指導があった(そんなことで、私はほとんどのナンバースクールの寮歌を覚えた)。
また、毎年、名古屋大学附属高校との定期戦があった。金沢と名古屋で交互にさまざまなスポーツの対抗戦だ。
私が2年生の時は、名古屋だったが、応援団を急拵えして、『南下軍』と称して名古屋に南下した。旧制第四高校に『南下軍』という寮歌がある。この寮歌は第四高校寮歌『北の都に秋たけて』と並び称される第四高校の代表的な寮歌だ。その歌を応援団の連中と歌いながら、金沢から名古屋まで特急しらさぎで南下したことを覚えている。
そんな青い経験があって、東京大学に入学して応援部に入部した(と言っても2年生からの途中入部だ。それまではボディビル&ウェイトリフティング部に入っていた。私はウェイトリフティングがメインだったが、クラブ活動はボディビルの先輩たちと一緒にする。
彼らはオタクの人たちが多く、それぞれの肉体美を極めるというので相当ストイックな生活をしていた。
私が練習のあと、「先輩、一杯飲みに行きましょうか」と誘っても、「せっかく鍛えた体の線が崩れる」と言って、冷たく断られるのが日常茶飯事だった。私は田舎っぺで人恋しいところがあり、この部は私には似合わないと常々思っていた。
そんな時に、応援部でリーダーとブラスバンドが分裂する騒ぎがあって、応援部が潰れる寸前という話が朝日新聞地方版に載った。それを見て、それでは"昔取った杵柄"でもあるし、ここは"男気を出して"、応援部の門を叩いたのだ。
東大応援部は、男の世界だった。義理と人情の塊だった。
先輩たちも応援部を何とか元の隆盛な部に戻したいと、必死に応援してくださった。お酒もたっぷりご馳走になることは頻りだ。
私はそんな応援部にドップリと浸かって、3年間を過ごした。そこで学んだことは授業の比ではない(ただ、私は勉強をしなかっただけのことだが)。
応援とは何か。
選手を応援する。援けに応える。応援でゲームを勝たせる。
ことあるごとに後輩たちと飲みながら、「応援とは何か」、「応援で野球を勝たせることができるのか」、「点差が開いて勝つ見込みがないような試合でも、何で『勝つぞ、勝つぞ、東大」と叫ぶのか」、「応援にどんな意味があるのか」等々、"応援の哲学的議論"を戦わせたものだ。そして、そんな議論が私の生きるベースになった。
東京六大学や国立七大学の応援団の連中とも親しく交流をした。
その時感じたことは、東京六大学応援団はサラリーマンで背広をきているが、国立七大学応援団は帰宅して普段着に着替えた付き合いということだ。
その時からずっと思っている。
応援とは心だ。思い遣りだと。その心は背広ではない。普段着の中にこそ、その心はあるんだと。
そんなことで、私はアットホームな国立七大学に惹かれているのだろうと思う。
[七朋会]には、そんな想いがある。心だ、思い遣りだ、論語の恕の心だ。それが国立七大学応援団にはある。その想いをずっと一生持ち続けていきたいと思う。
そんな想いを持って、[七朋会] のホームページをつくっていきたいと思う。
稲盛和夫さんから多くのことを学んだ。それは、思い遣り、恕の心、仲間を大切にすること、一人でできることは限られている。信頼できる仲間とともに、夢を追いかけて、夢を実現することだと。
それは私に言わせれば、まさに"応援"なのだ。"応援"が私の生きていく原点だ。
[七朋会]で心を若く保ち、心を清め、そして、[OUEN Japan]で、私の夢を実現させるのだ。
私は生涯に亙り、恕の心を持って、人のために、世のために、尽くしていきたいと思う。
不動院重陽博愛居士
(俗名 小林 博重)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
