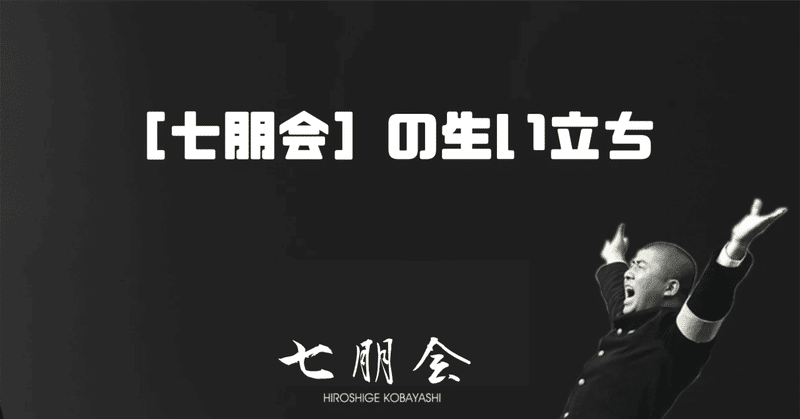
[七朋会]の生い立ち
[七朋会]は、昭和50年3月に卒団(部)した私たち国立七大学応援団(部)のOBたちの同期会から始まった。
国立七大学とは、北海道大学・東北大学・東京大学・名古屋大学・京都大学・大阪大学・九州大学の7つの旧帝国大学だ。
神田神保町にある学士会館は、一般社団法人学士会が運営しており、学士会はこの七大学のOB・OGの有志が会員だ。
理事長は東京大学教授、理事は七大学の元総長や元事務次官が就任されている。
日本の野球は、旧制第一高校から始まった。大学では早慶戦が有名だ。その早慶戦から拡がって、東京六大学野球連盟ができた。そのメンバーは、早稲田大学・慶應義塾大学・明治大学・法政大学・立教大学・東京大学の6大学だ。
応援団(部)も野球の応援からスタートしたようだが、連盟は、昭和22年(1947年)、東京大学応援部が創設されたと同時に創設された。
そのようなことで、東京六大学応援団連盟は今年(2023年)で76年の歴史がある。
私たち国立七大学応援団(部)の同期は、東京六大学応援団連盟のような連盟をつくりたかった。
昭和48年の暮だったろうか、私たち同期が幹部になる直前の冬に京都で集まった時に、そんな話が出たように思う。
しかし、東京六大学応援団連盟のように明治神宮球場という大学野球のメッカがあるわけでもない。
ただ、毎年、"国立七大戦"と称して、各運動部がバラバラに試合をして、それを総合体育大会と命名している、そんなに求心力がある大会とは言えないイベントを核にして、果たして"国立七大学応援団連盟"をつくることがどんな意味があるのかという意見が出て話は終わってしまった。
それもそうだ。応援団は毎年夏の1週間、その年の主管校の都市に集まり、ちょうどその時にしているさまざまな試合を応援するだけで、満遍なく応援するわけではない。
どちらかと言えば、応援団員たちの交流が目的と言ってもいい(そんなことで、私たち同期は仲良くなったのだ)。
結局、国立七大学応援団連盟は話だけになってしまったが、「同期会はずっと続けていきたいね」と言うことで、たしか東北大学団長の木島明博君だったろう。彼が、"七つの大学の朋友たち"と言うことで、私たち同期の会を"七朋会"と名付けたのだ。
それが、私たちが天命を知る"知命"の歳(五十路)に、誰彼となく、「七朋会をやりたいものだ」と言って、12月に青山表参道のビルの屋上で、4大学(北大、東北大、東大、京大)の仲間が集まって忘年会を開催した。卒業以来、30年近くが経っている。これが第1回の[七朋会]だった。10人前後だったか、私たち同期だけではなく、1〜2年後輩たちも集まってくれた。
それが、7大学に拡がり、年代も後輩たちにも拡がり、先輩たちにも声かけして集まってもらって開催してきた。
会場は、新宿だったり、神田神保町の学士会館だったり。ここのところは東大駒場の生協食堂になった。東大駒場での開催は、10年くらい前からだろうか。
何だかんだいって、20年続いている。
たった年に1週間しか会っていない応援団の同期たちの同期会が20年続いているのだ。それが先輩後輩に拡がっている。
私は幹事長ということもあり、OUEN Japan という応援の本質を追求(追究)するNPOの団長ということもあり、OUEN Japan の仲間たち(朋友、心友)にも集まってもらって、青春の息吹を思い起こし、後半人生を青春の心意気で生きていく、その起点として、"七朋会"を考えている。
しかし、私たちの生命は有限である。人生100年時代といっても、私は後29年だ。29年もあるとも言えるが、29年しかないとも言える。
応援の思いを持った友情が永遠に続いていってほしい。それは私にとって、[OUEN Japan]であり、[七朋会]なのだ。
そんなことで、私たち一代に終わることなく、七朋会を少しでも組織的に変化させていきたいと思っている。アウフヘーベンするということだ。
そんな思いがあって、七朋会の銀行口座をつくろうと思った。その顛末はこの次に書くことにしよう。
不動院重陽博愛居士
(俗名 小林 博重)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
