
【二輪の景色-21】適合者。
健康、意欲、ヘルメット。意志に、工具に、見た目のよさも不可欠かな。魂が宿っていなけりゃただのガラクタ。青天、命、そしてノスタルジー。十全でなければだめなんだ。
ひとつでも欠けたら乗る資格を失くしてしまう。孤独で孤立で自律がなければ、オートバイには乗れないんだよ。だから貴女に。
もし仮に非適応者の烙印押されてしまったら、乗合バスにでも乗ればいいのさ。ロングシートに手すり付き。乗り心地はふかふかで、船のようにゆったり走る、同調圧力駆動のノアの方舟もどきに。
貴女に限って異体同心だなんてまやかしに幻惑されるとは思いませんが。
ーーなぜバイクに乗るの?
だって人は、最後はひとりに帰っていくものでしょう? だから。
ーー貴方ははどこにいくつもり?
そうね、だいたいね、胸騒ぎのする方向に。
ーー徒然なるまま、風に吹かれるまま?
ハンドルが人差し指を差す方角に。
ーーところで、これは何?
誓約書。乗ってきたオートバイを譲ります、という。契約書もセットでついている。登録用の書類も完備。オリジナルのキー2本付き。
ーー譲られたらいよいよ?
そう、貴女の番。飛行機雲に導かれて天に向かうのは子供ばかりではないのだよ。大人だって、尾を引く雲に乗って天国に昇る。ひとつの命が空に向かって地上を離れていったなら、引き継ぐ者は覚悟を決めなきゃならないよ。
緩和ケア病棟ーーそこは都心からほど近い森を持つホスピスだった。留鳥が終の住処をこしらえ、渡り鳥が小さな湖で四季のいずれかひとつを織りなしては旅立っていく。季節ごとに詩は音色を変え、森の楽譜は毎年粛々とめくられていく。新しく明けた季節に始まり、次に引き継ぐと終わっていく。繋がれた季節もまた、始まっては終わっていく。幕を閉じては開いていく演奏会のほんのひと区間、僕はそこで時間を過ごした。
遠い昔に誕生に祝服を受けた者も、そこでは葬送行進曲の風に担がれ逝く。
地球というレコードがまわり続ける限り演奏会から音がやむことはないけれど、演奏される1曲ごとの楽譜は終止符まで歌ったそばから閉じられていく。残像への健気な哀愁などどこ吹く風の顔で、粛々と、冷酷に。
曲と同じように、ひとりにひとつずつ託された物語は、起承転結の結までいくと終わるようにできている。これまでの人生で刻んできた脈拍も、最後の余韻を指揮者が引き出すと、羽ばたき続けた命は終焉に着地する。
●● ●● ●●
というわけで、私のところへやっってきたというわけなのよ、このバイク。と私。
で、どうするつもり? このバイク。と同僚。
これまでうちの車庫には普段使いの軽四輪しかなかった。ところが今は、あの日に引き継いだ趣味のオートバイが割り込んでいる。しばらくの間磨かれることはなかったはずなのに、そのオートバイはおろしたてのハンドタオルみたいに無垢でこざっぱりとした顔で輝いていた。
使ってなんぼの工業製品。されど、使われずに崇め奉られてきた工業製品でもある。そこに老いを感じなかったのは、魂という血液が注がれ、脈々と寡黙な躯体を生かし続けてきたからだ。
バイクを前にすると、雲に乗って旅立っていったあの人を感じた。病室でひとり逝ったあの孤独なバイク乗りのことを。
死は、覚悟しても覚悟しきれるものではない。レモンを知らない人にレモンを見せつけても口中に唾が溜まらないのと同じで、死を知らない人に死のなんたるかはわからない。いきなり死とは何かを哲学しても、レモンを知らない人が得体の知らない黄色い楕円の何かを口に押し込まれるほどに不気味で不安に思だけで、結局のところ解答に辿り着けず匙を投げ出すことになる。一度でも死んだことのある人がいたら訊いてみたい気もするけど、応えてくれる人が現れたら、それはそれで恐ろしい。死を教えてもらう前にきっと心臓が止まってしまうだろう。
入院してきたあの人のことをほんの少しだろうけど理解できる部分があった。死の覚悟は、命をヤスリで削るその初動みたいなものとあの人は言っていた。あの人は削られていく身に痛みを走らせ、体内を駆け巡る痛みを追うようにして手のひらを這わせていた。
その痛みに手を添えて、さすってあげたことがある。こんなことしかできないけど、と思いながらさすっていた。すると「楽になった」とあの人は言う。
私の手は死を追いやったり、消し去ったり、小さくしたりすることはできない。大事なところに、私の手は届かない。だからありがとうと言われても、ちっとも嬉しくなかった。
「そんなことはありませんよ」あの人は、私が口にしたかった本心を理解していた。「手を差し伸べようだなんて、土台無理なことは考えてもらわなくてもいいんです。あちらの世界に移る時は誰だってひとりなのですから。ひとりで死んでいくことが怖くないと言ったら嘘になりますが、ひとりぼっちの気がしないんです。逝く時はひとりですが、道中はひとりじゃなくなるような予感がするんです」
ひとりじゃなくなる?
末期になると、痛みは虫歯に針を刺すほど恣意的で冷酷になってくる。我慢しても痛みは執拗で、堅牢な城でもぎりぎりと穴を開けられ城壁を裂かれ、制圧されるようになってくる。少しでも楽になるようにモルヒネを投与するのだけれども、私はてっきりあの人が幻覚を見て不思議なことを口走ったのだと思った。死んだら「ひとりじゃなくなる」どころか「ひとり」として存在することさえできなくなる。
なのにあの人は「痛みは生きていることを証明する体から発せられる救難信号ですから」と言って、内心で気を遣う私を真正面から気遣ってくれた。そしてこんなことも言っていた。「私はイエス・キリストに帰っていくんです」と。
あの人はカトリックの信者だった。
私はキリスト教のことはよくわからない。だけど、もう何年も前にエフエム局で聞いたブラジルの神話のことはよく覚えていた。
それは、信者の男と神様が2人並んで海辺を歩いているシーンから始まる。どこに向かっているのかは語られていないのでわからない。ある時、男が立ち止まって振り返ると、砂浜の足跡がひとり分しかついていない箇所がある。男は驚きと落胆と怒りとで神様にくってかかった。「あなたはいつだって私のそばにいるとおっしゃっていたではないですか。なのに、神様、あなたは嘘をついた」。すると神様は静かにお答えになった。「あれは、あなたをおぶっていたからですよ」
あの人に寄り添う神様と重なる。
あの人は、彼岸で神様に出会うと信じて疑わない。そしてその神様こそが帰っていく場所ってことなのかもしれなかった。
んん?
宗教の神秘性は西洋医学に身を置く現実主義者の私にはよくわからないけど、終わりが無でなく続きが始まる転換点であるのなら、死の恐怖も和らぐだろうことは理解できる。信心が強ければ強いほど、死の恐怖は減っていくものなのかしら?
心残りがあるとあの人はずっと言い続けていた。乗り手を欠いたバイクへの未練だと言う。
「軟弱者だから、雨の日には乗ったことがないんです。一度だけ不慮の事故みたいに土砂降りにやられたことがありましてね。入道雲が上がってきたと思ったら、その直後に来たんです。高まった波が海岸手前で崩れて一面を飲み込む豪雨。高速道路を走行中だったので、逃げ場はありませんでした。パーキングエリアもサービスエリアも案内板さえ出てこない、高速道路上の僻地でした。あと1時間もすれば調布飛行場あたりまでのところを東に走っていたのです。あのあと、生きる気力を無くしました。大袈裟な言いまわしではなく、感覚的にはまさに現実で、どん底でした。
人間の社会で生きていると、不思議なもので、すべてが比較されてランクが決められてしまいます。腕のいい革職人の手による革質が不ぞろいな手作りバッグより、名のある均一に作られたバッグのほうがはるかに価値が高いとされているでしょう? 人の価値観はさまざまで、マイナーでも確かなものを選ぶ人も少数います。ですがこのようにしてマジョリティを形成するほうに人の気持ちの多くがなびいてしまいます。支持されればされるほど善とされ、比較されたものたちが質の階層に当てはめられていくのです。これがランクの構造です。
オートバイが濡れたくらいで死んでしまいたくなるなんて嘘だ、と揶揄することは簡単です。人はランクの呪縛からなかなか逃れられない生き物ですから。でも僕はあの時、世間が拘束したがるランクの縛りとは無縁のところにいました。
とにかく、バイクを濡らすなんて一生の恥とばかりに、自責の念の重圧に押しつぶされそうになっていました。悔しくって、辛くって」そう言ってあの人は人を深刻の淵まで連れて行っておきながら、悪戯っぽく両肩を上げてみせた。吸い込んでぱんぱんに張った肺から空気を抜くみたいにして。
ふだんは言葉を抜き出すみたいにして話すあの人が、あれだけ冗長に話したのは初めてのことだった。話し終えたあの人は、肩をすくめたあと、唇の横に寂しさを走らせた。ほんの一瞬のことだったけど、私はそれを見逃さなかった。他人には冗談ぽく話しても、理解の一線は越えられないことを暗示した寂しさだった。
でも私はその傷口のような一線が間近にあるのを感じた。その一線は私にもある。だからわかる。
これから死んでいく人が、死よりも重く、あるいは同等に受け止めたものが、他人から見れば他愛もないことだったことに、おかしくて笑みをこぼすところだったのだろうけど、私には笑えなかった。
生命力が轍にはまったみたいに一段階落ち込んだ時、「もらってもらえませんか」と声を振り絞るようにか細くあの人は言った。
もらってもらえませんかって、私はまだお嫁にもらわれてもいないし、娘だから誰かをもらえる立場でもありません、婿ならもらう余地は残されていますけど。何やら不穏なものを感じて、私は話をはぐらかした。
もちろん何を言いたいのか、わかってはいた。
オートバイの話をしているのだ。
だけど、そんなこと、できるわけがない。患者さんの持ち物。受け取れば、引き継がなければならなくなってしまうもの。しかも、念とも言い換えられる魂が込もった人様の大切な財産を。ましてやルールもモラルも、その行いは厳しく禁じている。
結局、きちゃったわけだと同僚が言った。
そうなんだよね。
あの人の残したオートバイは、看取った私に託された。私でなくてもいいものなのに、ほかの誰もが引き受けられるものではなかった。私がいちばん天国に昇ったあの人の近くにいる。だから、私が引き受けることになった。私はあの人から見て適合者だったのだと思う。
オートバイはエンジンに火を入れるたびに物語が始まっていく。あの人が言っていたことだ。終わっては次の物語へバトンが渡されていく。次は私だった。
私には荷が重すぎるお荷物だった。免許も持っていない私にどうしろと?
託されたオートバイに近づき、手にした鍵をキーシリンダーに差し込んでみた。キーは、待ちくたびれていたみたいに、意志をもってすっと右45度に回った。それから忠犬のようにクウンと甘え(燃料ポンプが甘えた声で目を覚まし)、メーターの針を凝った肩をほぐす腕のように右側いっぱいまで振り切って(準備は整ったよと言ってるみたい)、ぐるりと2眼の目玉の視線を整え(回転計も速度計も「さあていっちょやってみますか」と気合を入れたみたいにして)、火を入れろとそそのかしてくる。
エンジンのかけ方なら知っている。クルマ同様、セルボタンを押せばいい。クルマもバイクも構造的にはそう変わらないはずだから、きっと問題ないだろう。だがその前に、ギアが入っていないことを確かめなければならない。だけど……あれ? どうすればニュートラルがわかるの? クルマなら、ギアがNでニュートラル。観察すると、メーターの中でNのランプが緑色に光っていた。たぶんこれがニュートラルのしるし。合ってるかどうかはわからないけど、隣には教えてくれる人なんていなかったから、いっちょう試してみましょうか。
で、私はオートバイに寄り添ったまま、セルボタンを右手親指で押し込んでみた。
合っていますように。なむさん。
キュル、ばるん。
エンジンは、よくできたガスコンロのように一発で火を安定させた。
免許さえとっていないのに、バイクの始動問題は一発で解決した。
それでも、今さらバイク? バイク適齢期はとっくに過ぎているのに?
そりゃ、バイクには憧れはあったよ。助手席で横顔見つめるクルマより、うしろからぎゅっとしがみつくバイクに今でもどきどきするもの。乗っけてもらったことは一度もないけど、そんな夢のような時間がやってくればいいなとも思ってた。そういえば、事あるごとにオートバイのことを考えてきていた。
バイクと関わるのでも、私はてっきり後ろに乗る側の人だと思っていた。それなのにまさか自分が操る人になるとはねえ。とはいっても、免許はない。物理的に乗れる状況が整ったとはいえ、法律的には許されないことだった。
エンジンのかかったバイクにまたがってみた。足が、届かん。それに、車体のなんと重いこと。二輪は自転車しか知らないから、鉄の錘みたいなエンジンを積んだバイクは、とてつもなく重いものだということをこの時初めて知った。
アクセルを手前に絞り込むと、うねりがあがると同時に車体がぶばばんと弾けて沈み込んだ。
エンジンをかける前は大きな装飾品みたいな顔で澄ましていたくせに、いったんエンジンがかかると、まるで心臓でできた生き物みたいに躍動感をまき散らし始めた。
バイクに跨って走り出すところを想像してみた。車庫を出て、一路高速道路へ。縦横に走る高速網で向かう先は決まっていた。胸騒ぎのする方角へ。
アクセルを開ける。すると法定速度を振り切って、なおも先へ加速する。左右のバックミラーに映っていた車や景色が輪郭を無くし、水彩絵の具を垂らしたみたいに後ろへ流れていく。物も風景も空気さえ溶け合って、ミラーの中でひとつのマダラ模様を形成していった。
すごい。私は未知の景色に目を奪われた。
きっと夢のような時間に浸れるのだろうと思った。
描いた世界を瞼のシャッターを切り、胸に留めた。
そしてその瞬きは、同時に私を現実社会に引き戻した。
夢のような世界に連れて行ってくれるこいつは、心臓剥き出しの速いが無防備の博打のような乗り物だ。賭けるものはひとつだけでは済まなそうだ。
傍で見ていた時には感じなかったバイクに乗ることの恐怖が内蔵から滲み出してきた。乗車中にアクシデント遭えばたいへんなことになる。看取る者が看取られることになるなんて洒落にもならない。
●● ●● ●●
緩和ケアの最終章で思い出を受け取ることはあるけれど、まさか思い出の品を受け取ることになるとは思ってもみなかった。
くどいようだけど、バイクの免許はもっていない。今のところ。だけど。
エンジンをかけたままバイクを降りて、クルマの横でぶるぶる震えながら荒い息を弾ませているバイクをまじまじと見つめた。
バイクの免許、取らなくっちゃならないねえ。
留学も経験した。東京でOLもやった。冒険は飽きるまでしてきた。だからそろそろ落ち着きたかったのだけれど、神様はまだそれを許しちゃくれないってことなのかな。
しかたあるまい。
私は凝りと溜まった疲労で重くなった腰を、今一度上げる覚悟を決めた。
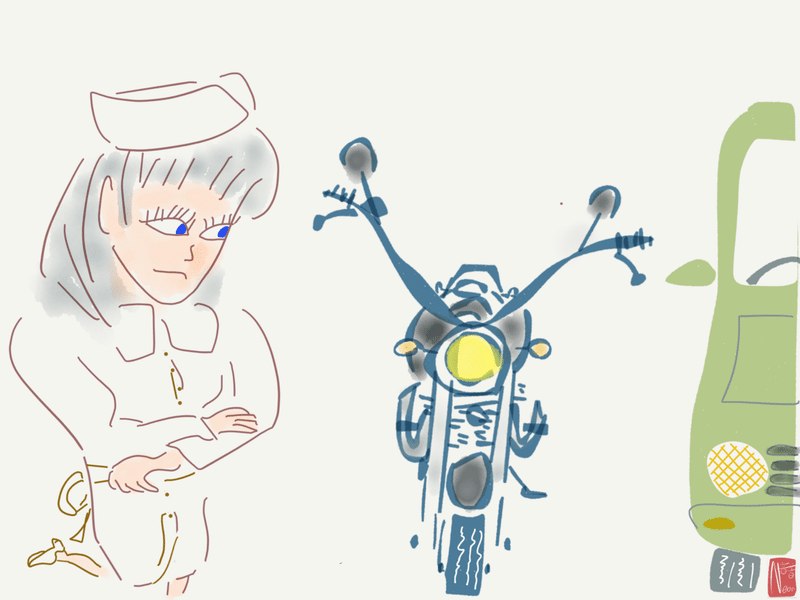
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
