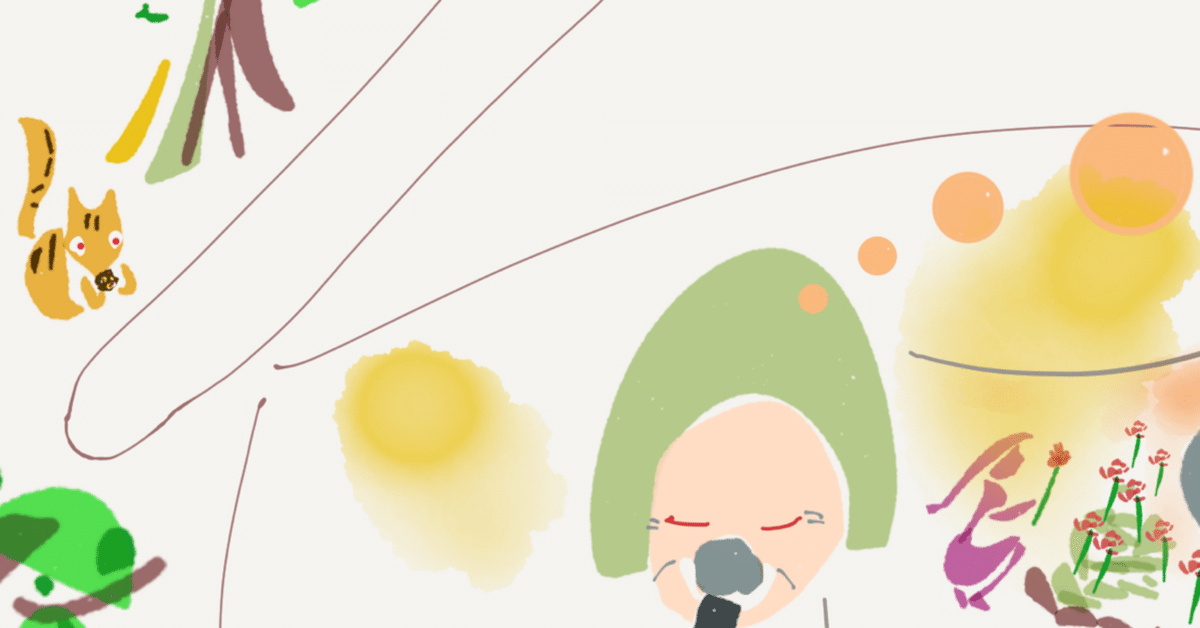
森の中のフォーク喫茶。
「下手なんじゃない。見せているんですよ」
そのフォーク喫茶は、集落を超えた森の中にあった。現代の建築なら防音に抜かりはないけど、どうやら騒音を問題にしているふうではなかった。音は開かれた窓から自由に行き来できる仕様だったし、木立の合間に設えた止まり木に気ままやってきては囀る飛び入りの掛け合いもウェルカムで、通りががりが門戸を叩くそちらの窓も開かれていた。
解き放ちの家。それがそのフォーク喫茶の名前だった。
その傾きから陽の光が入り込み始める間際の時間帯、窓辺の席で、一口サイズサンドウィッチを飽きもせず眺めては、思い出したようにひとつつまみ上げてグラスビールに口をつける。昼間のビールは苦い。その苦さに、サンドイッチの残り香が混じる。今のはドライトマトだったか。てんでトマトらしからぬ芳醇な味わいが、口中に入り込む苦味と戯れた。
マスターの立つカウンターの左手に、小さなステージがある。開かれた窓から光の粒子が満遍なく店内に入り込むのに、ステージだけが闇に浮かぶ宇宙基地のように時間感覚を夜に誘う。20人も入れば全席が埋まる小さな空間に、昼と夜という無限の塊が同居する雲を掴むような空間だった。
なるほど、この店は集落の中に在ってはいけない、そんな思いを確信させる説得力が店内に溢れている。
ステージでは、懐かしのフォークソングを年配のおばちゃんが歌っている。カラオケ店でなら聴くに堪えない音程の、声色の、出立ちの歌も、ここでは咎められることなく、聞き流されることなく、次の曲選びに余念をなくす客もなく、すべてが受け入れられる。どんなリクエストにも応えるギターの名手が必ず一人は客でいて、カラオケマシンの常備されていないステージを支えている。マスターに確かめた訳ではないけれど、この店はそういうシステムになっていることがぼんやりと理解できるのだった。
おばちゃんに歌は歌われている。うまくはない。客はまばらだが、どの目も歌うおばちゃんに注がれている。だけど、注いだ目の先にあるのはおばちゃんではない。おばちゃんの過ごしてきた、歌う歌が寄り添っていた時代のカケラの彼女のひとつのアーカイブ。
「下手なんじゃない。見せているんですよ」
おばちゃんが歌い始めようとする間際、マスターは確かにそう言ったのだった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
