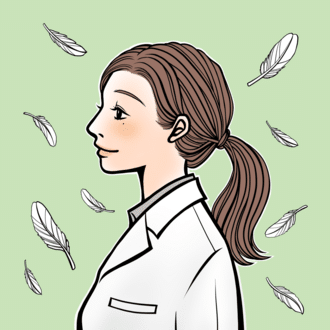SIADH患者におけるエンパグリフロジンの血漿Na濃度の上昇を目的とした無作為化試験
はじめに
今回の論文
今回の論文はSIADHの治療において、SGLT2阻害薬であるエンパグリフロジン(以後、Empa)が血漿Na濃度を上昇させる新たな治療の選択肢となり得るか検討した無作為化試験の論文です。
背景
SIADHでは抗利尿ホルモンの分泌過剰により尿濃縮能が亢進して持続的な水利尿不全が惹起される。原因としては中枢神経系や肺疾患、悪性腫瘍、薬剤、疼痛など多岐に渡る。有病率の高い疾患ではあるが、根本原因の治療以外のSIADHの治療オプションは限られ、推奨される水制限では成功しないことも多い。他の治療の選択肢であるバソプレシン受容体拮抗薬は高価なことやNaが過剰補正のリスク等を伴う。以上からSIADHに対するさらなる治療の選択肢が必要である。
SGLT2阻害薬であるEmpaは、尿中Glu排泄を介して浸透圧利尿を促進し、SIADHに対する新しい治療選択肢となる可能性がある。
目的
入院中の低Na血症患者において、標準的な水分制限に加え、SGLT2阻害剤(Empa)を4日間投与した場合、プラセボと比較して血漿Na濃度がより高くなるかどうかを検討した。
方法
試験デザイン
前向き二重盲検プラセボ対照無作為化試験
期間
2016年9月から2019年1月までスイスのバーゼル大学病院にて実施
対象
対象患者は18歳以上で、甲状腺機能低下症および低コルチゾール血症を除外し、循環血漿量正常、血漿浸透圧<275mmol/kg、尿浸透圧>100mmol/kg、尿Na>30mmol/Lで臨床的にSIADHと診断された低Na血症(<130 mmol/L)を有する患者。
●除外
・3% 食塩水による治療を必要とするような重度の低Na血症患者
・腎障害、肝障害のある患者
・収縮期血圧<90mmHg
・1型糖尿病
・SGLT2阻害剤、塩化リチウム、尿素で加療されている患者
・血圧低下に対する禁忌(くも膜下出血など)
・重度の免疫抑制患者
・末梢動脈疾患ステージ3または4
・妊娠または授乳
・終末期医療を受けている患者
要件を満たした患者(88名)を1:1の割合で無作為に割り付け、水分制限(1000 ml/24 h)に加えて、経口Empa(25 mg)またはプラセボを1日1回4日間投与。
評価項目
●主要評価項目
baselineから投与4日後の血漿Na濃度の絶対変化量
●副次的評価項目
・他の時点の血漿Na濃度(baselineから24h、48h、退院時、退院後30日までの絶対変化量、12hから4日までの曲線下面積[AUC])
・血漿および尿の尿素、尿酸、浸透圧(baselineから 4 日目までの絶対変化)
・Glu、尿中Na(AUC 12/24hから4 日間)
・体重(AUC 24hから4 日間)
・全身状態の変化
・低Na血症の症状(baselineから4日目、30 日間の変化)
結果
試験終了者87名(1名は誤診断により除外)のうち、43名(49%)にEmpa、44名(51%)にプラセボが投与された。baselineの血漿Na濃度は両群で同等であった(中央値:Empa群 125.5mmol/L、プラセボ群 126mmol/L)。
主評価項目
Empa投与群ではプラセボ投与群と比較して、血漿Na濃度の中央値が有意に上昇した(それぞれ10mmol/L vs 7mmol/L、P=0.04)。重度の低Na血症(125mmol/L)およびbaselineの浸透圧レベルが低いほど、Empaによる治療が奏効する可能性が高くなった。

(B) 血漿Na濃度のbaselineから治療終了までの絶対変化量

(D) 介入中の血漿Glu濃度の経過。(A,B) 表示された線は、それぞれの線形回帰線
副次的評価項目
Empa投与群では、
・尿浸透圧が大きく上昇、それに伴い尿中GluのAUCも顕著に増加
・血漿UA値および血漿UN値の上昇はわずか
・血漿GluのAUCが低下
尿中Na濃度および体重は群間差がなかった。
忍容性と安全性
Empa群において試験に影響する有害事象6件
・一時的な腎機能低下(最高Cre上限 2.5mg/dL) 4件
・Naの過剰補正(24h以内に15mmol/Lと17mmol/L) 2件
Empa群において低血糖及び低血圧の事象は発生せず
研究の限界
・SIADHの病因が2つの治療群間で不均等に分布していること
→病院によって治療への反応性が異なる可能性がある
・本施設における尿検査では自由水排泄量の計算ができない
→ただし尿中Na、UN、UAの排泄量からEmpa群で自由水排泄量が増加すると想定
・水分制限を行わない場合のEmpaの有効性や、外来での長期治療としての使用感や安全性については検討していない
入院中のSIADH患者において水分制限を行った場合、Empa投与群ではプラセボ投与群に比べ血漿Na値の上昇が大きかった。Empaの本疾患の治療薬としてのさらなる研究が必要。
結論・考察
入院中のSIADH患者において水分制限を行った場合、
Empa投与群ではプラセボ投与群に比べ血漿Na値の上昇が大きかった。
この治療効果は、治療前の血漿Na濃度および浸透圧レベルが低い患者においてより顕著であった。
バプタン製剤はコストや血漿Na過剰補正のリスクに関する懸念が複数の論文で示されており、その使用については議論が残る。
一方、Empaは確かにコストはかかるが、長期の心血管保護効果や腎保護効果が報告されている安全性プロファイルが確立されており、幅広く入手可能で、忍容性が良好であること、またNa過剰補正の報告についてはバプタン製剤が25%程度と報告されているのに対し、かなり頻度が低く、新たな治療の選択肢になり得るかもしれない。
My Comment
日常的に低Na血症患者さんを見ることが多いのですが、自分がこれまで診察してきた中で圧倒的にSIADHの患者さんが多く、治療も自分で調べたり上級医に聞いたりしますが、結局のところ、尿中のNa排泄量や尿酸値を見ながら「なんとなく」水分制限、効果乏しければ塩分負荷みたいな感じにやっていました。(3%食塩水は使用したことないです) そしていつもなんとなくよくなってしまうという…
今回なぜこの論文を選んだかといいますと、
外来で見ている糖尿病患者さんがSIADH(おそらく外傷性・ストレスによるものと判断)で入院された時に、いつも通り水分制限と塩分負荷で乗り切ろうとしたがうまくいかず…上司に相談した所、「糖尿病もあるしSGLT2阻害薬使ってみたら?」とこの論文をいただき、読むに至りました。
実際、糖尿病も治療しないといけなかったし、高齢の方ではありましたが、ADLも良好、体格もよかったためジャディアンスを導入。
その後、すっかり良くなりめでたしめでたし。(ついでに糖尿病も)
ただここで、SIADHになる高齢者というと痩せてて、ADL悪くて寝たきりみたいな人も多い印象で。そういう人にSGLT2阻害薬って廃用も進むし、UTI起こしそうだし、積極的には使いにくいなというところが本心ではあります。この時期だと脱水によるAKIとか正常血糖ケトアシとかのリスクもありますし、、なので個人的には高齢だとしてもある程度ADLが保たれて、体重もある方への使用ならば考えてもいいのかなと思います。
(が、なんせ専門医もないペーペーの話なので、もし間違ってるなどあれば教えてください…)
いいなと思ったら応援しよう!