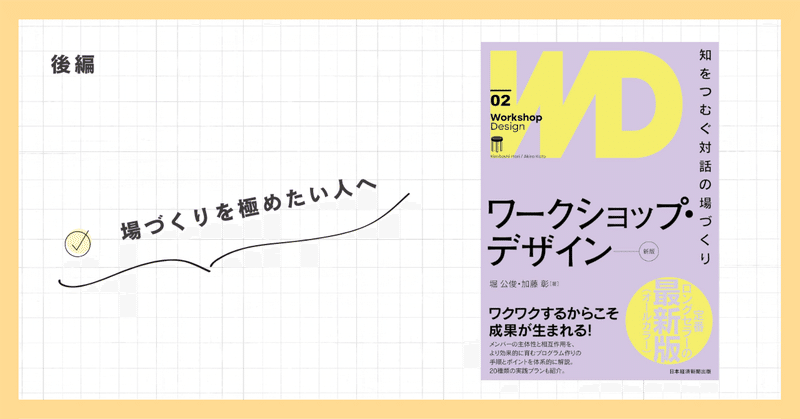
今日から使えるワークショップネタ25選
🙄「こんにちは、秋山です。
今日は、PBLを研究している方とお話ししたり、システムコーチングの説明会に行ったりと、組織開発まつりな日でした。最近、打ち手が人事制度や人材開発に偏りすぎていたなーと反省。会社は独立した個人ではなく、影響しあう個人の集まりだってことを今一度ちゃんと意識しないと、大きな変革は起こせませんね…まだまだ無力だ、非力だ、凡人だ。頑張ろうと思える日でした。
さあ気を取り直して、今日はワークショップデザインの後半です。いってみよーやってみよー!」
後編は、4つの章で構成されています。
第三章 技術編
第四章 実践編
第五章 研究編
第六章 熟達編
特に気づきが多かった、技術編(アクティビティを使いこなそう)と熟達編(ワークショップ・デザインの力を高める)に特化してまとめていこうと思います。
めちゃ使えるアクティビティ事例25選
アクティビティは目的に合わせて、5つに分類でき、ワークショップの序盤から終わりまで時系列で並んでいます。
①場を温める
②資源を引き出す
③話し合う
④つくりあげる
⑤分かち合う
🙄「それぞれのステップで、へー!こりゃしらなかったぜ!というものをご紹介してみます。」
①場を温める
財布の中身
財布の中から1つアイテムを取り出し、それに関連する自己紹介をする。自己開示が進んで良い方法。
借り物競走
オンラインで使える技。テーマを決めて、それにまつわるものを一人一個持ってきてもらい、一人づつ順番に紹介する。
私の取扱説明書
・商品説明:特技、強み、ウリ
・用途:こういう時での活用がおすすめ!
・上手な使い方:好ましい依頼の仕方・任され方、嬉しい褒め言葉、やる気の出る環境
・上手なお手入れ方法:いつも元気でいるためにしてほしいこと
・調子が悪くなると、こうなります
・これだけはしないで!
グループ名を決めよう
最初の共同作業としてグループ名を決める。メンバーの共通点や、めざしたい方向性を踏まえたものにすると良い。独断や多数決ではなく、コンセンサスを取ることが重要。
インプロ
グループで順番に、即興で物語を紡いでいく。
今日は暑いですね>夏ですもんね>夏といえば、そうめんですね>何事も水に流したいですね>流れるプールに行きたいですね
逆に、前の人が言ったことに引っ張られずに発言するパターンもある。頭を柔らかくしないとなかなかむずかしい。
②資源を引き出す
ワークショップの最良の素材=資源は、参加者の持つ経験、考え、思い、ワークショップでの経験です。いかにうまく引き出すかで、ワークショップの良し悪しが決まります。
人間マトリクス
体全体を使ったアンケート、自由に動き回れるスペースがある時に使う。会場に仮想の線を引き、賛成か反対かで分かれて立つ。近くになった人同士で、なぜその位置?と話し合うと、自然と話がはずむ。
手挙げアンケート
「〇〇についてどう思いますか?賛成はぐー、反対はちょき」ルールを決めて、意思表示をしてもらう。その後に意見や体験を引き出すと、簡単に資源が引き出せる。人間は一旦意思表示をしたら、それを貫こうとする一貫性の原意が働くため。
🙄「へーおもしろい!!同じ意見を聞き出すのでも、意思表示を挟むだけで、資源の引き出しやすさが変わるのか〜。ワークショップ奥が深いぜ。」
ペアインタビュー
テーマを提示し、2人ペアになって、一人がインタビューする側、もう一人がインタビューされる側になり、とことん語ってもらう。ストーリーテリングとも呼びます。インタビューした側はメモをとっておき、それに基づいて他のメンバーにストーリーを紹介する。意見に対する理解が双方深まると同時に、しっかり語れた・他人に聞いてもらえた、という感じが持てる。
🙄「これはLDC(通っていたリーダーシップについて学ぶ大学院)でめちゃめちゃやった!意見を聞いてもらえたって感じがするのはとてもよくわかる。聞いてもらえた相手のことを好きになるんだよな〜。もっと取り入れていこう。」
分解ゲーム
テーマを決めて、それを分解定義してもらうワーク。
たとえば、「コミュニケーション」というテーマを3つに分解してみる。「みる・聞く・話す」「伝える・納得・行動する」などなど。
ロールプレイ
特定の役割を演じるなかで、その人の体験を擬似体験するワーク。組織開発の流派の一つは演劇から始まっているので、納得のワーク。役割と設定を決めて、実際に演じてみる。その過程で感じたことを共有する。
フォトランゲージ
色々なものやシーンの写真を100-200枚集める。「今の組織の状態は?」「新サービスのイメージは?」といった問いかけに対して、写真を一枚選んで、なぜそれを選んだのか理由をシェアする。
ケーススタディ
有名なのがハーバード式のケースメソッド。実際におこったケースを素材に、事細かく情報提供された後に解決策を導くもの。対照的なのが、インシデント・プロセス。ごく簡単な出来事だけが提示され、参加者はファシリテーターに質問を通じて必要な情報を収集して、問題分析や解決策を立案していく方法。
🙄「インシデント・プロセス、問題解決スキルも高まりそうでとてもいいな。ちょっと謎解きみたいで楽しそう。」
③話し合う
引き出された個人の資源は、話し合いを通じて相互作用を起こしていきます。
ブレーンライティング
ブレストはそうしても特定の人に発言がよりがち。ゆっくり考えたい人もいる。そんなときは、ライティングするのがおすすめ。A4を準備して(オンラインだったらdoc)、上部にテーマを書く。テーマにそったアイディアを一人3つずつ書いていく。書き終わったら次の人に回す。次の人は、前の人のアイディアをベースに書く。無理に繋げる必要はなく、全く違う角度からでもOK。
アンチプロブレム
本来考えたいテーマとは正反対の極端なテーマを設定する。「どんな職場にしたいか?」にたいして「絶対に行きたくない、最悪な職場はどんなところか?」をブレストする。その後、理想である本来のテーマに戻る。正反対を考えてみることで、意外な目の付け所が潜んでいるのが深い。
アイディアチェックリスト
アイディアを強制的な切り口から出していく方法。
オズボーンのチェックリスト、SCAMPERと呼ばれる。
・変えたら?
・拡大したら?
・逆にしたら?
マンダラチャート
大谷翔平のあれ。9マスをかき、真ん中にテーマを書く。その周辺にテーマに関するアイディアを書いていく。文章でられるするよりも、アイディアが出やすい。

ワールドカフェ
大人数を4-5人のグループに分けて、オーナーをきめ、何度かグループをシャッフルするやり方。前のグループではどんな話をしたかをまず最初にはなし、そこからシェアを始める。最後に、最初のチームにもどって、どんな話をしたかを共有する。
大人数であっても、全体でどんな話がされていたのかを共有できる効率的な方法。
6つの帽子
ラテラルシンキングを、強制的に特定の視点から意見を出すことができる方法。帽子の色に応じて、どんな視点で参加するのかを変えていく。
・白:事実と情報のみをみる
・赤:感情的にみる
・黒:マイナスの側面を見る
・黄色:プラスの側面を見る
・緑:独創的な視点で見る
・青:戦略を組み立てる

ロールプレイやディベートと組み合わせる、特定の帽子どうしを戦わせるなんてやり方もある。帽子の色や視点はこれに限らずOK。
リーダーズ・インテグレーション
チームの中で、リーダーとメンバーの相互理解を深めたい時に有効な方法。まずはリーダーにチームをどうしたいと思うのかを語ってもらう。リーダーには退出してもらい、メンバーだけで以下を話す。
・リーダーについて知っていること
・リーダーについて知らないこと
・リーダーに、知っておいて欲しいこと、期待すること
・リーダーに対して貢献できること
おわったら、リーダーは戻ってきて、上の内容を聞き、必要なところは答えつつメンバーと意見を交わす。
④つくりあげる
ワークショップも後半、広げたり深めたりしたアイディアをアウトプットして形にしていく。
フォースフィールド
現在のポジションを中心に一本の線を引いて、目標の線を右に引く。現状を目標に推進する力と、阻止する力を書く。それぞれの影響力に応じて、太さや長さを変える。

最後にチャートを見ながら、それぞれの力をどうコントロールするのかを決める。
セブンクロス
縦横に7マスずつ描き、49のアイディアを並べる。重要な

⑤分かち合う
ワークショップの最後では、成果を分かち合い、振り返ることが大切。
バザール型
プレゼン型だと興味のないものまで聞かないとならないの。ポスターセッション型にして、聞きたいところだけつまみ食いする方法。もっと手軽なのが、回遊型。成果物をその場に残したまま、回遊して他のグループの成果物を眺めていく。
2→4→8→16
結論を出す必要がある時に有効。何に結論を出して欲しいのかを告げた後、まずペアになって話し合い、2人の結論を紙に書く。次に2つのペアが合流し4人になり、結論を共有し、さらに話し合い4人での結論を紙に書く。それをくりかえし、8人16人とふやしていく。16人になったところで、全体に各チームの結論を共有してもらう。
立ち上がって歩いたり、話あったりするので、場の一体感がでるし、活性化が進むやり方。
2ストライク3ボール
活動自体の振り返りでは、お互いのネガティブな意見を出しにくい。そこで活用できるのがこれ。数を決めておく、先にいいところを共有する、悪いところではなく改善点を。というのがミソ。I like I wish、プラスとデルタなどにた手法がある。
改善点だけを抽出するときは、悪魔の批判者という方法もある。険悪にならないように、ゲーム感覚でやるのが良い。
友人への手紙
ネガティブな意見を遠慮なく出すために、手紙にして渡すという方法もある。
・ワークショップの中で、相手に対してどんな印象をもったか
・どんな点がよかったか
・もっと頑張って欲しい点は
・その他気づいたこと
プログラムを引き立てる隠し味
同じ系統のアクティビティが続くと、人間飽きるもの。集中力を保つためにも、緩急つける・幅を持たせることが必要です。最後のプログラムのチェックリストとしても活用できそう。
成果志向<>関係性志向
短時間にアウトプットを生み出そうとすると、成果を目的としたアクティビティになりがち。関係性にも目を向けよう。
プッシュ<>プル
プッシュとは、20分に50個のアイディアを出すなど、追い込んだり、競争するワーク。盛り上がるけど、疲れる。それに対してプルとは、しばらく隣の人と雑談しましょう、など自然の動きにまかせる、湧いて出るのを待つアクティビティ。
発散<>収束
片方に偏ると、盛り上がりに欠けたり、成果にかけたりする。バランスが大事。
構成的<>非構成的
メンバーのコントロールの使い分け。オープニングは非構成的なワークで緩めにはじめて、場があったまるのを待つ。議論に火が付いたら、構成的なアクティビティで一気に結論までもっていく。
頭<>身体
頭ばっかりつかうと、疲れてきます。動きのある活動や五感を使うのも大切です。
抽象的<>具体的
テーマには「我々の使命は?」などの大所高所に立ったマクロのものと、「現場での一番の悩みは?」といったミクロのものがある。両方を行き来することで、問題を立体的に捉えることができる。
さらにテーマを分解すると、正誤問題、功利的(損得)問題、規範的(善悪)問題、情緒的(好悪)問題がある。同じものが続くと食傷気味になるので、注意。
理論<>感情
ワークには、事実や情報を元にロジカルに考える論理的なものと、直感や自分の気持ちに向き合うものがある。
活動<>振り返り
アクティビティが続くと流れ作業のようになってしまう。適度な振り返りを入れることで、思考や活動に深みが出てくる。
グループサイズ
最初から最後まで同じ顔ぶれだと飽きる。
場
同じレイアウトや場所だと飽きる。転換点を仕込んでおくと良い。
テーマを練り上げる
問いは、思考と行動の起爆剤。いい問いは、以下の変化を引き起こす。
みんなが、おお!と前のめりになるテーマ・問いを考えよう。
・好奇心や創造性を沸き起こす
・内省的な対話を引き起こす
・隠れていた、触れてなかった前提を引きずり出す
・エネルギーと前向きな行動をうむ
・さらなる問いを喚起する
・組織の中に問いが伝播して、みんなの動きにつながる
🙄「ここは、ファシリテーターの腕の見せ所って感じなんだろうな」
問いを磨く6つのポイント
①型:問いの形
- yes/no:今の仕事に満足していますか?
- which:一番満足したのは、どの仕事のときですか?
- what:一番満足した経験は、なんですか?
-why:それはなぜですか?
上の方が答えやすいので、口火を切るのに適しており、下に行くほど深く考えさせる問い。
②範囲:問いが扱う範囲
・当社は何をすべきか
・事業部はどうすべきか
・チームはどうすべきか
・一年後どうすべきか
・明日どうしたらいいか
③方向性:問題探索と可能性探索
問題探索とは、〇〇を引き起こしている原因はなにか?可能性探索とは、〇〇の中でどんな機会を見出せるか?
失敗や欠損よりも、成功や強みにフォーカスする方が、人間行動につながりやすい。
④階層:目的回帰か、手段創出か
目的に立ち返るか、手段を生み出すか、思考の階層を変える。手段に走り、目的を踏み外しそうになった時、目的回帰は有効。
・これで本当にお客様は喜ぶのか?
・なぜ〇〇するのか?
⑤跳躍:前提の破壊度合い
・〇〇の他に何があるか?
・これをしてて、本当に価値があるのか?
・もし〇〇がなかったら、何ができるか?
・緊張感に満ちていても居心地がいい職場とは、どんな場所か?
現状の常識にとどまっていては答えられないような問いが、大きな変革を引き起こす。
⑥置き換え:ちょっとした言葉の言い換え
「仕事をしていて不満に思うこと」>「仕事をしていて悲しいこと」
「我々の今後のあるべき姿は?」>「どんな会社になっていて欲しいと思うか?」
単語や助詞を意識的に使い分けると、発言のしやすさが変わってくる。
個人的感想
面白すぎて、サマリーと言えない長さになってしまった。
明日から使えるワークがてんこ盛り。さらに、考え方のベースが丁寧に構造化されていて、ワークショップを社内で実施する人は必見な一冊。
ワークショップって奥が深いな〜
人材開発と組織開発、両方をブレンドして行えるとても価値のたかい手法だし、やってて楽しいって正義だよな
秋山のワークショップに参加すると、チームにスイッチがはいる、と言われるようになりたいな。
以上!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
