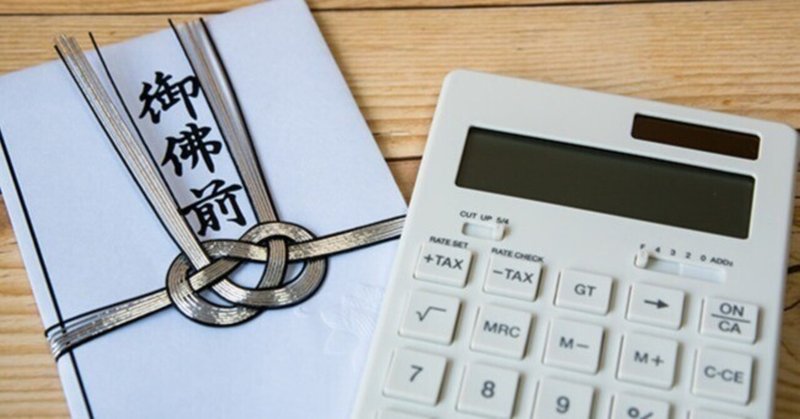
家族葬で香典を送る上で知っておきたい香典の相場
<こんな人におすすめ>
・まずは家族葬で香典を用意すべきケースを知りたい方
・家族葬における香典の相場を知りたい方
・香典の相場で分からないことがあった場合の対応を知りたい方
親戚や近しい友人が他界し、家族葬で送り出すこととなったものの香典の相場がよくわからないという人もいるのではないでしょうか。一般葬だけでなく家族葬でも香典で包む額を知っておけば、突然の訃報に慌てることなくすぐに準備ができます。
そこでこの記事では家族葬で香典を送るときの相場についてご紹介します。そのほかに香典額を相談できる場所や香典に関する豆知識についても触れますので、いざというときにすぐに対応できるよう、事前に知識を身に着けておきましょう。
葬儀をお急ぎの方は「0120-215-618」までお電話ください。


まずは家族葬で香典を用意すべきケースを理解しよう
葬式の知らせが届いて、準備をするうえで頭に浮かぶのは香典のことではないでしょうか。ケースによっては香典を用意しなくても良いこともあるため、まずはどんなケースで必要かを知っておきましょう。ここでは香典が必要なケースと不要なケースについて解説していきます。
家族葬の案内を受けた場合は香典の用意が必要
近しい人が亡くなり、家族葬を行うとの知らせを受けたときは香典を用意する必要があります。届いた葬儀の知らせで葬儀の日程と場所を確認し、それまでに用意しておきましょう。
葬儀の知らせのとき、香典の辞退を申し出る人もいます。受け取らないと言われると用意すべきかどうか迷ってしまうところですが、念のため香典を持参しましょう。ほかの参列者が渡しているかどうかを見て、渡すか渡さないのかを判断をすることがおすすめです。
家族葬の案内を受けていない場合は香典の用意が不要
家族葬の知らせを受けていない場合は、香典の用意は不要です。家族葬は限られた人だけが参列する小規模の葬儀形式です。親族全員が参列するわけではないので、亡くなったことと家族葬を行ったことを後日はがきなどで知らされることもあります。
葬儀後に弔問したいときはまず、はがきに弔問と香典の辞退について記載されているかを確認しましょう。記載されている場合はどちらも避け、記載されていなければ遺族に弔問が可能かを確認します。遺族側の都合がよい日に香典を持って伺いましょう。
家族葬における香典の相場
家族葬と一般葬は葬儀形式が異なる部分も多いため、香典の相場も一般葬とは違うのではと考える人もいるのではないでしょうか。相場を知っておけば、どちらの形式でも対応をスムーズにできます。いざというときのために事前に確認しておきましょう。ここからは家族葬での相場を故人との関係別に紹介します。
両親
父や母が他界した場合に包む目安金額は3~10万円です。香典を用意する本人の年齢によって目安金額が変わります。20代の人は3~5万円ですが、30代になると5~10万円に上がります。40代以上では10万円以上の金額を包む人もいるようです。
1親等にあたる親が他界すれば、包む金額も高くなります。これまで育ててくれた親への気持ちを表すものなので相場より高い金額を包む人もいるかもしれませんが、出費が厳しい場合は目安の最低額を用意するだけでも十分でしょう。
祖父母
祖父、または祖母のどちらかが他界した場合に包む目安金額は1~3万円です。こちらも本人の年齢によって金額が異なり、世代が上がるほど金額も上がります。20代は1万円、30代は1~3万円、40代は3~5万円が一般的な目安額です。
この額は宗派によって異なるということはあまりありません。どの宗派であっても年齢に合った目安額を包めば問題とならない場合が多いでしょう。
兄弟
兄弟姉妹が他界した場合に包む目安金額は3~5万円です。20代の人は3~5万円、30代、40代の人は5万円程度となっています。40代以上の人の中には5万円以上包む人もいるようです。
香典を持参する本人が結婚していて夫婦で参列する場合、一般的に香典の名前は夫の名前にします。二人分の香典となりますので、相場より少し多めの額を包んだり、香典のほかに供花やお供物を用意したりするとよいでしょう。
その他の親族
両親、祖父母、兄弟以外の親族の場合は1~3万円です。世代別の目安金額は20代が1万円、30代が1~2万円、40代が2~3万円です。いとこや甥、姪の場合も伯父・叔父と伯母・叔母と同じ程度の額を包むとよいでしょう。
故人が親族でない場合は、相場額は低くなります。友人の場合は5,000円から多くて3万円、会社の上司や同僚の場合は5,000円から1万円、近所の住人の場合は3,000円から1万円です。故人と本人の関係によって額が異なりますので、お金を包む前に周囲にも確認しておくことがおすすめです。
家族葬における香典の相場であっても4と9を避けることが大事
香典の相場は関係性や年代によって幅広くなっていますが、4万円と9万円を包むことは避けましょう。4は死を想起させる数字、9は苦労を想起させる数字としてタブー視されているからです。
一人で出す場合はこれを意識しておけばいいのですが、連名で出す場合は全員の合計額を確認しておきましょう。例えば三人分の連名で一人が3万円を包むと合計額が9万円になります。合計額に1万円を足すなどして調整しましょう。
香典の相場で分からないことがあれば相談しよう
葬儀の知らせを受け、香典の相場を確認したものの、自分にあてはまるかわからず包む金額の判断がつかない……と悩む人もいるのではないでしょうか。包む金額が決められないときは相談してみることが大切です。ここでは香典の額について相談できるところを紹介します。
家族葬を経験した方に相談
家族葬を経験したことがある人に相談すれば、どれくらい包めばよいかを聞くことができます。相談するときはまず、どの関係にあたる人が亡くなったのか、どれくらい包んだのかを聞きましょう。例えば、親が亡くなった場合に相談するのであれば、親の家族葬を経験したことがある人に聞くのがベストです。
また、知人に葬儀に詳しい人がいれば、そうした人にどれくらい包めばいいかを聞いてみることもおすすめです。現状を知る人からのアドバイスは参考になるでしょう。
Yahoo!知恵袋
周囲に家族葬の経験がある人がいない場合は、インターネットの相談サイトYahoo!知恵袋に相談する方法もあります。Yahoo!知恵袋にはさまざまな相談が寄せられており、香典額の悩みを投稿している人もいます。
まずは同じ悩みを抱えている人がいないかを検索し、いなければ相談を投稿してみましょう。回答が来るまでに多少時間がかかるかもしれませんので、早めに相談をしておくことがおすすめです。
信頼できる業者
葬儀にまつわる相談は葬儀関係の業者に聞くことがおすすめです。葬儀にまつわるさまざまな知識を持っているため、的確なアドバイスをくれるでしょう。
香典の金額がわからなくて悩んでいるのであれば、「小さなお葬式」に一度ご相談ください。「小さなお葬式」では24時間365日、葬儀にまつわるご相談を受け付けていますので、お気軽にお電話ください。

家族葬における香典の相場以外に知っておきたいもの
香典の額の相場が確認できたら、そのほかの知識についても身に着けておきましょう。香典袋の違い、渡し方などを知っておけば、マナー違反になることもありません。ここでは香典の相場以外に知っておきたい3点のポイントを解説していきます。
香典を入れる香典袋
香典を入れる袋にはいくつかの種類があり、包む金額によってどの袋を選ぶかが変わります。1万円以下であれば封筒に水引が印刷されたものを使いましょう。1万円以上の場合は多当折りのものを使います。
水引には黒と金色がありますが、金色の水引は主に関西エリアで使われています。関西エリア以外に住んでいる場合は黒の水引の袋を選びましょう。3万円以上であれば、銀色の水引がついている多当折りの袋を使います。金額によって相応しい香典袋が異なりますので、包む額を決めてから購入しましょう。
香典の渡し方
香典を渡すタイミングとしては一般的に通夜か告別式での受付で渡しますが、家族葬は通夜を行わなかったり、葬儀場の受付を設けていなかったりすることもあります。その場合は拝礼をするときにご霊前にお供えするか、遺族に直接渡しましょう。
直接手渡す場合は「突然のことでお悔やみ申し上げます」「ご愁傷さまでございます」と一言付け加えます。長い言葉は必要ありませんので、短くお悔やみの言葉を述べながら渡しましょう。
家族葬を行う家の宗派
香典は表書きが必須ですが、表書きは葬儀を行う家の宗教、宗派によって書き入れる言葉が異なります。浄土真宗の場合は御仏前、浄土真宗以外の仏式の場合は御香典、御霊前、御香料のいずれかを書きます。神式の場合は御玉串料か御榊料と記載しましょう。
キリスト教の場合は御霊前、御花料のどちらかを記載します。無宗教の場合は御霊前です。宗教、宗派によって書く表書きが異なるため、事前に調べておく必要があります。葬儀の知らせを受けたときに宗教、宗派について確認しておくことがおすすめです。
家族葬での香典返しの相場等を知ることも大切
喪主、遺族は香典をいただいたら香典返しを行う必要があります。香典返しにもマナーがありますので、マナーに従ってお返しをしましょう。ここでは家族葬での香典返しの費用、品を送るタイミングについて紹介します。
香典返しの相場
香典返しは半返しが一般的とされています。半返しとはいただいた香典の半額相当の品をお返しすることです。1万円では5,000円、3万円では15,000円、5万円では25,000円です。
包んだ額と同額、またはそれ以上の額相当の品をお返しすると、相手に気を遣わせる可能性があります。高すぎるものは選ばず、香典の半額相当の品を送ることを心がけましょう。
香典返しを送る時期
お返しを送る時期は、一般的には忌明け2週間以内とされています。四十九日が忌中にあたるため、四十九日の法要を終えてから送り始めましょう。お返しが遅くなりすぎるのはよくないので、お返しの品を前もって決めておくことがおすすめです。
中には葬儀当日に香典返しをするという人もいます。ただ、当日にお返しをするとなると短期間でお返しの品を用意しなければいけませんし、香典額に関わらず、全員に同じ品を送ることになります。
包んだ額とお返しの額に大きな差が出ると相手に失礼となる可能性もあります。家族葬では香典額を確認し、後日お返しの品を送るようにするとよいでしょう。
まとめ
家族葬の香典の額は故人との関係性、または自身の年齢によって大きく変わります。大体の相場額、その額に見合う香典袋の種類も知っておきましょう。知識があれば突然の訃報に慌てることなく、通夜、告別式に向かうことができます。
包む額や香典袋、または渡し方について気になる点、不安なことがあれば「小さなお葬式」にご相談ください。24時間365日、どんな小さな疑問や不安も受け付けています。専門スタッフがいち早く解決できるように対応させていただきます。
葬儀をお急ぎの方は「0120-215-618」までお電話ください。


