
Vol.8「満中陰」
どうして、四十九日なの?
突然ですが《問題》です。
なぜ四十九日目なのでしょう?
① 来世の行き先が決まる日だから
② 土葬をすると、ちょうど白骨化する頃合いだから
③ 始終、苦が身につかないようにという語呂合わせ
正解は、、、
法事と法要の違い
故人が亡くなった日(命日)から数えて7日目を初七日(しょなのか)と言います。この日に初めて故人の法要を営みます。
法要とは、お寺さんにお経をあげてもらうことです。法要の後の食事を含めた行事を、法事と言います。
初七日から四十九日まで
初七日の日は、葬儀の日から間もありません。遠方から集まる親戚や休暇の都合も配慮して、ほとんどが葬儀の当日に行われます。
お骨上げの後の還骨法要(かんこつほうよう)と併せて行う法要を繰上初七日、葬儀式に繰り入れて行う法要を繰入初七日、または式中初七日と言います。
仏教では、命日から数えて7日ごとに法要を営みます。
二七日(ふたなのか)、
三七日(みなのか)、
四七日(よなのか)、
五七日(いつなのか)➡︎5×7=三十五日とも言います。
六七日(むなのか)、
七七日(なななのか)➡︎7×7=四十九日です。
四十九日までの間を忌中、仏教用語では中有(ちゅうう)、もしくは中陰(ちゅういん)と言います。
四十九日目を忌明(きあけ)、または満中陰(まんちゅういん)と言います。
なぜ49日なの?
Vol.4「仏衣」でも書きましたが、仏教では人は亡くなると旅に出ます。その旅をする世界が「冥土(めいど)」です。
冥土の旅路では、七日おきに七回の裁判を受けます。そこで生前の罪を裁かれます。五七日の裁判官が、かの有名な閻魔(えんま)大王。 そして七回目…四十九日目の裁きが下ります。この判決により、極楽浄土に行けるか否かが決まります。極楽浄土へ行けない人は六道(地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上)のいずれかの世界へ生まれ変わります。
冒頭のクイズの答えは①、
人は何度も生と死を繰り返します。仏教ではこれを「輪廻転生(りんねてんしょう)」と言います。
お釈迦様はこの六道輪廻(ろくどうりんね)にいる以上永遠に苦しみからは逃れられないとし、輪廻を超越した浄土という場所が、極楽世界だと考えました。
六道輪廻から離れることを「解脱(げたつ)」と言い、輪廻から解脱して涅槃(ねはん)に入る。これが仏教の目的です。
追善供養
七日ごとに法要を行うのは、死者が少しでもいい世界に生まれ変われるように裁判官に“陳情”しているようなものです。裁判所の傍聴席で、「この人めっちゃ善人でした!」と猛アピールするのです。これを「追善供養(ついぜんくよう)」と言います。
追善供養は裁判が終わってからでは遅いので、
早めに繰り上げて行います。四十九日が平日で親戚が集まりにくいなら、その日の前の土日に繰り上げます。
四十九日が3ヶ月にわたるのを嫌がる方がいますが、これは「始終苦が身につく」(49日が3に月)という、「友引」と似たような不吉な語呂合わせが原因です。
一周忌の次は三回忌?
四十九日が終わると、次は没後100日目にあたる「百箇日(ひゃっかにち)」です。
その次は没後1年目の初めての命日にあたる
「一周忌(いっしゅうき)」、その次は没後2年目の、2回目の命日にあたる「三回忌(さんかいき)」…
2年目なのに「三回忌」?
怪奇ですよね?
実はこれ、3回目の忌日という意味です。忌日(きじつ)とは、亡くなった日…祥月命日(しょうつきめいにち)のこと。
1回目の忌日は亡くなったその日。2回目は一年目の祥月命日、つまり一周忌。2年目が3回目として「三回忌」となるのです。
一周忌以降の法要を「回忌法要」と呼びます。
三回忌以降は6年目の「七回忌」、その後は十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌、三十三回忌、五十回忌とされます。
五十回忌以降の法要は遠忌(おんき)と呼ばれます。
一般的には三十三回忌か五十回忌をもって最後の法要「弔(とむら)いあげ」とします。
なぜ、1日前から数えるの?
葬儀、もしくは初七日の時に、お寺さんが遺族に渡す予定表を見たことはありますか?
これには初七日から満中陰、百箇日、一周忌など、法要の日程が書かれています。この表を「中陰表(ちゅういんひょう)」、もしくは「逮夜表(たいやひょう)」と言います。
この表を見ると、気がつくことがないですか?
初七日の日を数えてみてください。
亡くなった日から数えて7日目のはずなのに、6日目になっていることがないですか?
例えば、8月15日が命日として、初七日が7日目ならば8月22日なのに、6日目の8月21日になっていることがあります。
この数え方は寺院や地方によって異なりますが、関西では1日早い6日目で計算することが多いです。「亡くなった日の前日から数える」とも言われますが、
**さて、なぜでしょう? **
これには、逮夜(たいや)という言葉が関わってきます。
逮夜とは、故人の命日や法要の日の前夜のことです。昔は逮夜、つまり法要の前の夜から親族が集まり、次の日まで読経をして食事を振る舞ったそうです。
現在では逮夜の法要はしませんが、浄土真宗の本山で行われる親鸞聖人の遠忌法要では逮夜(前日の日没)からはじまります。
「逮夜表」とはつまり、法要の前夜の日程表です。いずれにしても、法要は遅くなるよりも早めに、という風習に従った形かも知れません。
神道の霊祭
神道では霊祭(れいさい、みたままつり)と呼ばれるものが、仏教の法事にあたります。
亡くなった日を1日目と数え、10日目が十日祭(とおかさい)。十日祭は初七日と同様に式当日に行われます。以降、10日おきに二十日祭、三十日祭、四十日祭と続き、五十日祭をもって忌明けとします。
神道では、亡くなった人の魂は家と遺族を守る守護神になると考えられています。仏教は四十九日で次の世に生まれ変わりますが、神道は五十日で家庭を守る守護神として自宅の祖霊舎(それいしゃ、神棚)に迎え入れます。
神道では、死は穢(けが)れとされるため、葬場祭や霊祭は神社では行いません。式場や自宅、墓前で執り行われます。
その後は亡くなって100日目の百日祭、1年目の命日の一年祭、満3年の命日が三年祭満5年目の五年祭までは一年ごとに式年祭を催します。十年祭からは10年ごとに五十年祭まで行います。最近では三十年祭で「まつりあげ」をします。「まつりあげ」の後はご先祖様として祀られます。
キリスト教の追悼
キリスト教には、供養という考えはありません。
カトリックでは、法要にあたる儀式(ミサ)を「追悼ミサ」もしくは「追悼式」と言います。故人の死後、3日目、7日目、30日目に教会で親しかった人を招いて追悼ミサを開きます。
1年後の昇天日(命日)には、「死者記念ミサ」を盛大に行います。
プロテスタントでは、法要にあたる儀式(礼拝)を「記念集会」もしくは「記念式」と言います。故人の死後、7日目、10日目、30日目に
所属していた教会、もしくは自宅で行います。
その後の記念集会は、1年後、3年後、7年後の
昇天記念日(命日)に教会で行われることが多いです。
ミサや礼拝の後は教会や自宅で茶話会などを行い、故人を偲びます。
満中陰は関西だけ?
香典返しのことを「満中陰志」と言いますが、
満中陰という言葉を使うのは、関西を中心とした西日本の一部だけなんだそうです。
法要の呼び方は、関東では「忌明け法要」、全国的には「四十九日法要」で通じます。
香典返しの表書きは「志」が一般的です。
喪中とは?
親族が亡くなってしばらくは、「喪に服す」と言って結婚式などの慶事を避けます。一年以内のお正月には、年賀状の代わりに喪中ハガキを送ります。
四十九日や五十日祭までを忌中と言いますが、
では、喪中はいつまでなのかご存知ですか?
故人との関係によって期間が異なる忌中と喪中。実は、明治時代には法令として決められていました。
太政官(明治前期の最高官庁)布告の「服忌令(ぶっきりょう)」という法令によると、故人との続柄が…
夫、または父母…13ヶ月
父方の祖父母・夫の父母…150日
妻・子供・兄弟姉妹
母方の祖父母・叔父・叔母…90日
昭和22年に撤廃されましたが、これがおよその目安になっています。
現在では、一親等が一年、二親等で3〜6ヶ月、
三親等では必ずしも喪に服す必要はありません。しかし、故人との付き合いの度合いや地域性、宗教によっても考え方は異なります。
また、浄土真宗には忌中も喪中もありません。
喪中はあくまでも故人を偲ぶ期間なので、最終的には本人が決めることでもあります。
まとめ
・満中陰 四十九日で ひと区切り
・法要は 早め早めに やりましょう
・亡き人を 偲ぶ思いが 供養です
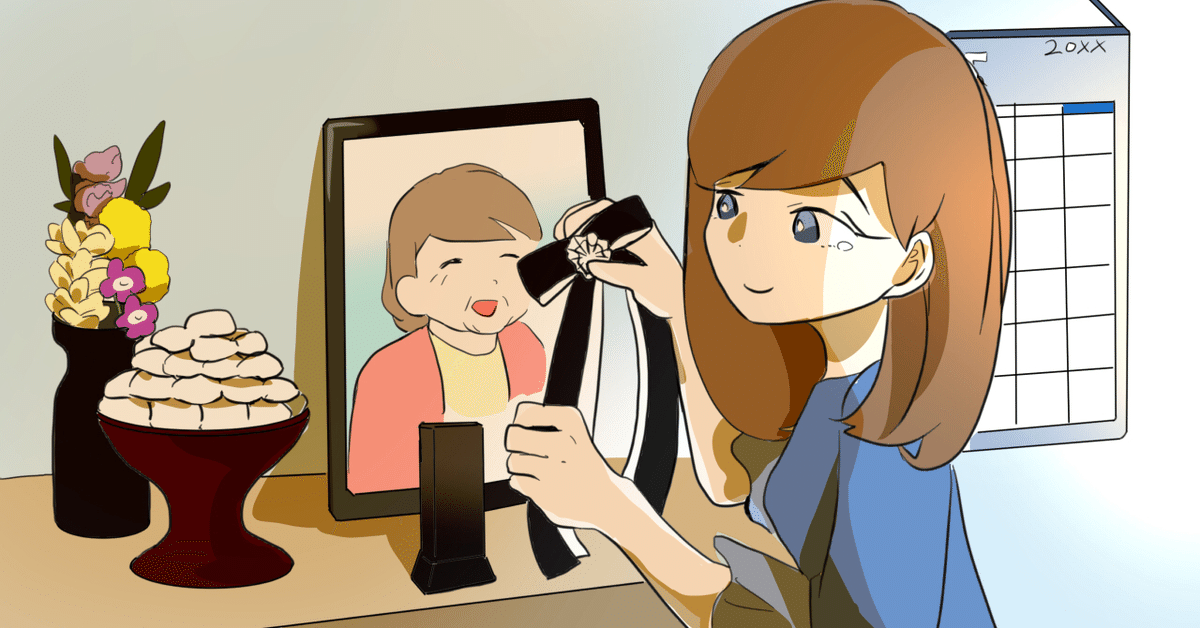
イラスト きむら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
