
◆読書日記.《樋口克己『図解雑学・ニーチェ』――シリーズ"ニーチェ入門"8冊目》
※本稿は昨年2021年4月26日に呟きの形式で投稿したレビューを日記形式にまとめて加筆修正したものを掲載しています。
樋口克己『図解雑学・ニーチェ』読了。
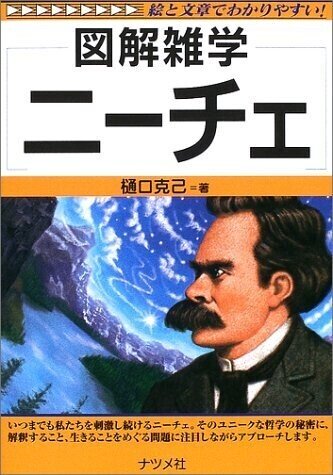
「絵と文章でわかりやすく様々な学問を解説する」ナツメ社さん評判の「図解雑学」シリーズだが、本書はそんな「図解雑学」シリーズの中でも異色ではないだろうか?
何しろ本書は「入門編」では全く、ないからだ。
因みに、ぼくとって本書は「読了」ではなく正確に言えば「再読了」だった。
本書は、ぼくが確か十年くらい前にニーチェの『ツァラトゥストラ』を読もうと思って、事前準備として読んだ"入門書"代わりの本だった。
その時『ツァラトゥストラ』を読む準備としたのは本書一冊だけだったが、これは今から思えば失敗だったと思う。
何しろ本書は冒頭にも述べたように「入門書」としては、書かれていないからである。
「絵と文章でわかりやすい!」と謳われているこのシリーズに、こういう内容の本を持ってくると言うのは如何なものかと思わざるを得ない。
AMAZONレビューなんかを見ても「難しい!」という声があちこちからあがっている。
それもそうだろう。これは入門書なんていう書き方ではないからだ。
それなのに、多くの人がこれを「入門書」だと思って読んで「やっぱり哲学は難しい」とか「ニーチェは難しい」という感想を漏らしている。
こうやって思想・哲学の門が狭まっていくのである。迷惑以外の何物でもない。
では、本書は何故「入門書」ではないのか? あまりに「著者なりの解釈」が多すぎるからだ。
それは「一般的な解釈」でもなく、誰か有力なニーチェ研究家の一意見でさえもない。
しかも本書では、そういった「著者なりの解釈」を「これは筆者の解釈であるが~」等と断っている箇所が全くないという所もたちが悪い。
これが例えば、分かりやすい思想・哲学の入門書を書いて評判の高い竹田青嗣氏であれば「これは私の解釈なのだが~」とか「〇〇の見方では~」等と「誰の解釈なのか」という断り書きがちゃんとしてある。
本書ではそれがなく、主語さえなくただ「この思想は〇〇〇といったように解釈できる。故に~」という書き方なのだ。
主語もなく、こういった書き方をしているのであれば、これを「入門書」だと思って読んでいる初心者は、これを「ニーチェ思想の一般的な解釈の仕方なんだな」と思い込んでしまっても仕方がないだろう。これは明らかに著者の書き方が悪い。
本書の「入門書」としてのマズさというのはこれだけに留まらない。解説のバランスも悪いのだ。
例えば、本書ではニーチェの著書のひとつ『悦ばしき知識』について、珍しく多くの頁を割いているという特徴がある。これは、他の入門書では見られない特徴だ。
何しろこの『悦ばしき知識』は"アフォリズム集"(相互に繋がりのない断片的な文章の集まり)なのだから。
だから、『悦ばしき知識』を「それ総体」として論じる、という事はできないはずだ。
出来るとしたら、『悦ばしき知識』の中の個々のアフォリズムを解説する事か、この本の全体的な思想傾向を抜き出して解説するか、だろう。
だが著者は、『悦ばしき知識』の中の「悦ばしき知識」という言葉に関わる箇所のみを抜き出して解説しようとする。
それは600以上に渡る個別のテーマについて語ったアフォリズムを集めた『悦ばしき知識』の中でもニーチェの「悦ばしき知識」に関わる部分のみ――1番目のアフォリズムや110番のアフォリズム、123番のアフォリズム等――を抜き出して、「悦ばしき知識」とは何かという事を解釈しようとするのである。
どうにもこれは、「ニーチェ入門書」と言うには些末すぎる議論だ。
ぼくが推測するに、この本の著者・樋口克己氏は「入門書を書こう」という意識は薄く、自分の書いた幾つかのニーチェに関する論文の中に出て来る議論を敷衍して本書を作り上げたのではないだろうか。
ぼくがそう思うのには、理由がある。
本書の著者・樋口克己氏が本書の「著者略歴」欄に上げている自らの論文に、しばしば本書で取り上げられる「入門書に書くには些末すぎる議論」をテーマに掲げているものが幾つも見られるからである。
例えば、上の『悦ばしき知識』について樋口氏には「ニーチェの<悦ばしき知識>という認識」という論文がある。
そもそも、他の入門書で「悦ばしき知識」をそんなに詳しく解説したものは見た事がなかった。
そもそも他の入門書では「悦ばしき知識」をニーチェの重要概念だとして取り上げてはいないのである。
その他にも樋口氏には「因果性と生成――『善悪の彼岸』三六節における「力への意志」説――」という論文があるが、本書ではまさしくニーチェの「力への意志」に関する解説でしばしば、『善悪の彼岸』の36節を取り上げて解説している。
これは、本書に著者の書いたこの論文の内容を転用していると見て間違いないのでは?
因みに、他の入門書では「力への意志」について、ことさらに36節をクローズアップして解説するといったような仕方は採っていない。
それだけではない。
ニーチェの入門書ではニーチェの主著を中心にして、その内容を解説していくものが多いのだが、本書ではニーチェの思想に関わるテーマを幾つか取り上げ、それに関する内容をニーチェの記述から幾つかピックアップして解説するという方法が採用されている。
そういう手法が採られているからだろうか、本書では主著の内容よりもしばしばニーチェが残した「覚書」のほうを取り上げて解説しているのである。
ニーチェが書籍という形で残したものよりも、メモ書きとして残した様々な文章を多く引用する等と言うマイナーな解説方法を、果たして入門書が採っていいのだろうか?
以上、本書は「入門書」を目的としたものではなく、恐らく著者が今までに書いてきたニーチェ関連の論文の集大成的な「著者なりのニーチェ論」ではないかと思われる証拠が、そこかしこに散見されるのである。
これは入門書ではない。「樋口克己氏なりのニーチェ論」である。
それが何故問題かと言えば、こういった「著者なりの解釈で、一般的なニーチェ解釈ではない」ものを「入門書」と勘違いしやすいパッケージで売るという事は、このシリーズの広範な読者に偏ったニーチェ像を伝えていく事にほかならないという事である。
ナツメ社さんには、猛省を促したい所である。
ただし、本書を「樋口克己氏なりのニーチェ論」として読めば、これはこれで面白い論文だと言えるし、ぼくは半ばそういう風に読んだ(しかし、もう半分は、上のような人を騙すかのような売り方に腹を立てながら読んでいたのだが/笑)。
本書の特徴はニーチェ思想を「生の哲学」をベースにしているという点であろう。
ニーチェの「生の哲学」とは、「生」をテーマに論じるという事であり、また「生」の立場から考える、という事でもある。
これは在る意味、ハイデガーの「解釈学的現象学」の方法論とも近いものがあるかもしれない。
生きている者が、生きている立場から考えるからこそ「生」が解釈できるわけである。
それはつまりは、自らの肉体であり、欲望であり、自らの立場のパースペクティブで解釈するという事だ。
逆に言えば人間は、そういった自分の肉体や欲望といったものから離れて解釈する事はできない、常に自分の光学によってしか解釈ができない――これを著者の樋口氏は「生の光学」と言っている。
この「生の光学」を樋口氏は、ニーチェの「悦ばしき知識」という考え方にも、「永劫回帰」にも、「権力の意志」にも関連してくる考え方として提示している。
これは竹田青嗣氏ならば「欲望相関性」で解釈しているだろうし、三島憲一氏ならばもっと「美的救済論」に寄せて考えてくるかもしれない。
という事で、本書のニーチェ解釈は他の入門書や解説書が採り上げていないテーマに焦点を当て、非常に独自の解釈を提示してユニークなのだが、「ユニーク」だからこそ「入門書」としては、あまりに偏っているのである。
「図解雑学」にするにしても図解の必然性もなく、「わかりやすく~」と言う割には内容も踏み込み過ぎている。
返す返すも、本書がもっと別の形態で出版されていたら、もっと無心に読めたのにと残念に思えてしまう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
