
◆読書日記.《ジグムント・フロイト『自我論集』》
※本稿は某SNSに2020年6月17日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。
ジグムント・フロイト『自我論集』読了。
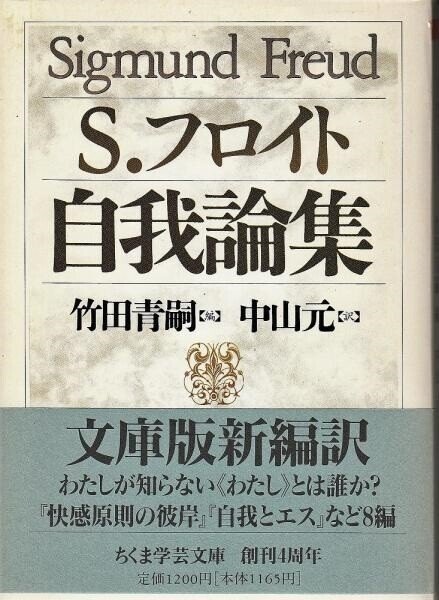
本書はフロイトの執筆した数多くの論文の中でも、「自我―エスー超自我」の構造に関するフロイト自身の論考の移り変わりを代表的な論文を中心にして年代順に並べて編んだ「フロイト学説における自我理論の変遷」に関する論文集である。
ということで、あくまで「フロイトの論考の移り変わり」が明確に浮かび上がるように論文の選別と配置を行った(編者の竹田青嗣はそこに関わったのだろう)論文集となっているので、ぼく的には今までのフロイトの論文集と比べて若干「まとまりの悪さ」のようなものを感じてしまったのだが、これは仕方がない事だろう。
何しろフロイトが論文を書いていた頃は、人間の深層心理を神経症患者の症例研究から分析していく精神分析理論をフロイト自身が切り開き始めたばかりであり、医学的に定説となっている確固とした理論があるわけでもなく、様々な学説が群雄割拠し始めていて、フロイト自身も暗中模索だった部分があるのだから。
フロイトは本書の論文にも、他の本に掲載されている論文にも、何度も何度も自分の理屈はあくまで暫定的な仮説にすぎず、今後様々な症例や研究によって理解を深めていくべきだという但し書きをしている。
ということで用語のブレはフッサールの現象学ほどではないがある程度はあるし、概念の定義も何度か変更を余儀なくされている。
本書はそういったフロイトの自我論に関する「思考遍歴の記録」であって「結論」ではないので注意が必要だ。
なので本書は「精神分析理論に関する知識を学びたい人」向けの編集方針ではなく、初期精神分析理論の紆余曲折に見られるフロイト自身の「理論構築の方法論の骨法」を窺い知ることのできる編集と捉えるべきだろう。
そういう見方をすれば、本書ほどダイナミックに思考が変遷するエキサイティングな論考もないだろう。
どうやってフロイトは神経症患者らの症例研究によって人間の自我モデルを構築していき、どうやって「精神分析」という新しい学問分野を切り開いていったのかという、彼の苦労というのも良く分かって面白い。
そういう視点から見た本書での白眉は何と言っても『快感原則の彼岸』である。
この一編ではフロイトの迷いだったり、それを踏み越えて打ち立てる仮説の立て方だったり、自説の修正を迫られた場合の発想の転換方法だったりといった、フロイトの論考ドラマをたっぷりと堪能できる。
彼一代で精神分析というジャンルを打ち立てた「天才」と呼ばれた精神分析医・フロイトほどの頭のいい人物の頭の中の理論の移り変わりを辿るというのは読んでいて実に興味深い。
未知の分野を切り開いている世界レベルの頭脳というのはどういった発想法や理論構築法を行っているのか参考になるテクストだ。
……という言い方をするフロイト本人に対して失礼な気がしないでもないが、フロイト自身がその自分の暫定的な思考遍歴の軌跡を記録しているという事は、そういう意図も少なからずあったはずではないだろうか。
そして論文というものは、確かに後世の研究にバトンタッチするために書かれるものでもあるのだから。
「自我―エスー超自我」と「意識ー前意識ー無意識」という構図自体は、正直本書を読まずとも恐らく晩年の『精神分析入門講義』を読んだほうがよほどフロイトの安定した思考が分かり、まとまってもいるが、「フロイトの自我論の成立過程を追う」という意味で編まれた一冊だと思えば編まれる意義はあっただろう。
そういう「編集意図」を事前に踏まえて読まないと、特に初心者にはかなりハードルの高い本となるかもしれない。
本書ではぼくも最初の方の1910年代に書かれた論文には「えっ!フロイトってこんなこと言ってたっけ?」みたいな記述も出てきて混乱させられてしまうほどだった。
そんな暗中模索の初期理論から一皮むけるきっかけの一つが例の『快感原則の彼岸』だったのである。
フロイトの初期理論では、人間の心的なプロセスを制御している原則は「快感原則」と「現実原則」との対立で成り立っていると考えていた。
だが、それだけでは説明のつかない症例が神経症には存在していたのだ。それがマゾヒズムであり反復強迫であった。
フロイトの初期の欲動の種類は「自我欲動」と「性欲動」の二種類で対立関係になっているという考え方で、簡単に言えば「自我欲動」は個体の生を維持するために働いている欲動であり、「性欲動」は種を存続させていくために働く欲動だと考えられていた。だが、このどちらもマゾヒズムも反復強迫も説明できないのである。
例えば戦争による外傷神経症の患者は、なぜ何度も自分の体験した辛く苦しい戦場での体験をフラッシュバックで追体験したり、夢の中で反復して経験して苦しまなければならないのか?
フロイト学説では、夢というのは「願望の充足」という目的があって見られるものであるはずだったのだ。
だが、自分の辛い体験の記憶をまざまざとリアルに追体験させて自己を苦しませなければならないというのは、どういう欲望の成せる業なのか?どういう心的力学が働けば、自分を苦しめる事を求める心性というものが発生するのか?
――この問題を解決するにはもう「快感原則」だけでは説明しきれなかったのだ。
そこでフロイトは、「快感原則の彼岸」にその答えを求める事となる。
この理論転換のために「現実原則」と「快感原則」の他にフロイトが設定するのが英国の精神分析家バーバラ・ローが提案した「ニルヴァーナ(涅槃)原則」であった。
「涅槃原則」というのをフロイトは、人間の心的状態を「安定状態」に移行させる事を目標とし、「死の欲動」に寄与する原則と考えた。
また、これに合わせてフロイトは、欲動の原理についても修正を図る事となる。
フロイトは人間の幼児期からの性欲の成長過程に関する理論を構築していく上で「自我欲動」と「性欲動」は一つに纏められるのではないかと考え始めるのである。
何しろ性欲動は、幼児の時期は自我欲動に依託して表れ、その後も一部は最後まで自我欲動と結びついているために両者を確然と区別するのは難しかったのである。
そこでこの「欲動」の種類にも先に挙げた「死の欲動」を導入し、自我欲動と性欲動を纏めた「生の欲動」と、それに対立する「死の欲動」の二項対立関係を考案したのである。
このようにして心的プロセスを制御する三原則――「現実原則」「快感原則」「涅槃原則」と、その原則に則って働く欲動――「生の欲動(エロス)」「死の欲動(タナトス)」が固まっていくのである。
この修正によって自らを責め苛む反復強迫や自らを傷つける事を目標とした性倒錯・マゾヒズムを説明できるようになる。
また、「メランコリー(鬱病)」の症状であり、反復強迫の症状といったものに関わる「自己を苛む自責感」というのはどこから来るのか?という問題を解くために、今度はフロイトは自我を道徳的・倫理的に監視する「超自我」という審級があるという仮説を立てる事となる。
この「超自我」の考えを取り入れ「意識―前意識ー無意識」の局所論的な心的構造についての考えを整理しなおし、そこに心的なプロセスの一貫性を成す組織である「自我―エスー超自我」の三対の考え方をくみ上げて心的構造に組み込むに至る論文が本書に収録されている『自我とエス』となる。
このように本書はフロイト学説の「結果」だけを知りたい読者にはかなり煩わしい論考プロセスにつき合わなければならないと思ってしまうだろうが、フロイト学説の「考え方」の流れを初期から理解するには実に分かり易い纏め方をしている。そういう意味では「入門書」から一歩踏み込んだ段階の論文集だと言えるだろう。
◆◆◆
因みに、本書の編者である竹田青嗣氏が本書の解説で面白い指摘をしている。
フロイトの精神分析理論というのはあくまでフロイトが神経症患者の臨床研究から「治療のために」構築した「説明概念」であるという事。
だからこそ「無意識というのは果たしてあるのかないのか?」という設問は見当外れだという事だ。
フロイトの築き上げた精神分析理論は今では「無意識」や「自我」「抑圧」「反動形成」と、一般用語となってしまっているほど浸透しているために、いわゆる「俗流心理学」として誤解を与えかねない理論でもあるが、フロイトが当初意図していた事は「思想/哲学」ではなくて、あくまで「いち治療法」なのである。
そういう意味で考えれば「無意識」を「説明概念である」と喝破した高田明典『構造主義方法論入門』は正しかったと言えるだろう。
しかし、このフロイト理論の応用のしやすさこそが、安易に精神分析理論を小説や映画での犯罪心理に応用してしまったりする「俗流心理学」を生み出す結果となってしまった。
とは言え、精神分析というのはかなり応用範囲の広い「使い勝手の良い」理論であるからこそ、そういった通俗的な理解で利用されやすいという欠点も孕んでいるのだろう。
だが、それでも精神分析の影響は広く(シュルレアリスム等の美術や精神分析批評等にも応用される)、また一定のプラス成果も出しているのである。
◆◆◆
また、本書で竹田青嗣氏は、現象学者らしく「一般的に言って現象学は深層心理学や構造主義と折り合いが悪い。それらは長く批判し合っていたし、とくに構造主義からの現象学批判は激しいものがあった」と指摘している。
現象学派と言えばフッサールーハイデガー―サルトルーメルロポンティ系列の学派である。
特にサルトルは主著の『存在と無』でフロイト批判を行ったし、「フロイトに還れ」を構造主義的に一大思想に練り上げたジャック・ラカンは現象学批判の態度を表明していたと言われている。
――不思議な事だが、ぼくの中では現象学も構造主義も精神分析も、お互いを補完し合う折り合いのいいものとなっている。
フッサールの超越論的現象学の話もフロイトの精神分析の話も、ぼくが最近書いた文章では頻繁に引用している思うし、構造主義の祖レヴィ=ストロースも大好きな思想家だ。構造言語学のソシュールも面白い。
これらについては最近の脳科学の書籍のレビューで「一体のものとして繋がっている」旨説明した事と思う。
ぼくの中で全ては「人間の精神的/心的/知覚的プロセスの謎」という点でリンクしている。
超越論的現象学はその謎を「クオリア問題」的に人間の内側から、精神分析はその謎を症例研究分析を使って人間の外側から、そして構造主義はそれを社会的・構造的に、そしてそれらを脳科学が解剖学的なアプローチで解明する。
全ての謎はこれら多角的なアプローチによって理解が深まる――のではないか、とぼくは考えているのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
