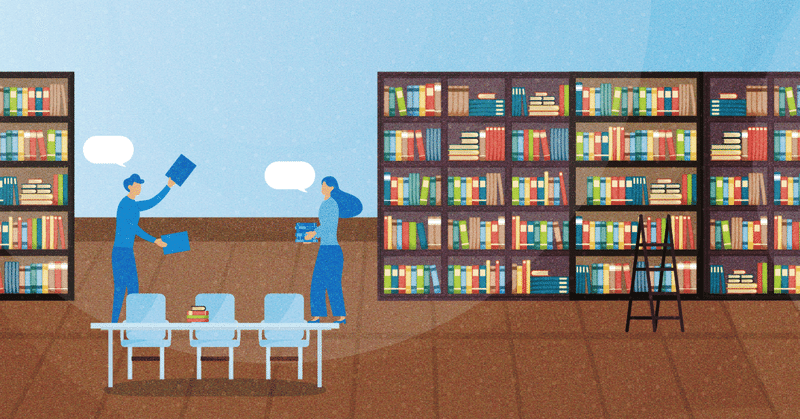
書店員日記 「POPってどう描きますか?」
店主はミステリ読みなので、POPを描くのも必然的にミステリが多くなります。
どんな小説でもそうですが、ミステリは特にその性質上、先入観や情報をなるべく入れずに読んだ方が面白いものが多いです。
クイーンの「国名シリーズ」や有栖川有栖さんの「学生アリスシリーズ」のような、いわゆる「犯人当て」ミステリであれば、ある程度内容がわかっていたところで面白さが減じることはないかもしれませんが、「どんでん返し」を売りにしているタイプのミステリは、何も知らない状態で読みたいものです。
できることなら、「どんでん返し」があるということすら知らないで読んだ方が面白いはずなのですが、最近のミステリは帯に「驚愕のどんでん返し!」のような惹句がよく書かれていますね。
店主は思うのですが、びっくり箱はそれが「びっくり箱であることを知らない」ほうが驚けるに決まっています。びっくり箱だってことは言っちゃったけど、何が飛び出してくるかは言ってないからネタばらしにはならないでしょ、という理屈には頷くことができません。
ましてページ数まで指定して「ラスト20ページのどんでん返し!」みたいな帯を書くのは論外。
読者は「ラスト20ページまでで明かされた真実はどうせひっくり返っちゃうのね。じゃあこいつが犯人じゃないね」とか「動機は別にあるんだね」とか、そんな風に思ってしまいますよね。
それでもなお、読者の想像を超えて驚かせてくれる作品ももちろんあるのですが、知らないに越したことはないでしょう。
ただ、そのミステリの一番のポイントが「どんでん返し」にある場合、ではどのように作品の魅力を伝えればいいのかはとても難しいと思います。
出版社の人たちにせよ、書店員にせよ、自分がその作品を読んだときの「驚き」を何とかしてお客さんに伝えたい。
そしてできれば「買って読んでみようかな」と思ってほしいわけです。
その兼ね合いがとても難しいです。
店主は「お客さんにその作品の魅力を伝える」と同じくらい、「その作品の内容をお客さんに伝えない」ということを大事に考えています。
その結果、何を言ってるんだかわけがわからないPOPになってしまうことも多いのです。
実例を挙げます。
「花束は毒」(織守きょうや/文藝春秋)という作品です。
店主は結構好きな作家さんで、好きな作品です。
決定的なネタばらしはしませんが、作品の内容には触れるので未読の方はここで回れ右してください。
この作品は、結婚を間近に控える男性に、「その結婚をやめろ」という脅迫のような手紙が何通も送られてくるところから事件が始まります。
主人公と探偵は、その差出人を探るべく調査をはじめるわけですが、被害に遭っている男性はどうもその調査自体に消極的な様子。
最初の謎は「なぜ彼は差出人を探ることに及び腰なのか」ということ。
そしてその謎が判明すると、次は「その差出人は誰なのか」という謎に取り組むことになります。
ひとつ謎が解明されると、また別の謎が立ち上がってきて、「謎」で読者の興味を牽引していくというミステリの王道パターンですね。
実はこれらの「謎」が「真相から読者の目を逸らすためのミスリード」になっていて、最後の「どんでん返し」に繋がっていくというのがこの作品の趣向なのです。
で、この「花束は毒」に店主が付けたPOPというのが、これです。

このPOP見た方の思うことは「面白そうだな! 買ってみるか!」よりも「ん? どういうことだ?」でしょう。
この作品の魅力は「イヤミス」的な読後感やキャラクタがとても良く描けていること、ラストまでの美しい流れなどが挙げられますが、やはり一番のポイントは「背筋がゾクッとするようなどんでん返し」にあると思います。
それを事前に明かすべきではないと考える店主は、こういうなんだかよくわからないPOPを描いてしまうわけです。
おそらく出版社の方たちも、店主と同じことを考えているのでしょうが、彼らの仕事の性質として「何を言っているんだかわけがわからない」帯を作るわけにはいかないわけで、そうすると「100%騙される戦慄ミステリー!」とか「罠、また罠。」とか書かざるをえないのでしょう。
お客さんに出来る限り内容を伝えず、先入観も持たせず、でもその本を買ってもらえる。
そんな魔法のようなPOPが描けたらスゴイよなあ……というのは、出版社の皆さんも書店員も、常に思っていることなんです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
