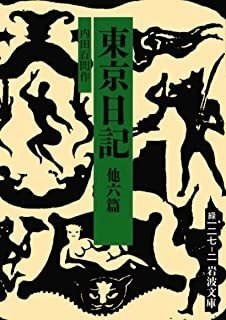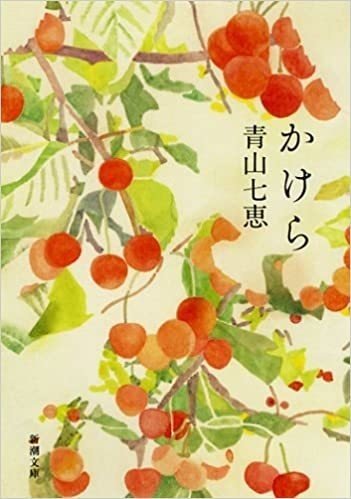第三回おぺんぺんの会
第三回おぺんぺんの会は課題図書が前回よりも一編多いです。すこしこわい当日図書を含めた四編についての議事録です。今回も長い!はいどうぞ!
内田百閒「サラサーテの盤」(岩波文庫 『東京日記』収録)
(ラ)なんかわかんなくなっちゃった、この話。
(虎)今回の三編は常識で何かを捉えるとか、物語の筋が重要というものではなくて、この小説を読んでいってどう感じるのかが重要な作品だね。元々人間が書いているもの、他人が書いているものって簡単に理解できるものではないし、特にこの「サラサーテの盤」っていう作品は難しいというか、よくわかんないじゃない。中砂っていう友人がいて、その奥さんが来て「本が置いてあるはずなんですけど」って幽霊みたいにやってくる。でも幽霊ではない。怖がらせようとして書いているんだよ。わからなくさせようとして書いてる。わかりやすく読者をスッキリさせようとして書いている小説じゃなくて、苦心させようとして書いているんだよ。
(ラ)なんか誰が誰かよくわかんなくなってきちゃって。
(虎)それは、ちょっとどうなのかと思うけど。4人しか出てこないじゃない。そこは難しいところじゃないと思うけど。
(ラ)じゃあなんで、Ⅰ、Ⅱって分かれてるの?
(虎)それは場面が変わるから区切るためでしょ。これは、何が言いたいのかよくわからないじゃない。最後の一行とかもさ。不気味っていうだけ。でも不気味だなって思ったらそれでいいの。奥さんが幽霊じゃなくて、生きてるってなんで思えたの? いつも家にいる時どうしてた?
(ラ)玄関に入ってこなかった。
兎に角上がれと云っても、いつもの通り土間に生えた様な姿勢できかなかった。
(虎)書き手の主人公が、オフサさんがおかしいとか精神異常者であるとかっていう風に書いてるけど、実はそうじゃないんじゃないか。おかしいのは自分(主人公)なんじゃないかって思っちゃってるでしょ?
(ラ)確かにレコード借りにきて、一回家に帰ってないくらいの速さでもう一回訪ねてくるとかね。
(虎)でもことごとく当たっているでしょ? 「サラサーテ盤のツィゴイネルワイゼン持ってきてください、あるはずなんで」って、でもないよってなるけど、最終的には又貸ししてたことを思い出すでしょ? 正しいのはオフサさんの方なんだよ。でも怖がらせようとして書いていて、訳わからなくさせようとして書いてるから、わかんなくていいのよ。もちろん細かく読んでいって、内田百閒のこと研究していったらわかるかも知れないけどね。それで、印象に残ったところはあった?
私はまんまと罠にハマり、訳がわからなくなり、途中から集中して読むこともできず、おもしろさに気付く前に読み終えてしまった。鈴木清順監督作品の映画『ツィゴイネルワイゼン』も観た。本を読むときの時間と映画の鑑賞時間とではあまりにも映画の尺が長すぎるように感じた。
(虎)何が怖くさせてるかって、音なんだよね。
宵の口は閉め切った雨戸を外から叩く様にガタガタ云わしていた風がいつの間にか止んで、気がついて見ると家のまわりに何の音もしない。しんしんと静まり返った儘、もっと静かな所へ次第に沈み込んで行く様な気配である。机に肘を突いて何を考えているという事もない。纏まりのない事に頭の中が段段鋭くなって気持が澄んでくるようで、しかし目蓋は重たい。坐っている頭の上の屋根の棟の天辺で小さな固い音がした。
(虎)一つ一つ音を消していってるでしょ。完全に音を消してるんだよね。そして「小さな固い音」ってこれ小石が転がってるだけなんだけど、それが全くの無音状態の直後にある音だから不気味で怖く感じるのよ。ここの描写はほんとすごい。ここだけじゃなくて物語の中の音についてものすごく緻密に描くことで恐怖心を煽っているっていうのはあるよね。当然レコードの話だから、レコードの音になんて入っていたのかとか気になる。これは音小説だね。
G・ガルシア・マルケス / 鼓直・木村榮一 訳「この世でいちばん美しい水死人」(ちくま文庫『エレンディラ』収録)
(ラ)「サラサーテの盤」は状況的には普通でしょ? だから余計難しく考えちゃったけど、この話は変なところが多すぎたからそういうもんかって受け入れられて読めたからおもしろかったなぁ。
(虎)まず一つに驚異的な現実だよね。ありえない話。コロンビアっていう土地と伝承を用いながら描いているでしょ。その土地だったら、信じてしまいそうな出来事っていうか。死体についてはほとんど語られず、周りの変な行動が描かれているでしょ。やっぱり日本っていう場所で、現代に暮らしていたら、ありえない状況じゃない完全に。でも説得力があるのはコロンビアっていう国だからなのか、どうしても信じちゃうっていうか。例えば、エステーバンって名前つけちゃうとか変だしね。
泣いているうちに、あわれなエステーバンがこの世でいちばんおとなしく従順で、痛ましい人間のように思えはじめた。やがて男たちが戻って来て、水死人は近くの村の人間じゃないようだ、と伝えたが、それを聞いたとたんに、泣きくずれていた女たちが喜びの声をあげた。
(虎)こういう騒ぎみたいなのがなんとなく信じられるものとして描かれているのはマジックリアリズムだよね。驚異的な現実が描かれている。土着性みたいなものは当然日本にもあって、民話とか紐解いていったときに、そんなはずないじゃないってことでも信じちゃうでしょ? 例えば、地方に根付く民話で天狗がいるとかね、実在しないはずだけど、いないとも言えない何かがあるでしょ。そういうのって人々が語り継いできた伝説とか伝承とかっていうものに基づいていると思う。日本だったら、中上健次とかもそうだね。紀州の伝説とか民話とか。現実が現実として立ち現れても不思議でないような想像力というのを発揮しているよね。それで、この話は特になんだけど、この土地じゃない人がくるっていうのが大事で。
(ラ)水死体として?
(虎)水死体じゃなくてもいいんだけど、要は何か自分たちと違うもの、異なるものが急にやってきて、それで騒動を巻き起こすっていうのが非常に重要なんだよ。なんでかっていうとコロンビアってスペインに征服されていたから、異人に対して非常に敏感なんだよ。日本なんかと比べてもさ。日本なんか海に守られて異人が征服するなんてことほとんどないんだから。弥生時代はあっただろうけど。その土地に住んでいる人たちにとってはさ、外から何かがやってくるっていうのは一大事なのよ、一大事。それで騒いじゃう。それを描いている訳だから、水死体がどういう水死体で、実際ほんとはどうだったのかっていうのは割とどうでもよくて。仮に水死体じゃなくてもよかったんだと思う。水死体がこの村のものではないってわかったときにさ、ヤッター!ってなるでしょ。ああいうのとか妙な感情だよね。僕らには全然わかんない感情だけど。ラテンアメリカってこういう「違うものが入ってくる小説」が多い気がする。こういうのって外に出ないと自国のおかしさってわかんないからさ。小説にしてしまってようやく「すごいおもしろいぞ我が国は」みたいなさ。
(ラ)なるほどね、でも読みやすいねぇ。
(虎)あと一番謎なのはさ、水曜日ってなんなんだろうね。
せっかくの水曜日にこんなご迷惑をおかけすることもなかったでしょうし、
真夜中を過ぎるとようやく風も収まり、海も水曜日の昏睡に陥った。
(虎)水曜日の謎っていうのがあるね。今ちょっと調べるね。
キリスト教だと懺悔の日らしい
(虎)妄想を語るっていうのって楽しいじゃない。人がいて、この人はこうでこうなのかなとか妄想するときってあるでしょ? その話って結構面白いじゃない。いわゆるストレートな小説っていうのは妄想まではいかないじゃない。嘘は嘘じゃない、妄想と言えばそうだけどみんな理路整然と描くけど、この人は妄想を妄想のまま描いている感じがしてそれを受け入れられる文体っていうのかな、書きっぷりの良さっていうのがあるよね。それはさっき言ったその土地に根付いているような何かがやっぱりあるじゃない。
村といっても、荒れ果てた土地に粗末なバラックが二十軒ばかり点在しているだけで、石のごろごろしている中庭には草花ひとつ見当たらなかった。
(虎)強風にさらわれるかどうかビクビクしていたっていうのはそういう言い伝えがある訳でしょ、たぶん。強風が子供をさらうなんてこと絶対にあり得ないからね。例えば、日本だったら雷なったらへそ隠す、へそが取られるとか。
(ラ)夜爪切っちゃいけないとか?
(虎)そう。でも絶対そんなことないでしょ? そういう迷信みたいなものを小出しにすることによって、なんかその妄想に妙な説得性を生んでる。そうすることで、僕らがついつい考えてしまう常識で読んでしまうと変なところだらけなんだけど、そういう導入があるから、楽しく読めちゃうんだね。
青山七恵「かけら」(新潮文庫『かけら』収録)
(ラ)この話はさ、なんか穏やか〜な時間だなって思うんだけど、ちょっとこの主人公の女の子がひねくれてるから、なんかお父さんとの距離感っていうのが絶妙でしょ?
(虎)そうだね。
(ラ)一緒にさくらんぼ狩り行ってるけど、別行動だし。かけらをテーマにした写真についても、お父さんがこういうの撮ったらいいんじゃない? とか言うとイラっとしたりするし。あとバラのアーチがある綺麗なところとか...
(虎)あー実はなかったところでしょ?あれ怖いよね。
(ラ)怖いよね。あれなんだったんだろう、やっとお父さんの言うこと聞いてそこに行くけど、見当たらなくてイラっとするみたいな。
(虎)僕がやっぱり気になるのは、兄貴だね。小説の中では、主人公とお父さんがずっと一緒にいて、昔、お父さんについて興味というか考えようと思ったけど、ある日考えるのをやめた。やめたけれども、旅行に行くことになって写真を通して見てみるとかしてさ、要は自分が期待している他人とのやり取りみたいなのってあるじゃん? 感情じゃないけどさ、気持ちの揺れみたいなのをずっと描いているわけじゃん。で、お父さんってどういう人なんだろう、って考えるけど、兄貴はさ「お父さんなんてむしろ簡単だぞ」って言う。実際に兄貴はお父さんのことを理解していて簡単だと思っているのか、全然わかってないくせに簡単だって言ってるのか、わかんないよね。
「だってぜんぜん芯がないんだもん。気骨とか、覇気とか、ぜんぜん」
(ラ)兄貴にそういうことお父さんに求めてたのかって言われて、求めてなかったって言うもんね。
(虎)この小説いい小説なんだけど、ここまでして親兄弟に固執する感情ってなんなんだろうって思うよね。自分から見える、この話だと父親の捉えどころの無いままでいいんじゃないかって思うけどね。見たまんまでいいんじゃないかって気もするんだけど、するもんなの?
(ラ)でも、最初に興味を持ったのって高校のときでしょ? この主人公には彼氏がいて、全然違うタイプと付き合ってて、男の人なんて最初家族しか知らないけど、自分も好きな人が出来てって考えたときに、お父さんも結婚してるわけだから、男としての魅力があるのかもしれないって思っちゃう感じはわかる。
(虎)そうなの、僕だったら母親にでしょ? 一切思ったことないなぁ。
(ラ)考えるのやめてたけど、さくらんぼ狩りに行っておばちゃんたちに囲まれてさくらんぼ取ってあげたりとか、転んだおばあちゃん助けたりとか。
(虎)危険な転び方したよね。
(ラ)家族の枠をとっぱらってお父さんを個体として見てもう一回考えちゃう。
(虎)お父さんって言われちゃうから、ふーんなんて僕は思うけど、他人をカメラを通してどういう構図で、ファインダーを通して見るのかっていう話で、それはすごい巧みじゃない。小説の中にカメラっていうもう一つの枠を作って、撮って、見てみるっていう。レンズの三重構造くらいになってて、すごい上手な小説だよね。そうすると人っていうのはどういうものなんだっていうことにすごい一生懸命考えている青山七恵。そして文章がうますぎる青山七恵。お父さんがさ、平凡に描かれてるけど、実は平凡じゃないやばいやつだって気付いた?
(ラ)え、なんで? きのこの味噌汁めっちゃ飲むところ?
(虎)それは好きなんでしょ。
ジュースがテーブルの上をつたい、そこに広げてあった夕刊の角をゆっくり濡らしていった。読んでいる父はそれでも何も言わなかった。
(ラ)やばい?
(虎)やばいっていうか普通じゃないじゃん。
(ラ)家族の中で気配がない人っていうのを徹底してるんじゃないの? キャラみたいなのを。朝5時に出て新宿散歩するのは変だけどね。
(虎)ハゲてるしね。写真と記憶みたいなのが気に入ってて、あれ? この場所来たことがある気がするって主人公が思うでしょ。それは実際に覚えているんじゃなくて昔撮った家族写真を見て思い出したって、いいよね。
(ラ)さくらんぼ狩りで撮った写真も現像するまでに3週間くらい経っててさ、何回も何回も繰り返し見てようやくお父さんに気付くっていうのもいいよね。
(虎)多分10年後、20年後にさ、なんかの拍子にこの東の空見てるお父さんの写真見て思い出すんでしょ。しみじみおいい小説ですね。
夏目漱石/「夢十夜」(岩波文庫『夢十夜』収録)
(虎)一夜でさ、接吻するでしょ。十夜は?
(ラ)ぶた、、
(虎)それは人間の感覚で言うと触覚でしょ?
二夜はお寺に行ってさ、最後時計の音で終わるでしょ。
九夜は鈴の音出てくるでしょ? 聴覚
六夜は彫刻でしょ?
五夜も彫刻、視覚でしょ。
対比になってるの、怖いんだよ。この小説。
(虎)一夜と十夜の共通点は人が死の床にある。一夜の「私」はさ、女の言うことを聞いて待ってるんだよ。十の正太郎も女の言うこと聞いて待ってんだよ。おんなじでしょ? 一夜は百合にキスして十夜は豚にキスする。太陽が昇って落ちるのと、豚の鼻叩いて、要は上って落ちていくわけでしょ。すごい巧みに作ってるんだよ。
(ラ)怖い。。
(虎)怖いんだよ。でもそれは、僕が「夢十夜」オタクだから一生懸命読み解いて気付いたんだけどね。
(虎)あとね、二夜と九夜には短刀が出て来て、一生懸命努力しても実らないでしょ。
三夜は盲目の人が出てきて八夜は?
(ラ)床屋の鏡?
(虎)そう。爺さんのやつは?
(ラ)水に入って出てこなかった。
(虎)死んじゃったでしょ? 八夜は?
(ラ)自殺しちゃう。
(虎)ほら、すごい面白いんだよ。一から十全部に共通していることが一つあるんだよ。会う/会えないをテーマにしてるんだよ。
(ラ)一夜は百合になって会ってる!
(虎)そう、二夜は再会しようとして果たせない。三夜は?
(ラ)自分が殺した相手と再会してる!
(虎)四夜は、爺さんと再会できない。
(ラ)待ってるけど、上がってこないもんね。
(虎)五夜は恋人と再会できない。六夜は自分で彫っても仁王に会えないでしょ。七夜は客船に戻りたいけど戻れないし、八夜はちょっと無理やり感あるけど、粟餅屋に会えないでしょ。どれも再会する、会う会えないがあるんだよ。九夜は父に会いに行くけど、死んでるから再会できない。十夜で正太郎は家族と再会できてるでしょ。
あと、共通点一個しかないって言ったけどもう一つある。全部「落ちてる」んだよ。太陽が昇って落ちるとか、自分が落ちるとか、豚が落ちるとか。恋人が崖から落下するとか。床屋では髪が落ちるでしょ、切って。というような巧みな小説なんだよ。
(ラ)これわかってから読むとまたおもしろいね?
(虎)そうだね、でも夏目漱石はそこまで意識せずこうなってるかもしれない。
(ラ)自分の中の癖みたいなこと?
(虎)そう。でも対比は巧みにやってると思う。僕は第一夜が一番好きで、これは、男の(私)ね。女性に対する愛じゃない。100年待ってるんだよ。すごいのがさ、女性と百合の描き方が全く一緒なんだよ。
(ラ)確かに!読んでてすぐわかるもんね。
女は長い髪を枕に敷いて、輪郭の柔らかな瓜実顔をその中に横たえている。
すらりと揺らぐ茎の頂きに、心持首を傾けていた細長い一輪の蕾が、ふっくらと瓣を開いた。
(虎)描写も一緒だし、日本語の美しさもあるよね。100年で「百」合なのもすごいよね。100年待ってるって答えたときに女どうした?
長い睫の間から涙が頬へ垂れた。
(虎)最後の百合見て。
そこへ遥の上から、ぽたりと露が落ちたので、花は自分の重みでふらふらと動いた。
(虎)涙との対比もすごい。描写も美しい。一見わかりにくいけど、イメージできちゃう。しかもすごいのが、死体埋めてるって結構怖いじゃん。そんな末恐ろしいことだよ、そんなの。でもそういう感じが出ないのは、真珠貝で掘ってるからだと思うんだよ。第一夜は特にすごい小説だと思うよ。あと、100年待つ、お百度参り、100年前にお前は俺を殺した、10円札100枚! 「夢十夜」は100が好き!
今回の特にサラサーテの盤は難しいなと思ってしまったけど、議事録を書きながら再読したら、怖さをすんなり楽しめた。難しく考えぎちゃうので、気楽に読んでいってみようと思いました。
次回以降、おぺんぺんの会はコロナを考慮して往復書簡のようなかたちで進めていこうと思います。
フランツ・カフカの「断食芸人」からスタートです!
(ラザニア)