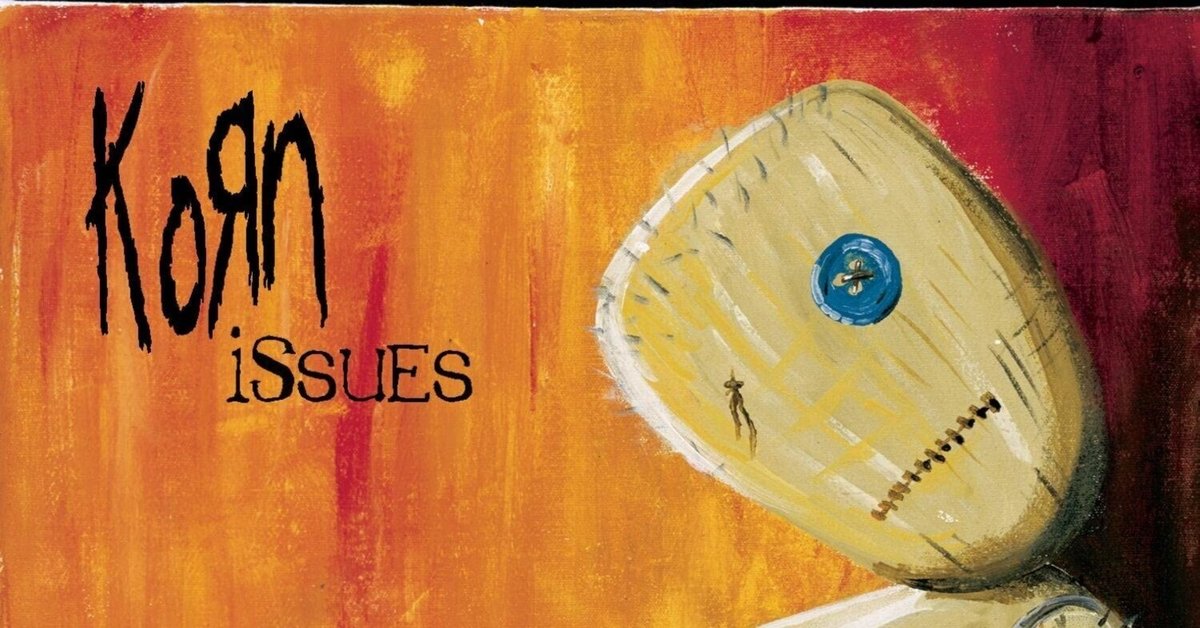
[過去原稿アーカイヴ]Vol.7 KORN『Issues』ライナーノーツ(1999年)
1999年にリリースされたKORNの4枚目のアルバム『Isuues』のライナーノーツ。通常ライナーノーツは4000字前後ぐらいを目安に依頼が来るが、この時は8000字近い大長編となってしまった。そのまま掲載してくれた当時の担当ディレクターには感謝している。なお文末には1997年に『ミュージック・ライフ』誌に寄稿したコラムを併載する。
今後過去原稿を続々アップしていきます。マガジン「過去原稿アーカイヴ」に登録をどうぞ。
https://note.com/onojima/m/m1f1bcef5c6a3
1年3ヶ月ぶりのKORNの新作である。ファースト・アルバム『KORN』から数えて、5年間で4枚のアルバムというのは、昨今の欧米のトップ・アーティストたちの制作タームがかなり長いものとなっていることを考えれば順調、いや異例なほどのハイ・ペースと言っていい。もちろんこれはKORNの高い創作能力と表現意欲のあらわれではあるだろうが、しかしその歩みは決して平坦なものではなかったはずだ。ことにセカンド・アルバム『ライフ・イズ・ピーチィ』(96年発表)からサードの『フォロウ・ザ・リーダー』(98年発表)を経て今作に至るまでの3年ほどは、バンド史上きわめて重大な転換期だったと言える。ことに、傑作と世評の高い前作『フォロウ・ザ・リーダー』は、このバンドあり方自体を問い直すような問題作であり、それにともなっておこなわれたツアーの数々は、過渡期にあった彼らを浮き彫りにしていた。まずはそのあたりから話を進めていこう。
それまでクリープという名で活動していた彼らがKORNとなったのは、ヴォーカリストのジョナサン・デイヴィスが加わってからである。つまりジョナサンが持っていて、他のメンバーにはなかったもの、それこそがKORNをKORNたらしめたと考えても差し支えないだろう。
それはよく知られているように、ジョナサンが幼児期から少年期にうけた数々の虐待やいじめによるトラウマが関係している。だがそんなワイドショーじみたスキャンダルを知らずとも、ファースト・アルバム『KORN』の尋常ではない暗さ、重さを聴けば、彼がどんな人生を送ってきたかわかるだろう。詳述は避けるが、そうした経験でジョナサンがため込んだ怨念や情念こそが、ヴォーカリストとしてのジョナサン・デイヴィスの最大のモチベーションだった。彼は決して、自分以外の誰かのために歌っていたのではなかった。抱え込んだ生き地獄のような苦しみと狂気を吐き出し微分化することで、心の奥底に負った理不尽なまでに深くて大きい傷を癒そうとしたのだ。そしてその情念の暴力的なまでの熱量が、KORNの音楽を他のヘヴィ/ラウド系バンドと圧倒的に峻別するポイントとなっていた。曲の最中で感情が高ぶって嗚咽してしまうショッキングな「Daddy」に顕著なように、ジョナサンの叫びは外に向かうのではなく、もっぱら自己の内面に向かっていた。それに応じて聴き手は否が応でも自己の内面に潜行していく。内奥に抱えたそれぞれの問題に対峙せずにはいられないのだ。それがKORNの音楽を、ひたすら重いものにしていたのである。
セカンド・アルバム『ライフ・イズ・ピーチィ』も、ほぼ同じ傾向を持った作品だった。ウォーの「ロウ・ライダー」をしゃれのめしたアレンジで取り上げるなど、ファーストには希薄だったユーモアのセンスを感じることができるが、アルバム全体から立ちのぼってくるのは、ジョナサンの抱えた空恐ろしいほどの絶対的な孤独であり、人間はしょせんひとりであり、ロックが唱えてきたはずの連帯も友愛もしょせんは幻想でしかないという冷めたシニシズムである。初めてこのアルバムを聴き終えたあとの、なんとも後味の悪い、灰を嘗めるような印象はいまでも鮮烈に記憶している。
だがどんなに耐えられないと思えた苦痛も、絶望的な悲しみも、重苦しい不安も、歳月を経るに従って癒えていく。生きていくということは、そうやって生々しく渦巻く情念を浄化し、風化させることだ。ジョナサンも例外ではない。『ライフ・イズ・ピーチィ』が全米チャート3位という成功をおさめ、愛する伴侶との間に子供もできた。ジョナサンを突き動かしていた狂気じみたルサンチマンは確実に薄れていく。吐き出さずにはいられなかった孤独の情念は、いつしか彼の中から消えていく。そういった状態で作られたのが前作『フォロウ・ザ・リーダー』だった。
もともと彼らはきわめて高いミュージシャンシップを持った職人集団、技術者集団としての側面を持っている。というより、ジョナサン以外のメンバーは、きわめて優秀だが、しかしジョナサンのような文学的契機を一切持たない職人気質なミュージシャンたちなのだ。そんな彼らが作り出すKORNのサウンド・フォーミュラは、展開が多く複雑な演奏、凝りに凝ったリズム・アレンジ、ネジれた音色など、他の同工のグループとは一線を画する個性を持っている。ジョナサンの重苦しいルサンチマンが薄れ、煮えたぎるような孤独の情念が拭い去られたあとに残ったものは、そうしたきわめて音楽的なバンドであるKORNの姿である。
彼らが来日したおりにヘッドと、フィールディにインタビューしたのだが、ジョナサンの書く歌詞や彼が歌うことで表現しようとしているものに関して、驚くほど無頓着なのが印象的だった。「あいつはシンガーで、あいつなりの仕事をこなしているだけさ。あいつのことなんて、なんにも気にしてないよ」、あるいは「音楽の進歩とはより複雑で高度な演奏ができるようになること」といった発言は、ジョナサン以外のメンバーがどのような姿勢でバンドの音楽に臨んでいるかをよく示している。それが顕著にあらわれたのが『フォロウ・ザ・リーダー』なのである。かってジョナサンを駆り立てた初期衝動が低下した結果、露わになったのはいわば「いかにかっこよく刺激的なヘヴィ・ロックを作るか」という一種の技術論であり、それまでのKORNを支えていた文学論ではなくなっていた。これはKORNというバンドのあり方そのものを根本から変えるような変化だったと言っていい。きわめてよくできてはいるが、前2作ほどの魂の深みには達していないアルバム、というのが『フォロウ・ザ・リーダー』に対するぼくの率直な感想である。
一方、立場がきわめて微妙になったのがジョナサンだ。自らを支えてきたモチベーションが低下しつつあったジョナサンは、その支えを観客との一体感に求めた。初めて自分以外の他者、つまり観客に対峙したのである。きわめて個人的なセルフ・セラピーであったはずの歌を、音楽を、観客に向かって放ち、共有しようとしたのだ。それは言ってみれば<トラウマ・エンターテインメント>とも言うべきものであり、初期のような切実な自己告白とはまったく位相の異なるものだった。そのあらわれは99年初頭の来日公演や、『ファミリー・ヴァリューズ・ツアー'98』のビデオにはっきりと見て取ることができる。同ビデオのライナーで石井恵梨子さんが指摘するように、観客に向かってマイクを差し出したり、歌詞の一部を唱和させたり、といった行為は、それまでのジョナサンでは決して考えられないものだった。
ロック・アーティストが大きな存在となるにあたっては、不特定多数の観客を巻き込んでいくダイナミズムが必要だ。ロックが大衆音楽である限り、不特定多数の大衆の意志を代弁する一種の民俗音楽である限り、それは避けて通ることができない。そして大衆を巻き込むにあたってもっとも手っ取り早く効果的なのは、歌の世界を送り手と聴き手が共有することだ。それは自然発生的に実現されることもあるが、アーティストが意図的に共有しやすい歌もしくは環境を提示することで、そのスケールは爆発的に増大する。KORNの場合、『フォロウ・ザ・リーダー』が全世界で450万枚というセールスをあげ、『ライフ・イズ・ピーチィ』をはるかに上回る商業的成功を収めたことがそれを証明している。「80年代LAメタルみたいなわかりやすいものを作りたかった」というメンバーの発言もそうだが、ファーストやセカンドがただ自分たちのために演奏されていたのに対して、いわばこれからKORNに接する子供たちのために作られているのである。そうしてKORN/ジョナサン・デイヴィスは、観客に向かってより広く開かれ、その歌の世界はより多くのキッズに共有され、支持された……。
だが話はここで終わらない。本来共有すべきではない、共有できない歌を共有したツケは確実にまわってくる。そうした歪み、ねじれにもっとも敏感だったのは、初期のジョナサンの叫びを我がこととして捉える豊かな想像力を持った一部のファンではあったろう。だがぼくは、ほかならぬジョナサンにそんな危機感があったのではないかと思えてならない。ジョナサンは新作に関して「ファーストのころのようにヘヴィになる」とオフィシャルのウエブ・サイトで発言していたらしい。それがどういう意図の言葉なのかよくわからないのだが、「モトリー・クルーのようなロックをやりたい」などとトンでもない放言をしていた他メンバーの意向に引きずられ、結果『フォロウ・ザ・リーダー』のようなのようなアルバムを作ってしまった、という思いが彼の中にあったのではないか、と邪推を巡らすことは可能だ。「ファーストのころの曲は今となっては単純すぎて物足りない」などと他メンバーは発言していたわけだが、そのようなアルチザン的・テクノクラート的な価値観とはまるでちがうところからジョナサンの表現はスタートしていたはずだからだ。
ぼくはいささかジョナサンの文学性に肩入れしすぎているかもしれない。だがファーストやセカンドから受けた異様なインパクトは、どう考えてもジョナサンという存在から発せられたものであることは明らかだったし、彼の並はずれた情念の放射がKORNの音楽に形式を超えた衝撃を与えたことも、また確かだったのである。その熱量が失われたKORNが、多くの凡庸なヘヴィ・メタルが陥ったような、形式主義が飽和した果てのドン詰まりにはまりこまないとは誰も言い切れまい。
ようやく話は本作『イシューズ』に移る。プロデュースはブレンダン・オブライエン。蛇蝎のごとく嫌っていたパール・ジャムのプロデューサーに頼んだのはいかなる理由なのか、各誌に掲載されるであろうインタヴューを待つしかない。収録曲のうち「Beg For Me」と「Falling Away From Me」は、先のウッドストックですでに披露されている。日本盤には日本のみのボーナス・トラックとして、ファースト・アルバム『KORN』のアウトテイクである「プラウド」という曲、さらに未発表のリミックス、ライヴなど5曲が入ったボーナス・ディスクが期間限定でつく。
なんと、ぼくの手元にある情報はたったこれだけである。歌詞の内容も明らかにされておらず、彼らがどのような意図で、どのようなテーマでアルバムを制作したのか、この時点で知る材料はない。だから断定するのはかなり危険なのだが、それでもなお、ぼくはこう言い切っておこう。これは前作『フォロウ・ザ・リーダー』に感じた不満を払拭し、なおお釣りがくるほどの深度と強度に達した傑作である。
お得意のバグパイプによるイントロから始まる小品にはいきなり「Dead」という全力投球なタイトルがつけられており、これからの波瀾万丈な展開を期待させるが、アルバム全体としてはむしろ淡々とした印象のものに仕上がっている。続く「Falling Away From Me」はいかにもKORNらしいヘヴィ・チューンだが、静と動を往還する曲構成、さらにジョナサンのヴォーカルが終始抑えめであることもあって、激しさや暴力性というよりはむしろ落ち着いた、静的な印象さえ受ける。「Trash」も同様に、ジョナサンの決して声高に叫ぶのではなく、なにかを希求するようなヴォーカルが印象的だ。そして続くスピリチュアルと言いたいほどの静寂感の漂うスロウ・チューン「4U」で、このアルバムの印象は決定づけられる。つまりこのアルバムは、もちろん従来の彼らを性格づけていたヘヴィ・チューンもふんだんに盛り込まれてはいるが、総体的な印象としては決してヘヴィではない。いやもっと正確に言えば、これみよがしな音響的なヘヴィネスは、ここでは追求されていない。にも関わらず、ここでのKORNの音楽、ジョナサンの歌はとてつもなく重く聴こえる。
ヘヴィな音楽とは何か。たとえばエレキに深いディストーションをかけまくって音を歪ませたり、イコライザーで低域の60ヘルツ近辺を極端にブーストすれば、音響的なヘヴィネスは簡単に作り出せる。KORNほどのテクやセンスがあれば、巷の様式メタル・バンドがそうであるように、はったりじみたダイナミクスで圧倒して表面的なヘヴィさを演出することはいとも簡単だろう。だがそんな音響・演出効果は慣れてしまえばそれっきりだ。むしろKORNは、人間の内奥に深く分け入って深層を抉りだしていくような、そんな内面的なヘヴィネスを追求しているように思えるのだ。ここでのKORNの音楽には、安易に同化することを拒否する、ある種の厳しさが漂っている。それは『フォロウ・ザ・リーダー』でのわかりやすさ、共有されることを前提とした形式主義とははっきりと異なる位相にある。
先に引用したジョナサンの「ファーストのころのようなヘヴィなアルバムにしたい」という発言を聞いてぼくはいくばくかの不安を覚えていた。ファーストのヘヴィネスの根源はジョナサンの抱えた巨大な心の空洞にあったことは明らかであり、今の功なり名遂げた彼にそんなものは求められない。つまりは内実もないまま表面的なヘヴィネスを偽装するか、音響ヘヴィネスではったりをかますか。ぼくが恐れていたのはそれだった。
ところが、ジョナサンの抱えていたルサンチマンの大きさは、たった5年やそこらで、ちんけな小金を得たところで払拭されるようなものではなかったし、彼のぱっくりと開いた傷口から流れ出る血は、少々の小市民的幸福を得たところで、癒されるものではなかったのである。一旦狂気の淵にまで追い込まれ、魂の臨界点を超え自分の中にあるなにもかもを吐き出し、なお嗚咽を続けるまでに歪んだ心は、完全な塑性変形を起こしてしまっていた。重度の覚醒剤中毒患者が、完治したように見えても執拗なフラッシュバックに悩まされるように、一度極点まで行った者の見る景色は、決して以前と同じではありえないのだ。
『ミュージックライフ』誌98年10月号には、レコード会社のKORN担当である井上ヒロカズ氏によるフジ・ロック来日時の興味深いリポートが掲載されている。それによるとジョナサンは、インタヴューで幼年時代に関する質問を受け続けるうちに心身症気味になり、インタヴューに応じることさえできなくなったという。まったくなんという業の深さか。
ふつうであれば時とともに忘れていく情念や怨念を、その都度呼び戻しふさがりかけた傷口を無理やり押し開き砂を擦り込むように刺激する。プロのミュージシャンとして活動し始めた5年あまり、ジョナサンはそのようなことを繰り返してきたのである。
もちろん、レコーディング中に感極まって嗚咽してしまうような激情は、ここにはない。以前のような狂気じみたルサンチマンやオブセッションもない。「Hey Daddy」などという、なにやらパロディめいたタイトルの曲もある。表面的には静かな川面を見るように穏やかで静的なジョナサンがいる。だが川底を覗き込めば、一旦摂取したら軽く10年はイッたままになるような強烈なドラッグに浸かったジョナサンの孤独な魂が転がっているのが見えるのだ。
KORN、レイジ・アゲンスト・ザ・マシーン、リンプ・ビズキットといっしょくたにして「新世代モダン・ヘヴィネス」というような言い方をする。確かにヘヴィ・メタルやハードコアをベースにファンク、ヒップホップの要素を加えたミクスチュア・サウンドという点で、彼らには共通点があるし、ぼく自身も軽い気持ちでKORN・レイジ・リンプと三大噺めいた言い回しで語ることがある。だが考えるまでもなく、これらはまったく異なる存在なのだ。
レイジにとってもっとも重要なのはそのポリティカルなメッセージであり、音楽はそれを伝えるための手段に過ぎない。メッセージである限りはできるだけ多くの人たちに共有されねば意味はない。奇しくも同時期に発売される新作も、そのような方向性は堅持されている。いっぽうリンプのやっていることは、ライヴなどを見れば顕著だが、ソツのないエンターテインメントという以上でも以下でもない。エンタテインメントである限りは、聴き手に共有されるか、ハリウッド映画のような良くできた絵空事の世界を作り出して客の興味をつなぎ止めるしかない。
KORNはそのいずれともちがう。彼ら、いやジョナサンにとって音楽表現は共有すべきメッセージでも、よくできたフィクションでもない。ただ丸裸な、十全な自己の魂を、反吐を吐くように打ち付けていくものなのだ。
『イシューズ』を聴いてぼくは、まるで寒風吹きすさぶ荒野にたったひとり取り残されたような、ひどく寂しげな空気を感じた。彼らは結局共有すべき幻想もメッセージもフィクションもないのだ。そこにあるのは周囲の狂騒とはまるで関係なく、ただ絶対的に孤立した者の姿である。そんな彼らにもっとも近い場所にいるのは、これまた新譜を出したばかりのナイン・インチ・ネイルズであり、両者が共通して抱えるテーマは、「コミュニケーションの不全」である。それが現代に生きるぼくたちにとってもっとも重要な案件であることは論を待たない。
このアルバムの発表にともない、彼らはツアーを開始するはずだ。そこでジョナサンはどんなパフォーマンスを見せるのか。デビュー時のような、客の方をまったく見ようともせず、ただマイクにすがりついて絶叫しているような自閉症的ライヴが、また再現されるとは誰も思うまい。おそらくは客席に手を振り、マイクを向け、唱和を促すエンタテイナー・ジョナサンを確認できるだろう。だがそれは、今にも壊れそうになる心の欠片を必死に拾い集め、自我という鎧で守っているような光景にちがいない。そんな妄想じみた思いにとらわれてしまう『イシューズ』は、ミレニアムの終わりに産み落とされた異形の傑作である。
1999年10月17日 小野島 大
(以下『ミュージック・ライフ』誌所載のコラム。1997年)
先月号のメガ・ロック大特集、おもしろかったなあ。写真見るだけでも大爆笑。ぼく個人は同時代的にはパンク/ニュー・ウエイヴ系しか関心なかったから全然お馴染みのないバンドばかりなんだけど、なんだかとっても楽しそう! だいたい当時のイギリスのニュー・ウエイヴ系って陰々滅々としてて、貧乏臭くて、第一全然楽しくなかった。見る側もそうだし、演る側もそうだったと思う。そのように楽しくない音楽を深刻な顔して演ったり聴いたりしていたのは、そうせざるをえない切実さがあったからだ。その一方でアメリカのメガ・ロック系を馬鹿にするのが自称ツウのニュー・ウエイヴ系ロック・ファンの典型的メンタリティだったわけだが、いま思えばそうアタマから毛嫌いせずに、ちょっとは体験してたら良かったかなあ、と少し後悔してしまった。
意味もなくゾロゾロと登場するパツキンのネーチャン、空を飛び、派手派手な光をまき散らし、グルグルとドラム・セットは回り、股間は不自然に膨らみ……そりゃ、毎日女の子と遊び回り、デッカイ車を乗り回し、クスリや酒をやり放題、湯水のように金を使いまくって、それで世の中八方丸く納まってりゃ言うことない。思えばバブルのころってそうだったのだ。L.A.ガンズの人がしみじみと「忘れたくないよ。素晴らしい思い出だから。本当にエキサイティングな時期だった……」と、遠い目で(?)そういう時代を懐かしんでいるさまが、思わず涙を誘う。いやあ、人生いろいろですな。
時代は移り、景色は変わった。今それまで傍流(オルタナティヴ)と呼ばれていた音楽がメインストリームになった。
コーンのセカンド・アルバム『ライフ・イズ・ピーチィ』は、なんと全米チャート初登場3位を記録した。この音で全米3位かよ、なんて思うのはぼくがズレているということなのか。ストレートにフラストレーションを発散できるようなタイプの音ではない。演奏やアレンジはかなり複雑だし、サウンドは相当に暗く、救いがない。歌詞カードがついていないので歌詞について言及はできないが、いずれにしろ温かい愛や明るく輝かしい未来やパツキンのネーチャンについて語っているとはとても思えない。全体にゴツゴツとして、暗闇の中を手さぐりで進んでいくような、そんな感覚がつきまとっている。さらりと流れていかない。聴き流そうと思っても、いちいち躓く。ひっかかる。どこかで同化することを拒否するような冷たさがある。このいびつな感触はなんなのだろう。
80年代型メガ・ロックが飽きられてしまったのは、80年代型の、なにもかもスムーズに進行していくことへの決まり悪さ、みたいなものだと思う。
いわゆる80年代型メガ・ロックのレコードを聴いていて(少しは持ってるのだよ)思うのは、起承転結がすごくはっきりしているということ。一通りのものはすべて揃っていて、それが順を追って流れるように進行する。お金を払ったぶんはたっぷりと楽しませてくれる。破綻というものがまるでない。どんなにハードなロックンロールをやっていても、最終的には落ちつくべき場所に向かって整然と進行していく。
カタルシスというのはロックを聴く際に重要なポイントのひとつだが、聴き手がその音楽の構造を承知していればいるほど、それは容易に得ることができる。ある種の様式的なヘヴィ・メタルがいつまでも需要を失わないのは、そういう理由だろう。
だが世の中、そうそうスムーズにコトが進行するとは限らない。金持ちの家に生まれた子はとてもハンサムでスポーツもできて頭も切れてギターもうまくて性格も良くて、みんなに愛され仕事も大成功、美しい奥さんと可愛い子供に恵まれメデタシメデタシ……なんてことばかりなら世の中苦労しない。どうもおかしい、こんなに何もかもうまくいくはずがない……80年代型メガ・ロックのそうした楽観主義に対してのカウンターが、90年代以降に顕著になったわけだ。聴き手はそういうことを訴えるアーティストに対して共感し、思い入れを持って聴くようになった。パール・ジャムはその典型だろう。
だがコーンの音楽は、それとも違うような気がする。コーンの内包しているネジ曲がった異物感は、共感とか思い入れといったベタついた感情を一切拒絶しているように思える。どこか、自分の抱えている問題はいつまでたっても個的なものであり、それを理解してもらおうとは思わない……と言いたげな、醒めた感覚があるのだ。聴き手ばかりか、自分自身でさえ突き放し、客観的に見てしまうような、シニカルなユーモア感覚。だから彼らの音はどのサークルやジャンルからも隔絶した個性的なものであり、それゆえにひどく孤立しているような印象を受けるのである。そういうありようは、ぼくが知っているアメリカン・ロックの伝統とはちがう。むしろ70〜80年代のイギリスのニュー・ウエイヴに近い。聴いていて楽しくなるような音楽ではないこともそうだし、それでも耳を傾けずにはいられない切実さがあることも同じである。人間だれしもがひとりなのだ、どこまで行ってもひとりなのだ、と。そういうことだ。
バブリーな80年代型メガ・ロックの隆盛から10年。まるでおとぎ話ののようなキラびやかな彼らの世界を、うらやましく思うときもある。だがそこに後戻りできないことも、また確かなのだ。
よろしければサポートをしていただければ、今後の励みになります。よろしくお願いします。
