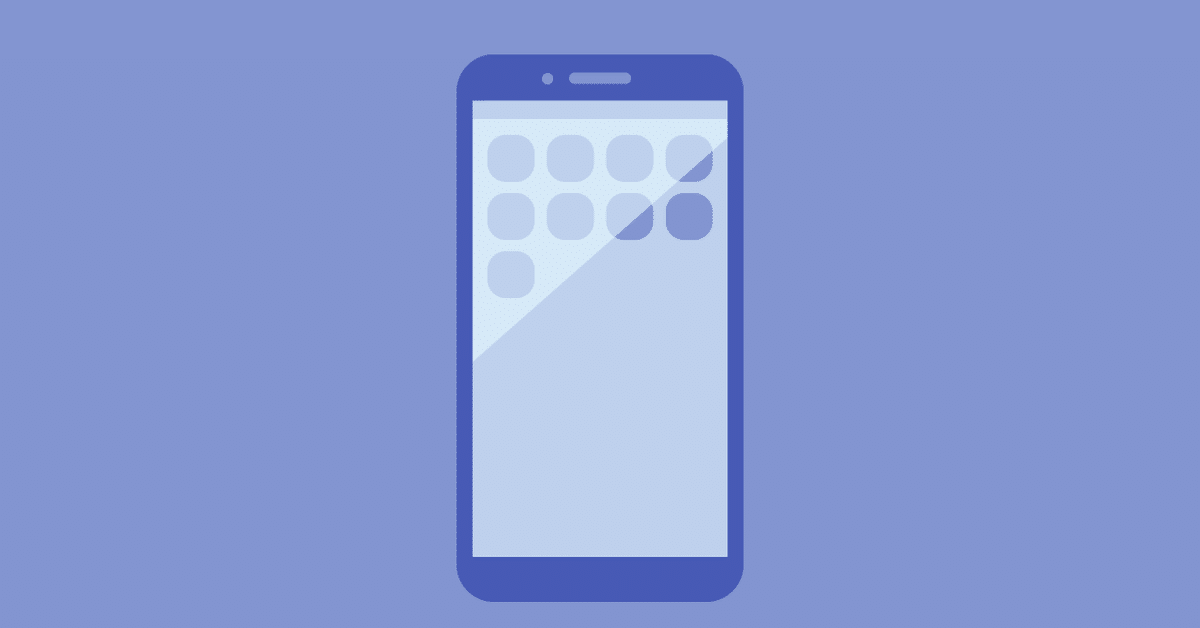
【黄昏学園SS-7】価値観と劣等感 ー友達の登録ー
キッチンの作業台にコップを置いて、冷蔵庫から出したペットボトルの緑茶を注ぐ。
きれいな薄緑色が揺らぐコップをお盆に乗せているうちに、自然と左手の小指に視線がいった。
榎本さんに「何かこれ恥ずかしくないっすか?」って言ったけど、恥ずかしさと一緒に、こそばゆいような嬉しさがあった。
ゆびきりなんてしたの、いつぶりだろう。
今はもう友達と呼べるような人はいないものの、おれもうんと小さい頃に、さっきみたいに友達と小指を結んだ。その約束の内容はおろか、小指を交わした相手の顔すら、おぼろげで覚えていないけれど。
──ああ、そうだ。それから。
『ことくんは泣き虫だねえ。もっと強くならなくちゃ。強くなって、弟のたっくんと、お姉ちゃんのいおちゃんのこと、守ってあげなくちゃ。できる? じゃあ、ママと約束ね。ほらことくん、ゆびきりげんまん──……』
ずいぶん昔の話だ。
物心ついて間もない頃だったと思う。
おれはお盆をリビングに運んで、ソファーの前のローテーブルにコップを置いて「どうぞ」と榎本さんにお茶を勧めた。
彼女は短く「ああ、感謝する」と礼を言って、静かに緑茶に口をつける。
何かお菓子もあった方がいいかな。
収納庫の扉を開いて、ガサガサとお菓子を漁る。ポッキー、プリングルス、ホームパイ、バームロール、ぷち大福、かっぱえびせん。姉ちゃんは最近ダイエットだって言って食べないけれど、おれと竜希は夕食までお腹を空かせていることが多いので、塞翁家にはお菓子のストックが大量にある。
「……あの、榎本さん」
目を合わせていない気軽さから、おれは彼女に声を掛けた。
視線の端で榎本さんが顔を上げる。おれはあえてそっちを見ないようにして、お菓子の袋をいくつか持って、キッチンへ行った。
「さっきの話なんすけど、実はおれのところも同じなんすよ。だから、話聞いててびっくりしました」
「さっきの話? どの話のことだ?」
「お母さんが、心の病で別居してるって話」
榎本さんが口をつぐんだ。
気まずい沈黙を埋めるために、おれはあえてお菓子の袋を大きな音を立てて開ける。食器棚から普段はサラダを盛り付けている木の鉢を取り出して、お菓子を小分けにして乗せていく。手を動かしながら、おれは続けた。
「だから、お母さんに元気になってほしくて、とびきりの良いニュースを伝えたくて、そのために依頼をこなしてる榎本さんの気持ちは、おれにも分かるような気がして」
今ではもう、母さんにとって恐慌の引き金でしかないおれには、けっして真似できないけれど。
「そうか……」と榎本さんがつぶやいた。
はい、と短く返事をする。
「それで」
おれはそこで言葉を切って、お菓子を盛った木の鉢を榎本さんの前に置いた。
榎本さんが「それで?」と鸚鵡返しにして、立っているおれを見上げている。
おれはあえて分かりやすく、目を細めて、にやりと笑った。
「それで、ますます榎本さんにお節介を焼かない訳にはいかなくなったっす」
いつも伏せがちな榎本さんの目が、大きく見開かれる。
一瞬の沈黙。
しばらくして、彼女は溜め息をついた。その顔には呆れと、一周まわって晴れがましいとでも言いたげな微笑みが浮かんでいる。
「……しつこく食い下がるのは身をもって知ったつもりだったが、織田君が塞翁君のお節介は折り紙つきだと言っていたのはこういうことか。どうやら門前の虎を選んだのは大きな間違いだったようだな」
「え、ちょっと待って。オダネネ、榎本さんにそんなこと吹きこんでたんですか!? それになんすか、門前の虎って」
「いや、こっちの話だよ。今更選択を悔やんでも、塞翁君は拘束を止めないだろうし」
「拘束って!? 榎本さん、オダネネにどんな話聞いたんすか!?」
わめくおれを無視して、榎本さんはぷち大福をひとつ手に取った。個包装を開けて、片手を添えて大福を口へと運ぶ。
学校の食堂で一緒にオムライスを食べたときから思っていたけれど、榎本さんは所作が丁寧で、綺麗に物を食べる。その大福くらい、おれのことも丁重に扱ってほしい。
榎本さんは、もむもむと大福を咀嚼して飲み下したあと「うまい」と小さくつぶやいた。
「あ、ですよね。これ業務スーパーのやつなんすけど、おいしいからリピ買いしてて」
「ふむ……最近の小売店の商品は、和菓子屋に勝るとも劣らないのだな。もうひとつ頂こう」
「どうぞどうぞ。好きなだけどうぞ」
「塞翁君は? 君もあれだけ走ったんだ、喉が乾いただろう?」
榎本さんの向かいを、五指を揃えた手でやんわりと示される。
どうやら同席を促されているらしい。
「あ……どもっす」
頭を下げて、おれは台所に行って緑茶をコップに注ぎ、それを持って榎本さんの向かいのクッションの上であぐらをかいた。
榎本さんの目の前で飲んだり食べたりするのは避けたかったけれど、せっかくの好意を断るわけにもいかない。
片手で黒マスクを伸ばして持ち上げ、あごの方にできた隙間からコップを差し入れて、緑茶を飲む。そんなおれの様子を、榎本さんが大福を食べながらじっと見つめている。なんだか視線が刺さって、いたたまれない。
「……大福も食べるといい」
「は、はい」
勧められるまま大福を手に取る。
個包装を剥いて、またマスクを持ち上げて大福を差し入れて、手を離してマスクをもとに戻し、大福を咀嚼する。
……やっぱりじっと見られてる。
おれは気まずくなって、視線を足もとに下げた。
こくんと大福を飲み下し、居心地の悪さをごまかすように笑う。
「ん、やっぱりおいしいっすね」
「……塞翁君」
改まった様子で名前を呼ばれて、おれは顔を上げて「はい」と硬い声を返した。
榎本さんが真剣そのものといった表情のまま、口を開く。
「私はよくヤクルトを飲んでいる」
……何の話?
ぽかんとするおれに構わず、榎本さんは続ける。
「祖母が頼んで、定期便で届けて貰っているからな。ヤクルトを常飲しているおかげで免疫力はバッチリで、最近では風邪ひとつひいたことがない」
真剣な表情のまま、ぐっと親指を立てる榎本さん。
へえ、ヤクルトって凄いんだなあ。おれも体調管理のために飲もうかな。
そんなことを考えるおれをよそに、榎本さんは迷いのない目をおれに向けた。
「だからな、塞翁君。たとえ君が万年風邪気味で、私にうつすまいと家のなかでもマスクをつけているなら、それは思慮が過ぎるというものだ。ここは君の家だ。私に構わず、マスクは外すといい」
あ。
あー……。そういう……。
「や、えと、ちがくて」
おれはあわてて否定した。
「おれは万年風邪気味でマスクをしてるんじゃなくて……その、自分の口もとが、好きじゃなくて」
「……口もとが好きじゃない?」
「そう。だから、マスクをしてるんす」
人より発達した八重歯と、その八重歯のせいで締まりがない口と、口の下にあるほくろが──自分の口もとが嫌いだ。やかましくてガチャガチャしていて、すごくみにくい。
昔はそんなこと考えもしなかった。
けれど、あの「塞翁小虎」が世に出回ってから、おれは自分を強く印象づけるであろう口もとが、どんどん嫌いになっていった。
今では家族以外に口を晒すのが嫌で嫌で仕方ない。
さすがに食事時はマスクを下げているけれど、それでも人の向かいで物を食べないようにしたり、できるだけうつむいたりと、おれなりに口を直視されないよう、いろいろ工夫をしている。
そんな事情は伏せて要点だけを伝えると、榎本さんは「ふむ」と相槌を打った。
「興味深いな。記憶にある限り、そんな奇妙な口ではなかった気がするが……。どれ、今すぐ私に見せてみるといい」
榎本さんは、さらりとそう言った。
「え、ええ……!?」
たじろいで後ずさるおれに、榎本さんが顔を近づけてくる。
しまった。人に口もとを見られるのが嫌だって、はっきりそう言えば良かった。
おれは訂正しようとして──榎本さんの視線に囚われる。
だめだ。おれを見る眼がきらきらしている。どうしよう。これ、好奇心に火がついた顔だ。
榎本さんはこうなると止まらない。だから畢生綴りの件では、榎本さんに危険が及ばないように、彼女が興味を持ちそうな情報を伏せて、八色さんに報告をしたのに。
……丁重にお断りしたい。
そう思ったおれの脳裏に、ついさっき自分が口走った言葉が雷のように走った。
不平等。
榎本さんを説き伏せた言葉が、今度はおれに襲い掛かってくる。あれだけ食い下がって、彼女が言いたくないことを吐かせたのに、ここで榎本さんの提案を断って自分を守るのは、不平等じゃなくて何なのか。
「うぅ……」
うなった挙句、おれはついに観念した。
片耳の後ろに指をかけて、ピアスに引っかけないよう気をつけながら、黒いウレタンマスクを外す。
羞恥で自然と視線が下がる。覆う物がなくなった口もとが外気に晒されて頼りない。恥ずかしくて顔が熱くなってきた。
おれは覚悟を決めてこぶしを握り、ぎゅっと目をつむって顔を上げて、榎本さんに向かって「あ」のかたちに口を開いた。
目を閉じていても、じっと見られているのが分かる。
なんだか汗かいてきた。ここは歯医者かな。歯医者より嫌だな。はやく終わらないかな。はやく帰りたい。いや、ここがおれの家なんだけど。
しばらくして、急にほっぺたをつまんで伸ばされる。
「っ!?」
何? なにごと?
驚くおれをよそに、ほっぺたが上に持ち上げられる。
あ、そっか。「あ」だと八重歯が見えにくいんだ。オダネネのときみたく「い」の口にすべきだった。でも今さら急に変えたら、今度は榎本さんがびっくりする。
おれは観念して、されるがままになった。
オダネネに口を見せたときは、パーティーの高揚も手伝って、そんなに恥ずかしくなかったんだけどな。相手がある程度気心が知れたオダネネだったし。
オダネネは、おれのコンプレックスを否定せずに、受け入れてくれた。
でも、榎本さんは?
悪いものは悪い、間違ってることは間違ってる、変なものは変って、思ったことをはっきり言いそうだ。
永遠のような一瞬が終わった。
手が頬から離れる。榎本さんの気配が遠ざかる。
おれはゆっくりと目を開けた。
目の前に、あごに手をあてて考えごとをしている榎本さんがいる。
しばらくして、彼女はおれに視線をやって、こう言った。
「成程。塞翁君が自分の口を恥じているのは、名前負けしているからか」
「え」
短い一音を発して目をまるくするおれに構わず、榎本さんはうんうんと頷いてみせる。
「いくら小と冠されていても、虎は虎。自分の未熟な牙が好きではないのだろう?」
え? 未熟な牙?
呆然とするおれをよそに、榎本さんはふいにやわらかく笑った。
「……案ずることはない。君のその目立たない小さな牙も、私は好ましいと思うよ」
──おれは言葉をなくした。
そんな風に言われたのは、初めてだった。
おれは込み上げてくる感情を止められなくなって、
「ぷっ」
と、小さく吹き出した。
すぐに笑いを抑えようと「くっ」と息を殺したけれど、一度笑いだすともうだめだった。
「ふはっ」と声に出した途端、我慢できなくなって「あはははは!」と腹を抱えて笑い出す。
名前負け。
目立たない。
だめだ、ひさしぶりにツボに入った。榎本さんが眉根を寄せておれを見ているのに、笑いが止まらない。涙目でひーひー言いながら爆笑していると、榎本さんの眉間にしわが寄った。
「あ、違……っくく、あの、決して、ばかにしてるんじゃ……っ、ふはっ、なくてっ」
「笑いながら言っても説得力がないぞ」
「そ、そうっすよね! ……っく、す、すみませんっ」
おれは目もとをぬぐって、急いで呼吸を整えた。まだ弾む息のまま、なんとか榎本さんに弁解する。
「……あの、笑ったのは、おれの悩みが、ばかみたいだなって思ったからで」
本当にばかみたいだ。
榎本さんからしてみれば、おれが特徴的だと思っていた八重歯は、それくらいのものでしかないんだ。
おれは彼女に頭を下げる。
「榎本さんの物の見方に救われました。……ありがとう」
お礼を言っても、榎本さんは「うん……うん?」とつぶやいて、頷きとも小首をかしげるともつかない角度で、曖昧に首を前に倒している。
それくらい彼女にとっては、さっきの発言は特別でも何でもないことだったんだと分かって、おれはますます嬉しくなった。
オダネネが榎本さんを「おもしれー」と言っている理由が分かった気がする。
榎本さんは既存の物の見方に捕らわれない。榎本さんならではの視点で物を見て、思ったことを口にする。
彼女の価値観に、困惑する人もがいるのも理解できる。でも榎本さんは気づいていないかもしれないけど、そんな視点もあるんだって、そう気づいて気持ちが救われた人は、おれの他にもいるんじゃないかな。
このことを伝えたい。
でも、今言ってもさっきのお礼のように、おれの言葉は榎本さんに届かないだろう。
まだおれは榎本さんと、そんなに言葉を交わしていない。オダネネのような信頼だって得ていない。
おれのことも信じてほしい。
困っているなら助けたい。
力になりたい。
お節介や心配とはまた別の角度から、そんな気持ちがむくむくと沸き起こる。
「そうだ、榎本さんってLINEしてます?」
おれはポケットからスマホを取り出して尋ねた。
「突然何だ? 私も花の女子高生だから、友達の織田君とLINEくらいはしているが」
「良かった。じゃあ、おれとも交換してください」
「何故友達でもない塞翁君と私が、LINEを交換する必要があるんだ?」
悪気は一切ないんだろうけど、ちょっと言葉のナイフが刺さった。
めげずにおれは言い返す。
「依頼を手伝うなら、連絡は必須じゃないっすか」
「別に解決部のDMで良いだろう」
「解決部の誰にも言えないことを、解決部のDMで? 誤送信したらどうするんすか」
「む……確かにそうだな」
こうしておれは榎本さんとLINEを交換した。
友達登録(思えば、家族や知人や企業かもしれないのに、この総称はどうかと思う)を済ませてすぐ、おれは「グループLINE立ち上げるんで、やりとりはそっちでしましょう」と言った。
学校の人達に声を掛けられてもLINEの交換は断っているのに「榎本沙霧」の名前があるのは良くないと思ったからだ。榎本さんも「塞翁小虎」の名前があるのを見られたら、困ることだってあるだろう。その点グループLINEなら、グループ名が表示される。
「グループLINE? 二人なのにグループでいいのか?」
「榎本さん、実はグループLINEは一人でも作れるんすよ」
おれはそう言ってトークルーム作成のアイコンをタップした。
同時に、玄関から「ただいまー」の声がする。
……あ。しまった。
すっかり忘れてたけど、この状況はまずいかも。
おれが焦っているあいだにも「はーもー、竜希連れてって良かったわ、駅前スーパーの特売ヤバすぎ。牛乳も鶏肉も底値でさー、小虎も一緒なら、お一人様一パック限りの卵、もう一個攻められたのに」と伊織姉ちゃんが喋りながら廊下を歩いてきて、リビングのドアを開ける。
ドサッ、とエコバックが床に落ちる音がした。
伊織姉ちゃんの視線は、榎本さんに釘付けだ。
「小虎、あんた……」
絶句する姉ちゃんに、おれはあわてて口を開く。
「あ、えと。姉ちゃん、こちら解決部の仲間の」
「うおっ、小虎が女連れ込んでやがる!?」
姉ちゃんのあとにリビングに入った竜希が、いきなり爆弾を落とした。
「竜希!! 言い方!!! 榎本さんに失礼!!!!」
おれが怒鳴っても、竜希は榎本さんをものめずらしそうに、しげしげと眺めている。
注目を浴びている当人の榎本さんは、誤解を受けているのに気づいているのかいないのか、トレードマークの学帽を取って「黄昏学園高等部一年、榎本沙霧だ。塞翁君にとっては解決部の後輩にあたる」と言って、綺麗なお辞儀を披露した。
「うわ丁寧な子! あたしは塞翁伊織。小虎の姉ね。こっちは弟の竜希」
竜希の頭をつかんで強引に下げさせている、姉ちゃんの表情はどこか嬉しそうだ。
姉ちゃんはうきうきした足取りでキッチンに行って、エコバックを漁りはじめる。
「沙霧ちゃんチョコレート好き? リンツ買ってきたんだけどさ、ウチの男どもは質より量だから、あげるのもったいなくて。良かったら一緒に食べない?」
「あれ? 姉ちゃんダイエットは?」
「だまれ小虎」
ドスの効いた声で凄まれて、おれはリビングのすみっこで小さくなった。
すぐにダイニングテーブルで、コーヒーとチョコレートの女子会が開かれる。
姉ちゃんは榎本さんと喋りながらよく笑ったし、いつもはお菓子を持ってさっさと自分の部屋に引き上げる竜希も、なぜかソファーに座って、テレビで休日の昼間特有の通販番組なんかを見ている。
「沙霧ちゃん、小虎は解決部ではどう? みんなに迷惑かけたりしてない?」
「いや、よくは知らないが……塞翁君はよく解決部の仲間に、親しげに声を掛けられているよ」
「へー……小虎が」
「姉ちゃん、その意外そうな声はどうかと思う」
「小虎はちょっと黙ってて。じゃあさ、沙霧ちゃん個人としてはどう? 小虎ちょっと天然だからさ、困らされたりとかしてない?」
問われた榎本さんは「困らされたこと……」と宙を見上げた。
それから「ああ」と声を上げて、左手の小指に視線を落とす。
「そういえば今日、しつこく塞翁君に迫られて、契りを交わす羽目になったのは、些か困らされたと言えるか」
「「は!?!?!?!」」
姉ちゃんの声と、盗み聞きしていた竜希の声が、綺麗にハモる。
「……小虎、あんたまさか」
「マジかよ、ありえねえだろ」
軽蔑とも殺気ともつかないふたつの視線が、おれに襲い掛かってきた。
「違う!!!! ゆびきり!!!!」
おれはたまらず、リビングが揺れるくらい大きな声で叫ぶ。
◆ ◆ ◆
塞翁家を後にする頃には、外は薄暮の薄闇に包まれていた。
「榎本さん送ってくる」と塞翁君は言い「またいつでも来てね」と微笑む伊織さんに見送られて、私は塞翁君と屋外に出た。
玄関扉が閉まると同時に、塞翁君は私の手を引いて、家の裏手に連れて行く。
「これだけ時間が経ってたら大丈夫だと思いますけど、念には念をってことで」
そう言って、塞翁君は着ていた白いコートを脱いで私に被せてきた。
彼にとってもオーバーサイズのコートは、もともと着ているインバネスコートを脱ぐことなく楽に羽織れるのは利点と言えたが、私が着ると丈が長すぎる。
「手が出ないんだが」と文句を言うと「帰宅まで我慢してください」と言われて、今度は塞翁君の付けていたチェックのマフラーを、首もとにぐるぐる巻きにされた。
どうやら塞翁君は、服装の印象を変えることで、もし追っ手がいても気付かれないように工夫をしているらしい。
最後に学帽を外されたので「それは私が持つ」と言い張った。
もこもこに着込んだ私は、薄着の塞翁君の先導のもと、路地裏の道を歩き始める。彼の肩には、IKEAの青い大きなショッピングバッグが下がっている。中身はあのアタッシュケースだ。空だったそれには、今は塞翁君の旅行用品が詰まっている。勿論旅行用品はフェイクだ。灰谷と連絡を取り、無事にアタッシュケースを処分できたら、中身を塞翁君に返却する手筈になっている。
「アタッシュケースは隠さずに持ち帰って下さい。もし家の人に、それは何だって聞かれたら、解決部の仲間から預かった荷物だって言ってください。おれの名前を出してもいいんで」と塞翁君は言った。
確かに、こそこそとアタッシュケースを隠して持ち帰った後に、祖父母に見つかって言い訳をするよりも、普通の荷物のように堂々と持ち帰った方が、祖父母に怪しまれる可能性は低くなるだろう。
塞翁君は黙って私の隣を歩いている。
私の吐く呼気が、白くわだかまっては消えていく。
路地裏はひと気がなく、しんと静まりかえっている。さっきまでいた塞翁家は、あんなに賑やかだったのに。
うつむいてマフラーに顎を埋めると、ほのかに塞翁君の整髪料の匂いがした。
つられて、塞翁家は活気があって、雑多な生活の匂いがしていたなと思い出す。厳粛で静かな私の家とは、まったく違う匂いだった。
いつもの癖で学帽の鍔に触れようとして、今は学帽を被っておらず手も出ないことに気付いて、私は手慰みに袖で前髪を撫でつける。
途中で道案内を交代して、私と塞翁君は言葉少なに帰路を辿る。
家の手前の曲がり角で、私はコートとマフラーを塞翁君に返した。
「もうここでいい。私の家はあれだ」
「榎本さん家って和風なんすねー……」
受け取ったコートを着込みながら、塞翁君が私の家を見上げている。
最後にアタッシュケースを受け取った私は「世話になった」と塞翁君に礼を言った。
「いや、なんだかんだ助けられたのは、おれの方かもしれないんで」
「どういうことだ?」
「こういうことっすよ」
そう言って、塞翁君は黒マスクを顎まで下げて、笑顔を見せた。
そんなに牙を褒められたのが嬉しかったのだろうか。
良く分からないが、風邪でないのならマスクは外した方がいい。その方が表情も分かりやすい。
私は彼に笑みを返した。
「これからしっかりおれを頼ってくださいね」
「……善処しよう」
「秘密がバレたのがおれなんかで、頼りなく思うかもしれないっすけど、これオダネネや解決部だけじゃなくて、御家族にも誰にも言えないことっすよね?」
一人でどうにかしようと思ってたんでしょう? と塞翁君が言う。
私は黙り込んだ。アタッシュケースの処理の提案を私が受け入れた時点で、依頼の件を家族にも内密にしていると、塞翁君は確信したのだろう。
私の内心を見透かしたように、塞翁君は八重歯を見せて、ニッと悪戯っぽく笑う。
「残念でした。おれ、榎本さんを一人になんてさせませんから」
◆ ◆ ◆
塞翁小虎。
私は自室でパソコンと向き合い、解決部の掲示板を開いて、彼名義の発言をスクレイピングする。
検索タグを打ち込むと、解決済みと情報提供が何件か引っ掛かった。それら一件一件に視線を走らせて、解決部における塞翁君の働きを確認する。
神保町へ聞き込みに行ったりするなど、意外と行動力はあるようだ。
私が依頼を出した血濡れナース事件では、バイト先の先輩から話を聞いて情報を得ている。あれだけ反発しあっていた織田君と、最近よく一緒にいることを加味すると、彼は人の気持ちを汲む術に長けているのかもしれない。
この先誰かの嘘や本心を探らなければいけない場面、もしくは交渉事において、私では気付かない他人の心の機微に、彼ならば気付ける可能性がある。
勿論、厄介事に塞翁君を巻き込む訳にはいかないのだが……。
ピンポン、とLINEの通知音が鳴った。
私は机に裏返していたスマホを手繰り寄せ、ポップアップをタップする。
塞翁小虎
「グループLINE作りました。こっちでもよろしくお願いします」
シュポッと音がして、可愛らしく擬人化されたサメが両手を合わせて「よろしく」と言っているスタンプが追加で送られてくる。
本来なら個人名が記載されているはずのヘッダーにあるグループ名を見て、私は顔を綻ばせた。
……一度、彼の能力を試す模擬試験を行ってもいいかもしれない。
彼にどの程度サポートしてもらうかを考えるのは、それからでも遅くはないだろう。
「お手並み拝見といこうか、塞翁君?」
私はグループ名と、その隣にあるオムライスのアイコンを指でなぞり、ふふっと小さく笑みを溢した。
グループ名:黄昏学園 裏解決部
部員:ニ名
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
