
エアコミケ3参加作品合同誌「少女文学 第四号」小野上明夜サンプル
去年は「初コミケ、リアル参加したかったな」と書いていたのですが、今年はもう最初からエアだとはね。悲しみはいったん脇に置いて、2021/05/04(火)発行の「少女文学 第四号」のご案内です。特集は「少女×戦争」。
全体の詳細な案内と通販については、紅玉先生の記事をご覧ください。
毎回すごいゲストをお迎えする本なんですが、今回はいやすごい本当にすごい。初版はすでに完売も納得のラインナップですので、お手に取っていただければ幸いです。6/6合わせの再版も予定しております。
一部では合同誌本体よりも愉しみ……楽しみにされていると噂の居酒屋もあります。
神尾先生は今回も「持ってる」。刊行記念ということで、自作にはまだ深く触れておりませんが、美男美女の王子様と王女様が結ばれてハッピーエンドになる話です。
軽くプロットを話したらみんな引いて、話せば話すほど引いたけど、まあええやろってことで書いた話もありますが。居酒屋ももう一回行われる予定ですので、こちらもお楽しみに!
そういうわけで、テーマに沿って、戦争を利用するタイプの「少女」のお話です。サンプルは以下です。
「蛙になったお姫様」
あらすじ
血蛙病に罹患し、赤剥けた蛙のごとき醜い容姿と病気の伝染を恐れて隔離小屋に捨てられたギーヨは、常に生き残ることだけに精一杯の人生を送っていた。フウロの守り神と呼ばれる軍師となった後も、己の性別など意識せずに生きていた。
しかし美貌の王子アーゼリーと出会ったことで、彼女の中に愛されたいと願う「少女」が生まれる。王子と軍師以上の関係は望まない、と自分に言い聞かせていたギーヨだが、やがてアーゼリーは愛らしい姫君に本気の恋をした。
※※※

※※※
闇の向こうから迫り来る死をも焼き付くさんと、砦中に掲げられた無数の火が冬の夜に吠えている。哀れなもんだな、とロトワは鼻を鳴らした。大袈裟にわめけばわめくほど、虚しさを増す負け犬の遠吠え。自他共に認める皮肉屋の男にとって、王都の守護者と謳われしナズンの砦は、すでに渓谷の狭間に巍然としてそびえる墓標でしかない。
「ご苦労さん! はい、通して通して」
突然の来訪に戸惑う兵士たちの間をすり抜け、厚手の外套の裾を飄々と翻しロトワは進んでいく。途中で自前の護衛にも待機を命じ、砦の最奥にある主の私室へと単独で辿り着いた。
「よう、元気かね、血蛙(ちがえる)殿!」
叩扉もそこそこに踏み込んできた闖入者を見て、豪奢な椅子に凭れてぼんやりと酒杯を傾けていた人影がはっと身じろぐ。ロトワは気にせず大きな書斎机の前まで進み、軽薄なしぐさでその上に座った。
「……ロトワ殿。なぜここに」
「なーに、名高き軍師ギーヨ閣下も、いよいよ後がなくなって錯乱したと聞いたのでね。無様な面を拝みに来たってわけさ。お前さんの面が見るに堪えないのは、今に始まった話じゃないが」
漆黒のローブに包まれたギーヨの容貌は、遠慮なくロトワが評したとおりのものだ。目鼻立ちが分からなくなるほどにぶよぶよと醜く肥えた彼女の肌は、どこもかしこも赤く爛れている。膿と脂で塞がれた頭部の毛根からはほとんど毛が生えていないのに、眉の毛だけがふさふさと太いのがかえって不気味だった。
用兵の才能が高く評価されるのと平行して特異な容貌の噂も広まっているが、初めて彼女の麾下に入った兵は必ず先輩兵士に尋ねるのだ。血蛙殿が戦上手であることは聞き及んでおりますが、失礼ながらあれはうつったりしないのですか、と。
「ふん、なるほどね」
燭台の火を浴びて一層赤い頬を、ギーヨは慣れきった態度で歪めた。
「なら好きにすればいい。あんたの逃げ足は見事なもんだ。あたしの自爆に巻き込まれるようなことはあるまいよ」
乱暴に酒杯を置くなり、投げ出すように彼女は吐き捨てた。彼女でなくとも投げ出したい状況であることは間違いなかった。
北の強国スエルブによる侵攻が始まってから早半年。現在ロトワが一応の忠誠を誓っているレンダーラ王国は、同盟国である隣国タイナと協力して必死の抵抗を続けてきたものの、今や陥落は目前。文字どおりナズンは最後の砦だが、スエルブの主戦力は明日の朝には到着予定だ。長く深い侵攻のせいで戦線が伸びきっており、兵の疲労も激しいという情報はあるが、消耗度合いはレンダーラのほうが上。ナズンさえ陥とせばスエルブの勝利。あと一息で苦労が報われると王自らがさかんに鼓舞しており、残念ながら士気は高いとの話だった。
籠城戦となれば多少は持ち堪えられようが、しょせんはただの時間稼ぎ。天才軍師として名を馳せたギーヨであっても、現在ナズンに残された戦力では長く抵抗できない。王都を守る兵は戦闘経験に乏しく、ナズン陥落の報を聞けば総崩れになるのは必至。なればこそとギーヨは、今こそ起死回生の奇策を使う時と、口角泡を飛ばしてまくし立てたとの報告をロトワは受けていた。
「思ったよりも冷静だな。最早どうにもならぬ、この上は一人でも多くの敵を巻き込んで自爆だと騒いでいると聞いたが?」
足止め程度では意味がないと、ギーヨは今となっては貴重品となった火薬を方々から集めさせた。スエルブ軍が砦内に侵入してきたところを見計らい、盛大に自爆して敵軍を殲滅させるというのが彼女の計画だった。陰湿だが緻密な策謀で知られた彼女が考えたとは、到底思えない計画だった。
あの女、とうとう唯一価値がある頭まで血膿にやられちまったらしいです。報告の結びに、斥候は苦笑していた。ロトワも苦笑いした後、自分の眼で状況を確認するため、秘密裏にナズンの砦を訪れたというわけだ。
「女心は移ろいやすいのさ」
探るようなロトワの視線を軽くいなすギーヨ。ふてぶてしい態度に加え、赤剥けたような皮膚は感情が読みにくい。相手の腹を探る力に長け、ギーヨとある程度の付き合いがある俺以外ならここで終わりだろうと自負しながら、ロトワは切り込んだ。
「それとも、俺が道連れとしちゃ役者不足なだけか」
じじ、と音がして、燭台に並んだ蝋燭が一本、身悶えるようにしながら消えた。一段暗くなった室内で、ロトワの目は鋭さを増す。
「錯乱してるのは間違いねえなぁ。ギーヨ、お前本気でアーゼリー陛下に惚れてるのか。あの方のために、あの方に任された砦ごと、敵を吹き飛ばす気なのか?」
「そうさ」
ギーヨの答えはいっそ軽快に響いた。
「お前一人で?」
「ああ、できればね」
隠すほどのことでもないとばかりに、ギーヨはそれも認めた。いかれた軍師殿の自暴自棄には付き合えないと、ナズンの兵士たちは逃亡を企てている。言われたとおりに火薬を用意し、砦のあちこちに仕掛けはしたが、敵軍が攻め寄せるに従って大半は王都へ逃げる手筈が整っていた。自爆したければ、どうぞお一人で、という寸法だ。
そこまでの情報を斥候は持ち帰った。彼に見えている情報がギーヨに見えていないはずがないとロトワは睨み、その予想は正しかった。彼女の暴挙の理由さえも。
「王は俺でも認めざるを得ない善人だが、タイナの王女一筋だ。お前が何を差し出そうが、女として愛しちゃくれんぜ」
「分かっているよ。そういう人だから、あたしは好きになったんだ」
ぐつぐつと、本物の蛙のように濁った笑い声を上げたギーヨは大儀そうに酒杯を持ち上げたが、中身が空だったことに気付いて広い肩を竦めた。
腐った木の床の上に転がり、生臭い空気を吸って吐く。幼いギーヨにとって、それが生きるということだった。
血蛙病。赤泥蛙。膨れ病。見渡す限り灰色に垂れ込めた空とじめじめとした湿地帯が続く、この地方の風土病に、物心付いてすぐ蝕まれた。腐った水を好む蠅が媒介する病気であり、人から人へ感染するものではないのだが、それが分かるのはギーヨが名を挙げてからの話である。呪われた地として土地全体が差別されている中でも、血蛙病を発症した者は白眼視される。湿地帯の外で嫌われ、よそには移り住めぬ民にとって、伝染病は死活問題だからだ。下手に庇おうものなら、一家全員が「消毒」されてもおかしくない。
滑らかだった肌が一面赤く腫れ上がった幼子を、両親は慣習に従って汚い沼の脇にある隔離小屋に投げ込んだ。幸いに後から生まれた弟妹には病は寄りつかなかったため、長女の存在自体を忘れた一家は貧しいながらも助け合って暮らしているらしい。
元家族の状況がギーヨの耳に入ってきたのは、そこまで生きていられたのは、彼女が生まれつきひどく頑丈だったからだった。隔離小屋とは名ばかりの、家畜小屋より劣悪な環境でも生き抜けるぐらいに。祟りでも恐れているのか、日に一度は食べ物が投げ込まれるが、それ以外の施しはない。最初はギーヨが一番小さかったので、体が大きい年上の病人に独占されて、何も食べられないことが多かった。やむなく口に入るものはなんでも試し、腹を壊しながらも年を重ねた。幸いに新たな病人はどんどん補充され、年上の者たちもどんどん死んでいったので、数年も生き延びれば飢えに苦しむことだけはなくなった。
頑丈な上に賢いギーヨは、食べ物を持ってくる係や、ある程度年がいってから隔離小屋に投げ込まれた者たちがしゃべるのを聞いて、少しずつ小屋の外の知識を身に着けていった。特にこの湿地帯の外の話に心惹かれた。遙かな昔、まだ親に愛されていた時代にも、少しだけ聞かせてもらったことがある。遠いどこかには乾いた地面と、輝く青空があるのだと。
行ってみたい。気付けば十を過ぎていたギーヨは好奇心を抑えきれなくなっていた。不作が続き、与えられる食べ物が減り始めたという理由もあった。このままここにいても、昨日死んだ男みたいに殺されるだけだ。
隔離小屋には床さえない。ぬるつく地面に少しずつ穴を掘り、食料を蓄え、脱出準備を整えたギーヨは篠突く雨に紛れて小屋の外に出た。分かっているのは湿地帯の向こうにあるという、一番近い村の方向だけだ。雨に阻まれてなお、壁に邪魔されずどこまでも広がる視界に歓喜しながら、ギーヨはいくつもの小さな沼を越えて歩いた。
やがて雨がやみ、地面が少しずつ乾き、森の中に入ってしばらく進むとどこからか女の悲鳴が聞こえた。木陰に身を潜めながら近付いていけば、若い女に数人の男が群がっている。衣服のあちこちを破かれながらも女は必死に男たちの手を逃れ、ギーヨが隠れているほうに近付いてきた。
咄嗟にギーヨは木陰を出た。女は止まれず彼女にぶつかった。さっきまでげらげら愉しげに笑っていた追っ手の男たちが、ぎゃっと悲鳴を上げて飛び上がる。
「やべえ!」
「沼の化物だ! 本当にいたんだ……!!」
散り散りに逃げていく男たち。ギーヨに救われた女はといえば、真っ青な顔をしてその場にへたり込んでいる。当座の難は逃れたものの、到底救われたという顔色ではない。無理もないな、とギーヨは冷静に考えていた。己の姿が他人にどう映るかは理解している。だからわざわざ出てきたのだ。女の服が、完全に破かれてしまう前に。
「あんたの服をくれ」
その声に、女は大きく瞳を見開いた。
「あなた、もしかして、女の子なの……?」
ひどいなりだとは分かっていたが、女に見えないのか。ギーヨは苦笑いして己の姿を見下ろした。
彼女が身に着けているのは汚らしい腰巻き一枚のみ。病人たちの誰かから剥ぎ取ったもので、それでも隔離小屋の中では贅沢品だった。あそこに投げ入れられる時点で血蛙病患者は死んだも同然なのだから、素裸で放り込まれる者が圧倒的に多いのだ。いなかった者とされた存在に副葬品は必要ない。
そのため、年齢からすれば女らしさが出てくるはずの全身はほぼさらけ出されているのだが、なにせ彼女は膨れ病の患者。赤く爛れた肌は膨張し、溶けた蝋のように重なり合い、性別を感じさせない怪物の輪郭を作り上げている。女物の服を身に纏ったところで焼け石に水。人里に近付けば追われるだろう。
それでも可能性が減らせるかもしれない。第一、雨に濡れた体は冷え切っており、身に着けるものの必要性を感じていた。女同士だと分かって油断したのか、逃げようとした女を殴り付け、「うつさないで」とわめく彼女から着ている物を奪ったギーヨは、再び村を目指した。
辿り着いたのはフウロという名の小さな村だった。ギーヨはその外れに住居を定め、ごみを漁ったり農作物を盗んだりしながら生活を始めた。
何度も殺されそうになった。だがギーヨはそのたびに「殺したきゃ殺しな。この土地を祟って、みんなあたしと同じにしてやる」と脅した。狙いは当たり、湿地帯が近いだけに血蛙病への恐怖と偏見を強く持っている村人たちは彼女を恐れた。調子に乗ったギーヨが祟られたくなきゃ貢げ、と言い出してもそれに従った。
こうしてギーヨはフウロの村外れに住む祟り神となった。ギーヨとしては生活に必要なものを貢がせたかったのだが、フウロの村の人々も貧しい。食べ物や着る物が用意できないからと恐縮しいしい、持っている物を手当たり次第に寄越すことがあった。大抵は愚にも付かないがらくただが、ある日数冊の本が持ち込まれた。
聞けば何年か前、フウロという辺境の出身ながらレンダーラ国王軍に参加するまでに至った男がいた。彼が里帰りした際、故郷の助けになればと何冊かの兵法書を持ち帰った。生憎とフウロには彼以外に本を読める者がおらず、ただ本というものがひどく高価であるとだけは知られていたため、貴重品として保存されていたのだ。
ギーヨも文字など読めない。しかし己の武器は醜い容姿と機転だと知っていた彼女は知識を得ることに貪欲だった。初めて兵法に触れる者向けで図解が多かったこともあり、これでなんとか文字を覚えられないかと、暇があれば兵法書を捲って時を過ごした。
それから数ヶ月して、村人たちが不安そうに囁きをかわす姿が多く見られるようになった。近隣の村を荒らしている野盗たちが、フウロ周辺に出現し始めたらしい。彼等に目を付けられ、焼かれた村は数多いという。気の早い者は夜逃げの準備をし始めていた。
ギーヨとしても、寄生先であるフウロを守る必要があった。文字を覚えるまでには至っていないが、兵法書で身に着けた知識が役に立たないだろうかと彼女は考えた。聞く限り野盗たちは、騎馬の利を生かして大きな顔をしているだけで、そう頭を使っている風でもない。逃げ惑うことしか知らない、無知な田舎者相手だから蹂躙できるだけだ。
一か八か村長に掛け合った。あまり乗り気ではなさそうだったが、ほかに頼る道もなく、ギーヨの献策は至って単純だったので最後には承諾してくれた。野盗たちの襲撃に合わせて逃げたふりをし、五人で一組になって物陰に隠れ、盗みを行うため馬を止めた野盗どもをできるだけ大勢で取り囲み、手製の槍で主に馬を思いきり突き刺す。それだけ。逃亡を偽装して誘い込み、一対多数に持ち込むという、兵法の初歩の初歩だ。
村人たちも気乗りしない様子だったため大した訓練ができたわけでもないが、真面目にやらなきゃ祟る、とたっぷり脅してやった効果はあったのだろう。一目散に逃げ出した村人たちにすっかり油断していた野盗たちは囲まれて次々と落馬し、運の悪い者はそのまま死んだ。混乱した愛馬に蹴り殺されたり、槍に突き殺されて死んだ者も多かった。村人たちも無傷とはいかなかったが、被害は想定よりもずっと小さく抑えられた。
こうして祟り神は守り神へと変わった。フウロの人々はギーヨに深く感謝した。ギーヨ自身も、自分の人生が再び大きく転換する手応えに全身の血が沸騰するような興奮を覚えた。
野盗どもが仕返しに来るかもしれない。それを口実に、兵法書を参考に元からあった用水路を延ばして村の周りに溝を掘らせた。村人たちへ定期的に訓練も行った。噂を聞きつけ、野盗に怯える別の村から教えを請う者が現れ始めた。初対面の者は必ずギーヨの面相に怯えるが、今ではフウロの人々が率先して「あの方を怒らせない限り大丈夫だよ」と笑ってくれる。ギーヨが村に住み着いてからもう何年も経っているが、血蛙病の患者は出ていなかった。
評判が高まるにつれ、退役した軍人などと話す機会もできた。手持ちの兵法書の内容を解説してもらい、文字が読めるようになっていった。識字能力を手に入れたことで、学びの範囲は一気に広がった。手当たり次第に本を集めては読み、普遍的な知識を手に入れるのと平行して、ギーヨはより深く兵法を学ぶことに没頭していった。
隣国タイナとの戦争の噂が漂い始めたせいだろう。世情は不安定になり、ただの野盗ではなく傭兵崩れなども人々を脅かし出していた。国王軍も動いているようだが全てを救う力はない。貧しく学のない人々を束ね、暴力に対抗する才能が必要とされていた。
あたしの人生を輝かせる鍵が見つかった、とギーヨは感じていた。知謀もさることながら、人ならざる者のような姿がある種の風格の源となっていた。時には水に毒を混ぜたり、非戦闘員を襲ったりと容赦のない手を打つギーヨだったが、己を慕う人々を効率良く守るため。やり方は良くなかったかもしれないけど、ギーヨ様がいなければ私たちは死んでいた。生まれ育った村を盗人たちに焼かれかけた娘は、フウロの守り神を崇拝しきった眼で見つめていた。
いつしか近隣の街や村の兵力を統括し、意のままに動かし始めたフウロの守り神の名は、ついにレンダーラ王の耳に入った。ギーヨ殿に是非お目にかかりたいと、国王の名で王都へ招聘された。
意気揚々とギーヨは出かけていった。その先に待ち受ける運命は、聡明な彼女にも思いも寄らぬものだった。
「初めまして、フウロの守り神殿。私はアーゼリー。この国の王子だ」
レンダーラの王宮、始祖の名を掲げたブレナムール宮殿の一室に迎え入れられたギーヨに、その人は気さくな笑みを浮かべながら軽く頭を下げた。純金の長い髪が、動きに合わせて明かり取りの高窓から差し込む陽光を弾く角度を変え、新たな輝きを振りまく。一連の光景を、ギーヨは瞬きも忘れて見守っていた。
「申し訳ない。父の名を借りて招いたが、実はギーヨ、君に会いたかったのは私なんだ。タイナとの戦争の噂は君も聞いているだろう? レンダーラの未来のために、若く才能ある軍師を雇い入れたいと思っていてね」
「さ、左様でございますか。光栄です。ありがとうございます」
へどもどとギーヨは口の中でつぶやいた。レンダーラの至宝、麗しの王都とその中心である宮殿については吟遊詩人たちの語りで何度も聞いていたため、実際に目にした時は思ったほどではなかったと感じていた。へぼ詩人どもの見る目のなさを呪うしかない。古代より語り継がれし妖艶な柱のくびれだの、宝石の粉を惜しみなく使った壁画の贅沢などより語り継ぐべきは、アーゼリー王子の美だろうに。
実際はギーヨが己の野望に必要であろう内容以外を聞き流していたのだが、そんなことはどうでもよかった。目の前で動き、しゃべるアーゼリー王子はあっという間にギーヨの胸の奥に彼だけが住む部屋を作った。若い緑の瞳が楽しげな笑みを浮かべ、形良い唇が息を吸い、吐く。そのたびに心臓が知らない速さで駆け出して、引き留めるのに苦労した。
フウロのあたりにもそれなりに見目のいい男はいた、と思う。美醜の概念ぐらいは持っている。恋も愛も存在は知っている。しかしギーヨは、生まれてこの方誰かに胸をときめかせるという経験がなかった。物心付いてすぐ病によって悍ましき姿へと変貌し、腐った水の中を這いずるようにして生きてきたのだ。老若男女を問わず、初めてギーヨの姿を見た誰もが瞳に怯えを走らせる。諦めるという意識もなく、恋愛への憧憬を持たずに生きてきた。
その壁を、幸運を易々と破砕した男が、不思議そうに小首を傾げる。豪華な襟の狭間からちらりと覗く首筋の、意外な逞しさに目眩を覚えた。
「ギーヨ殿? 申し訳ない、私の話は退屈だっただろうか」
「いえ、とんでもありません。私のほうこそ、す……素晴らしい宮殿に気後れしてしまったようで……大変失礼いたしました」
初めて野盗どもを追い返した際の功績を褒められていた、ぐらいは聞き取れていたが、まともな反応を返せずにいた。しどろもどろに思ってもいない言い訳をする自分があまりに情けなく、普段から熱を帯びた手の平が汗ばみ、爛れた皮膚に染みて痛い。
情けない。そう、情けないことに、ギーヨは猛烈な恥ずかしさに見舞われていた。血塗れの蛙のごとき面相は醜悪に過ぎ、馬鹿にされることさえ稀だ。来ないでくれ、うつさないで、何度言われたか分からない。傷付く前に日常となった人々の恐怖を畏怖に変え、ここまで生きてきたはずだったのに、アーゼリーが己の姿をどう思っているのかが気になって仕方がない。村を出た直後、助けてやった女が口にした「あなた、女の子なの……?」という素朴で残酷な疑問が耳の奥に蘇ってきた。
自分が女であることを、ギーヨは特に意識せずに生きてきた。性別以前に彼女は化物であり、人間扱いされていなかった。赤く腫れて膨張した肉体は男女の区別を失わせている。子供の頃は声だけは不自然なほどに幼かったが、長じるにつれ声帯まで膿んだのだろう。焼けたように掠れた声しか出なくなり、特に何も言わなければ男だと思われていた。
それで何も問題はなかったのに、アーゼリーを目にした瞬間、ギーヨの中に少女が生まれた。好いた男に高く評価されたいと願う、浅ましくも一途な少女が、ギーヨの声で勝手にしゃべり出す。
「重ねて失礼ながら、王子殿下は……その、私の姿が気にならないのですか」
王宮に入る前、「決まりですので」との名目で侍医の確認を受けていた。これまでギーヨが接してきた人々の中に血蛙病の発症者がいないことぐらいは分かっていようが、確認せずにはいられない心境は理解していたので好きにさせた。お眼鏡にかなってこの部屋まで案内されるまでの間も、控えめながら不安そうな注視は感じていた。宮殿に住まう人々も、内心は病に冒された容姿を悍ましく思っているだろうに、アーゼリーの瞳にあるのは純粋な好奇心だけだ。
「そうだね、全身が赤剥けているようで痛そうだな、と思うよ。でも、実際はそうじゃないんだろう?」
そんなことはどうでもいいとばかりに、アーゼリーはすぐに兵法の話に戻った。自然すぎるぐらいに自然な態度だった。おかげでギーヨの心臓も少し落ち着き、いつものように堂々と話せるようになっていた。
嘘吐きめ。心の中で舌を出す。
二枚舌、三枚舌ぐらい操れなければ王族は務まらない。ましてアーゼリーは未来の王である。タイナとの戦に備え、有能な軍師候補の機嫌を損ねてはまずいと考え、このような態度を取っているに違いない。もしもギーヨを蝕む病が伝染するものであれば、即座に摘まみ出されたに決まっている。
くだらない男だと思った。そうでなくては困るという本心に、彼女の聡明さは眼をつむった。
※※※
サンプルはここまでです。実際の本文は↓のような感じです。
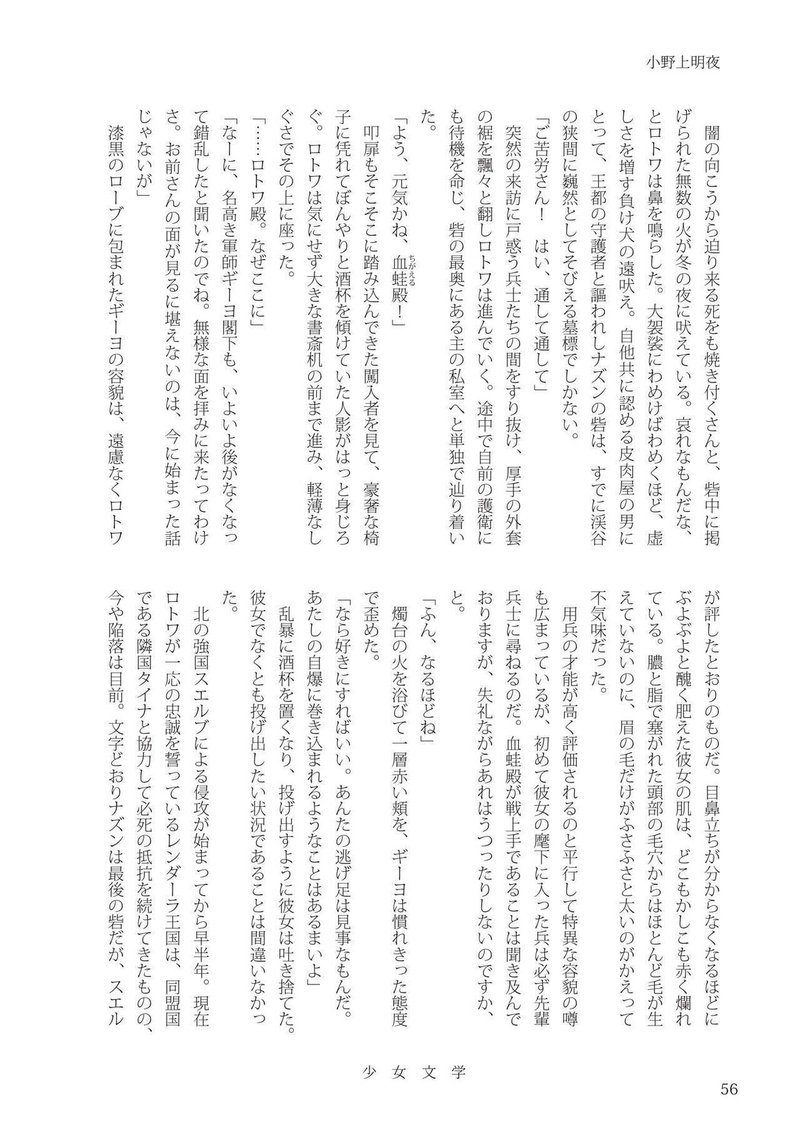
対面で頒布できる日はいつ来るかな……ひとまずは通販にて、よろしくお願いします!
header design by ☆
小説家。「死神姫の再婚」でデビュー以降、主に少女向けエンタメ作品を執筆していますが、割となんでも読むしなんでも書きます。RPGが好き。お仕事の依頼などありましたらonogami★(★を@に変換してね)gmail.comにご連絡ください。
