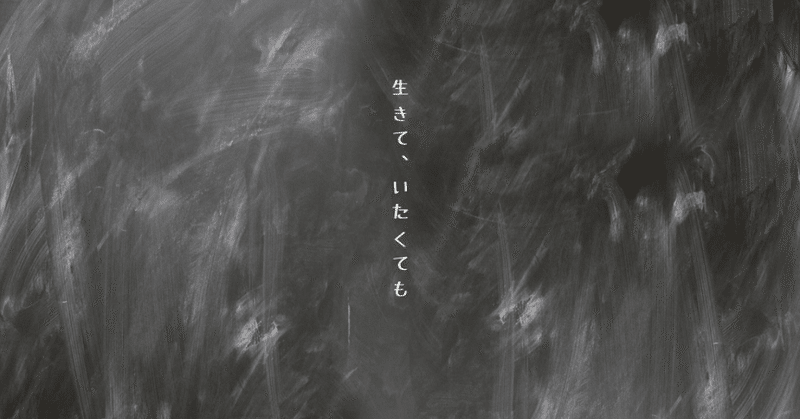
生きて、いたくても――Nov#19
僕に渡された二五個のコップは、小さなグループになって分けられている。朝、昼、夕暮れに夜。そして最後に訪れる、夜明け。新たな役割を与えられた、五つずつのオブジェクト。その全てに、買って来た色紙を切って作った紙吹雪と、二振り程の塩が入っている。
雲は、空の内三割。白と青の対比が綺麗な、景色としては黄金比の晴れ。昼過ぎと言うのもあるけれど、急に冷え込みが強くなった最近の平均からすれば気温も暖かいと言える。文化祭の開催条件としては絶好の環境だ。僕たちにとっても、この少し涼やかなくらいの日が、何となく凛として相応しい気がした。
人の数も賑やかさも、普段とはまるで違う。祝日である所為か、昨日よりも人の入りは多い様に感じた。屋上に居ても、校庭の喧騒はよく届く。偶見が目を向けた。
「いよいよだね」
首に掛けたヘッドフォンが、長い黒髪を纏めている。普段家で使っているものを、こっそり持ち込んだらしい。今回の「クエスチョン」にこの子は外せない、と言うよく分からないけれど強い主張だった。常に激しい曲や、気分の高まる様な曲ばかりを流していると言うから、単に自身の昂揚を盛り立てる為の道具だと思う。
その機体は、今は文字通り鳴りを潜めてしんとしている。今の心境を例えようと思ったら、僕たちはきっとこのヘッドフォンだ。静かだけれど、すぐそこには強いエネルギーが堰き止められていて、一度回路が繋がりさえすれば、衝撃を伝えるべく動き出す。今、僕の中で渦巻いている熱源が体中に流れ出したなら、その音はきっと、アンセムにでも聞こえるだろう。
「しかしさ、よくここまでやったよ本当」
そう言って、偶見がディスペンサーを構える。細長い円筒状の器具に紙コップをセットすると、ボタンを押せば一つずつ取り出す事が出来る、業務用のものだ。ただ、見た目に重厚感があり、今は一種の兵装みたいに見えた。本物のロケット・ランチャーと比べてしまえば安っぽいだろうけれど、横に寝かせて持てば充分近いものを想起させる。
胴回りは当然コップを入れる器具と言うだけあって持つには太く、片手で握る様に持ちつつボタンを押す、その両立は難しい。しかし、もう片方の手はコップを受け取る為に空けておくから、どうしてもその作業を片手でこなす必要がある。なので、改造、とまでは行かないけれど、ディスペンサーの側面、ボタンを押せる位置に、掌を通して親指のつけ根で引っ掛けられる様なバンドを取りつけた。
僕はその器具に、自分のコップをリロードして行く。円筒の上部につけられた蓋を開け、四つを適当な順序で装填した所で、三上が「夜明け」の山から一つ、僕に手渡した。「その復讐が、結実します様に」。頷いて、祈りにも似た彼女の言葉とコップを受け取る。
そんな彼女は、物々しささえあるディスペンサーを手にすると、尋常ではない存在感があった。傍らに置いてあるガス・マスクとの組み合わせは、見た目だけならテロリストと勘違いされても文句が言えない。
「それもさ。って言うかもう、やり過ぎまで行ってるよ。高かったんじゃない?」
「ううん、全然。本物なら兎も角だけど、コスプレ用のとか、サヴァイヴァル・ゲイムなんかで使う、こう言う型のフルフェイス・ゴーグルとかなら、安いのも結構あるよ」
そう、この計画では正体を隠す事も必須だった。顔を明かしたところで、百害あって一利なし、だ。
その為に三上はこの大仰なマスクを、僕はまだ無難と言えそうな、狐の面を用意した。僕の場合は家の中を探した結果それしかなかったのだけれど、二人は態々買い揃えたらしく、やや申し訳ない気分になった。恐らく、選んだなりの拘りもあるだろう。
偶見に至っては、縁が白くて太い伊達眼鏡とアフロのかつら、派手なアニマル柄のジャケットに加えてつけ髭と、最早何を目指しているのか判然としない混沌のセットだった。だけど、数日前に一度それを全て装備してみせた偶見のヴィジュアルは、少なくとも絶対に彼女ではなかった。一人だけ顔が出ている事になっていても、心配は不要そうだ。
「それじゃ、そろそろ着替えて行きますか」
偶見が立ち上がり、そうだね、と三上が続いた。その後ろ姿を見送りながら、極力無作為に三つの塔を統合する。朝、夜、夜、夕暮れ、夜明け。夕暮れ、昼、夕暮れ、昼、夜明け。
二人のディスペンサーは、前もって補充されていた。込めた思いの期限が経過しない様に、と三上に新鮮さを求められた僕の分だけは、当日に準備する取り決めだった。
全てを終えた所で、僕も通学鞄を開く。制服を脱ぎ、私服と狐の面を身に着ける。季節にはまだ少し早い厚手のダウン・ジャケットも、服装としては常識的だから、対比される狐の面は尋常でなく浮いてしまって悪目立ちする。二人も塔屋とタンクの間、庇の掛かったあのスペイスで、テロリストと怪人物の異様なコンビ姿を変えている筈だ。
目立たない様に、やや身を伏せて欄干から眼下を見渡すと、屋台のテントや、トラックの中心に置かれたステイジなんかで区切られた校庭の中で、人がブラウン運動さながらに犇いている。さっきから時折鬨の様な歓声が聞こえるのは、ちょうどステイジで行われている軽音楽部のライヴに発せられたものだろう。彼たちにはプログラムでも少し長い四五分の時間が与えられている事、結構本格的で校内でも人気がある事、偶見から全て教わった。驚く事に彼女はフライヤーを大方覚えてしまったらしく、案内図や日程などを見なくとも、凡そ文化祭の全体を把握している。とても真似出来ない芸当だ。「珠ちゃん、こう言う事大好きだから」三上がそう言っていたのを思い出す。「その調子で、教科書も覚えたら?」
「あのね、記憶には質があると思うの。教育システムが悪い」勿体ないお言葉だった。
ステイジからまた、喝采が轟く。共鳴するみたいに、大きくなった僕の脈動が重なり、混ざり合う。
「宮下君、おっけー?」
「うん、大丈夫」
その合図で向こうから二人が姿を現す。偶見のエキセントリックな相貌は先刻知っていたけれど、三上は黒いロング・コートに、ファーのついたフードを被っている所為で、いよいよ不審者だ。奇抜に過ぎるからか却って現実感がない割に、まるで胃の底から突き上げる重低音の様なインパクトで、と言うか実際に胃が痛くなった。不安しかない。僕は人生の踏み外し方さえ踏
み外したんだろうか。
「うわー、何か、宮下君だけ攻めてる感じがない」偶見は平然そのものだった。「逆に被ってよ、そのお面。上下逆さに」
「……それ、どう言う事?」
果たしてそれが「攻めている」のかは分からないけれど、言う通りに外す。天地を入れ替えてみた面構えは珍妙で、「上下逆」と言う、いかにも奇を衒った小細工でありながら、何となく気の抜けた感じの所為で、僕にも妙な余裕が生まれてしまった。悪くない。その指示に大人しく従って着け直す。
「……ふふっ、いいですね、それ。さっきより、ずっと」
「うん、凄くいいよそれ。完璧。よし、もう他の準備は大丈夫だよね」
偶見がそっと扉を開いて、階下の様子を探る。
「じゃあ、行くよ」すぐにOKサインが出た。「『スプリー・スリー』のお目見えに」
互いの顔を見合わせて、全員が弾かれた様に踏み出す。
「凄い事になるよ、絶対」
偶見が小さく零した声を聞いた。
ディスペンサーの中で、命の鳴動が始まったのを感じた。
