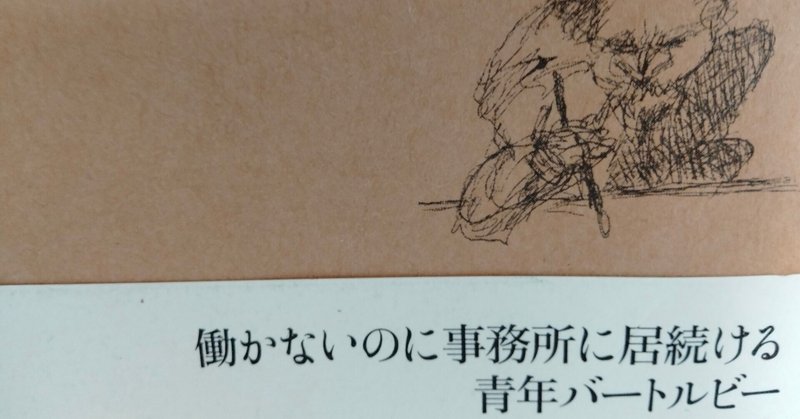
【書評】『バートルビー 偶然性について』:ジョルジョ・アガンベン
近代の民主主義に基づいた市民社会では、生得的に「権利としての自由」がある(ことになっている)。そのなかでも、具体的な行使が保障されている権利は、もっぱら積極的な行為としての「~する自由」だ。
もちろん「~しない自由」もあるには、ある。たとえば「黙秘権」。だが、発言の自由が認められている場で「あえて話さない」のは、ときに第三者に対して否定的な印象を残す場合がある(「発言できない“何か”があるからではないか!?」)。
では、消極的な自由(~しない自由)の積極的な行使は、権利において認められているにもかかわらず、積極的な自由(~する自由)ほど社会的に容認されているわけではないのだろうか。
たとえばこれが、生産や労働といった経済活動の場合ではどうだろう。「~しないでいることができる自由」はどこまで容認されるだろうか。
もし、あなたが会社員だとして、職場の上司が『できるか、できないか、それが問題ではない。君がするか、しないかだ』と発言した場合、露骨な強制命令ではないにせよ、そこにはあまり選択の余地はなさそうだ。
では、『するか、しないかはもちろん君に委ねられている』はどうだろう。この場合も、『(ただし、君がやらない場合、他の者に任せるだけだ)』を暗に仄めかしているとすれば、本質的な意味での自由は奪われている。
逆に、あなたが上司の立場だとして考えてみてほしい。このような「行為」への催促はどれほど有効だろう?そして、それを拒否した部下に対してどのような評価をくだすだろうか?
本書の登場人物、バートルビーが譲ろうとしないもの。それは、この「~しないでいることができる自由」である。当然のことながら、上司にも同僚にも不評を買う。社会的にはほとんど誰からも認められなくなる。
それでも、最後のバートルビーの姿に、哀れさよりも、むしろ崇高さがあらわれていると感じてしまうのは何故だろう。
それはおそらく「~しないでいることができる」という《存在としての自由さ》は、「~する自由」という行為によって得られるものよりもはるかに重要だと、僕らが腹の底では分かっているからだ。
その姿は、あたかもあらゆる煩悩を捨て去って、断食によって即身成仏しようとする僧侶のようである(少し古い言い方だが、「ブラック企業」から「引きこもり」「おひとりさま」で「断捨離」する「嫌われる勇気」を持った「ミニマリスト」)。
「~する自由」の行使を催促し、「生産と消費」を際限なく拡大し続けようとする市場原理に疑問符がつけられている時代に、アガンベンが敢えて『バートルビー』を取り上げたことには、なるほど理由がありそうだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
