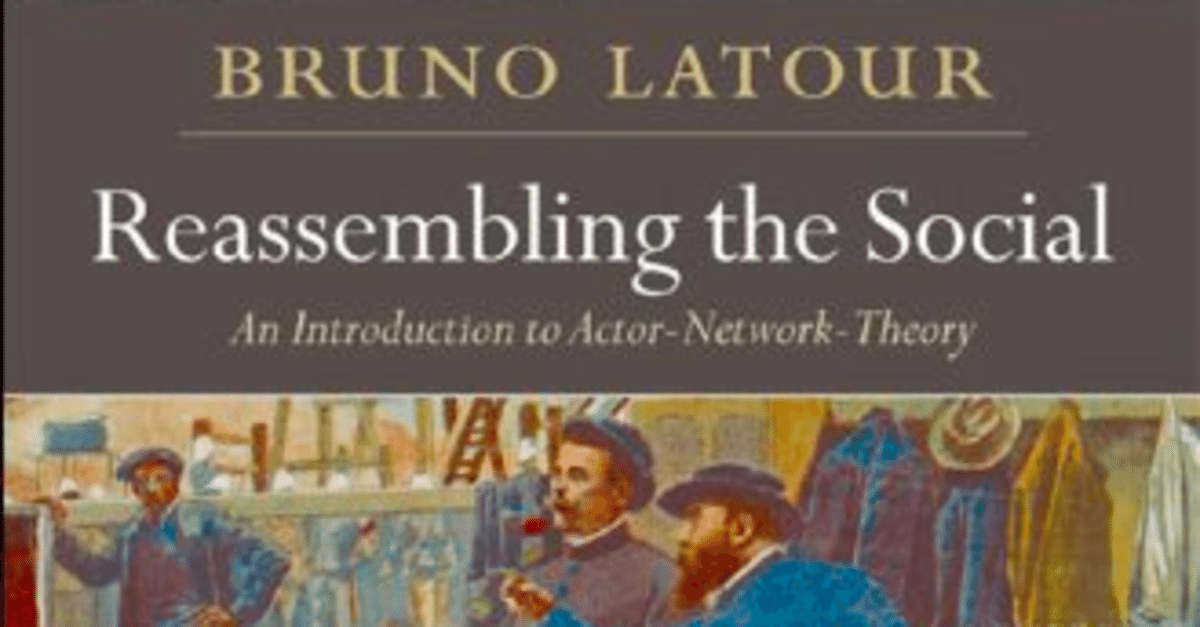
ラトゥール『社会的なものを組み直す』をわかるまで読む
第二回 統計について
さて、Latour が関係性と痕跡の「社会学」と呼ぶ Actor-Network-Theory の現状と評価についての説明に入る前に、彼が批判するsociology of the social (社会実体論)の基本になる統計の考え方について話をしておきたい。
三浦展(あつし)という1958年生まれの社会学研究者がいる。パルコ入社後マーケティング誌『アクロス』編集長から三菱総研での研究を経ていまは自分の会社で日本の消費・都市・郊外を研究する。多作な人で魅力的なタイトルの本がたくさん出ている。僕は割と読んでいる。
さて、たくさん読んでいて、また参考にもしているのだが、三浦展氏の方向はラトゥールの批判する社会実態論の典型である。それを理解するには社会の見方、いってみれば哲学の問題が大きく関係する。その哲学とは、統計数字をつかいながらも、思考や論述がニュートン的な決定論の流れ、つまりはカントの定式化した世界を断ち切っておらず、それが「社会的なるものの社会学」に特筆であり、ラトゥールがいうところの「関係性の社会学」とは大きく違うところなのだ。
ではどこがちがうのか?統計的手法をつかいながらも偶然性 chanceを導入できない、というところが違うのだ。科学哲学者イアン・ハッキングの『偶然をかいならす』を参考に、すこし詳しく見てみたい。18世紀も終わりになると、啓蒙時代の整理整頓された世界観とそれを代表するカントの哲学、さらにはカントが前提としていたニュートン的機械論的決定論のものの見方だけでは説明が出来ないと感じる人々が出てくる。それは社会の統計化から始まる。統計とは数え上げる enumerationという作業に始まる。国税調査をあらわすCensusという言葉はラテン語でcensereといい、古代ローマ時代から市民を登録して、財産を評価して、徴税を課す、という作業がおこなわれていたことがわかる。豊臣秀吉もそうだが、ナポレオンも徴税のために人々の財産を数え上げた。時代が近代になると、徴税に加えて、徴兵が目的として加えられた。そしてその結果は秘密にしていたという。
ナポレオン時代の終わりに、統計データが印刷される。これをハッキングは「印刷された数字の洪水」と呼んでいる。調査結果が印刷物として出版され、人々はそれに「熱狂」した。犯罪や自殺など「悪い行い」が計測できるようになり、それが毎年規則正しく起こっていた。逸脱の数字があらわれてきて、それを正常に戻すための方法「社会工学」が構想された。18世紀の終わりの話である。
最初のセンサス(国勢調査)を行ったのはアメリカ合衆国で、1790年のことだ。アメリカ独立の少しあとだ。このときは人口統計がとられた。いま、この瞬間の人口を数え上げる簡単なものである。1792年にワシントン大統領にアメリカ13週の人口数3, 929, 214という数字が報告さえたという。(注 伊藤陽一論文)
その後ヨーロッパ諸国でもセンサスの調査がおこなわれ、データの分類と計量のための新しいテクノロジーが導入された。マルクスは公式統計の細目や工場視察報告書をつぶさに読んで研究していたという。階級意識をつくりあげるのは、統計の数字なのかマルクスの理論なのか?あるいは、統計の数字が階級意識を決定論的にきめるのか?
ハッキングはこの問題、つまり人間を作り上げるのはなにか、の問題は最初は階級意識ではなくて、自殺、犯罪、狂気、売春と行った「逸脱行為 deviancy」を改善することができるという発想から注目されたという。印刷した統計数字を見ながら、マルクスもデュルケムも何が人間の行動を決定しているのかについて議論を展開したのである。
だが面白いことに、データがあつまってみると、データにはデータ独自の性格があることがわかってきた。これを大数(large population)の法則という。これはギャンブラーの間で知られていた。博打に勝つという「偶然 chance」に法則性があるのでは、という議論だ。17世紀の事だとされる。哲学史的にはライプニッツの話となるが、この話はもっとあとで詳しく説明したい。偶然の問題はライプニッツの同時代人であるニュートンの決定論の世界ではあまり真剣に議論されていなかった。ところが、経済的自由主義、個人主義、個人の集合としての国家概念が広く行き渡っていた19世紀の西ヨーロッパの諸国は、自国のセンサスデータを読むことで、データと社会現象のあいだには「大数の法則」があることに気がついてくる。
確率とは統計的結果について議論しているのではない。統計はstatisticsで確率 はstochastic。つまり違う言葉だ。決定論ではなくて偶然を前に出すのが確率論である。我々は確率論で、つまり決定論の外で思考をする時代に生きている。実証的とは証拠を集めて、データを分析して、実験をデザインして、信頼性を評価することである。論述するとは 推論 inferenceをつかって論証 argumentする事である。論述の形は数学的にはトートロジーになり、それを「論理学」と考えるひねくれ者が論理学者にはおおいが、社会科学では統計学的推論つまり大数の法則が成立すれば良いとされる。また政策や戦略において何をするべきかは決定論的にではなく、確率論的につまり大数の法則によるデータの分析の結果によってなされている。これが20世紀前半の出来事であり、21世紀のわれわれもここに生きている。我々は、数字をあつめて仮説をつくったり、演繹をしたりする。計測する道具を工夫して実験をする。アナロジーをつかって仮説を作る。関数あるいはパラメーターをデータを比較したり整理したりして見つける。だがこうした作業を大数の法則にしたがっておこなっていることを忘れてはいけない。
大数とはlarge populationの訳であり、populationとは母集団とも訳されるが、まさにそうで、何をもってpopulationとするかの定義がないと始まらない。西ヨーロッパでは社会とは何かが問われるようになり、このpopulationの定義なしには議論は進まないのだ。そしてこの作業をおこなうなかで、偶然chanceというじゃじゃ馬をを飼い慣らし(taming)て決定論を紛れ込ませたのが19世紀から20世紀初頭に代表される思考である、というのがハッキングの主張である。つまり統計的資料がそろってきており、その分析のための大数の法則が整備されているにもかかわらず、その根幹の偶然の考え方を丸めてしまったのが19世紀なのである。これを打ち破ったのが20世紀初頭に登場したアブダクションを提案したC.S.パースなのだが、この話もまたライプニッツの話と同じで、もうすこし後で詳しく展開したい。
さて、話をもどすと、大量に印刷された統計データから偶然ではなくて必然性を、つまり偶然性を飼い慣らした思想家がいる。1人はマルクスであり、もう1人はデュルケムだ。
デュルケムの社会的実体the socialの社会学がどのように形成されていくのか、を次は見てみたい。ここはラトゥールは何をどのように乗り越えようとして関係性の社会学を提案しているのかを理解するために超えなければならないところだ。
重要なまとめ 2:統計 statistic と確率 stochasticは別の概念である。
Aという現象がBという現象を決定論的に生み出すのか、偶然にうみだすのか?では世の中の出来事や仕組みの成り立ちを説明する方法が決定的に異なる。19世紀に様々な活動の記録が統計としてまとめられたときに、その統計からAという現象がBという現象を「決定論的に」うみだすという考えがうまれた。これは統計データを決定論的に「飼い慣らした」ものであって、統計データを偶然の説明とみる確率論とは大きく違う哲学である。Aという現象がBという現象をうみだしたのは偶然であるとするのが確率論の哲学であり、17世紀のライプニッツから20世紀初頭のパースに続くもので、この考えを退けてきたのが19世紀から20世紀の哲学なのだ。sociology of associationはこの確率の世界を扱うものである。
(続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
