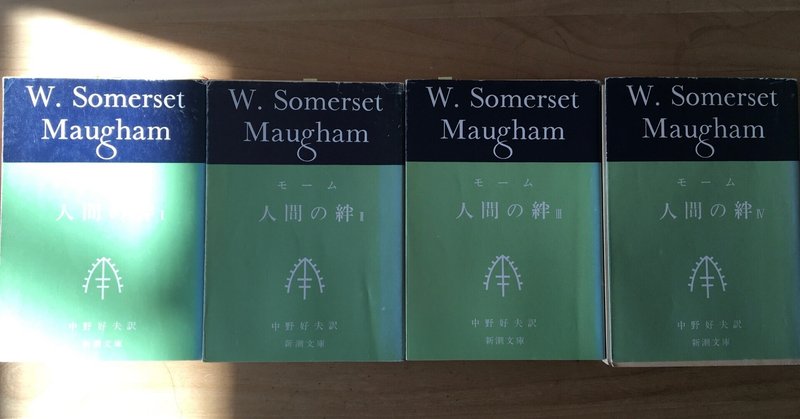
【1周年】#186『人間の絆』サマセット・モーム
本当に素晴らしい作品である。全4巻でとても長い。長いので、今日という日まで読み直す機会がなかった。丁度ヘルニアと思しき症状になってしまい、床に伏せっていた3日間。読み続けた。
「教養小説」というジャンルは若き日の私が自分の執筆舞台と見なしたものだった。最初の大きな衝撃はヘッセの『デミアン』で、『シッダールタ』『知と愛』がそれに続いた。しかしこの2年ほどの間に上記の内の後二作を読み直したが、当時の感動はもう得られなかった。ヘッセの物語は概説的、耽美的、思想的、自己中心的という所に大きな短所があると思う。かなり勢いで書いている。緻密さはない。それでも若い時分にはかなり引き込まれるのが不思議で、どうも若さとヘッセの間には奇妙な引きがある。しかしこの魔法も年を取ると駄目である。どれも作品としての完成度は低く、申し訳ないが、全貌のスケッチというくらいの出来に留まっている。
そうなってしまうのにはいくらか宿命的な原因がある。ヘッセが追求したのは内面性だった。人はどのように心と格闘し、心と和解するのか、ということが全てだった。外的現実には興味がなかった。だからヘッセの物語が描くのは徹底的に、主人公が何を考えたか、感じたか、望んだかであって、それ以外のことーー他者の言動や感情や、外的状況ーーなどはあくまでも料理を乗せるお皿か、必要最低限の情報としての背景に過ぎない。だから表現は非常に乏しく、説明は割愛され、主人公が望んだ通りに容易に変質する。結果、主人公があることを望めば、その通りに必ず現実は道を譲る。
ひどく素っ気なく言ってしまえばこれはご都合主義である。しかし悩める若者にはこれがとても響く。なぜなら若者はまだ現実のしぶといその不動性を知らず(認めたくもない)、強く望めば現実の方が折れてくれるはずだと信じている。言葉を裏返せば、自分の信念や感情は、世界よりも強く大きく重要であると信じている。これをロマン主義と言う。
ロマン主義は確かに年を取ってから振り返ると青臭いが、別に悪いものではないし、若者はそうであるのが普通だと思う。むしろそうであってくれなくてはとさえ思う。改めて驚嘆すべきことは、このロマン主義をヘッセが終生手放さなかったことかもしれない。普通だったら、「まあそうは言ってもね」と言ってロマン主義の火を吹き消し、現実世界に妥協するものである。やっぱり、こういうのを才能というのかな。
で、ようやく本書の話なのだが、言うなればヘッセの独白的、観念的、概略的物語を、ほっそりした弱々しく、しかしきらめいた一筋の光とするならば、そこにシークケバブのようにみっしりと肉の厚みをつけて、現実の人生と同じ重みを付与したものが、この『人間の絆』であると私は思う。この肉付けの分は非常に象徴的に、ヘッセが1巻で語りおおせたものが、モームにおいては4倍量になっているという訳である。
20年ぶりに本書を読んで、青春の痛ましさを久しぶりに味わった。自分は何のために生きているのか、なぜ生まれてきたのか、死んだらどうなるのか、そもそも人間とは何なのか、真実とは何なのか、愛がほしい、愛されたい…という強い、強すぎる欲求と願いと問いである。またそこに得体のしれない恐怖と不安、他人への憎悪と依存、優越感と劣等感、性欲や闘争心が絡みつく。もう本当に苦しいと言ったら苦しいことこの上ない時代。それが20代である。
年を取れば「まあ、そりゃそういうものだよ」「若い頃は分からないけどね…」なんてことを言えるようになるが、渦中にいる時には息をつく間もない。大人が平然と受け入れている現実を受け入れることが全く出来ない。だから平然と受け入れている大人を軽蔑する。そして正義感と理想だけはやたらと大きく、しかし生き抜く力は全く無いので世の中からはてんで相手にもされない。
それを後年、惨めと見るか、青臭いと見るか、それとも美しいと見るか、羨ましいと見るか。それはその人がどのような青春を辿ったかによるのだろう。若さだけがもたらす狂気と混沌と欲求に翻弄された人は、若者の、我が身を神話化して悲嘆するその姿も、良きものとして見つめることが出来るだろう。
フィリップの心の中に沸き起こった苦しみとその中で見出した答えに対して、私はとても大切なことを思い出した。自分もまたそうだった。しかしいつからか、そんな自分は過去のものになったのだということを。初めてこの本を読んだ時、大学生だったはずだ。今は42歳だ。私は普通とは違う仕事をしている。そのおかげで内面を見詰める時間は人よりも何倍もあるし、ほとんどそれは仕事と直結してもいる。その意味ではいまだに青い所のある自分。この経済社会の激しい摩擦と緊張の中で生きている人たちからしたら、ひよっこのように柔らかい肌と心をしている。が、それでもなお、本書を読んで、自分は年を取った、こんなふうに空が落ちてくるほどの悩みに苦しまなくなった…と気付いた。それが良いかどうかは即断出来ない。今の自分は「空が落ちてくるなら落ちてくる。それが神の意志なら私には受け入れることしか出来ない」と、まあこんなふうに考える。かなり魂の温度は下がったと言える。
フィリップはそうではなく、なぜ空は落ちてくるのか、そんな不安定な世界に生まれ落ちてしまった自分とは何なのか、人間とは何なのか、生まれてくるとは何なのか、と問いが広がっていく。行き着く先は絶望であり、それを理性によって乗り越えようとした時、ニヒリズムに到達する。ただニヒリズムは結局詭弁の域を脱することはなく、否定的である。価値ある答えというものは肯定的でなければならない。フィリップは幸運だった。彼はそこまで行き切った末に、理性的理解を超えた愛に出会うことが出来た。要するに身も蓋もない言い方をすれば「それでも僕は愛する人に出会えたから幸せなんだ!」というのが本作の結論。
本当に、凄い身も蓋もないけれど。でもそれで良いと思う。頭で考えて分かろうとして分かろうとして、分からなくて…要するにこれが若さ、未熟さというものの真髄なのだと思う。成熟するということは、「頭で分かるということは所詮、全貌把握のために使える機能の何割かでしかない。心で分かること、肌で分かることもあるし、むしろそちらこそが重要である」ということを知ること、それを何度も何度も繰り返し体験することなのだと思う。だから、心で、肌で理解する、という入り口に立てた時点で本作は終わっている。
うむ、実に明晰な書評だ。
後半、読み飛ばしても良いかなという箇所もありつつ、またちょっと終盤に向かって展開が早いかなとかちょっと無理かなと思う箇所もありつつ、全体として非常に整っていて厚みと豊かさがあり、笑いもあり、非常に深い感動を与える作品。顎が外れるほどのあばずれの悪行、愚行、そんな女に翻弄されるフィリップに「おまえ!しっかりしろ!」と何度心の中で叫んだことか。しかしその彼が次第に曲がりくねった道から辿るべき一筋を見つけ出していく過程は、大きな解放感を与えてくれる。フィリップが、そしてモーム自身が恐らく嫌悪していたのであろう伯父が投影されている伯父については、私はこの歳になって読み返すと「優しい、良いおじさんじゃないか」と思って弁護したくなった。確かにケチで俗物だが…子供の頃のフィリップの手を引いて教会への道を歩く姿など、ほんの数行の描写ながら、子の親となった後の身には、深く響くものがあった。本人がどういう評価を過去に下しているかは別として、その過去は不器用ながらもわずかながらも温かさがあって始まったから、絶望を超えて再び温かさに向かっていくことが出来たのだと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
