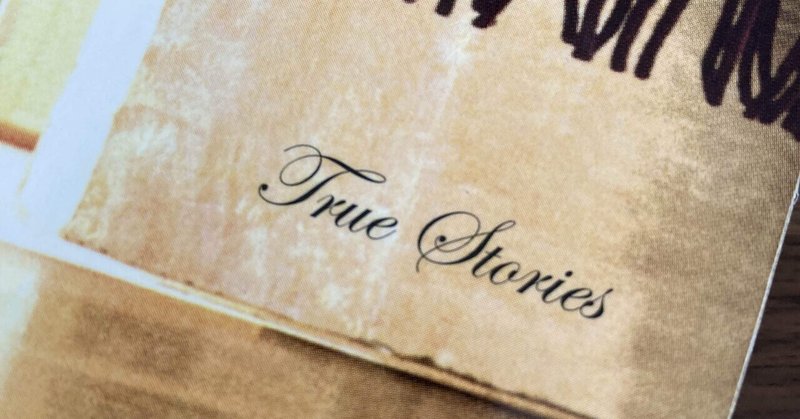
Cパラニューク“Stranger than Fiction”を読んで
“Escort”については別のエントリで書いたのだけど、他をまとめて。メモです。
Testy Festy
モンタナで開催される性の祭典。
初っ端からすごいシーンで始まるんだけど、チョコレートプティングとか、どこまで本気でやってるのか分からない。性衝動と、面白おかしくしてやろうという思いと、面白おかしくやらないとやってられないという思いと、面白おかしくやることを求められている感じが交錯している気がする。
Where meat comes from
レスリングに魅了された男達。
減量や練習はキツいし、ひどい怪我を負う。それでもレスリングに戻ってきちまうんだと嬉しそうに話す男たち。
でも彼らのほとんどが地方の体育館でキャリアを終える。切ない。何偉そうに言ってんだアマのくせにって思ってごめんね。
試合に負けた選手たちは、明日は月曜だ仕事があると解散していく。「力を出し切ったってことが大事なんだ。ゴールを据えて、目標に向かって全力疾走してみたっていうことがさ」。
You are here
映画スタッフの面接に集まる脚本家志望者。みな自分が何に苦しんでどうそれを克服したのかを売りにきた。いわゆる「太陽が輝いて、鳥たちは歌っていて、パパは私の上に乗ってる」文学。この響き好き。でも大体採用されない。せっかく人生を切り売りして、このトラウマを未来に残してやろうと思ってたのに。
後半はパラニュークの持論が展開される。面接はどこいったの。でも読ませるんだからすごい。時間切れです、と言われても、分かった分かった、でもさあ、と話し続ける(若)パラニュークが見える。相手の決めた設定時間に負けちゃダメだ。
Demolition
13日の金曜日、オンボロコンバインを戦わせる試合が開催される。
3000人によるPledge of Allegiance。帽子をとるとらないで怒号が飛び交う。軍にいる息子のために米軍の旗掲げて中東を揶揄するコンバインを運転する父ちゃん。バーベーキューも始まっちゃって、ザ・アメリカの田舎って感じで好き。でも参加者は身を気遣ってくれる奥さんがいたり、身持ちの堅い職業についてたりする。
畳み掛けるような詳細な描写と暴力性がパラニュークっぽい。
Live as a dog
白人男性は壁紙と一緒。よくも悪くもジロジロ見られない。じゃあ注目されるってどんな感じなんだろう?
ということで犬の着ぐるみ着てみました(えっ)。サンタフェスでは500人のサンタが暴れまわってもなあなあなのに、僕たちは美術館を追い出されます(そうでしょうね…)。
行く先々で殴られたり石を投げられたり、若いお姉ちゃんに写真を撮られたり。しかしこういった人たちはみんなサングラスや車の窓、ファッションという名のマスクを着けている。
Confessions in stone
シアトルからオレゴンに向かう飛行機から見える城。アイダホには個人が建てた城が多いらしい(https://1043wowcountry.com/no-wonder-there-are-so-many-castles-in-idaho-we-have-a-family-owned-castle-building-company-in-sandpoint/)。
見物客が入り込んだり、湿気に弱かったり、漆喰がボロボロになったりする。子どもは城のことで揶揄われるし、妻は来訪者の多さにうんざりしている。
一軒目を建ててから大学に行って建築を学んだりして、城を建てても建てても満足することはない。
趣味にせよ暇つぶしにせよ、今日も城はそこにある。男たちの懺悔の現れとして。モデルはディズニー映画だけど。
Frontiers
マッチョな男の腰巾着をやっていた僕はステロイド剤を処方されて男らしく良い気分になる。
ステロイドを使用し続けた老人の遺体を解剖しても、ボディビル雑誌の「あの人は今」コーナーの体を壊した男たちの写真を見ても、僕はステロイドをやめない。
けれどあるとき睾丸がほとんどなくなっていることに気付いて、とうとう薬をやめることにする。そんな僕は…
読みやすく、面白かった。こういうよく分からないモヤモヤしたもののために身を滅ぼしていく人間の話ってたまらない。
The peple can
潜水艦乗組員としての日々。金属に包まれて、船内の空気は一応処理された誰かの吐息。眠る時はすぐ横に核ミサイル。
独自の文化を形成する船内。なかなか楽しそう。あと数日で家に帰れるとなるとめっちゃテンション上がっちゃって寝れなくなるのでピザとか貰える。そして港には家族や恋人が待っていて、キス、キス、キス…。
なーんて、こんな綺麗に終わるはずがない。なんか大人しいなと思ったよ。
自殺しないでね、と書かれた貼り紙。生きるって大変だ。
The lady
自宅に住まう幽霊の「レディ」に悩まされる友人から電話がかかってくる。
僕は友人がバカンスに出かけている間、家で過ごさせてもらうことにする。未来が見えるとかいう面倒くさいタイプの人間たちをパーティに招く。
そいつらも幽霊が見えると言うので始めはバカにしていたが、守護霊やら自分でも忘れていたトラウマやらを掘り当てられる。
けれど目に見えない世界なんて僕は信じない。その理由がね…。
In her own words
女優ジュリエット・ルイス(1972-)のインタビュー。
ジュリエットは映画「ファイト・クラブ」にも出たブラッド・ピッドの元カノで、サイエントロジーを信仰している。トム・クルーズやジョン・トラボルタも信者として有名。
家族の話、女優としての話、サイエントロジーの話の合間合間に、支離滅裂な質問リストを読み上げる。しかしそれに答えることはない。
この話はなんだかよく分からなかった。とりあえず最後のタクシーの話は面白い。
Why isn’t he budging?
同性愛者である政治コメンテーターのアンドリュー・サリヴァン(1962-)。
「人に言われるんだよ…『あなたはどの集団からも距離をとってる』って」「自分の役割が分からないんだ。…ある立ち位置につけば、代弁していたはずの集団から責められる。…」
そりゃその集団の中身だって色々でぴったり一致することなんてない。人には色んな側面や属性があるから。でもその集団に属する人は代表には自分と同じ気持ちでいてほしいんだろうね。勝手に自己投影されて、期待される側も困るだろうけど、声をあげられない人は誰かに望みをかけるしかない。難しい。
Not chasing Amy
Amy Hempelの“The Harvest”(1998)ほかを礼賛する話。(片付けの方ではない)ミニマリズムについてで、はあなるほどなあという感想のほかに、作家って自分自身と向き合うことばっかやってて大変そうだなあと思った。あと幻想を打ち砕かれたら怖いから、どんなに憧れてる人でも実際に会うのは嫌だっていうのも分かる。タイトルは誰に向けての言葉なんだろう。
Reading yourself
マリリン・マンソン(1969-)はタロットを捲りながら語る。
「人が見たり聴いたりしてくれるようなものを作りたいなら、まず君が人に耳を傾けなきゃダメさ」。深い。
マンソンは語り続ける。家族のこと、音楽のこと、コロンバイン高校銃乱射事件の犯人に悪い影響を与えたとバッシングされたこと。
女性が部屋に入ってきたときと出ていくときは立ち上がるマンソン。年老いた両親のために家を買ってあげたマンソン。いろいろ大変だけど頑張って前向きにやってる感があるぞマンソン。がんばれマンソン。
Bodhisattvas
1998年、ハリケーン・ミッチの被害を受けたホンジュラスで救援活動を行った女性が語る。
元保護犬を連れて行った先は、死体の臭いが鼻をつく泥だらけの町だった。生きている人を救助したいのに、見つけるのは死体ばかりで落ち込む犬たち。たまに生きている人に会わせてあげると喜ぶ犬たち。「それで良いのよ。あなたたちは良いことをしているわ」と褒める飼い主。
「私は菩薩の存在を信じているの」。周囲を明るく照らし助け出す存在、犬こそがそれだと言う。犬のおかげでまともな人間になれている気がすると。犬モノほんと弱いからやめてほしい。
Human error
おもちゃ発明家ブライアン・ウォーカー(1956-)は、有人ロケットを製作すると豪語して有名になった。その後どうなったのか。
ADHDでディスクレシアで後年は躁鬱を公表したブライアン。ロシアとの友好を掲げネットで知り合った子持ちのロシア人と結婚したものの、彼女がネットで獣姦ばかり検索していたことをきっかけに別居。落ち込んで何もできなくなったブライアン。ロケットコンテストでは資本も教育もある周囲を見てさらにダメージを負う。有名になったことでファンやマスコミにも追われ傷を癒す暇もない。
けれど彼はまだ夢を諦めていなかった。彼の作るロケットの機内にはなんの操作盤もないからヒューマンエラーの心配もなし。ブライアンはロケットの先端に立って、一番高いとこまで行ったらロケットの先端がとれてパラシュートが飛び出すのでそれで着陸する。かくして歴史的偉人の仲間入り。
町々を飛ぶグライダーも作ってるところだし、ゴーカートも作ってるし、新しく女性を紹介してもらったし、愛も、名声も、家族も、まだまだこれから!あと山火事を一発で消すジェットミサイルみたいなのも作れると思うし、時空移動は厳しそうだけど瞬間移動はできると思う。
「昔あったテレビ番組みたいに、歴史上の人物に種付けしてあちこちで子孫を繁栄させたいんだ。クレオパトラだろ、マリー・アントワネットだろ、そんで殺されそうになったら逃げてさ。そんで結局、オレ自身は何も果たせないっていう…」
どうしてこんな悲しい話書くの?
Dear Mr. Levin,
人間はあまりに手に負えなさそうな問題からは目を逸らして現実逃避する。じゃあ人はどうしたらそれを真正面から見れるようになるのか。アイラ・レヴィン(1929-2007)は、はじめにユーモアで魅了してきて、次に最悪なシナリオを展開することで、逃げ場がなくなるまで追い詰めて、日常に隠れた恐怖に対面させてくる。
しかも内容は10年くらい先に流行る話だったりする。中絶議論だったり、フェミニズムに対する男性の反発だったり、監視社会だったり。先取りして視聴者に恐怖を与えた上で、将来どうそれと相対すれば良いのかを教えてくれる。
ショック療法的なものか、それとも「あれに比べたら今の生活はマシ」と思わせるためか、いずれとしても、レヴィンの作品は生きることの恐怖を和らげてくれる。
ホラーって、お金払ってまで怖い思いなんてしたくないから避けてきたんだけど、なるほどそういう視点から前向きに観てみようかなあ。
Almost California
『ファイト・クラブ』が映画化した。飛行機を降りればマスコミに囲まれ、サイン会はフラッシュが眩しくて、ポーズつけて雑誌の表紙とか飾っちゃう。
でも高級ホテルのジェットバスは1時間してもお湯が溜まらなくて、手に持ったお酒はぬるくなってきた。ダメだって書いてあったのに強力な除毛剤を使って頭を剃ったものだから超痛い。見た目を良く見せようとしたために失敗したんだってバレるのすごいやだ恥ずかしい。
初めての長編小説が売れに売れて、急にセレブの仲間入りしたことへの戸惑い。ショービジネスへの反発と争いきれない心。『サバイバー』のそれはこれだったのね。
The rip enhancer
ブラピの唇。大きくてぷっくりした唇って良いよね。とりあえず25ドルで唇増大ツール買ってみた。吸引力を使ってぷっくりさせるんだって。ペニス増大ツールとか乳首増大ツールとシステムは一緒。近い将来、みんな大事なイベントの前にはこういうの身体中にくっつけて整えてから出かけるようになるんだ。ちなみに唇増大ツールのHPは921人目のお客様、ペニス増大ツールは50万人目のお客様だった。
2分たっぷりツールをつけてみたけどブラピみたいにはなれなかった。Dの発音がBになっちゃうだけ。だから洗って人にプレゼントすることにする。
こうしたツールは今こうしている間にも、何かが自分を助けてくれるんじゃないかって思ってる自分みたいな人間の元に届けられている。
爆笑させたと思ったら不意をついてハッとするようなこと言うからすごい。バカだなーって思ったかもしれないけど、形は違えどそういうの買った経験みんなあるんじゃないの。高尚な本とか、頑張って進学した良い大学とかさ。
Monkey think, monkey do
『ファイト・クラブ』を読んだ人から「ああいう悪戯、実際やってますよ!」とよく言われる。真似するやつが出てくるから映像化はよくないって言われたけど、元々やってる奴らはたくさんいる。人はルールを与えられるとそれを破りたくなってしまう。それが自由を証明する唯一の手段だからだ。
これは実現できそうだぞ、と思ったら、それをやってしまう。学校での銃乱射も、ステファン・キングが書く前は存在していなかったと言うけど、キングがそれを発明したわけでもなし。
テロ犯を事前に捕まえることができても、そいつを死刑にしたら共鳴者がまた別の事件を起こす。それぞれが置かれた状況に対応しながら自分なりに生きていくんじゃなくて、自分の可能性を否定してよその誰かを攻撃する人生。
まさにタイラーの崇拝者のことで、『ファイト・クラブ』が悪影響与えること、すごい気にしてたんだなあ。
Brinksmanship
ストリッパーがいて、ゴキブリがビールに溺れるようなバー。友達が入院してる病院に一番近いから、ここに通っている。ストリッパーに「若い内からこんなところに来て、年取ったらどうするつもり?」と聞かれる。そうこうしてる内に友達も、友達に寄生していたガンも死んだ。
ある日は床を磨いていた。ある日は病院に行ったらこのままじゃ肝臓がやられるって言われた。ある日は尿管結石が出てきた。ある日は『ファイト・クラブ』の授賞式だった。ある日は、肝臓の不調を指摘してきた主治医が死んだと連絡が来た。
チカチカとしたライトのように人生は目まぐるしく変わる。義兄が死んだ。父も死んだ。祖父は最近発作が頻発していて、親友からガンが見つかったと連絡があった。でも仕事があるから、それをやらなきゃ。
人はいつか死ぬし、それはいつかは分からない。ヒーローは来ない。どう生きるか、ちゃんと考えないと。
Now I remember..
ホテルのレシートが出てきた。こういうものがないと何でも忘れちゃう。父さんや爺さんがどんなガラクタでもいつか使うんじゃないかってとっておいてたみたいに、残しておかないと。
本もそうだ。モノを書くことで人は記憶を伝達し情報を拡散することができるようになったというけれど、もっと重要なのは、メモ書きが人の思考にとってかわるようになったということ。
メモは何も教えてくれない。質問しても答えてくれない。でもこのホテルのレシートがなかったら、人前で自分のペニスを吸うチワワの話とか、ヘアピンつけたままグラミー賞の会場に行ったこととかすっかり忘れたままだった。
有名になったことで小説やひいては本全般に関して自問自答し、不信や悩みを抱いていたのが分かる話。
Consolation prizes
『ファイト・クラブ』が映画化されて以来、あちこちで「ファイト・クラブはどこにあるのか」と聞かれる。いつか誰かが勝手にファイト・クラブを作り上げるのかも。もうあるのかも。空っぽの人生や不在の父親の怒りをぶつけるクラブは。
『ファイト・クラブ』は、あの映画は、監督であるディヴィッド・フィンチャーのものであってもはや自分の作品ではない。
親子関係もそんなようなものなのだろうか。いつの間にか自分の手を離れて勝手にやっていく。
父が殺される前、鶏小屋の床をメッシュにしたらどうかと話したら、鶏は自分の巣にはフンをしないと言われた。七面鳥はオスが小鳥を温めてやるんだと言うので、動物のオスでそんなに母性のある種はいないと言ってやった。けれどどうやら二人とも間違っていたらしい。
そんな風に思えるパラニュークは、ファイト・クラブに行かないだろう。父は不在だったかもしれないが、全知全能の神ではなかったし、不在になったのは彼のせいではないし、殺されてしまえるほどに人間だったと分かっていれば。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
