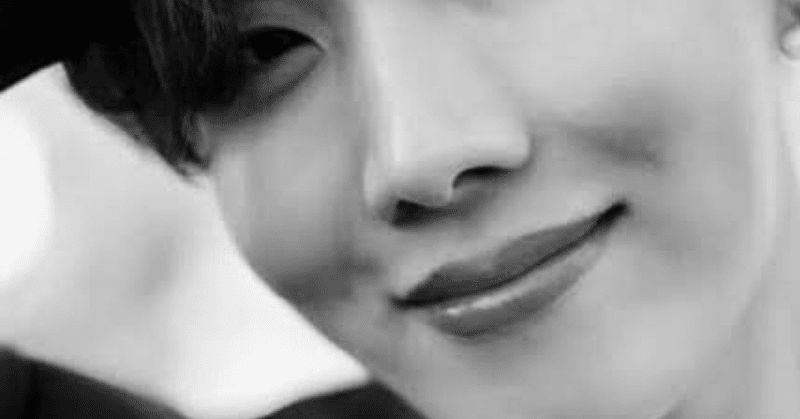
私の好きな人 最終回
ホソクさんに「時間ある?」と呼び止められて、私の心には何かを期待する気持ちとどうせ何も起きないだろうという冷めた気持ちとが同居していた。ホソクさんの向かい側に座り、彼が「xx社なんだけど…」と話を始めた瞬間、私の心はサーッと一切靄のないクリアな世界になった。いつも余計なことにドキドキしたり、ないことを想像して笑みがこぼれたりする煩悩だらけの心が綺麗スッキリ掃除されてしまったような、そんな感覚。
——この恋は、終わった。
そう思った。長い、片思いだった。
チェックシート式みたいな無味乾燥な質問にYesとNoと数字で答えるような、そんな形式的なやり取りを終え、私たちは店を出た。
クリアになった私のハートと同様、夜空には雲ひとつなかった。風もないのにツンとした空気は今がもう完璧に冬であると主張しているようだ。
「おー、寒いなぁ」
ホソクさんは上質そうなカシミアのマフラーに少しだけ顔をうずめて、私の襟元に手を伸ばした。
「はいっ?」
「襟、折れてたよ。もう大丈夫」
「あ、ありがとうございます…」
奥二重の小ぶりで柔和な瞳。そこに少し皺を寄せて優しく微笑む私の好きな人。深い恋の沼からやっと這い上がれたとさっきまで思っていたのに、やはり私はまだ沼の中にいるようだ。ホソクさんの笑顔がある限り、私は永遠に救われない恋の囚人なのかもしれない。
「今日俺、とんだ恥かいちゃってさ。ここ最近デスクに埃が溜まるようになってたから業者が変わったんだと思って問い合わせしたんだよ。でも何も変わってないらしくて。それで隣の部長に掃除の人がサボってるって愚痴ったら、デスクの拭き掃除なんてずっとされてないって。もしデスクが綺麗なら、それは会社の誰かがしてくれてるってことだ、って」
「あぁ…」
「…森山さん、でしょ」
「…はい」
「やっぱりー」
ホソクさんは独特の低いしゃがれ声で、謎が解けたことに満足したような安堵の声を吐いた。
「俺ね、自分の身の回りのことは全部把握していたいタイプだし、結構そう出来てる自負があったんだよ。だけど全然気付いてなかった。灯台下暗しっていうか、自分の恵まれた境遇に甘えきってたっていうか」
私を思い出してくれたことは嬉しいが、長い間ずっとホソクさんに片想いしていたことまで悟られた気がして、私は微笑みかけるホソクさんの目を見られず俯き気味に頷くことしかできなかった。
「それで今日は一日中、森山さんのことばっかり考えてたんだよね」
ホソクさんは「へへへ」と恥ずかしそうに笑いながらこめかみを掻いた。
「って、そんなこと話す予定はなかったんだけど、今なら酔ってるし、酒のせいにもできるかなーなんてね。あはは、ちょっとズルいかな」
「いえ、酔ってるからできる話って、あります」
「だよね?…で、あのさ、さっきの"既存"ってやつだけど」
予期せぬ単語に驚いて視線を上げたのと同時にホソクさんは立ち止まり私に視線を落とした。少し先に駅の改札に続く長い通路の入口が見える。蛍光灯が眩しく、人工的で、無機質で、いつも見ている景色。でも私は今、冬の澄んだ星空の下で、何年も恋焦がれている相手と見つめ合っている。
「森山さんは、俺の"既存"?」
「あ…その…私がホソクさんの"既存"だなんて、とてもおこがましいんですが…上司部下という関係でお互いをよく知っているので、''既存"という言葉を…」
「じゃあ"既存"の森山さんは俺の恋人候補になるのかな?」
恋人候補、というワードが脳にガツンと響いた。そんな言葉を使われて喜べるくらい、私はホソクさんに恋している。私は覚悟を決めた。
「というか………私が好きなんです。ホソクさんのこと、ずっと、大好き、なんです……すみません」
ホソクさんは私に近づき、そっと、ゆっくり、優しく私の髪を撫でた。
「どうして謝るの」
「…」
「俺も、だから。部下だからそういう目で見ないようにしてきたけど…」
優しさの後光が差しているみたいなホソクさんの柔らかな微笑みは、迷い子のような私の顔を明るく照らした。ホソクさんは少しだけ屈み「先に言わせてごめんね」と囁いた。予想だにしていない展開に、私は自分がどこかで倒れて夢の中を彷徨っているだけなのではと思った。言葉ももう、何も出てこない。
「俺、かなりハードな彼氏だと思うけど、森山さん大丈夫そう?」
「は、ハード、とは…」
「多分、俺の彼女になるのは俺の部下になるより大変だと思うよ。ついて来れる?」
「は、はい。よくわからないけど、頑張ります」
「ははは。その代わり俺は甘えるのが下手な森山さんを甘えっ子に育てるね」
ギュン!甘さゼロの5年を過ごした私には糖度が高すぎるホソクさんの言葉で今にも窒息しそうだ。でも、二人の間に生まれた甘い空気を吸って、憧れのホソクさんと恋人関係になれたらしいことをじわじわと実感する。
「森山さん、明日、予定は?」
「何も、ないです」
「じゃあ迎えに行ってもいい?」
「はいっ」
「うん、決まりね」
元気よくそう言うと、ホソクさんは私の背中にそっと手を当てて歩き出した。私の背中は彼のしなやかな指の圧を感じていた。歩く時の振動のせいで彼の指は私の背中を優しく這うように動いた。気絶しそうだった。指がコート越しに背中に触れただけでこんなに感じてしまうのに、果たしてホソクさんに直接触れられたら、私はどうなってしまうのだろう。明日の行き先についてずっと話しているホソクさんの横で、私はそんな馬鹿らしい心配ばかり膨らませた。
・・・
「上司と部下って感覚は抜けないね、なかなか」
遅いから家まで送ると譲らないホソクさんは駅から家までの坂道を歩きながらそう言って笑った。
「私は…ずっと上司のホソクさんを好きだったから今のこの感じで十分、幸せすぎるくらいなんですけど…」
「森山さんが良くても俺が嫌だよ。これから二人でいる時は恋人の関係じゃなきゃ」
「…はい。私も、二人の時は部下って思われたくない、です」
「でしょ?どうしたらいいのかなぁ…あ、名前か。森山さんなんて呼んでるからダメなのか」
「あぁ、確かに」
突然、ホソクさんは私の腕をぐいっと掴んだ。見上げると、真剣な顔の彼がいる。
「…ちひろ」
!!!
身体が固まって心臓は止まって時も止まった気がした。それなのに、ホソクさんはぷっと小さく吹き出して自分の頬を両手で押さえた。
「おー!これはー、やばいぞー。すごい恥ずかしいぞー」
「え…」
「いやいや、初めてだったから。いずれ慣れるさ」
「もう、私…死ぬかと思いました」
「死ぬ?」
「心臓止まるかと…」
「これくらいで?ははは。そんなんで俺たち、どうするの、これから」
「うふふ。もはや修行ですね」
「…じゃあこれは?」
気付いた時にはもう身体は抱き寄せられていた。ホソクさんの刺すような視線にたじろぎ、瞳を閉じると、唇が重なった。私の唇は優しく丁寧に啄ばまれ、甘やかされ、ロマンチックに溶かしほどかれる。気持ち良すぎて身体が宙に浮いていくみたいだ。ふわふわと夜空に飛んでいくような感覚の中で、私は「上手なキス」の何たるかを知った。これまでのキスは普通のキスで、ホソクさんのは、最上級だ。
唇が静かに離れる時、ホソクさんの鼻が私の鼻に当たった。真剣な表情が緩み、彼はわざと鼻先をちょんちょんと擦り合わせた後、いたずらっぽく「どう?」と囁いた。
「もう1回…」
ホソクさんの襟元にしがみついたまま、さっきのキスの酔いから醒めることができない私はそう小さく呟いた。再び瞳を閉じる間際、ホソクさんの優しい瞳と綺麗な新月が見えた。私はそのまま、冬の夜に溶けた。
fin.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
