
この国に坂内がある限り
「石川県でおいしいラーメン屋ってどこ?」
この地に生まれ、純粋培養で大学生にまで育っていた僕は、しかしこの県外出身の同級生の質問に思考停止した。
ラーメン…?
おいしい…?
ラーメン屋とは…?
「ごめん、わかんないわ」
さっきまで調子よく加賀百万石を統べていた傾奇者も形無しだ。
石川はどちらかと言えば関西うどん文化圏。実際、インターネットで10分ほど調べてみると、47都道府県のうち、ご当地ラーメンが存在しないのは、何と石川だけである。
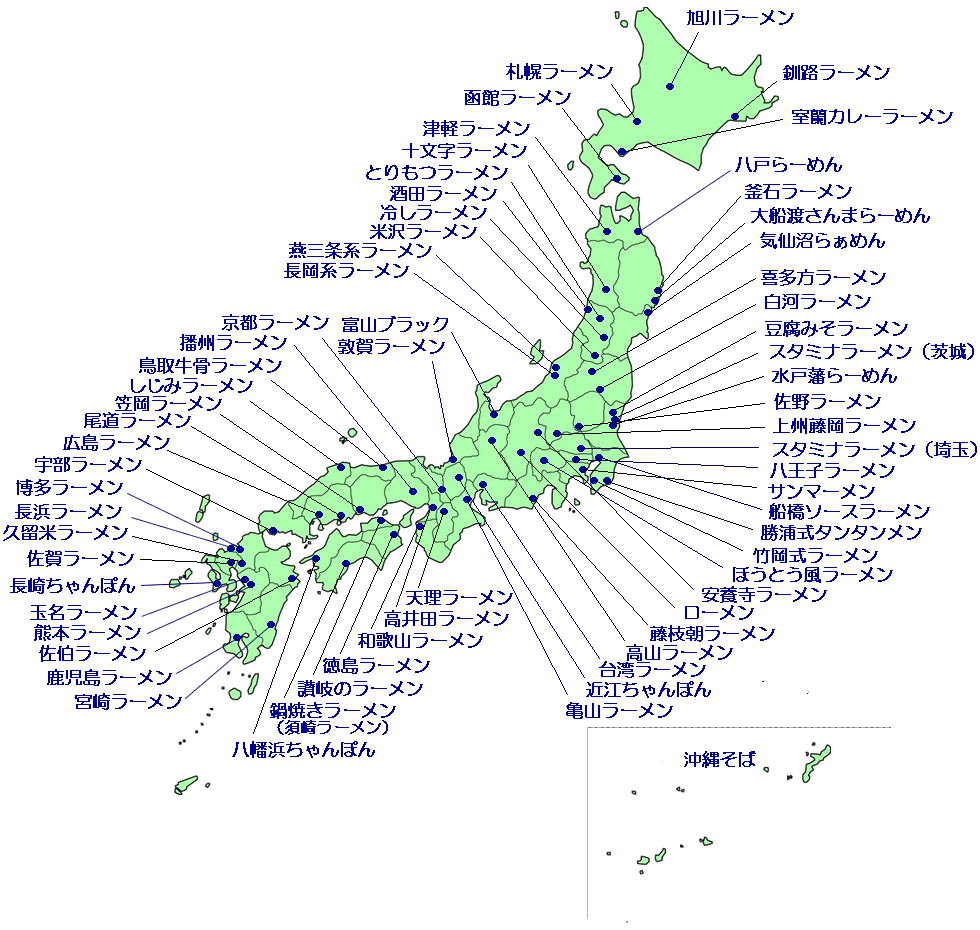
出典「フライフィッシングとネコと戯れる休日」様ホームページ
この国には何でもある。だが、ラーメンだけがない。ここで言う「国」とは石川県のことである。
個人的には山梨の「ほうとう風ラーメン」なんてだいぶ強引だと思うのだが、石川にはそういう紙一重の代物すらない。
いや…あれはどうだ?
石川県民に「なんでやろ?」とコールすれば必ず「8番!」とレスポンスが返ってくる、そのキャッチコピーでお馴染みのチェーン『8番らーめん』があるではないか。
いやいや。
8番はいわばファミリーレストランのようなもの。看板メニューの『野菜らーめん』も全国から見繕った野菜を、味噌・塩・醤油・とんこつ・バターと好きなスープでいただける、何でもござれのノンポリラーメンだ。
冒頭のやり取りは1998年のことだったが、その頃は全国的なラーメンチェーンはこの国にはなかった。そもそもラーメンをグルメの範疇で扱う感覚もこの国にはなかったと思う。ここで言う「国」とは石川県のことである。
当時、ラーメンとは中華料理店のメニューの一つであり、家庭においてはイトメンの『チャンポンめん』のことであった。
『チャンポンめん』は、トリップ感の強い原色イエローのパッケージと、ラリった感じの蚊みたいなキャラクターが目印。発祥の地、兵庫県と同程度の販売シェアを有する石川ソウルフードの一つである。「あっさりとした上品な味が石川県民好み」とされる。兵庫県民の気質のことはどうでもいい。
メルクマールの一つとなる、『きどたまよのラーメンでいこう!ー石川・富山・福井必食の200杯』(木戸珠代・倶楽部ムック文庫)がドロップされたのは、時代を下ること2000年のこと。ラーメンが有意なトピックとして扱われるには、我々石川県民はミレニアムを待たねばならなかった。
一躍到来したラーメンブーム。嬉々として北陸ラーメン巡りを始めた友人達。しかし、僕は「こいつら、最初に毒キノコを食べて死ぬタイプの人種よの」とブームには乗らない姿勢を貫いた。車、持っていなかったから。
サッカー日本代表の柳沢選手の実家が富山の有名店だとか言って遠征する者達もいた。いや、そこ8番らーめんじゃねえか。
確かに8番はフランチャイズ形式のチェーンでありながら、店舗によって個性があった。「俺の同級生の女の子の家が8番でよ。彼女の親父さんが作るラーメン、うまかったな。亡くなっちまってよ。彼女、どうしたかな」。僕の親友が遠い目をして語っていたことがある。また8番らーめんの話になってしまった。
このように石川県で加熱したラーメンブームを見てもなお、僕はラーメンとは出逢えなかった。車、持っていなかったから。
Time flies. 時は経ち。
2002年に大学を卒業して地元で就職し、2004年に転勤で上京した。僕もあれから二回目の引っ越しをして、何だかんだとつらいこともたくさんあるけれど、
転機となったのは、一回目の引っ越しで移り住んだ町、江東区木場だった。
この町には、ラーメン屋しかない。
いや、もちろん焼肉屋も蕎麦屋も定食屋もある。しかし、現実には存在しない。
どういうことか。
この町には江戸以来の下町コミュニティが形成されている。それらの店舗はローカルの人々のもので、僕のような根なし草の居場所はないのである。
店に入ると店員さんとお客さんが親しげに会話をしている。その中に、職質寸前の身なりの男が黙って紛れ込む。これは気まずい。逃亡中の指名手配犯の気分だ。
銭湯に行けば消防訓練上がりの青年団がいる。その中に、いくらでも町に貢献できそうな若い男が一人黙って紛れ込む。これは非常に気まずい。ちなみに木場の銭湯のお湯はどこに行っても死ぬほど熱いが、誰一人として水を加えようとはしない。
入れない。この熱い湯には。
そんなわけで自ずと万人向けチェーン店を選ぶようになり、そんな僕の胃袋に門戸を開いてくれたのがラーメン屋だった。今はもう倒産した180円ラーメンの『びっくりラーメン』、店の名前すら忘れた「京都ラーメン」、そしてもう一つ、僕を救ってくれたお店が『喜多方ラーメン坂内』木場店だった。
ここが僕とラーメンとの出逢いになった。ここまでは枕。ようやく本題にたどり着いた。
「喜多方」という響きが郷愁を誘う。東北、福島だな。雪の降る日に食べる温かいラーメンが脳内に浮かぶ。そう、僕は都会の雪景色の中で、丁度あの案山子の様に寂しい思いをしていた。
僕が坂内で注文するのはオーソドックスな『喜多方ラーメン』あるいは体調が下がり気味の時は細切りねぎをたっぷり載せた『ねぎラーメン』、それに餃子だ。ライスもあれば申し分ない。
坂内の店舗は、探していない時はよく見かけるが、食べたいなと思って探すと近くにはない。恋かよ。僕が京都に出張する時の楽しみは、駅ビルの拉麺小路店に行くことだ。そうだ、京都でも、坂内。
坂内の何がよいのか。世界には、ラーメン愛好家達がその豊富な知見を開陳するブログが五億くらいはあるが、僕は専門的な話はできない。僕はラーメン愛好家ではない。「喜多方ラーメン坂内」愛好家なのだ。
坂内の魅力は「絶妙なリアリティ」にあると言っていいだろう。
そのラーメンの特徴は「手作り焼豚・手もみの太縮れ麺・とんこつの透明スープ」とされる。食べログにそう書いてあった。
ラーメン屋なのに最初に挙げる焼豚は、肉々しい味わい。血の味のするレバーのように過剰ではないものの、「唐揚げは唐揚げの木になっている」と子供が誤答することは決してない、動物を殺めた味がする。雪が降りしきる東北の山中で、マタギが猟銃で仕留めた獲物の味だ。豚だけど。
太縮れ麺は、焼豚とマッチアップしても引けを取らない存在感を持ち、食べ応えがある。炭水化物のまろやかな味わいの中に感じる塩味。クリーンナップが振るバットの如く、麺から放たれる糖質が、生きる力をビシビシ与えてくれる。
とんこつの透明スープは、それだけを口に含んでみると飲み干してはならぬ類の濃さがあるが、風味は油気を感じさせずあっさりとしている。身軽な力士のような、水面下で脚を動かす水鳥のような、涼しい表情からは容易に見透せぬ深みがある。
そして、忘れてはいけないのが店員さんだ。坂内の店員さんは、だいたい垢抜けていない。悪い意味ではない。親戚のような、親しい友人の家族のような、何だか話は噛み合わないんだけれど、よくしてくれる人。そんな感じの方が多い。
おそらく会社の方針なのだろうが、どこの店舗でも、空いたコップにお冷や(麦茶)を注ぎにくる頻度が尋常でなく多い。気になって飲むのをためらうほどだ。
感心するのは、ちゃんと知識を持っていることだ。先日もある店舗でお客さんから「喜多方っていうのは福島のどの辺ですか?南の方?」と聞かれた店員さんが、「北ですね。山形に近いです」と即答していた。当たり前かもしれないが、意外とこういうことは気にしないものだ。
この辺りが、僕が「絶妙なリアリティ」を感じる部分であり、坂内を愛する理由である。
ラーメンでありながら、それが食事であることを感じさせる適度な重み。サービスでありながら、人間を信じたくなる丁寧さ、真面目さ、懐かしさ。現実と交錯するフィクションを見ているうちに、フィクションが現実化していくような世界肯定感、全能感がある。炭水化物のせいかしら。
素晴らしいラーメンだ。僕が死んだ後も、おそらく坂内は生き続けるだろう。
あなたがいつか坂内を食べる時「そういえばあいつ坂内好きだったな」などと思い出していただけると幸いだ。
この国に坂内がある限り、僕は生き続ける。
ここで言う「国」とは石川県のことではない。日本国のこと。いや、もはやワンネーション。それは世界のことである。
あなたの御寄附は直接的に生活の足しになります。
