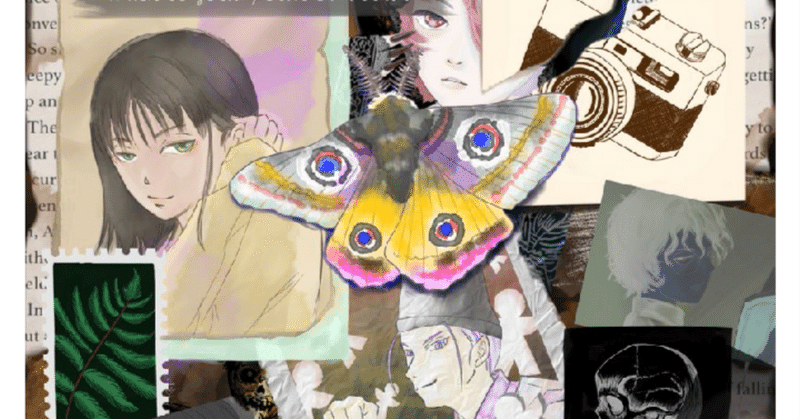
オカルテット4 腐れ縁
主要登場人物



四 腐れ縁
「あ、雨すごいですね……」
「そうね」
今や土砂降りとなった雨が樋(とい)を叩く音を耳に、平然と匙を進める冴歌。
「そ、そういえば鵜ノ目さんのその翡翠色の目はカラコンですか?」
気を遣ってか、星冶がインスタントのカフェオレを運んでくる。
「いえ、生まれつき。純日本人なんだけどね。じゃあ私からも一つ。保志さんのそのパーマは天然? それとも美容院でパーマを当ててもらってるの?」
「あ、僕は天パです。かなり癖が強いので、洗うときと乾かすときにけっこう苦労します」
いささか緊張がほぐれたのか、声のトーンが明るくなる。
「ふぅ。ごちそうさまでした」
「お粗末さまです。お皿ください」
礼を言ってから食器を渡す。
星冶は手際よく洗い、コンパクトな水切りかごに食器を立て掛けた。それから折りたたみテーブルの前に座った。声色こそ明るくなったものの、そわそわと落ち着かないようだ。
「あんな風に息巻かれたら、びっくりするわよね。でも、本当に悪い奴じゃないから」
「は、はぁ……」
沈黙が流れ、二人は何をするともなくそのときを待つ。冴歌はラウンジチェアのそばに置かれた小さな卓上にあるデジタル時計をぼんやり眺める。
その時計がきっかり十五分を刻んだとき、チャイムが鳴ると同時に激しくドアを叩く音がした。
「あら、思ったよりも早いわね」
たちまち星冶の全身に緊張が走る。
「私が勝手に開けるわけにもいかないし、開けてもらえる?」
怯える彼に「大丈夫よ」と声を掛け、その背を押すかのように少し後ろから付き添う。
恐る恐るといった足取りで玄関へ向かう星冶。チャイムとドアを叩く音は止まない。
星冶が三分の一ほどドアを開けた。すると、その隙間からにゅっとたくましい腕が伸びてくる。そして、体をすべり込ませて部屋の中に入ってくるガタイのいい男。黒のジャケットとスラックス、そして黒のビジネスシューズ。インナーは白いTシャツ。
服装的には目立つものはないが、主張が激しいのはその髪色だ。目がチカチカするくらいに明るいトーンのピンクがひときわ目を引く。
「テメェが保志って奴か!」
濡れねずみになっているピンク頭は、そこかしこに水滴が飛び散るのも構わず、むんずと星冶の胸ぐらをつかむ。
「あ、あぁ、はい……」
「初めて会った女を家に連れ込むなんて、いい度胸してんじゃねーか!」
「おお、お二人は、つ、付き合ってるんですか?」
完全にテンパっている星冶の口から思わぬ言葉が飛び出す。
「はぁ!? 誰がコイツなんかと!」面食らった冴歌と大和の声が重なる。
「冴歌! ほんっとうにコイツから何もされてねーんだな?」
「ええ。あぁ……いや、お昼とカフェオレをご馳走してもらったわね」
「はぁ……。そういうことじゃねぇんだけどな」
能天気な冴歌に調子を狂わされた大和は呆れ顔で頭を振り、星冶を解放した。その右手には血管が浮き出ている。
「あんたね、血管が浮き出るほどって……。どれだけの馬鹿力でつかんでたのよ! 保志さんがむせ込んでるじゃない」
「知るか! 元はと言えば、俺との先約をすっぽかして勝手に行動しやがったテメェが悪ぃんだろうが!」
「タ、タオル持ってきます……」
逃げるように洗面台へ駆け込んだ星冶は、バスタオルをおずおずと大和に差し出す。
「サンキュ」
素っ気なく礼を言い、受け取ったタオルでがしがしと乱暴に頭を拭く大和。
「テメェのせいで予定は狂うわ、雨に打たれてセットした髪が台無しになるわ、ほんっと今日は散々だぜ」
「天気予報を見てないの? 今日は曇りで六十パーセントの降水確率。昼すぎから土砂降りになるところもあるって、ネットニュースが言ってたけど」
淡々と言葉を紡ぐ冴歌はさらに続ける。
「だから、ずぶ濡れになったことに関しては、そもそも傘を持って来なかったあんたが悪い」
「そう言うオマエは、それ以外のことに関して反省すべきだと思うけどな」
ああ言えばこう言う。これが冴歌と大和の関係性だ。
「あー、えっと。横山さんでしたっけ? と、とりあえず上がってください……」
消え入りそうな星冶の声に促され、かかとをつぶして靴を脱いだ大和はそのまま靴下も脱いでバスタオルで足の裏を拭く。
「あぁ、着替えも用意しないと」
せわしく動き回る星冶に対して、他人の家にいながらもどっしりと構えている大和は百七十センチとちょっとの背丈。対する星冶は百六十センチほどだろうか、男性にしては小さい星冶。
「ただでさえツリ目でイカつい顔してんのに、いざ対面したら見上げるような背丈の男に凄まれるとか、余計にビビるわよ」
「オレにそうさせる原因となったのは誰なのか、よーく考えてみろよ?」
「あ、あの! ジャージで申し訳ないですが、フリーサイズなので……」
「おう」
「着替え終わったら言いなさいよ?」
後ろを向いた冴歌は、終わったと一声上げた大和と向き合う。が、ほどなく意図しない笑いがこみ上げてくる。
「あ? 何笑ってんだよ」
「だって、芋ジャージ……。ぷっ、くくく……。あまりにも似合わなくて」
ピンクはピンクでも主張の激しいショッキングピンク⸺本人いわく『ピンクパープル』に小豆色のジャージは、思いのほか不格好ではなかったが、これは色合いの問題ではない。
「ジャージとか制服って、誰が着ても似たりよったりで特段洒落っ気もないと思ってたけど、あんたの顔立ちが『似合っているかどうか』っていう概念を連れて来て……くくっ」
表情筋が動くほどに笑いが漏れる。
「す、すみません」
大和は「いや、アンタのせいじゃない。コイツにゲンコツを落とせば済む話だ」と、言うや否や一発。
「痛ったーい!」
「ブリっ子した声出してんじゃねぇ! 四十四のババアが」
「何よ、三十五の元ヤンが!」
今度は冴歌が無言で大和の左頬をペちんと叩く。その頬には、目尻のすぐ下から人中窩にかけて大きく切創痕が刻まれている。常日頃から左頬を気にしているの姿を目にしているだけあって、さすがに今のは失態だったかと思いきや、特に反応はない。
「で? なんか収穫はあったのか?」
仕事モードへと切り替わる大和。
「残念ながら」と、冴歌はテーブルの前に座る。
「じゃあ、ガセネタつかまされて、ガキの足音は聞こえなかったってことか?」
「いえ、その逆よ……」
うつむく冴歌に、大和は怪訝な顔つきをする。
「こういうのは作り話だとずっと思ってたけど、私にもたしかに聞こえたの。それも何度も何度も」
大和は「そうか」とだけ言った。そこにどんな感情が込められているのか、あるいは無感情なのかは繙(ひもと)けないようなつぶやき。
彼は、ところどころ褪色したブラウンのビジネスバックを肩から下ろし、小型のノートパソコンを取り出した。そして、床に座ると膝の上でタイピングを始める。
大雨に打たれたというのにパソコンの保護は万全だったようで、問題なく稼働しているらしい。小気味良い音を耳が拾う。
「あ、よかったらそこのラウンジチェアとミニテーブルを使ってください」
「サンキューな。でも、気遣いは要らねぇよ」
その口調はだいぶ穏やかになっている。
「あの、横山さんは何を?」
「大和でいい。別にどこに提出するわけじゃねぇが、報告書を作ってる。オレはコイツと組んで、今回のアンタみたいな超常現象の調査をしてるんだ」
「そうだったんですね」
突然、冴歌が「あ!」と声を上げると、二人の視線が注がれる。誰とも目が合わないように目線をさまよわせながら、先を続ける。
「でも、一つ気がかりなことを保志さんが教えてくれたわ。保志さんの町会の人が、中心部の近くにある馬頭観音の一体が破損しているのを見つけたって」
「そういうことは早く言えよ」と、大和のタイピング速度が上がる。
「悪かったわね。メモだらけでちょっと忘れかけてた」
「相変わらずのメモ魔だな、オマエ」
「これは保志さんにも言ったんだけど、亡くなった馬を弔う馬頭観音が破損したことで、町全体に今回みたいな異変が起きているのかも」
ピタリとタイピングの音が止まる。
「オカルトなんて信じてねぇオマエが? 本当にそう言ったのか!?」
大和は目を丸くして冴歌を凝視した。冴歌は視線を泳がせながら説明する。
「半分は自分のため、もう半分は保志さんのためよ。引き受けた依頼をこのまま原因不明で終わらせたくないから」
「さすが、その徹底追究の姿勢は相変わらずブレねぇな」
「それから彼。今はだいぶマシになったとはいえ、顔色良くないでしょ? 足音が聞こえていたときは喘ぐほどに苦しんでたのよ。そんな姿を見せられて、よけいに『何も判りませんでした』じゃ済ませられないと思って」
「なるほどな。オマエにも、曲がりなりにも人の心があるってことか」
「ちょっと! それどういう意味よ!?」
二人のやり取りを聞いていた星冶が、ふふっと笑みをこぼす。
「あ、横山さん。よかったらカフェオレをどうぞ。それにしてもお二人は仲がいいんですね」「お、悪ぃな。いただくぜ。コイツとの関係だが、仲がいいかどうかはさておき、付き合いはそれなりに長いからな」
入力を再開した大和は、再びその手を休めて目を閉じた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
