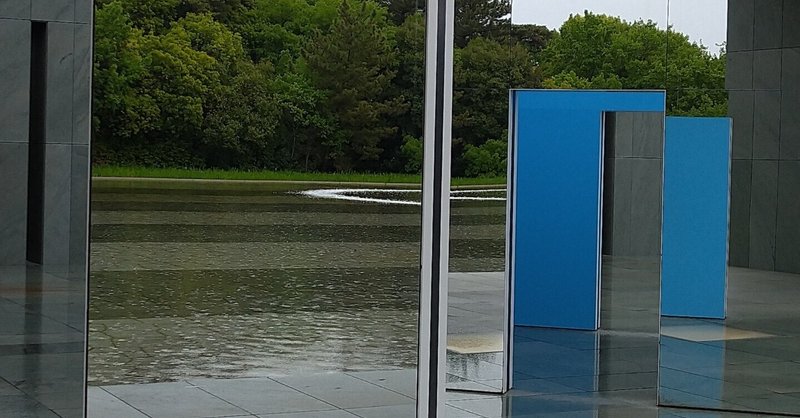
マジックアワーにしか見えないもの
昼と夜の境目、夕暮れ時を表す日本語に「逢魔が時」「誰そ彼時」など、異界との遭遇を思わせる表現があるように、英語でも光と闇が入れ替わる時間帯をマジックアワーというそうだ。このマジックアワーにフォーカスをあてたのが豊田市美術館で開催中の展覧会「サンセット/サンライズ」だ。
最近、仕事で忙殺されて心身ともに余裕がなくなっていたので、リフレッシュできればいいな、くらいの心持ちで出かけてみた。

章立ては以下の通り。第1章を除いては「闇と光」から派生するテーマで統一され、それぞれのテーマに沿う収蔵作品が選ばれ展示されている。
第1章 マジックアワー
第2章 眠り/目覚め
第3章 死/生
第4章 見えない/見える
第5章 黒/白
第6章 終わり/始まり
招待作家 小林孝亘
ゲスト出演の小林孝亘氏は愛知にゆかりがある(愛知県立芸術大学出身)だけでなく、今回のテーマと親和性の高い静謐さと存在感を持つ作風を持ち、収蔵品を中心とした展示、言い換えれば見慣れた作品が並ぶ中に新鮮な風を送り込む役割をしていた。
メインの会場は1Fの一番広い展示室。基本的には反時計回りで観覧順路が設定されているのだが、今回は逆向きでルートが設定されていた。それだけでふだんとは違う世界へ踏み込んだ気がする。そういえばこの展覧会のタイトルは「サンライズ/サンセット」(日の出→日没)ではなく、その逆だ。日没から夜明けまで。夢の世界もしくは魂の世界でもあるし、もちろん夜の世界を混沌とした現状になぞらえ、夜明けを待つ気持ちを表してもいるのだろう。

広い空間にゆとりをもった配置で幻想的な絵が並ぶ。理性や理屈で解釈するタイプの現代アートではなく、作品から受けた印象をゆっくり味わえるタイプの作品が多い。ありきたりな物言いだが、まさに癒しの空間。お気に入りの絵の前に小一時間座ってじっくり作品の世界に浸ることだってできただろう。(あいにく、監視員の方々が数多くいらして、しかも結構視線が刺さるのであまり長居はできなかったが)

コレクション展であるから、展示作品のほとんどがこれまで何度も見てきたものだ。「また会えたね」と思うと同時に「こんな見方もあったのか」と新鮮に感じることもある。例えば、久門剛史《crossfades #4 air》は2年前「らせんの練習」展でも出展されていた作品だ。当時は円周率が作り出す螺旋として見ていた作品だが、今回出展された3作は、それぞれ沈む夕日や深夜の月、そして朝日を表しているかのようにも見えて大変面白かった。
奈良美智《Dream Time》、ライアン・ガンダー《おかあさんに心配しないでといって》、ソフィ・カル《盲目の人々》、李禹煥《風と共に》、横山奈美《ラブと私のメモリーズ》、イブ・クライン《モノクロームIKB65》、エゴン・シーレ《カール・グリュンヴァルトの肖像》等、お気に入りの作品は何度見ても良い。しかし、シーレやクリムト、ベーコンの作品はよほど人気なのか常にどこかの展示室にあるので、グリュンヴァルト氏やプリマフェージ夫人やスフィンクスは少々お疲れではないかと思うほどだ。

ボルタンスキーの《聖遺物箱(プーリム祭)》に遭遇できたのはラッキーだった。実物を見るのはたぶん2回めだが、今回は予備知識がある状態で細部までじっくり見ることができてとても良かったし、空恐ろしささえ感じた。また、初めて見て「これはなんかやばい」と思ったのが、菊の花を題材にした福永恵美《greenhide》で、なんというかギンリョウソウのように脱色された菊の花のたたずまいが恐ろしいほど美しかった。

あくまでも私見だけども、恐ろしさと美しさの同居を可能にするのが夜の世界のマジックだと思う。
「サンセット/サンライズ」展を見終わって次へ進むと、小林孝亘新作展「真昼」の展示室に入る順路になっていて、小洒落た演出だなと思った。太陽が昇れば明るい真昼がやってくる。リアルな世界と対面するかと思いきや、「真昼」展で展示されている小林氏の作品は、画面こそ明るいトーンだけども、ルネ・マグリット作品のような不条理さ満載だ。さらに同じ部屋に荒木経惟《センチメンタルな旅》《冬の旅》が展示されていて鮮烈な生と死の対比が見て取れるという、なかなかに意味深な構成だった。明るい場所で目に映るものが幻影ではないと、誰に言い切れるだろう?

投げ銭絶賛受付中! サポート頂いた分は、各地の美術館への遠征費用として使わせていただきます。
