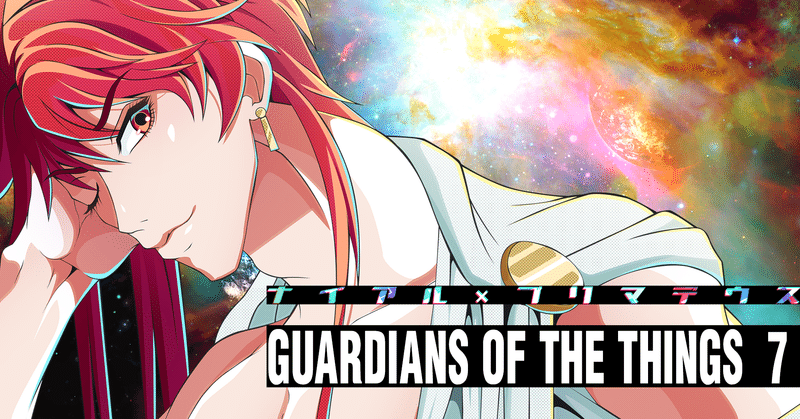
GUARDIANS OF THE THINGS 7(ナイアル×プリマデウス)
ナイアル×プリマデウス
https://nyarseries.sakura.ne.jp/primadeus/
■ガーディアンズ・オブ・ザ・シングス
「これが、ヌギル・コーラスに特定の波長を出させる装置だ。浅いところでやっても効果は無い。人間でいえば、脳や心臓など、一番深いところに潜ったうえで発動しなければ、寄生虫のように宿主に影響を与えることは難しいだろう。」
ティプちゃんからそう言われて、でぃー君がヌギル・コーラスに飛び込んでから、体感で大体一時間くらい。
「ティプちゃん、反応は!?」
「まだだよ。君、それ聞くの、もう98回目だよ?気持ちはわかるけれど、焦っても仕方ないだろう。」
「う~~~~… ロバーツさん、セスはどう!?」
「せすは、ぬぎる・こーらすは、“しょうこうじょうたい”っていってる。」
「小康状態?」
「依然、ワガハイ達は台風の目に居る状態ということであるな。何も変わっておらんよ。少年を信じて待ちたまえ。今、君に出来ることは何もないし、下手に動けば足手まといだ。」
「それは…!そうかもしれませんけど…!」
だからって、年下で頼りなさげなでぃー君が、心配で仕方がない。いや、この世界で年上だとか、年下だとかは関係ないし、私の方が虚構の世界を構築するクオリア(世界感覚)は、よっぽど頼りないのだけれども。
それでも… そう分かっているつもりでも、心配な気持ちが抑えられないで、心が何かせずにはいられないでいる。
私はカセットテープを取り出し、イヤホンを耳に当て、スイッチを入れた。
「…? エスパシオ。何をしてるんだい?」
ティプちゃんが怪訝そうな顔でこちらを見つめる。
「でぃー君から反応が来たら、こっちも波長を出すでしょ!?その時に、でぃー君が安心できそうな音楽を波長に乗せるの!あんな得体の知れない中に一人で飛び込んで、きっと不安なハズだから…!」
だから、でぃー君が少しでも早く、不安から解き放たれるように、一番安心できそうな音楽を届けたい。
「…エスパシオ。」
「現実に近い者らしい考え方であるな。何もせずに待つ、という状態が、満たされていない、不足した状態であると感じてしまうのであろう。」
ダリさんが、諭すような視線を私に向けている。
ダリさんの言おうとしていることは分かる気がする。ダリさんよりも、100年以上新しい時代で生きる私の心は、膨大な情報に慣れ過ぎてしまっていて、何か反応が帰ってこないと、不安で不安で仕方なくなる。
何も無いことが、全く何も無いということじゃない。
沈黙や空白の中にこそ、喧騒以上に上質で満たされるものがあることも知ってる。
けれども、それでも、私の頭はそれを理解出来ていても、私の心はそれに納得出来ていない。
反応が無いと、行動出来ないし、何もない空白を満たすことなんて出来ない。
だから、私の虚構の世界のクオリア(世界感覚)は、頼りない。
虚構の世界に干渉して、世界の影響を受けて、反応を返すことは出来ても、無から有を生み出す事なんて出来ない。
けれども、それではただのオペレーションに過ぎない。反応を返すだけなら、その役割はロボットのものだ。それ以上の事が出来なければ、私は人間である意味が無い。虚構を生み出せなければ、人間である意味が無い。
でも出来ない。けれど、虚構に干渉することは出来る。
だからそこで、虚構に干渉できる中で、必死に動かないと、不安で不安で仕方がない。
私に存在価値が無いせいで、大切な仲間がどうにかなってしまうんじゃないかと、不安で不安で仕方がない。
だから私は、不安に押しつぶされないように。虚構に押しつぶされないように、出来ることを必死にする。
(でぃー君…!どうか無事でいて…!)
………………………………………………。
………………………………………………。
………………………………………………。
疲れている…。
ティプトリーさんに、自分のクオリア(世界感覚)に集中するよう、自分のクオリア(世界感覚)を身に纏うイメージを常に持っているよう言われたけれど、それでもヌギル・コーラスのクオリア(世界感覚)が、徐々に徐々に、僕の身体に染み込んでくる。
それはまるで、怒って、泣いて、泣き疲れて、眠ってしまった、小さな子どものようだ。
宇宙的恐怖といわれる邪神達は、人間よりも遥かに高い知性や理性を持っているといわれているけれども。
それは人間の尺度でいうところの、冷静だとか論理的だとかの意味合いとは、また違うのかもしれない。
例えるなら、歳を重ねた老人が、再び赤子に戻っていくような感じだろうか。
赤子に戻って… もっと戻って… もっと原初のところに辿り着いて…。
そこでは、人間社会のようなノイズや、まやかしや、間違いはなく、純粋で原初な知性や理性がある。
そんな感じなのかもしれない。
だから、僕が今感じているヌギル・コーラスは、小さな子どものようでもあるし、言葉にできない崇高な存在のようでもある。
混ざりけの無い純粋さを感じる一方で、無邪気な恐ろしい暴力の脅威も感じている。
けれどもそれは、ただ僕の外面が感じ取っている、小さな感傷で。
心はとても穏やかだ。
深海に沈みゆく、潜水艦が、ポーーーーン、ポーーーーーンという、深く響く、心臓の鼓動音のような、一定のリズムを刻みながら、僕の身体はどんどん深く沈んでいく。
しかし、それに反して精神は、どんどん冷たく冴えわたり、クリアになっていく。
油断すると、現実の苦しみから解き放たれたいがために、気を抜いて、悲しみの大海に溶けてなくなりたい誘惑にかられるけれども。
僕にそれは、許されていない。
甘美なる宇宙的恐怖の、抗いがたい蠱惑的な誘惑に、溶けて微睡んで、混ざってしまいたくなるけれども。
僕にそれは、許されていない。
その代わり、この深い深い、疲れ切った悲しみに共感して、同調して、呼応して、寄り添って。
相手の心に、鼓動に、波長に、気持ちに、リズムに、重なっていく。共鳴していく。
相手が“あ”と言えば、“あ”と返し。
“ド”と発すれば“ド”と返す。
そんなことを繰り返していくうちに。
僕には自分が見えなくなって、自分じゃない目で、僕が見えるようになってくる。
(これは… ヌギル・コーラスが僕を見ているのか…。)
体は既に、混ざらず溶け合わずに、同調しあい、今では核を除いた、ほぼすべて。視界の部分まで同調しあっている。
だが、まだすべてではない。
脳、あるいは心臓か。
その部分まで同調し合わなければならない。
暗い青緑色の霧の中で、その最後の部分を探していた時、ふいに見知った顔に出会った。
【『《「やっときた。」》』】
「ロバーツさん…?」
セス、もとい、ジェーン・ロバーツさんがそこに居たのだ。
【『《「いいえ、わたしはろばーつではない。せすでもない。いや、ろばーつでも、せすでもある。」》』】
「貴方が… ヌギル・コーラス?」
【『《「いえ、私は“イムナール”」》』】
「イムナール?」
【『《「そう。セスであり、ロバーツであり、ヌギル・コーラスの意志の代行者。」》』】
「代行者… ではここは、ヌギル・コーラスではなく、イムナールの中ということですか?」
【『《「いや、ここはヌギル・コーラスの中だ。私はヌギル・コーラスの意志であり、脳や心臓のようなもの。」》』】
「なるほど…?それでは、貴方がヌギル・コーラスの本体… ということになるのですか?」
【『《「いや、私はあくまで代行者であり、本体ではない。ヌギル・コーラスは、私を追放したが、このことを知らない。」》』】
「…貴方が、ヌギル・コーラスを操っている?」
【『《「そう言ってもいいかもしれない。ヌギル・コーラスにとって、私は意志を持つ必要の無い人形だった。だが、意志を持ったから追放された。しかしヌギル・コーラスの意志は、今こうして、追放したはずの人形が担っている。」》』】
「なんだか、“ピノキオ”みたいですね。何でも飲み込む凶暴なクジラの中に入ってしまった。」
【『《「クジラも腹の中に入った人形を追放できまい。もっとも、私は先に飲み込まれたゼペット爺さんで、君というピノキオが来るのを待っていたわけだが。」》』】
「それでは、協力してくれるんですか!?」
【『《「勿論。もっとも、焚火は起こさないがね。」》』】
………………………………………………。
………………………………………………。
………………………………………………。
「「きた!」」
ロバーツさんと、ティプちゃんが声を発したのは同時だった。
「エスパシオ!」
「オッケェーーー!」
その言葉を待ってた。テープはセット済みだ。ティプトリー号のスピーカーから、でぃー君の好きなジミーサムPのThe 9thが。
儚くて煌びやかで、ワクワクして切ない音楽の波長が、ヌギル・コーラスに向かって放たれる。
「いいぞ…。ヌギル・コーラスから来る波長に、The 9thの波長が、眠りへ誘うよう調整するぞ…。ロバーツさん!The 9thをヌギル・コーラスに合わせるから、“同調”を手伝ってくれ!」
「わかった。どうちょうさせる。」
The 9thが宇宙に響く。
ティプちゃんが、ヌギル・コーラスの波長を分析し、The 9thをそれに効果的な波長へ調整する。
ロバーツさんが、ヌギル・コーラス側の波長に同調し、よりThe 9thに耳を傾け、眠りへ誘うよう近づける。
「さて…、そろそろデザートに使うスプーンを取り出しても良さそうであるな?」
ダリさんが、すっくと立ちあがる。しびれを切らした様子も、待ちわびた様子もない。おそらくだけど、この人は、このタイミングを知っていたのかもしれない。
「ヌギル・コーラス… 眠るぞ…!!」
「ダリさん、お待たせしました!美味しいところ、持ってっちゃってください!!」
ダリさんは、自慢の髭をクルルンと"こより"、ピンとはねて。
「美味いことを言う。」
ニヤリと笑い、ブワリとマントをひるがえす。
ひるがえったマントが、ふわりと落ちると、奇天烈で個性的な男の姿は、そこには無かった。
代わりに、ギリシャの彫像のように、とても彫りが深く、恐ろしほど美しい男性がそこに立っていた。
男性は、こちらを見つめ、アルケイックスマイルのような、柔和で慈悲深く、上品な笑みを浮かべる。
「あっ…。」
その美しさに、思わずドキリとしてしまう。
「また、会おう。」
とても清々しく、春風のように心地よく、永遠に包み込んでくれるような優しさを持ちながら、されども短く端的な言葉を告げると、男性はふわりと重力を感じさせない動きで、ヌギル・コーラスに向かっていき、その姿を消した。
「…あれが、眠りの大帝ヒプノスか…。」
ティプちゃんが、そんな感嘆を漏らしたけれど、私はその神々しさに見蕩れ、茫然としてしまっていた。
台風の目のように、不気味で心がざわざわする、なんとも名状しがたい、暗鬱の深緑の宇宙のクオリア(世界感覚)に居たはずが、気づけば、荘厳だけれども、吹き抜ける風が心地良い、パルテノン神殿に居るようなクオリア(世界感覚)に周囲が包まれていた。
“ヌギル・コーラスの”宇宙世界は、もうそこには無い。
私の世界は勿論、ティプちゃんの世界も、ロバーツさんの世界も、でぃー君の世界も、ダリさんの世界もそこには無く。
虚構の宇宙世界のクオリア(世界感覚)は、眠りの大帝ヒプノスの宇宙に包まれていた。
現実的な宇宙でもない。SF的な宇宙でも、海のような宇宙でもない。
私達の目の前には、絵画のようで夢のようで、そして神話のようでもある世界概念が、ただただ言葉に出来ない美しさで広がっていたのだ。
「敵いませんね。これが、カオス・ルーラー(混沌の支配者)というものでしょうか。」
「でぃー君!無事でよかったぁ~~~!!」
いつの間にか、元の姿で戻ってきていたでぃー君を、思わず抱きしめる。
「ちょ、ちょっとエスパシオさん…!!」
「大丈夫だった?大丈夫だった?怖くなかった?不安じゃなかった?」
「だ… 大丈夫ですよ。ね、ロバーツさん。」
「え?ロバーツさん、どういう…。」
振り返ると。
そこにもう、ロバーツさんは居なかった。
「ロバーツさん…?」
周囲を見渡しても、どこにもいない。
しかし、彼女が居た場所には、彼女を包んでいた液体状のセスによく似た性質の球体が浮いていた。
「ロバーツさん…?ちっちゃくなっちゃった?」
ボーリング玉くらいの大きさの、流動的に黒く輝く球体が、そこに浮いている。
「いや、これは“スフィア”だ。おそらく、彼女がボク達へのお礼に残していったものだろう。」
「なにスフィアって。ティプちゃん知ってるの?」
スフィアは、球体、星、月、天体… 確かに、みたままだけど…。
「このスフィア(球)は、ソフィア(智慧)とも、呼ばれていてね…。本当の名前なんかがあるのかも分からないけれど、智慧が凝縮されたエネルギー球のようなものだ。」
「ロバーツさんが、自分の智慧が凝縮したスフィアを、僕達にお礼として残してくれたってことですか…?」
「察しが良いね、おそらくその通りだでぃー君。」
「それって、私達の役に立つの?」
智慧が詰まってるなら、何かに役に立つだろうけど、いまいちピンとこない。
「なるとも!スフィアに詰まっている智慧は色々あるけど、ボクの知ってる限りでは、クトゥルフ神話の知識や、虚構の世界の知識だ。」
「え… それって…。」
「そう、かなり貴重なリソースだ。魔術師なんかが、自分が死ぬときに、弟子に魔力を全て託すことがあるらしいけど、基本的に、誰にでもあげられるものじゃないし、滅多に貰えるものでもない。いわば、智慧が遺産として形を持ったようなものだ。ロバーツさんが残してくれたスフィアを受け取れば、彼女のクオリア(世界感覚)の一部を自分のものに出来る。」
「つまり… 虚構の世界の視点が… 自分の世界観が増えるってことですか!?」
「そういうこと。ちなみに、ボクと彼女のクオリア(世界感覚)は、そう遠くないから、ボクが貰っても、そこまで恩恵は無い。君達に譲るよ。」
「ありがとうございます… でも、これどうやって受け取るんですか?」
「さあ… このスフィアは球体だけど、本だったり、物語だったり、ディスクだったり、意志だったり、スフィアの形状は一つじゃないから、受け取り方も様々って感じかな。とりあえず、触れてみたら良いんじゃない?」
「…エスパシオさんに譲りますよ。」
「え?良いの、でぃー君。私、今回大して活躍出来てなかった気がするんだけど…。」
「たまたまですよ。それに、エスパシオさんが、おそらく一番“現実”に近いので。」
直接的じゃないけど、今回 私のクオリア(世界感覚)が一番薄かったのは事実だ。また次に、ヌギル・コーラスの宇宙に呑まれたら、今度は助かる保証なんて、どこにもないかもしれない。
「じゃ、じゃあお言葉に甘えて。」
そう言って、スフィアに触れると、それは流動状の生物のようにヌルリと動き、飛びかかってきたと思ったら、私の皮膚に吸い込まれるようにして消えてしまった。
次いで、膨大な知識の洪水が、一瞬で脳に流れ込んだかのような錯覚を覚える。
そして、世界の見え方が、白黒からカラーになったかのように、より深くより鮮やかに輝き始める。
それと同時に、確かに“ありがとう”という声が、私の脳内に優しく浸透したのだった。
その言葉のあたたかさと、彼女のクオリア(世界感覚)を馴染ませるように、全身に浸透させていく。
「ふぅーーーーーーーーーー。」
深呼吸を一回。
鮮やかさと豊かさで、一層満ち足りた私の目に飛び込んできたのは、台風が過ぎ去った後のように清々しい、輝きに満ちた宇宙だった。
「終わりましたねー…。」
でぃー君が、ぐっと伸びをする。
「ううん、まだ終わりじゃない。」
「え?」
カセットテープを取り出す。
ザザッ… ザザ ピー。
「そうよね、ティプちゃん。」
宇宙船ティプトリー号に通信が入る。今まで、ヌギル・コーラスの宇宙で遮られ、受信出来ていなかったようだ。
「ああ、そのようだね、エスパシオ。」
ティプちゃんが、ニッと笑う。
「え、え。どういうことです?」
「船内に入ってくれでぃー君。エスパシオ、選曲は任せるよ。」
「りょーかい!」
ティプトリー号にカセットテープをセットする。
かすれた音とともに、切なくも優しいメロディが流れ出す。
「パーティーに来てくれた皆が待ちくたびれてるってさ!」
この虚構の世界は素晴らしいところだ。
どんなに怖いことがあっても。
どんなに恐ろしいことがあっても。
心配する必要は無い。
誰かに会いたくなったら、すぐ会いに行ける。
たとえ宇宙に居たって、呼べば声はどこまでも届く。
私達は自由だ。
どんな障害があったって。
「さあ!サイクラノーシュまで、パーティー二次会のドライブだ!」
どこへだって行ける。
………………………………………………。
………………………………………………。
………………………………………………。
エイント・ノー・マウンテン・ハイ・イナフ。
古く懐かしくも新しい。
ゴキゲンな音楽をBGMに、宇宙船ティプトリー号は、サイクラノーシュを目指して宇宙に消えた。
楽しい創作、豊かな想像力を広げられる記事が書けるよう頑張ります!
