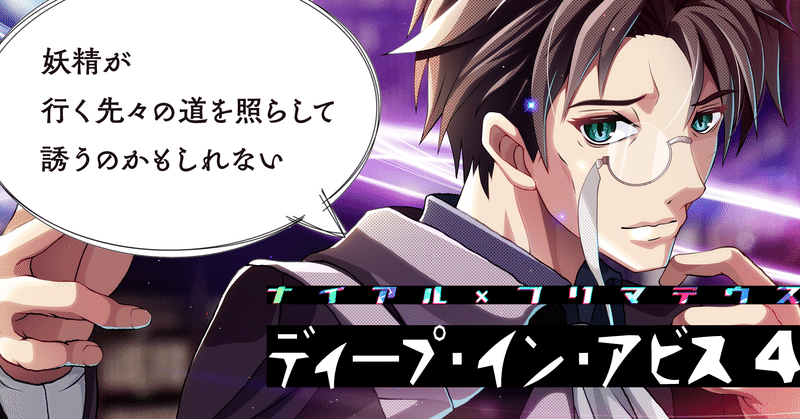
ディープイン・アビス 4(ナイアル×プリマデウス)
ナイアル×プリマデウス
https://nyarseries.sakura.ne.jp/primadeus/
■W・B・イェイツ
ナチス鋼鉄の潜水艦から、リラックスできるウッドテイストの潜水艦へ。
ウッドテイストの潜水艦から、人魚の話を経て眠り、極彩色の入り江へ。
極彩色の入り江で立ち塞がるは、暗黒の岩壁の扉。
そして、そこで出会ったリリゥという少女。
暗黒の扉の向こうに潜む悪魔、ロゴ・トゥム・ヘレと対峙すべく、俺達は岩壁に臨んだのだが…。
「どういう… ことだ、こりゃあ。」
俺もアナスンも歌って踊れる柄じゃない。
実際、岩壁を前に、楽し気なアロハで歌と踊りを披露したのはリリゥだけで…。
アナスンは詩を… 歌ではない、詩(うた)だ。吟遊詩人が語るような、流れるような詩を語り…。
俺はメトロノームがリズムを取るように、フィンガースナップで、ロゴ・トゥム・ヘレからの波紋の反射を探った。
歌と踊りに、詩語り、そこにフィンガースナップという、実になんとも奇妙な組み合わせのセッションを成し遂げたわけだが、俺は手拍子とかにしておけば、中世ヨーロッパのファンタジー酒場の雰囲気が出せて良かったかもしれない。
それはそれとして、だ。
リリゥに言われた通り、俺は音を奏で、その反響を探っていくことで、目の前の岩壁か、その向こうに潜む悪魔からなんらかのアクションがあり、そこから何かしら進展があると思っていた。
しかし実際は、俺達が奏でれば奏でるほど、そのリズムやメロディーは、まるで世界に融け込んでいくように馴染んでいき、仕舞いには、目の前の岩壁から感じていた感覚も、周囲の極彩色の世界も、全てがなめらかなマーヴル模様のように、自然に溶け合い、落ち着いてしまった。
「…おい、反応が… 世界感覚(クオリア)が無くなってねえか?」
「ええ… 世界がまるで、すっかり寝静まってしまったかのように穏やかです。」
目に映る世界は、暗黒と極彩色とで、こんなにもハッキリしてるのに。
何故だか、その色を見ても、不安に感じることも、心がざわつくことも無く、すっかり落ち着いてしまっていた。
いや、脅威が無くなること自体は悪いわけではないけれど、俺達は、悪魔に近づき、ヒムラーが持ってきてしまった像を、返すべき神殿に近づかなければならない。虎穴に入り込んで、虎児を返さなければならない。
だというのに、これでは困る。
「なあ、リリゥ。」
「大丈夫。ロゴ・トゥム・ヘレ眠った。これで、おニイさん達の、次への扉が開かれる。」
「…?どういうことです?扉の向こうの存在が眠ることで、岩壁の扉が開かれるという仕組みにでもなっているのですか?」
アナスンがリリゥに質問をする。丁度、俺も同じことを考えていた。
だが、リリゥから返ってきた返答は、俺達の想像とは違っていた。
「この岩壁は開かない。でも、おニイさん達の、次の世界への扉は開かれる。」
意味が分からなかった。
そして、今度は俺が質問をしようとした時だ。
グワン…!!!
急に。
足元の地面が無くなる。
「あ!?」「えっ!?」
リリゥは浮いている。地面に浮いている。
けれども、俺達の足元の地面は無い。だから落ちる。
さも、当たり前のように、夢の世界だというのに、現実の重力に逆らえないかのように落ちる。
「ちょ!まて… まてまてまてまて!!!!!!」
俺とアナスンはどんどん落ちていく。リリゥの姿が、砂浜に立ったままどんどん高く小さく遠くなる。
俺達は落ちていく。どこへ?どこへ落ちていく?砂浜の下はなんだ?海か?リリゥから目を離せず、自らが落ちていく先を背にして、そちらを振り向く余裕すらない。
虚空が迫る。背後に迫る。俺達は、どこへ落ちていこうというのだ。
どこへどこへどこへ???
「サヨナラ、おニイさん達。おニイさん達は、もっと深いところへ行くの。そこにおニイさん達が目的とするところがあるの。怖いけど安心して。夢のさらに深いところへ。もっと深いところへ。そこに神殿はあるのだから。」
その言葉に。
ピンときた。
「そうか… インセプションか。」
「なんですって!?」
思い至り、冷静さを取り戻す俺とは裏腹に、この後の展開が読めないアナスンが、俺に疑問を訴える。
「インセプションという映画がある。人の夢の中へ、そのまた夢の中へと、どんどん落ちて、入り込んでいく世界観だ。」
俺達は、リズムを奏で、調和することで、悪魔を眠らせた。そして、悪魔が居た世界は、溶けて流れ出す。
その流れに誘われて、俺達も流れ出す。次の世界へ流れ出す。
そう、眠った悪魔が見ている夢に流れ出す。
俺達は、扉を開けずとも、悪魔を眠らせることで、さらに深い悪夢へと落ちることになるのだ。
目指す神殿へと近づくための、さらに深い悪夢へ。
…………………………………。
…………………………………。
…………………………………。
…………………………………。
「どういう… ことだ、こりゃあ。」
そうして、俺はこの言葉を口にすることになったというわけだ。
俺達の目の前に現れた、さらに深い悪夢の世界。そこは…。
「ハシゴ…か。」
そこには無数のハシゴがあった。いや、ハシゴしか無かった。
脚立のようなアルミのハシゴ。
古びた図書館にありそうな木のハシゴ。
サーカスに出てきそうな縄のハシゴ。
アスレチックのような金属の網のハシゴ。
ありとあらゆるハシゴに溢れた世界で、それ以外には何もない。
建物も無ければ、柱も無い。結び付けた先も、途切れた先も、見当たらない。
ただ延々と、延々と、無数のハシゴが、そこかしこに、張り巡らされている。
「貴方には、この世界がハシゴに見えるのですか?」
「え?あぁ…。つーことは、アナスンは違うものに見えてるわけか。」
「ええ、私には無数の枝に見えます。」
「枝?木の枝?」
「はい。実に様々な枝が。」
さっきまで俺達が居た世界は、リリゥの極彩色の世界感覚(クオリア)と、ロゴ・トゥム・ヘレの暗黒という、強い個性のバランスによって、均衡が保たれていた世界だった。
しかし、今居るこの世界のように、見る者によって見え方が変わるという事は、誰か一人の強い世界観によって、統一された世界ではないという事だ。
だが…、この世界を俺はハシゴと見て、アナスンは枝と見ているのは、あくまで表面上のことに過ぎず、どうにもその本質や、世界の意味は同じように思われる。
(何を意味しているのかは、まだ読めないが…。)
「お二方。ここは立ち止まる場所ではございませぬよ。さあ、前へ。」
どこから現れたのか。
「…! アンタは?」
「歩きながら説明するよ。さあ、前へ。ここは、そういう世界だ。」
言いながら、その御仁は、俺とアナスンを前に促す。
「下を気にする必要は無い。自転車のようなものだ。足元ばかりを気にすれば覚束ないが、前へ前へと進めば、その力が安定を生む。」
「おっととと…。」
その言葉に倣おうとしても、ついつい足元を意識してしまう。俺とアナスンが、足元を意識せず、ハシゴあるいは枝を踏み外さず、スタスタと歩けるようになったのは、一分ほどの時間を要した。
「イエイツ。ウィリアム・バトラー・イェイツだ。わたしの世界は、意味はあれど、普遍的な形を持っていない。君達がハシゴや枝と見るように、階段や橋と見る者も居た。それがわたしの世界だ。どこかから、どこかへ、誰かを誘うことが出来ても、わたしの世界は、誰かの居場所になることは出来ない。」
「なんだか落ち着かねえな。たまにゃあ、腰を据えたりはしないのか?」
「勿論、現実ではそうするだろう。しかしわたしの世界では、それはしない。わたしの世界が落ち着くということは、それはつまり呼吸を止めるということと同じ意味だと言えば、理解してもらえるだろうか?」
「流れに身を任せる私には、とても出来そうにありません。それで、私達をどこへ誘って頂けるのでしょうか?」
アナスンが問う。が、しかし…。
「わたしは知らない。それは君達が知っていることではないのかな?わたしはただ、この世界で、前へ、前へと進むのみ。わたし達は目的地も見ている世界も、本当の意味では共有することは出来ない。しかし、同じ枝やハシゴを歩んでいくことで、目線を合わせて共感することはできる。さすれば、わたしと君達は友人になることが出来よう。わたしが友人の為に出来ることは、前へ前へと進むことだけだ。わたしが前に進むことで、ひとつ、またひとつと、進むべき先に明かりが灯る。そうすることで、友人は前に進むことが出来る。」
「アンタは… その、なんだ?水先案内人みたいな世界を持っているのか?」
歩きながら、俺も問う。
「いやいや、水先という言葉で言うのならば、アナスン。君の方が似合っているだろう。さっきも言った通り、わたしはこの先がどこに続いているのか、知らないんだ。」
「私達は、神殿を探しています。恐るべき邪神が待つ、深い海底の神殿を。」
「海底の神殿。それで?」
イエイツがアナスンの言葉に返事をすると当時に、周囲は一気に水に包まれ、ハシゴは白く大きな柱へと変わり、前へ前へと進んでいた方向は、前へ下へと向きを変えた。
「これは…!?」
「あぁ、わたしの妖精達が気を利かせてくれたのだろう。あるいは、君の話をもっと聞きたいのかもしれない。」
「アナスン、お前の見ている世界も?」
「ええ、水の中に入りました。世界の見え方が収束されましたね。イエイツさん、これは一体…。」
「わたしの世界の見え方、わたしが世界をどう見るかは、わたしの意志や無意識が、そう決めるのではなく、わたし以外の何かが、世界の見え方を変えているようだ。それが何かはわたしは知らないが、どうも気まぐれで、好奇心旺盛、そして一つの人格では無いように思えるため、わたしはそれを妖精達と呼んでいる。」
「妖精達…ですか。」
「ああ、わたし達の世界の見え方は、全て100%わたし達が決めているわけではない。他者の言葉、読んだ本、影響を受けた作品、それらが複雑に混じり合って、世界の見え方という… そう、レンズを創り上げているに過ぎない。妖精達を、なんと呼んでも構わないだろう。だが、君達が妖精に行きたい場所を教えてあげれば、わたしの世界はそこへ導いてくれるかもしれない。」
「なるほどねえ…。"アナタがどこへ行くか私は知りません、しかしアナタが行きたい場所へ誘うことはできます。"そういうことか。」
「大体は。」
便利なこった。いや、現実のAIも、厳密には違うが、似たようなことは出来てるか。
「妖精さん達に名前はあるのですか?」
「アレクサ?Siri?それとも、ジャーヴィスって呼べばいいかい?」
「ははは、好きにすると良い。」
「では、聞いてください、リゲイア、テレース、モルペー。」
「そりゃ、妖精じゃなくて、人魚の三姉妹じゃねえか?」
「ええ、水中の妖精達です。リゲイア、テレース、モルペー、私達はグルーンという恐るべき邪神の神殿へ行きたい。美青年の姿を持つと同時に、ナメクジのような異形の神が居る神殿へ、私の友人が誤って持ってきてしまった像(スタチュー)を返しに行きたい。」
「えーっと… そこには美しいお姫様と、踊り子さんが沢山居てだな?俺達は豪勢な美味い料理と、素晴らしい音楽で歓迎されるわけだ。そこは、この世の楽園と言って良いね。で、最後に帰る時にだ。」
「なんですかそれは?」
「何って、竜宮城だよ。浦島太郎の。流石に、聞いたことくらいは…。」
「ありますが、それは私達の行くべき神殿とは違うのでは?」
「まんじゅうこわいってやつさ。恐ろしい恐ろしいと思えば、その想像は事実以上に恐ろしく降りかかる。だが、見方を変えれば違うかもしれん。なればこそ、多少の虚構があっても良いと思った次第だよ。」
「まんじゅうこわいという悪夢… という虚構ですか。それも面白いかもしれない。」
アナスンがため息交じりに笑う。
「わたしは故郷の妖精譚を好むのだが。」
俺達の冗談に、イエイツが続ける。
「この手の話は、恐ろしくもあり、また滑稽でもある。そして、妖精は嘘つきであったり、気まぐれとも言われる。善しにしろ悪きにしろ、そういった曖昧なものから、君達が行くべき場所は形作られていく。そして、誘われる。故に、歩きながらのこうした会話も必要なもので、会話の節々から紡いだ言霊を使い、妖精が行く先々の道を照らして誘うのかもしれない。ハシゴも枝も、皆が使うが、誰のものでもない。それが私の世界だ。さて…。」
イエイツが足を止めて振り返る。
「どうやら、ここら辺が君達が下りる駅のようだ。楽しい話をありがとう。機会があれば、また会えるのを楽しみにしているよ。」
道の脇には扉があった。いや、俺は扉と見ているが、アナスンには門に見えるかもしれないし、他の誰かには改札に見えるかもしれない。
「あっ。」
礼も別れの挨拶も言う前に、既にイエイツの道は、遥か先へと延び続け、歩く先の道が次々に創造されると同時に、歩き終わった道は、もろもろと崩れ去っていた。
「確かに、彼の言う通り、彼は水先案内人ではありませんが…、強いて言うなら街灯夫のような方でしたね。」
「道を決め、前に進むのはあくまで自分。それを進むための手助けをしてくれるインフラ整備屋とも言えるかもなあ。」
「しかし、誰もが通り過ぎるけれども、誰のものでもなく、誰の居場所にもならないというのは、どこか悲しさを感じますね。」
「誰も居ない夜の公園のベンチに座ってりゃそう思うかもしれないが、フォレスト・ガンプみたいに、朝とか昼に座ってれば、色んな人とすれ違って、多くの話をするかもしれない。捉え方次第だろ。さ、行こうぜ。折角、誘ってくれたんだ。」
「ええ、門の向こうの神殿に、像を返しましょう。」
楽しい創作、豊かな想像力を広げられる記事が書けるよう頑張ります!
