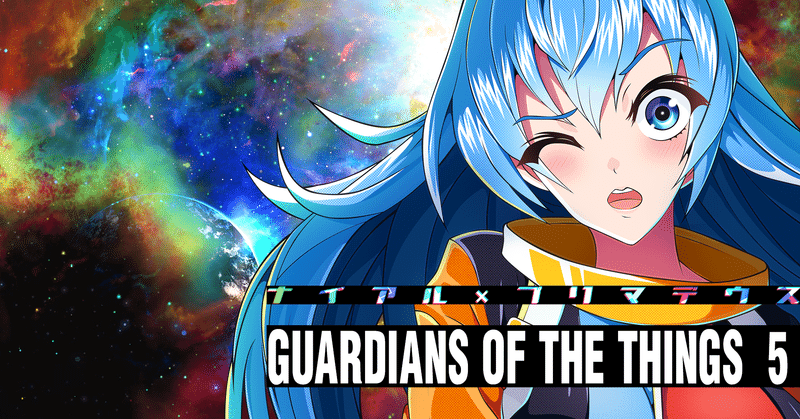
GUARDIANS OF THE THINGS 5(ナイアル×プリマデウス)
ナイアル×プリマデウス
https://nyarseries.sakura.ne.jp/primadeus/
■ヌギル・コーラス
ヌギル・コーラスの宇宙が、ティプトリー号を激しい振動の中に巻き込んだ。
…と、私は認識した。
フォース・フィールド展開。機体損傷無し。対象広範囲。もっと接近する必要がある。
…と、ボクは思った。
おこってる、いえ、おそれてる。きょうかんがとてもつよくなっている。
…と、わたしもせすもかんじてる。
宇宙の混沌よ。宇宙を支配せし万能なる巨大な神であっても、夢という恐怖からは抗えぬか。
…と、ワガハイは哀れむ。
キラキラしてる…!とても、身体に活き活きとした力が漲ってくる!不安が全て喜びに変わったかのよう…!
…と、僕は打ち震えた。
それぞれが、それぞれに世界を認識する。
真実はどこにも存在せず、どこにでも存在する。
強大なヌギル・コーラスという神話生物の宇宙、その世界の影響にじっと耐える者、探索する者、寄り添う者、俯瞰する者、そして受け入れる者。
それぞれが、それぞれに世界を見る。その、世界感覚(クオリア)での触れ方、接し方で、虚構の世界はいかようにも変化する。
だがしかし。
数多に存在する、世界感覚を凌駕してなお、強壮に存在する宇宙の混沌は。
感じ方の異なる波動を超えて、根源たる恐怖の切っ先を、鉗子で脳を押し広げるがごとく、すぶりすぶりと舐り込む。
「あっ… あぁ!駄目!来ないで来ないで…!」
「エスパシオ!?」
それは、世界感覚の濃度が薄い者から、丁寧に丁寧に、一枚ずつその虚構の皮を剥がしていく。
「ぁぁぁぁ‥‥ みみ… はぃって… ぉおおお…」
ロミーナ・エスパシオは、両耳を抑えても意味の無いことは分かっていた。しかし、だとしても、恐怖から逃れるために、その行動から抗えず、両の目を見開き、鼻孔も口も留め金が外れたかのように大きく開いて、耳の穴から直接脳内をまさぐられているかのように、涎を流しながら、言葉にならない嗚咽を漏らす。
「エスパシオ!エスパシオ!?何をされてるんだ!大丈夫か!」
様子のおかしいエスパシオを、ティプトリーが揺さぶるも、ティプトリーにはエスパシオを侵蝕しているものが見えない。感じることも出来ない。
「止めたまえ。当人が見た悪夢の怖いという感覚を他者と共有する時、そのヴィジュアルが共有できず、怖いという感覚だけ力説されて、上滑りするようなものだ。君にはどう足掻いても、彼女の恐怖は見えんのだよ。いくら共感しようとしてもね。」
サルバドール・ダリの、おちゃらけていた様子は、まるで嘘のように落ち着き払った紳士然としている。
「ワガハイの出番を失くす気かね?ワガハイは、デザートを食しに来たのであって、君達の介抱をするために来たのではない!」
ティプトリーが次の言葉を重ねる前に、それを遮るように、ダリは言葉を続ける。
「あまり共感すると、君も彼女の恐怖に飲まれるぞ。」
「…でも!」
「そう心配する必要は無い、一時的な恐怖症状だ。まずは、各々がしっかりと自己を確立し、この状況を乗り切ることだ。さもなくば…。」
「全員道連れ。そういうことだよねっ!」
「ウム。少年、世界に入った君は強いな。」
僕は今、とてもポジティヴだ。この状況では、異常に見えるほどに明るいかもしれない。けれども、分かってるからなんだ。普段とは違う自分を装ってでも、今はポジティヴじゃなきゃならない。
「ティプトリー!君らしくないよっ!こんな面白い世界、もっと楽しまなきゃ!」
「でぃー君…!」
こんな言葉、普段なら僕がティプトリーさんに言われるような言葉だ。異常な今に言うべき言葉ではないけれど、不謹慎と思われてもそれで良い。
チラリと横を見ると、ロバーツさんがうずくまり、プルプルと震えている。
今、世界感覚の濃度は、エスパシオさんが一番薄く、次にティプトリーさんだ。しかし、ヌギル・コーラスとの繋がりは、ロバーツさん、もといセスが最も濃い。
「ティプトリー。今は“冴えたやり方”の時じゃないよっ!恐怖はねー…。」
言おうか言うまいか、普段の僕なら悩んだろうけれど、今の僕は大して悩みもせず、言葉にする。
「伝染するんだっ♪」
そう、伝染する。これが厄介だ。
例えば、ダリさんや仮想の肉体となった僕は、今すぐにヌギル・コーラスに呑まれることはない。
しかし、エスパシオさんや、ロバーツさん、さらにはティプトリーさんが、ヌギル・コーラスに呑まれ、その狂気が、恐怖のクオリアとして広がってしまうと、話は変わってくる。
ヌギル・コーラスだけの恐怖に耐えれば良かったものに、エスパシオさんが加わり、ロバーツさんが加わり、ティプトリーさんが加わり… そしてそこに、さらに僕が加わってしまったら、眠りの大帝ヒプノスの化身である、ダリさんだって無事でいられる保証はどこにもない。
恐怖は連鎖だ。病気のように感染する。感染が広がらないようにするには、隔離するしかない。
少なくとも、病魔の嵐が過ぎ去るまでは。
例え仲間が苦しんでいると分かっていても、自分達の安全が確立できるまでは、まして近くに寄り添って、助けてあげることなんてできない。
マスクや消毒をして防げるなら、それもできようが、恐怖はマスクで防げない。
だから僕達は、自らのクオリアで恐怖を防ぎ、ポジティブで恐怖を消毒する。恐怖の嵐が過ぎ去れば、助けてあげることは出来る。
「ぁああぁ‥‥ ウゥ~…」
喘ぎ声を流しながら、ドサッという音とともに、エスパシオさんが倒れる。
「エス」
「エスパシオを助けたいならっ!ティプトリー号で嵐を抜けることが大事じゃないかなっ♪」
「はい!」と、中空に浮かぶ、ティプトリーさんのディスプレイ端末を押し付ける。やってから気づいたけど、Vの身体なら、デジタル出力されたものに、直接触れることが出来るんだ… 便利だな。
「…わかった!フォース・フィールド出力全開!一気に抜ける…!衝撃で吹っ飛ぶんじゃないぞ!」
後ろ髪引かれながら… 引かれる髪を引き離すように、吹っ切るように、ティプトリー号はグォンと加速する!
「すごーいっ!はやいはやい♪」
「スローすぎて、欠伸がでますぞwww それで限界?それで限界?」
僕はあえて馬鹿みたいにはしゃぎ、ダリさんもあえて再びウザく煽る。
「まだまだ…!」
ティプトリーさんが、デジタル端末のレバーをグググと押し上げると、さらに体感速度は加速する。
僕の目の前では、あまねく宇宙に蠢く、百鬼夜行のような宇宙の混沌が、次々と宇宙船の後ろに流れていく光景が見える。
もっともこれは、僕が見ている光景であって、ティプトリーさんには、もっとおぞましく見えているのかもしれないし、ダリさんにはアートの喜びのように見えているのかもしれない。
しかし、周囲の魍魎の圧力が徐々に徐々に軽くなり、眼前に大きな光の出口のようなものが、徐々に徐々に近づく。
その時だ。
「迂闊な」
「えっ?」
ダリさんが、どこから出したのか、右手に絵筆を構えクルリと回す。
その瞬間。
混沌の魍魎、大量の宇宙の臓器のようなものが、一斉に船内に雪崩れ込んできた。
「なん…で!?どうして…!!」
既にフォース・フィールドと呼ばれていた、バリアであろうものは存在せず、船の前方は無残にも打ち破られ、ティプトリーさんは、肉塊の洪水に一瞬にして呑まれてしまった。
エスパシオさんや、ロバーツさんの姿はとうに見えない。
僕の身体に、ビシャビシャと異生物の腸のようなものが、飛びついては流れ落ち、飛びついては流れ落ちているが、それが彼女たちの臓物のようで、気持ちが悪かった。
そして、そんな光景に呆然としていた自分に気づいた時、肉のシャワーは既に止んでいた。
船内は、おびただしい、寄生虫の肥溜めのようで、酷い有様だった。
けれど、まだ良かった。
肉のシャワーが止んで、目の前に現れたそれを見た時、僕の胃の中から芋虫が這い上がって抉じ開けてくるような恍惚を感じ、気が付けば今度は僕が、口から肉のシャワーを噴水のように垂れ流していた。
「少年よ。まだ、倒れるんじゃなアないぞ。」
僕の身体はガタガタと震えていた。
心が意識が、それと認識する前に、より敏感に反応していた仮想のVの肉体は、震えることを止められなかった。
温かいのは背中を支えてくれたダリさんの手だけじゃなく、腿から足を伝う失禁の感触からも伝わって来た。
(ヌギル・コーラスだ…。)
視覚には捉えられていない。でも、圧倒的な存在感の圧力が、世界感覚の圧力が、いつでも僕を飲み込まんと吸い付いてくる、意志を持ったヘドロのようだ。
ズブズブと、ズブズブと、宇宙に漂うヘドロが、僕を底なし沼に吸い込み、手や足から硫酸で溶かされて無くなってしまうかのような、強烈な不安感。
そして、吐いても吐いても、内部から寄生虫に犯されていくかのような、耐えがたい、名状しがたい嫌悪感。
嵐を抜けたら、大丈夫だとか思ってたのは誰だ。
僕は微動だに出来なかった。
一歩でも動けばきっと、この震える体が、心が恐怖を現実と受け止めてしまって、僕はきっと耐えられない。
仮想の身体だから、バーチャルの身体だから、どこか一線守られているような感覚が僕の中に有って。
それでも、それは、とてもか細い、一筋の糸で、なんとか繋ぎ止められているかのような、儚さだった。
「繋ぎ止めている糸を紡ぎたまえ。焦らずゆっくりだ。ゆっくりで良い。君に倒れられてしまうと、ワガハイも困る。」
ダリさんは落ち着いた優しい声で、僕を包み込んでくれる。しかし、それでも、その声からは、幾分か切迫した様子を感じ取れた。
だから僕も、か細い糸を紡いで、紐にすることが出来た。少なくとも、ダリさんの声から、僅かな変化を感じ取ることができる余力が、今の僕には残っていたということだ。
「紐に出来たら、今度はそれを三つに編んで太くしたまえ。それが出来たら縦の線、横の線、折り重ねて繊維にするところまで出来れば、君の正気は張りなおして持ちこたえられる。」
今は何も考えず、目の前の恐怖に呑まれないように、ただ正気の綱をまとめていくことだけに集中する。
それがある程度まとまって来た時に、ようやく僕は、再びまともに喋る事を取り戻した。
「悲しみ…。」
「ウム、分かるか。だがまずは、皆を助けたまえ。」
強大なヌギル・コーラス。僕は、その圧倒的な恐怖に呑み込まれそうになっていたけど、正気を持ちこたえて改めて感じたヌギル・コーラスのクオリアは、ただただ深い悲しみに満ちていた。
正気をなんとか繋ぎ止め、そして恐怖を全身で受け止めて、ゆっくりゆっくり僕が紡いだのは、正気に戻るための紐じゃなかった。
正気を裏返して、裏返った正気で、恐怖を受け入れ、裏の正気と恐怖を、ゆっくりとゆっくりと紡いで繋がっていくための紐だった。
「ティプトリーさんっ。エスパシオさんっ。ロバーツさんっ。」
三人を一人ずつ介抱する。
呆然と意識を取り戻した者、一時的に攻撃的になった者、怖くて怖くて泣きじゃくった者。反応はそれぞれだったけど、十分な時間をかけて、皆なんとか落ち着きを取り戻した。
(ダリさん…。)
ダリさんは、先に言った通り“出張ら”なかった。彼はじっと、ヌギル・コーラスを見据えている。彼が見据えているから、ヌギル・コーラスは動けないのか。あるいは、そもそも動こうとする意志は無いのか。
「ありがとう、でぃー君。君に助けられるとはね。まさか、フィールドが中和されるとは…。」
「痛たた… どういうことなの?ティプちゃん。」
ティプトリーさん、エスパシオさんも、なんとか正気を取り戻す。
「てっきり、僕のクオリアがやられるときは、ヒビが入るとか、段々削られるとか、そういうのをイメージしてたんだけど、違ったんだよ。一気に消えたんだ。」
思い返せば、エスパシオさんやロバーツさんへの侵蝕は、徐々に徐々に影響を深めていった。しかし、ティプトリーさんの場合は、一瞬にして吹き飛んだように見えたのだ。
「超強力なクオリアで一気に破ったのかなっ?」
そういうことなんだろうか?例えるなら、マシンガンでゴリゴリ削られていたのが、急にバズーカーに変わったかのような。
「いや、というよりも… “中和して無効化”されたって感じ。」
「中和して無効化?」
攻撃して破るイメージではなく… 打ち消された?
「ぬぎる・こーらすは、はちょうをかえたんだとおもう。えすぱしおや、でぃーにはむりだった。わたしはとりこまれた。てぃぷとりーは、はちょうをかえて、けしちゃったの。」
ロバーツさんも大丈夫なようだ。しかし…
「波長…?」
「なるほど、そういうことか!つまりそれが、ダリさんにヌギル・コーラスの悪夢を食べてもらう手段にもなりそうだね。」
「えっと、ティプちゃんどういうこと?」
エスパシオさんは分からないみたいだ。僕も分からない。
「水や音の波紋を想像してもらえれば分かりやすいかな。発生しているジェイムズ・ティプトリーのクオリアという波紋に、ヌギル・コーラスがボクと同じクオリアに調整した波紋をぶつけて、クオリアを打ち消してしまったって感じだろうか。ヌギル・コーラスとクオリアが非常に近いロバーツさんは取り込めば良かったけど、クオリアが微妙に違うエスパシオさんとでぃー君は削るしかなかった。しかし、比較的クオリアが近い世界観を持っていたた僕は、調整することで打ち消せてしまったんだと思う。」
なるほど… なんとなくだけど、イメージは掴めたような。
「はぁー… それで?ダリさんにヌギル・コーラスの悪夢を食べてもらう手段ってのは?」
重ねてエスパシオさんが問う。
「悪夢を食べてもらうには、そもそも眠ってもらう必要がある。…となると、どうやって眠らせるかが課題だね。麻酔や睡眠薬があれば良いけど、生憎 存在感は有っても、姿が判然としないヌギル・コーラスに効果的な影響を与えられるかどうか分からない。そこで、眠ってもらう波長を使うのが良いんじゃないかってことさ。」
「えっと、つまり… 音楽?」
「その通り。」
ピンと得意げに人差し指を立てる。依然、気は抜けないが、大分持ち直したみたいだ。
「ダリさんっ?」
「音楽か。良いのではないか?」
余裕のあるようだけど、緊張感のある声がこっちを見ずに返ってくる。ダリさんは、まだヌギル・コーラスを見据えたままだ。
ヌギル・コーラスの印象もまた変わっている。
圧倒的な宇宙的恐怖が、そこに存在するのは間違いないが、名状しがたい混沌の魍魎が雪崩れ込んでくるようなイメージはそこには既になく、ただただ底の深く視えない深淵が、途方もなく広がっている壮大な虚無感が、そこに漂っていた。
なんとも言い難いが、その虚無感が、とても悲しいのだ。
「何か… 見えるんですかっ?」
そんな悲しみを紛らわせたくて、一層場違いな明るい声で、ダリさんに問いたかったのかもしれない。
「何も見えんよ。ただ、考えていた。」
「何を?」
「君達が、音楽という手段を選んでくれて良かったという事をさ。ワガハイ達は、矮小なる人間風情であり、そんなちっぽけな存在が、宇宙に働きかけようというのは、実におこがましいことだ。宇宙は、世界は、ありのままでなくてはならない。されど、宇宙に響く反響が、リズムを生み、天球という音楽を創造した。その崇高であり、また原初である調律で、宇宙に働きかけようというのならば、それは世界の流れの一部であるのだろうな、という事をな。」
いつになく難しいことを、どこかシミジミと、清々しい顔で語るその表情は、彼がヒプノスであるということを、否応無しに思い出さざるを得ない、荘厳さだった。
「さぁて?ワガハイのデザートのために、気を取り直して、スンばらしい音楽を奏でてくれたまえよ!!ドゥフフフフwwwwww!!!」
…やっぱり、いつものダリさんだ。
楽しい創作、豊かな想像力を広げられる記事が書けるよう頑張ります!
