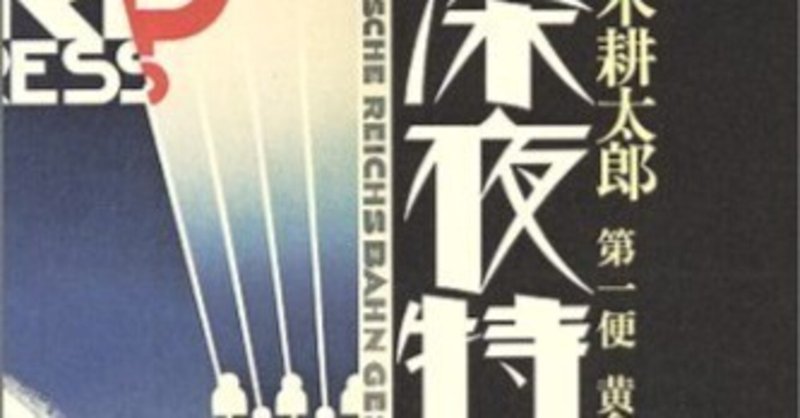
にゃるらが最近読んだ本 5選2023年 4月
↑前回の。
・死の講義――死んだらどうなるか、自分で決めなさい
死について考えることが妙に増えたので、ちゃんとした研究者の本を参考してみることにしました。
死後の世界、気になりすぎるぜ……。
死後の世界が気になるというより、正しくは「死後の世界」が無いと認識する人間はなにを基準に生きるのか、逆に敬虔な宗教家たちは死後の世界とどう向き合っているのか。そういった疑問に対して一気に解決してくれる本。もちろん、答えなんてないわけで、各宗教による「死」についての見解が並べられているから、その中でなにを信じる・信じないかは読者次第だよってことになりますが。
日本人のほとんどは、敢えて言うなら仏教系無宗派になるのでしょうか。なんとなくの仏教思想がある程度で、それはそれで無神論者には適した形なのかも。そういったことも書いてある。

さて、みなさんの考えは1~6のどれだ!? だいたいの死後の認識は大きく分けるとこの6つのどれかになるらしい。たしかにそうだね。
それもあなたの死生観なので正解はない。こんなこと考えてね-よって考えもアリでしょう。わからないものは考えないって割り切るのも賢いですしね。でも、暇だとこういうことがずっと気になってしまうんだ。
これが仏教の宗派ごとに詳しく見てみるとこうなる。

まあ順番に読んでいかないとわけわからないでしょう。詳しくは実際に本書を手にとってもらいたい。しかも仏教は派生がたくさんあるので答えはない。これも仏教の一部の話だし。仏教の場合は、概ね輪廻があるよって感じです。これが一神教だとぜんぜん違うけれども。
前述した通り、これは各宗教の考え方であって、答えではない。けれども、少なくとも熱心な信者は自身の死をこのように受け止めていることがわかるのは興味深いですよね。死は誰も体験できない、平等かつ残酷なイベントですから。できるかぎり「死」なんて忘れて生きていけたら幸せなのかもしれないし、死について考えていくほど暇がある方が幸せと呼べるのかも。
・深夜特急
言わずと知れた名作『深夜特急』。過去に一度読んだことがありましたが、一人旅を何度か経験した今読むと味わいも深くなるだろうと、再読。結果……。
めちゃくちゃいい……。沢木先生は海外での一人旅だし、時代も時代ですので僕とは苦労も刺激も段違いですが、わかる。一人で旅をする自由の孤独と楽しさ。旅先で出会うふとした登場人物たちの個性、わけのわからんイベントたち。それを軽快な語り口で淡々と書き連ねられており、著者の寂しさを追体験することで「気持ち」が溢れる。なんと素晴らしい小説なのだ。まさしく紀行小説の金字塔。
実際、80~90年代のバックパッカーたちにはバイブルだったらしい。さすがに現代とは環境が違いすぎて参考にはならないかもですが、各国へ足を踏み入れる際の心構えとして一読しておくといいかもしれません。それこそ就寝前の深夜に少しずつページを捲っていき、異国情緒に包まれながら眠るのもいいでしょう。ノンフィクション、カッコいいよね。
・絵どきデザイン史
デザインの歴史が年代順に並べられており、ある程度のさわりが学べる一冊。自分は何度か建築や家具の本について書いてきましたが、もっとシンプルに「デザインそのもの」自体に触れるのは初めてな気がする。興味の方向が広がっていることを感じますね。
大塚国際美術館で、大量の美術品を浴びた影響もあるのでしょうか。なんにせよ良いことだ。

例えば、僕はモンドリアンが好きなので、彼の影響を強く受けた『デ・ステイル』などのページを読んでふむふむとなるわけです。デ・ステイルに関しては、おそらく今後も日記なり本紹介で書いていく気がします。好きなんですねぇ。
赤と青の椅子……Red & Blue Chairいいよね。シンプルを極めた結果の構造がカッコいい。この本だとカラーで見れないのが惜しい。各々で検索してみてね。チェア業界の傑作デザインですよ。
こうしてデザインの歴史を順番よくめくっていくうちに、気になった部分を深掘りしていけばいくための本なのですね。暇なときに少しずつ読んで、「へぇ~」となるのに適した良書です。各デザインの実例をもっと見たかったですが、その場合はもっと高い本を買っていかないといけないか。
・日本中から嫌われている僕が、絶対に病まない理由 今すぐ真似できる! クロちゃん流モンスターメンタル術30
急に、芸能人の自己啓発本をオススメされて混乱しているでしょう。僕だってこういった本を読むことになるとは想像していなかった。メンタル術って、たいていは「文句言ってくるバカな人のことなんて気にせずいようね!」以上のこと書いていませんし、それが全てです。
が、この本は面白かった。というのも、「クロちゃん」という特殊な立ち位置が独特で、彼はテレビ番組のせいで「嘘つきで気持ち悪い嫌われ者」といった立ち位置になってしまった。おかげで番組からは引っ張りだこらしい。テレビとは無縁な僕でもなんとなくその情報を知っているほど。
テレビの視聴者層はある意味では純粋で、「嫌われ者」と認定されて以降、クロちゃんがなにをツイートしようとも必ず誹謗中傷が飛ばされ続ける。その件についてもちゃんと触れてある。もちろん、本人もいろんな偶然でこの立ち位置になったわけで、望んで嫌われてでも目立ちたいなんて考えていない。けれども結果的にはそうなった。
もちろん素だって十分に出しているでしょうが、所詮はテレビの演出であり、なにより有名人だって人間。リプライや引用だってあくまで愛のある範囲でのからかう程度であるべきなものの、「日本中から嫌われている」と自称するレベルでは、そんな制御が効かない。実際、彼のツイートを見に行ってみると、どんな日常ツイートにも必ずガチの誹謗中傷を投げるアカウントが散見される。
この本の面白いところは、そんな人間性を失ったアンチを思い切り切り捨てているところだ。僕だってそう思う。どんな理由であろうと無関係の人間、所詮はテレビやモニターの向こうの人間に暴言を投げて粘着していい理由にならない。クロちゃん自身もそう語っている。極めて冷静に。明らかにテレビの誘導でアンチになった人間たちが悪いが、本人たちは「テレビの悪者」を退治するつもりで今日も粘着する。すごい構図だ。ネットの嫌われ者はたくさんいても、テレビの規模だとここまでになる。
アニメアイコンによる嫉妬心混じった誹謗中傷ともちがい、もっとテレビに話しかけるしか楽しみのない中年の悲哀が込められたアンチ行為。どちらも当然バカでしかいのですが、前者側しか見えにくい僕らも、一度テレビ業界の苦悩を覗いてみるのも勉強になるでしょう。
・インターネットにおける誹謗中傷法的対策マニュアル〈第4版〉
ひょんなことからクロちゃんの本を読み、インターネットでの誹謗中傷が気になったので、せっかくですので弁護士による公正な対策マニュアルも読んでみました。現状、誰かを訴えるような気持ちは一ミリもありませんが、知っておいて損はない。自分は誰かから暴言を吐かれる側ですし、体調やタイミングによってはお金と時間をかけてでも許せない野次がくるかもしれない。
それにしても、アンチは裁判を異様に怖がる。好きなだけ暴言を飛ばし続けた上で、相手が正当防衛として誹謗中傷の話を持ち出したら、「そうやって裁判をチラつかせて脅す気か!!!」と激昂する。相手は絶対的な悪で叩かれて当然なのでサンドバッグであるべきであり、抵抗するなんて言語道断なのだ。が、裁判の場面はできるかぎり公正なものである。例え相手が実際に悪人であってもやっていいこと・ダメなことの線引きが存在しています。
こういった本では、その誹謗中傷と批判のラインが詳細に書かれている。相手が悪い・間違っていると感じていて、誠意を持って説明すれば「批判」になる。当然、前向きな議論のためには批判や意見性があるべきです。一方、ただただ相手を殴って気持ちよくなるための暴言は「誹謗中傷」。デマだったり誇張した内容が含まれていても後者に入りやすい。
当たり前ですが弁護士は賢い。基本は正当性のある勝負で裁判を行う。なので、アンチの言う「裁判をチラつかせて卑怯だ!」という主張はおかしい。法的に見てアンチ側が悪い可能性のほうが大であるし、それでも正しいと思うなら相手も法廷で主張すればよい。クロちゃんの件を見て改めて感じますが、たいていのアンチは面倒だから見逃されているだけで、誰が見たって暴言を飛ばす方が悪い。
話を本書に戻しますが、この本にもそのような事例やスムーズに訴える手段が詳細に書いてある。ここに感情はあまり入っていない。ただただ、「法的にはこのような場合は誹謗中傷になります・なりません」が並べられており、もしこの記事を読んでいる方で、本当に誹謗中傷に困っている場合は、その事例集たちと自身の環境を照らし合わせてみると良いでしょう。
サポートされるとうれしい。
