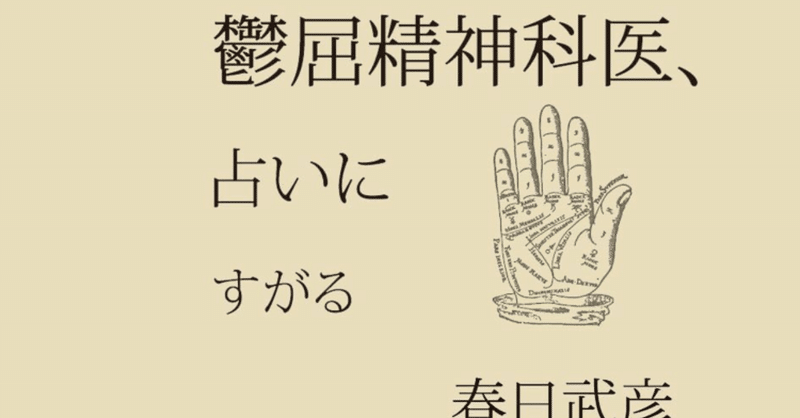
2020.2.25 自傷行為と占い 『鬱屈精神科医、占いにすがる』
最近、自傷行為という概念に興味がある。
とだけいうとなんだか心配されそうなんだけれども、私は定期的に興味のあるテーマが増えていく人間なのであんまり気にしないでほしい(ほんとに!)。自分や知り合いが自傷行為をしてるとかしてないとかそういう話ではなく、単に最近「そういえば面白い概念だなあ」くらいに思い始めたのだ。
私は、多かれ少なかれ人間は自傷行為をしながら生きている生き物だと思ってる。そしてそれが人間のいちばん不思議なところで、それこそが人間の文化なんじゃないか、とも思っている。
自傷行為とは、その名の通り自分を傷つけることだ。しかし一方で「自分にとって不快になる経験を反芻し、あるいは自分を不快にさせることで、自分にある面での癒しを与えている」行為でもある。不快が癒しになるとはこれいかに。でも考えてみれば、たとえば悲しい結末の小説を読んでどこか癒されることも、失恋ソングを聴いて涙を流すことも、自傷的な陶酔が必要不可欠に思う。逆に、笑うという行為ですら、「思ってたのと違った」という軽度の痛み(それは刺激なんだけど)に似た想定外があるはずだ。
そう考えると、感動や感激という体験には、ある種の「痛み」に似た刺激が必要なんだろう。自分で(死なないレベルの)痛みを求めて、刺激され、それによって自分の無感覚から醒め、輪郭を自覚する。それが文化に心を動かされるプロセスなんだと思う。
で、そんなことを最近つらつら考えていたら、週末に『鬱屈精神科医、占いにすがる』(春日武彦、太田出版)に出会った。全然関係ないように見えるけど、上に書いたような話に自分の人生と占いという別方向からアプローチしている随筆で、面白かった。
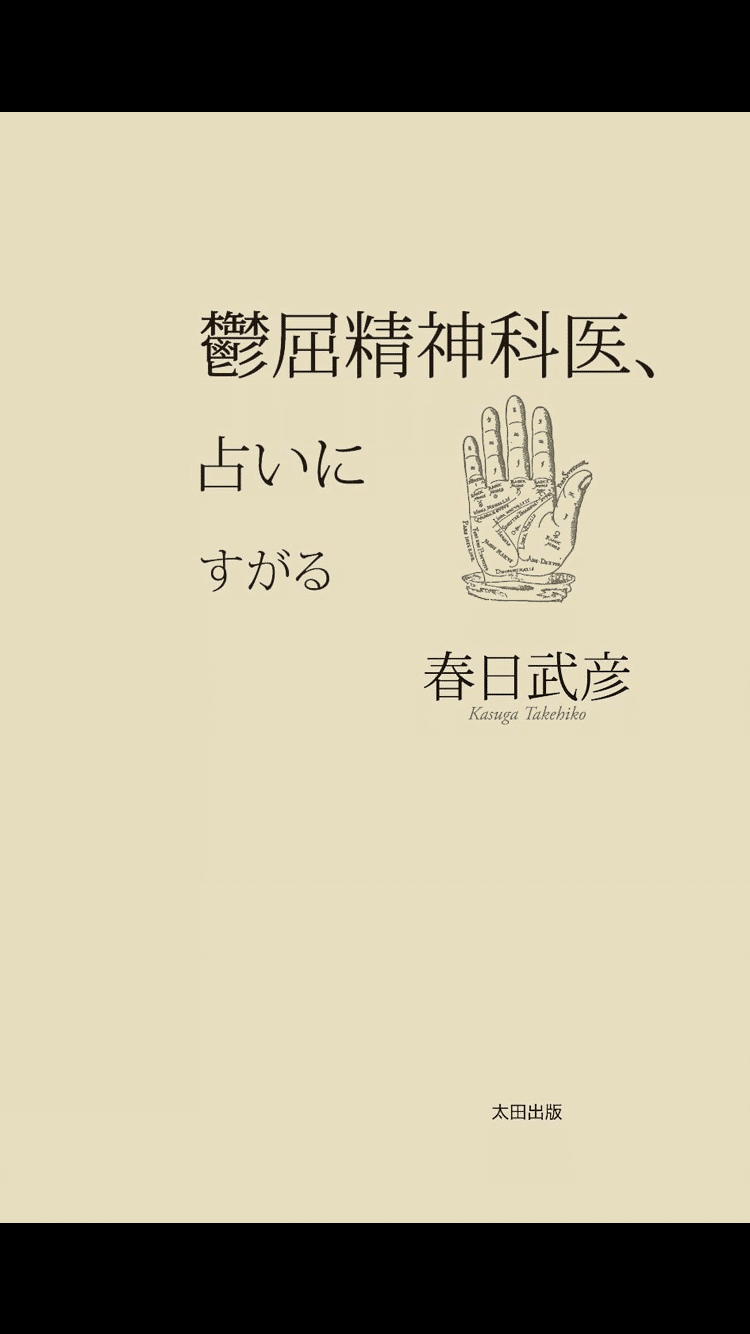
以下引用。
(a)自己嫌悪の主成分は、未練である。 (b)自己嫌悪とは、現実と自分との折り合いをつけるための(いささか奇妙な)セレモニーである。 (c)自己嫌悪には屈折した娯楽といった側面があり、しばしば依存性を伴う。
(中略)次に(b)である。自己嫌悪という代償によって、自分なりの立つ瀬を見出すことが可能になる。わざわざ自己嫌悪なんかしなくても良さそうなものだが、そのようなセレモニー(自傷行為的、と言い換えてもよかろう)を経て、やっと禊ぎだか償いをした気になれるし、自分に少しばかり奥行きが生じた気分になれる。生きることは無意味でないと自分に言い聞かせられる。
自己嫌悪のセレモニーが自傷行為、っていいなあと思う。だけどなるほどと思ったのは、たしかにそこには「奥行き」つまりは生きることの無意味じゃなさ、が存在している、ということだ。
つらいことを埋めるために忘れるためにずらすために自傷行為をするんだ、とよく言われるけれど。でも一方で、たしかにそこで取り戻せるのは、自分がコントロールできる範囲で自分の気持ちを動かしているという事実だったりする。そこで自分の身体と精神が一致する感覚というか、まさに現実の自分といまここでものを感じている自分との折り合いをつけてくれる感じがするのは、わかる、と思う。その必ずつらいことを自分で起こしているコントローラブルな感覚に、依存性があるんだ。
喜びは慣れる。けど痛みは慣れない。だから依存性があるのかもしれない。よくもわるくも。
まあ、自傷行為もこのあたりで終わっているといいんだけど、エスカレートしてゆくと、その自分の輪郭が、折り合いのつけかたが、わからなくなってゆくんだろう。するとどんどん、自傷行為が強くなってゆく。その時初めて自傷行為はほんとうに「現実の自分」を傷つける振る舞いになる。できればその前に止められるといいんだけど、バランスをとるというのはかなり高等テクニックなので、精神に余裕と客観性がないとできない。
世の中の人が、占いで自らを懺悔するくらいの自傷行為でとどまれることを祈っているよ……と本を読んでつくづく思った。こういう形で、他人の自己嫌悪を追体験するのも、変な話、癒されるし。本も占いもコンビニのポテトチップスも、生きてくのがつらくならないための発明なのだろう。まあ、みんなのらりくらりとバランスをとりつつ生きてくために、いろんな文化を発明できるといいよな、とほんとうに思う。
いい本だった。
いつもありがとうございます。たくさん本を読んでたくさんいい文章をお届けできるよう精進します!
