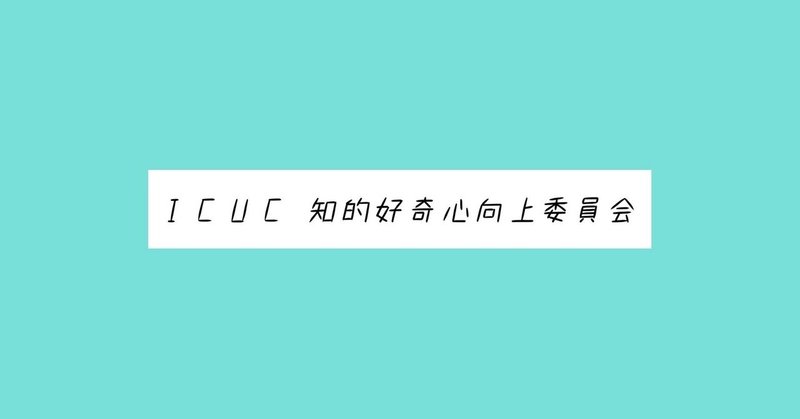
ICUC-086_2021.11.14【妖怪採集:フィクションとリアルの境界を往来すること】
【ICUC知的好奇心向上委員会】の私の知的好奇心の向上&趣味の文字起こし。I see, You see ! Intellectual Curiosity Update Committee
新刊図書
『AP アシスタントプロデューサー』角田陽一郎著エパブリック
『仕事人生あんちょこ辞典』角田陽一郎/加藤昌治(ベストセラーズ刊)
角田陽一郎86
「妖怪採集:フィクションとリアルの境界を往来すること」
ICUC知的好奇心向上委員会
文化資源学のワークショップ“妖怪採集”に参加して南千住を歩きました。その際に感じたことを話しております。「フィクションとリアルの境界はグラデーションである」
動画の内容(+文字起こしメモ&感想)
南千住妖怪採集
おはようございまーす。バラエティプロデューサー角田陽一郎でございます。ICUC知的好奇心向上委員会でございます。今日は11月14日でして、だいぶ秋めいたと言うか、だんだん冬…冬めいたと言うか。はは!何か寒くなってきました。と言いながらですね、今Tシャツ1枚で撮影してて、この画像が残るじゃないですか。全然秋めかないですよね…っふっふっふっふ。冬めかない。そんなことを思いながら、今日も今移動中なんで、移動中に撮影してみようかなーなんて。まあ撮影と言うかね、ちょっと喋ってみようかなーなんて思っております、と。
今日なに話そうかなーって思うんですけど。えーと。フィクションとリアルの境界が曖昧だなーって思ったっていう話をちょっと。どんな様な感じで話そうかなーなんて思いながら。…思ってはおります。
今日は日曜日なんですけど。昨日、土曜日にですね、南千住に行きまして。南千住駅前集合だったんですけど。南千住に行ったのって初めてかも知れないなぁ。素盞嗚神社っていうのがあって、そこには父とね、3回くらい初詣に行ったり。何か父がすごいご信奉している神社だったんだけど。大体車で行っちゃうもんですから、南千住駅前に集合ってなかなかやったことないなーみたいな。
北千住はね、よくインタビュー…街頭インタビューとかをよくしてたりしたんですね。それ、日本全国でもどこがいいとか、東京でもどこがいいとかあるんですけど。インタビューが撮りやすい街と撮り難い街みたいななのがあったりするんですけど、北千住ってのはですね、ちょっと飲み屋に行くとですね、飲み屋の前とかにキャラのいいおじさんとかが結構いらっしゃったりして。「面白いインタビューが撮れる街・北千住」ってのはボクらの(笑)間では通説になっていたことがあったりして。北千住は何回か行った事ありますね。やっぱり下町の気風のいい方がいらっしゃるということだと思うんですけど。
で、南千住で何やってたかと言うと「妖怪採集」というフィールドワークというか、ワークショップ。妖怪採集ワークショップに参加したんですね。これは今通ってる東京大学の授業の一つの市川先生という先生の授業のワークショップで。課外講義、課外授業だったんですけど。で、妖怪を採集するのに数時間ですね、南千住をぶらぶらしました。ボクなんか授業で聞いたことの受け売りだから全然何にも詳しくはないんだけど。妖怪って僕らが想像する妖怪ってやっぱり一番最初に想像するのは水木しげる先生の「ゲゲゲの鬼太郎」の影響が強いって言うか。何かああいう…一反木綿とか、砂かけ婆とかね、小豆洗いとかね、子泣き爺とか。ああいうある意味人格化されたものを妖怪と何となく認識しますよね。そこから色々…妖怪って江戸時代とかに絵巻に描かれてましたねとか、そういう様な感じできっと昔から伝承としてあるんだろうなーみたいな風に思っている方が多いんじゃないかなーと思うんです。
ボクも当然そう思ってたんですけど。その授業で聞いて一番衝撃を受けたのが、雷って昔は雷事態が妖怪だったらしいんですよね。だから人格化される前に。つまり、ちょっと異変というか…日常の生活の中でちょっと異変が起こると、それはもう妖怪だったんですよ。で、じゃあその雷みたいなものが起こった時に、それは何で起こったんだっけ?って考えたら、それを行っている行った人、行った人格が出てきて、それが妖怪の仕業で、雷が鳴ったみたいな。それがだから鬼だったりしてね。ゴロゴロゴロゴローと。
だから元々は現象のことを妖怪と言っていたということをその授業で聞いて。うわ!面白いなー!と思ったんですね。で、その現象みたいなものを司るもの…みたいなものが妖怪という考え方が派生してきてるみたいな。なのでその奇怪な現象というのは例えば日常で「あれ?何か消しゴム無くなっちゃったな」みたいな。きっと消しゴムを隠した妖怪がいるんだ!みたいな。ボクは時々言ってましたけどね、昔。若い頃とか。何か腕時計が無くなったら、「あれ?小人が持っていっちゃったのかな?」とか。そんなようなことって言ったりするじゃないですか。そういうような感じで何か奇怪な現象が起こることを、行った行為者がいて、それがいつしか妖怪になっていったみたいな事なんですよ。へぇぇ、面白いなあ!なんて思ったりするわけですよ。
なので、その土地々々とか、何かの奇怪現象に関してそれを司る人格的なもの、それがもしかしたらあらゆる自然現象に神様が宿ってるみたいなものとある意味表裏一体の考え方なのかもしれないですね。八百万の神というものと。
宗教観
ちなみに八百万の神っていう考え方は多神教と言われますよね。多神教って仏教とかもそうだしヒンドゥー教とかもそうだし。あらゆる神様がいると。そのある意味対抗、対立概念として一神教って言われてると思うんですけど。あらゆるものに神様が…あらゆる自然現象とか、あらゆる自然に神様が宿ってるって考え方って、一神教もそうなんですよね。その絶対的な神様があらゆるものを創ったっていうか。だから一神教の神様を信奉する宗教って偶像崇拝を禁止しているものって結構多いと思うんですけど、それは何故かと言うと、あらゆるものが神様が創ったものなのに、そこに偶像だけ作ってしまうと、偶像だけが神様になってしまったら、あらゆるものが神様がお創りになったっていうことがブレて来ますよね。なので偶像崇拝っていうのを禁止されているって聞いたことがあるんですよ。つまりあらゆるものを創った神様がいるってことと、あらゆるものに神様が宿っているって考え方って、本質的には一緒なんじゃないかなとちょっと思ってるんで。
ボクの、本当に人生の目標って一神教と多神教の融合なんですよね。だから、あのー…ね、レオナール藤田じゃないですけど。レオナール藤田ってね、晩年にフランスのリヨン大聖堂で洗礼を受けてカソリックになり、で、レオナールと名乗ると言うか、名付けられてレオナール藤田になりますよね、画家の。じゃないんですけど、ボクも何かね、晩年は洗礼受けたいなーなんてちょっと思ったりもしてたんですけど。でもそれってボクの中での想いって仏教徒のまま洗礼受けたいなーみたいな。だから何か…何か一つの宗教というものに囚われずに一つの宗教者になりたいなって思いとか、ちょっと妄想の様に思ったりしてることがあるんで、ボクは何か一神教と多神教ってのを融合したいなーなんて思ったりしてるんですよね。融合できるんじゃないか?実は同じことを裏表で言ってるだけなんじゃないかなーみたいな。
さらに言えば。という宗教観みたいなものがあるんで、すごい宗教というのを学問の研究の、何か一つの中核にしたいなーって思いがあるんですね。それって一方で文化資源学っていうのを東大でやってるんですけど、一応研究はテレビ番組、バラエティ番組みたいなことをやってるんですけど。それに対しても博士論文…博士でどういう風に進めようかなーと思ってる時に、まあメディアじゃないですか、テレビって。で、メディアって媒介って意味で言うと、神主さんとかも媒介って意味で言うと、何か宗教にメディアというものがすごい必要で、そのマスコミュニケーションのメディアって意味で言うと、メディア宗教学、宗教メディア論みたいなものってすごくできるなーと思った時に、何かボクの中でのメディアというものと、アカデミックなものを融合させたいみたいなことを…ビジネスとね、アカデミックと、クリエイティブな、A to B to C をエンターテイメントにしたいって野望がある中で、1個そのメディア化っていう考え方をすると、実は A to B to C という考え方みたいなものもすごい宗教と重なってくるんだよなーなんて思います。だから何か宗教メディア論みたいな考え方みたいなものをもうちょっと自分の中で体系が出来ると面白いなーなんて個人的には思ったりしてます。
拾い集める
妖怪から宗教の話に変わっていってしまいましたが。まあそういう意味では久しぶりに知的好奇心向上委員会的な、知的向上ってこういうことかなーなんて思ったりするんですよね。あらゆる情報がぐるぐるとスパイラルになって上昇していく、向上していくみたいな意味かなーなんて思うんですけど。
で、その文化資源学としての妖怪って授業を受けて、その妖怪を採集しようってのに南千住に行ったわけです。で、まあ色々こう神社とかね、お寺とか、この通りの名前は何でこういう名前なんだっけ?みたいなものを見ながら、街を歩きながら、ここにこういう建物・モニュメントがあるよねとかってことを探りながら、街をフィールドワークするんですけど。その街のフィールドワークって別にね、普段みなさんも参加されたことがあるかも知れないし、よくやってると思うんですけど、今回の妖怪採集というフィールドワークで歩きながらね、先生とそういう話で盛り上がっちゃいましたけど。面白いなと思ったのって、妖怪「採集」なんですよね。だから妖怪見学じゃないというか。妖怪を集めてみましょう、拾い集めてみましょうみたいな。その街々、場所々々、所々にある──というのがすごくボクは面白いなーって思ったりしました。
それを突き詰めて考えると、さっきの雷みたいな現象が人格的なものというか、キャラクタライズされて鬼みたいなものになっていくみたいなね。妖怪ってそういう風になって行くとすると、そこにどういう経緯か分かんないけども、フィクション性みたいなものが乗っかってるわけじゃないですか。
それってもしかしたら神話ってのもそうだし、おとぎ話ってのもそうかも知れないし。いや、何だったらね、作家が小説を書くってこともそうかも知れないし、アニメーターがアニメを作る、庵野秀明がエヴァンゲリオンというものを作るっていう事と、ピカソがキュビズムで絵を描くって事と、何か本質的には一緒なんじゃないかなと。…ゴッホが印象派で絵を描いて印象派になるというかね。というのと、その街を歩きながらそこに妖怪を採集しようとして出来上がって行くってリアルとフィクションの境界がもうめちゃくちゃ曖昧になって行くというか。境界って言うと結界みたいな線があって、ここからはリアル、ここからはフィクションみたいな風に分けてしまいがちなんですけども、本当はそうではなくて、そのリアルとフィクションのグラデーションの中でいつの間にかフィクションの方になって行くと、それが妖怪として現出するんだなって思うとすると、そのリアルな街をフィールドワークしている中で、そこに妖怪を採集するってことは、そのグラデーションの行ったり来たりを楽しむという…その場で、その場所で、そのplaceで、そのグラデーションを──今こっち側に行った、今あっち側に行ったっていう。こっち側に行った、また戻ってくる、みたいな。それって細田守監督の「化け物の子」みたいなものかも知れないし、宮崎駿監督の「千と千尋の神隠し」みたいなものかも知れないし、ピクサーの「トイ・ストーリー」かも知れないし。何分かんないですけど、何かそんなものと、その街々、場所々々で妖怪を感じるということってすごい似てる作業なんだなーって思ったんです。
それってね、じゃあアートって何だんだ?クリエイティブって何なんだ?あるいはスタディーズ、学問って何なんだ?研究って何なんだ?みたいなところ、何だったらビジネスって何なんだ?みたいな、何だったらボクがやってきたエンターテイメントって何なんだ?みたいな話って、全部々々…全部、全部、ごっちゃに──本当は境界なんて無くて。そこを行き来することの面白さ、スイッチバックすることの面白さみたいな。これはスタディー領域なんだけど、あれ?ちょっとこれ…ってクリエイティブ領域になって行くよなーみたいな。アーティスティックなものになって行くよなーみたいな。アカデミックなものからアーティスティックなものになって行くよねーみたいな事とかね。
ポンッと生まれる
それって日々暮らしてる中で皆さんほとんどの方はビジネスをしているわけで、そのビジネスみたいなものを考えると、じゃあそのビジネスの中にもクリエイティブ領域ってあるし、アカデミックな領域って当然あると思うんだけど、それがまた全部混ざって行くなーみたな。混じって行くみたいな。そうするとリアルなものとフィクションなものの境界が曖昧な所から妖怪がポンッと、それがまたポンッと出てくるって、自分がその街を歩いていてエッセイを書くとかね、随筆を書くみたいなこととか、今生きていてこういう風に思ったってことをオピニオンとしてまとめるとか、何か旅行していてその旅行記を書くとか、何だったら別にどこにも行かないで自分の一つの空間で日記を記すって事と、その街から、その場所から妖怪がポンッと出てくることって、何かもう同じ…同じじゃんって言うか、表裏一体じゃんって思ったわけです。
それをビジュアライズ出来るか?とかね、ストーリーに出来るか?みたいなことってのはまたストーリーまでは行ってないかも知れないし、ビジュアルとして絵に…だから水木しげる先生はそれを絵にさせてるのかも知れないし。柳田國男はそれをフィールドワークで集めたのかも知れないし。何かそうするとね、遠野物語とかね、ああいう物とかを読んでみて、採集していて、この家ではこういう様な言い伝えがあるみたいな所って、ボクが最初に、若い頃に遠野物語とかを読んだ時って、何かどこまでがフィクションで、どこまでがリアルか分からないじゃないですか。そこでこういう様な鬼みたなものが居たのか、座敷わらしみたいなものが居たみたいな話って。
でもそれって話してるのを聞いてると、話してる人って嘘ついてるのかなーなんて思っちゃったりもしたりするわけですよ、リアルとフィクションが明確に線引きがあると思っていた頃の私はというか。ところが、その線引きなんて明確にないんだなって分かった瞬間に、そういう事を本当に真剣に語っている方は別に幻想を抱いてるわけでもないし…。それがだから本当に体験した、あるいは体験したと自分の中で思っている幻視なのか幻想なのか、あるいはそうじゃなくて、単純に全くの妄想なのかも知れないし、あるいは本当に本当にリアルなんだって思ってるみたいなこと、何だったらUFOとかもそうかも知れないんだけど。そういう事と…じゃあ、コロナのワクチンが効くか効かないかでこういう風に思っているって事って…。とんでも学説だとか、とんでもとか、どういう事とかはさておき。あるいはエビデンスに彩らられた厳密な解釈であったとしても、それをある文明とか文化が信奉している事とかって、何か全部、全部、つまり妖怪ですよね?というか(笑) この世界は妖怪だなっていうか。うふふふ。この世界にはあらゆる所に妖怪がいるんだなって思ったんです。
当事者の採集と観察者の採集
だからそのフィールドワークで南千住を歩いてる時に、妖怪採集をしようって言って、何か色々なものを見て、写真とかも撮ったりしてたんでけど…パシャパシャね。大橋、荒川に跨っている橋のところをね、北千住側に行くと足立区になり…みたいなね。その川べりを歩くみたいなところを見ると、何かその場所々々で自分のイマジネーションが湧いてくる──ああ、その湧いて来て、何かぽーっと出て来たモノ、そのぽーっと出て来たモノをヒュッとギャザリングする。それが採集なんだなーって思った時に、何か今までボクという人間というのはテレビマンなので何か観察、オブザベーション、観察っていうのって一つのボクの中でのキーワードだったんですね。
だからテレビってカメラって客観的に撮るみたいなものがあるとすると、その現象みたいなものとか行為みたいなもの、行動みたいなものがあって、そこに参加するというよりはそこを脇から見て観察するということがテレビマンとしての矜持というかプライドみたいなものだなーって思ってたんですけど。だからむしろ参加してしまったらちょっと染まってしまうじゃないか、みたいな。だからちょっと端から見る、観察するということが結構…客観性が大事だからみたいな事というのもあるし。客観的に見て面白いかどうかみたなものが、映像で撮った時に番組として面白いんだよなっていうもの──つまり逆に言えばそのイベントとか当事者に自分がなってしまって面白いってなっちゃったとして、その面白いなーと思ったものを後で収録したものを編集室で見たりするとすっげぇつまんないみたいな。ああ、これは当事者として参加してるから面白くて、当事者として参加している面白さって映像で、番組で、表現して伝えるってすごい難しいんだよなーってこと。つまりロケ現場で盛り上がったけど編集したらつまらなかったって事をごまんと経験してきたので。
若い頃はそういうのでだいぶ失敗したと思うんですけど。そうならないためには自分の中でちょっと冷めたオブザベーションみたいな、観察者として盛り上がりを見て、それをこういう風にこの画角から撮影して、こういう様な感じでむしろ映像採集して、音声を採集して、それをどうエディティング…編集して行くと面白く見えるか?むしろそれを見た人が面白く見えるか?みたいな事ってのをずーっとずーっと、たぶん考え続けて来たんだと思うんです。
だから何かボクの中では妖怪観察というかフィールドワークって街を観察するとか、そういう風にちょっと端から見ることにむしろ価値を見出してたと思うんですね、今まで。ところが昨日妖怪採集というものに参加して、その市川先生とかとお話ししててですね、何かちょっと思ったのは、採集ということに価値があるんだなってことがちょっと分かったと言うか。その採集ということを、その場所に妖怪がいるの?いないの?ぅ~ん、いるよね?…いるよね?って思うところって一歩自分の中でのリアルからフィクションへグッと進めてるわけですよ。グラデーションがちょっとこうフィクション側に行くわけですよ。そうすると途端に──。
例えばね、それはもうすごい開発されちゃってここにもう昔の面影が全然なくなって寂しいねみたいな。昔はいい建物があったねーみたいな。建物があった方がいいなーなんて思ったりもするんだけど、何かそこでそういう過去の残像みたいなものがなくなってしまった寂しい街だなーみたいなものにまた自分のイマジネーションみたいなものが重なって行くと、じゃあそこに昔いた妖怪というのは今はもういないという妖怪は、どこに行っちゃったのかな?この世界から消えてしまったのかな?あるいは意外に隣の家にはいるのかな?とかね。何かこうイマジネーションがどんどん膨らんでいくわけですよ。
だから何かボクが何が言いたかったと言うと、その妖怪採集って主体になれるんだなと言うか。その街、その場所、そのポイントと言うか、何かそこを端から見ているというか当事者としてそこに入ってしまうってことが、実はそこでの妖怪が現れる、そこにポツンッと現れるためには、そこに入ってみるみたいなことってのがすごい必要なんだなーってことに気付かされたのがすごい、すごい、面白かったんですね。
催眠術
そう言う意味で催眠術ってあるじゃないですか。比較的バラエティ番組をやってたものですから、結構催眠術ってね、経験してるわけです、私としては仕事柄。で、催眠術の番組したこともあるし。で、当然それリハーサルの時に我々スタッフがね、掛かってみたりするわけですよ。で、掛かってみたりする時に──例えば皆さん催眠術ってあれ本当なんですか?とかボク聞かれるわけですよ。テレビでやってますけど本当なんですか?って聞かれた時に答えるんですけど。あのですね…、本当なんですか?って言ってる人には催眠術って掛からないんですよね。催眠術はですね、掛けて!掛けて下さい!もう掛かりたいです!って思うことが大事なんですよね。こちら側の。掛かりたいです!みたいな、もうマゾ心と言うか、スーパーマゾ心みたいなものがあると掛かるんですよ。
これ本当にそうで。椅子を2つ並べて、そこの上にボクが寝っ転がっったんですよ。で、ボクの上に巨体の男が立つみたいなことをADの時に、その寝るのやらされたんですよ、リハーサルで。そんな…ボクの上にそんな巨体な人が乗っちゃったらボク骨折れちゃうじゃん!とか、お腹痛くなっちゃうじゃん!胸が!とかって思ったんですけど。その瞬間に巨体が乗っても全然大丈夫だったんですよ。で、全然大丈夫で、うわぁ!この催眠術本物じゃーん!ってボク本当に思って。すごいな、全然痛くないわぁ!と思ったんですよ。
って思って。その日収録が終わって。家に帰って寝てて。翌朝胸が痛くて起きれなかったんですね(笑) だから。その掛かってる瞬間は自分が暗示掛けられちゃってるから痛くも無いんですよ。ところが寝て、暗示が取れたのか普通に、冷静に我に返ったら、朝…痛い。そりゃ痛いですよね、ボクの上に巨体が立ってたわけですから。「ぅわあ痛ぁ!」と思って、胸が痛くて起きたっていう思い出があります。
あとある催眠術の時にコーヒーを出されたんですよ。コーヒーを出されて「これからこれをオレンジジュースにします。…ハッ!」とか言って、「飲んでみて下さい」って言うわけですよ。コーヒーがオレンジジュースになるわけないじゃないですかと思って飲んでみたら…「全然コーヒーっすねぇ。オレンジじゃないと思います。」って、本当にオレンジじゃなかったんでオレンジじゃないと思いますって言ったわけですよ。そしたらその催眠術師の人が「そうかなぁ」ともう一回こうやりながら「何か酸っぱいと思うんだけどなぁ」とか言うわけですよ。コーヒーの酸味みたいな…あ、違う違う、コーヒーじゃなくてオレンジジュースの酸味みたいなもの。と言って、それをやってボクがもう1回飲んだら、すーごいそのコーヒーが酸っぱくなっちゃったんですね。柑橘っぽい。だからそれってその言葉みたいなものにどう乗っかるか?みたいなことで催眠って掛かる・掛からないんだなーなんてことは分かってたんです。分かってたんです。
ボクらは日々妖怪を生む
で、今回妖怪散策というフィールドワークに行って、その街に妖怪を採集するってことは、採集してやるぜ!っていう、ちょっと暗示にかかるみたいな。つまりリアルからフィクションに行く時の暗示に掛かる。もしかしたら宗教というものに帰依するというのもその暗示に掛かってやる、掛かっちゃうぞ!という前向きな感じみたいなものってのが、端から見ることで、客観的になることよりも中にぐっと入ってみることで見えてくることがある──というもの。その表出自体が何か妖怪の出現なのではないかなーなんてことが感じられました。
だからすごい何かね、見学ではなくて採集なんだっていうのって、昨日はたまたま妖怪採集でしたけど、何かボクがね、いつもこうやって毎週ICUC知的好奇心向上委員会でこういう風に喋ってますけど、この喋ってることもある現象とか、ある体験とか、ある事件とか、ある経験というものをしたもの──それが仮にリアルなことだとして、それを別個で悲しいと思うか?とか、嬉しいと思うか?とか、怒りだとか、可笑しかったとかって思うって、その感情というものがリアルに乗っかって来てるわけですよね。乗っかって来て、それを今度意見として、喋りとして表出するか、書き物として文章にするか、なんなら映像としてまとめて映像作品にするか、みたいな。何だったら絵に描くみたいなものって、結局その現象の妖怪化ですよね。
うん……そっか。ボク、あるいはボクらは日々妖怪を生み出してるんだなーっていう。日々神様を生み出してるとも言えますよね。それが怪しいものなのか、奇怪なものなのか、って意味では妖怪なんですけど。怪しくも奇怪でもないものでも、妖怪がいてもいいと思うんですけど、そうした場合、それは実は神様を生み出してるんだなーという風にも言えるんだなーって思いましたね。そうすると何かあらゆる自然現象に神様が宿っていると思うっていうのと、そこに妖怪がポンッと現れるって事はすごい一緒の事だし。全てのものにそういう神性が宿っているみたいなものに感じる、聖的なものがあると感じる事って、それが神様が創り給うしこの世界って思うって事と、やっぱり本質的には一緒なんだよなーなんて思いますよね。思うし、さらに一緒だたとするなら、ある一人に対してこの人に愛情を感じるという事ととか、もしかしたら憎悪ってのも、怨念ってのもそうかも知れないけど、そんなネガティブな話ばっかりだと嫌だから、その人のことを好きだって思うとか、愛おしいと思うってことも今言った考え方と何か一緒ですよね。
うん。この世界に自分というものの思考、想像みたいなものをどう浴びせると…想像というのはイマジネーションを浴びせると、クリエイション、創造、創る方の創造が生まれてくるんだっていう、想像から創造が生まれると言うか。創造のために想像すると言うか。そのソウゾウはどっちのソウゾウで言ってるかというと、どっちの字を逆っても大丈夫な意味で今言ってるんですけど、何かそんな様なことを感じられたと言う意味では、何かボクはすごい昨日のフィールドワーク、妖怪採集は知的好奇心向上委員会的でした。ICUC、Intellectual Curiosity Update Committee 的な(笑)回だったなと思ったと言うことでございます、と。はい、そんな感じで知的好奇心向上委員会、バラエティプロデューサー角田陽一郎でございました。何か久しぶりに文化資源学的なお話をさせて頂きましたけども。また来週よろしくお願いいたします。はい、バラエティプロデューサー角田陽一郎でございました。

文字起こし後の文字寝かし
(好き勝手に思った感想を書き残しておくことを文字寝かしと言うことにしました)
境界線が無いというのは、知らないうちにフィクションの濃い場所に来てたり、今どちらに居るのか分からなくなったりしそうだ。リアルからフィクションへ進んだり、迷い込んだり。妖怪はフィクションへ向かう時に生まれる気がする。フィクション側からリアルへ戻る時は妖怪をその場に置いて、自分だけ帰るような。
リアルからフィクションへ進んで、妖怪が生まれて、そのままフィクションへ進んで行くと妖怪の世界、妖怪のリアルに人というフィクションが入ることになる??リアルが人でフィクションは妖怪だと思ってるのは人間で、妖怪は妖怪がリアルで人間がフィクションだと思ってるんじゃないか?もし人が妖怪のリアルになれたら、その時は人間の世界へ戻る過程でも妖怪が生まれるかも知れない。それが角田さんの言う「中にぐっと入ってみることで見えてくること」じゃないか?と。コトブキさん言う体験もそうかも。
あらゆるものに神様が宿っているとする多神教と、あらゆるものを神様が創ったとする一神教。神様が創ったあらゆるものに神様の残滓?が残っていて、神様を感じられるとすれば、それは神様が宿っていると言える。つまり神様の発生方法が違う。一神教は最初に人格化された神様がいて創造する、多神教の神様は宿ったものから人格化していく。鶏と卵だ。
屁理屈かもだけど、神様が人を創ったなら、人が作った偶像は神様の創ったものとはやっぱり言えないの?人間は神様の廉価版だからダメ?元を辿れば神様なのにと思う。神様も”自分の偶像とか創っちゃってるw”と思われると恥ずかしいか(^^)
どこで妖怪になるか?神様になるか?を考えてみる。雷みたいな自然現象は力が強い、人が死んだり人柱として人を差し出すこともあり、影響範囲が大きいと神様で、小さくて弱くて、命に関わるような怪我や病気ではなく、いつも人の側にいるものが妖怪、かな。
漆原友紀著「蟲師」という漫画が好きなんだけど、今回初めて思ったのは、この漫画では蟲は妖怪ではないし、そもそも”妖怪みたいな人格化されたキャラクター”は出てこないってこと。人が蟲に近いものになった場合はちょっと妖怪のようになるけど、基本的には蟲というキャラクターはいない。どちらかと言うと神に近い蟲の話も登場する。妖怪が人格化する前の現象自体を蟲と呼んでいて、主人公の蟲師のギンコだけが蟲の姿を捉える話。作者の祖父母などの不思議な体験を元に創作したって紹介が挟まれてて、それも面白い。これは妖怪としてキャラクター化するほど一般的(?)にならなかった現象をベースにした創作なのかな?もう一周、全10巻読みたくなった。
宗教にメディア。今ではすっかりそんなものは危ねぇ!逃げろ!ってなもんだけど、A to B to C の考え方が宗教と重なる。絵画は宗教を原点に持つってことは豊津徳で分かったけど、絵画も彫刻も文学も歴史も科学も政治もエンタメ(祭)も宗教が原点で、それらが宗教のメディアだったから、A to B to C to … は宗教と重なって当然なんだ。宗教を原点にみんな繋がりがある。文化資源学って垣根を横断するものだと仰ってたし、バラエティとは色々って言ってたし、連関って言葉を何度か聞いた。宗教の「中にぐっと入ってみることこと」が角田さんのこれからのバラエティには大事なんだ。
今回の話を聞いたら、神様の進化の過程を少し戻ると、どこかで妖怪と分岐してるんだと思ったけど、そうすると…宗教の中心が神様なら、宗教って妖怪を土台に成り立ってることになるな。
人の生活という超リアルな中から妖怪や神話というフィクションが勝手に生まれていく。ことわざとか単語も、意識せずともどんどん生まれてくる。人がどうしてそれらをストーリーに仕立てることが多いのか分からないけど、人って人以外のものもずいぶん多種多様に生み出せる装置なんだな。
今の人は目が悪くなったから妖怪や妖精が見えないとか、大人になると見えなくなるって話は定番だけど、それはどうしてなんだろうか。人間社会というか人の世の当事者ではあるけど、他の世界、地球の当事者だって意識がなくなったからなのか?
毎回聞いてちょっと嬉しいのはグラデーションの話。若い頃から人の気持ちは白黒はっきりでは嘘だと思ってたから、角田師匠のお墨付きを貰えたよう。本当はこんなにグラデーションで、どっちが白か黒かも分からないほどだったんだと気付かされたのがコロナ禍の在宅ワークだと思う。スーツを着ない。電車に乗らない。オフィスに行かない。グラデーションだったと分かったからこそ、自宅だけどそれなりの格好をする。化粧をする。仕事スペースを作る。そんな風に自分なりの切り替えをする人の話をよく聞く。私はずるずるいつまでもやっていたい人だけど、ちょっと変えてみようかと思ったり…。
豊津徳。今週はついに京都からLiveらしい。とても楽しみ。残念なのは文字起こし。前回10月の回からついに追い付かなくなった。お二人のリモート対談の時だけでも…とも思ったけど、10月分が追い付かないまま11月になったら諦めようとも思っていた。ICUCだけでも手一杯な週もあるから…私にとって良いことではあるんだけど…やっぱり諦めるしかないかな。その代わり作業中のBGMとして回そうかな、そろそろ「渋谷で角田陽一郎と」と2020年の3ヶ月分になっちゃったし。悔しいなぁ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
