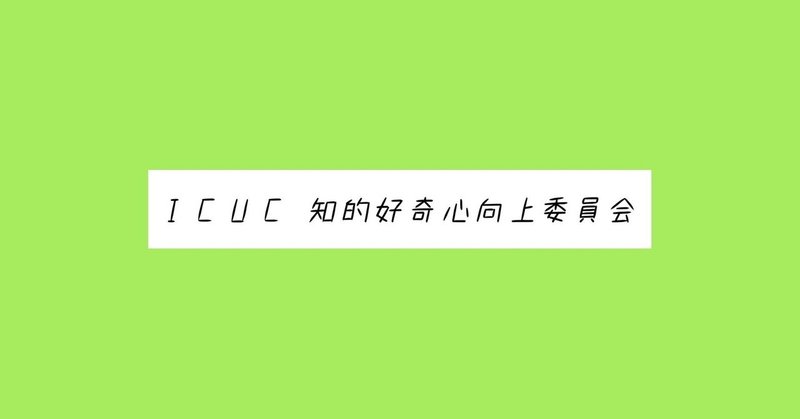
ICUC-115_2022.6.26【弱さを見せること、強がること】ICUC知的好奇心向上委員会
【ICUC知的好奇心向上委員会】の私の知的好奇心の向上&趣味の文字起こし。I see, You see ! Intellectual Curiosity Update Committee !
角田陽一郎115「弱さを見せること、強がること」ICUC知的好奇心向上委員会
今まである意味自分の弱さを見せることが、誠実さだと思っていました。
でも強がってみる、ということが実は必要なんだと、最近ようやく気づいた気がするのです。
動画の内容(+文字起こしメモ&感想)
僕はオモテ面で弱さを出している
おはようございまーす。バラエティプロデューサー角田陽一郎でございます。知的好奇心向上委員会115回目を配信しようと思っております。今日はね、日曜日の夕方でございますけど。なんか全国すんごい暑くて。ただ僕、この海の街にこのアトリエがあるんですけど、アトリエの中はそんなに…まあ暑いけど、すげぇ暑いなぁっていう東京のあの暑さみたいなものはそんなに感じず、なんか快適かなぁなんてのは思ったりもします。
で、今日は何を話そうかなーなんて思ってるんですけど。テーマで言うと自分の弱さを見せることというのと、あるいは自分が強がることっていうことについて話してみようかなーなんて思うんですけど。まあこのICUC知的好奇心向上委員会も含め、角田陽一郎という、バラエティプロデューサーという人間がいるんですけども。基本的には、なんて言うんでしょうね、虚勢を張る、あるいは虚勢を張らないで自分のありのままを出すとすると、自分のありのままを出す方を基本的には自分のブランディングにしている、あるいはしてきたと思うんです。うん、でも一方でプライベートな自分とイメージとしての自分とがあった時に、それでいいのかなーなんてことは思いながらもね。そこで嘘をついてもしょうがないし…みたいなこと。それってこのICUC知的好奇心向上委員会ってのは一番如実に表れていて。公人・角田陽一郎というよりは私人・角田陽一郎がどれほどの気持ちで、どんなことを考えてるか?みたいなことを喋ってるんだと思うわけです。一方で、翻ってと言うか、YouTuberみたいな方が喋っているものって、まあすごい個人としての魅力がある人がその個人の強さ、弱さみたいなものを出すってことでいいんでしょうけども。なんかもうちょっとライフハックと言うか、お得な情報みたいなものって──編集の Premiere Pro の使い方みたいなね(笑) 例えば解説動画みたいなものって、その人の強さ、弱さみたいなものはそんなに関係なくて。その情報がどれだけ役に立つか?みたいなことで多分作られれていて。で、その情報を知りたいって人が検索した時にああこの情報は役に立つなーっていうとたくさん見られるみたいなことなんだと思うわけです。
ってことを考えるとですね、このICUCみたいなものって、僕がこういう風に喋っていることって、なんの価値があるのかと言うとほぼ無いですよね?うん。だから親しい人にね、このICUC知的好奇心向上委員会を見て頂いている方とかがいて、時々話というか意見を聞くと、この角田さんというブランドというものよりも、角田さんの中の弱さみたいなものを出していて、良くも悪くもと言うか。まあそういう風に言うと大体悪く言う感じではないけども、基本は良く言ってくれてるけど、本当は良いかどうかは分かんないけども…みたいな感じで。つまり作っていない自分みたいなものをこのICUCでは表明しているんだろうなーなんて思うんですね。で、一方で。それってメルマガ、自分がやってるメルマガDIVERSEっていうのもすごい個人的な気持ちとかを書いているから、基本的には弱さみたいなものを出している。まあその自分の時のこう…なんか自分のその時思っている鬱々とした気持ちみたいなものを文章にしてるんだなーって思うわけです。
で、それって果たして価値があるのかなー?って思うと、エンタメとしての価値はほぼゼロですよね。ほぼ無い。うん、だからあれですよ?例えば僕がすごい有名人でとか、アイドルでとかならば、そのアイドルの公式のオフィシャルな立ち位置が例えばどこかにあって、その裏側みたいなもの、B面みたいなものは例えばこのYouTubeでは見られるみたいなことだったら、まだ成立はしてるんだと思うんだけど。僕は(笑)オモテ面でその弱さみたいなものを出しているわけで。それって本当にコンテンツとして価値があるのかな?って言うと、まあ究極的には無いんだろうなーなんてことは思うわけです。
自惚れる必要がある
で、思った中でね。このICUCであったっけな?そういうところ調べときゃ良かったんだけど。なんかこう自分という人間が自惚れた方がいいよなーみたいなことは数週間前にたぶん語ったと思う…語ったかな?語ってないかな?(笑) 語ったと思うんだけどな。ま、少なくとも直近で書いたメルマガDIVERSEには自惚れる必要があるっていうことを書いているわけです。うん。それはなんて言うか、ちょっとそう思った方がいいんだなーっていう思いがあってね。でも自惚れた方がいいって思ってますって言ってることは、つまりそういう風に言わないと自分のネガみたいなことばっかりを言い続けちゃうんだろうなーなんて思ったりするわけです。
で、ところが。まあじゃあ、その自惚れた方がいいみたいなことを自分に言い聞かせてるとですね──つまり自分という人間がすごい人間なのか?すごくない人間なのか?という事の実態、実態があるのか?無いのか?も含めて、よく分かんないで。まあ、そういうもんだろう、と。そういうもんだろうと言うことで自分は自分がやれる範囲でやりますよって、ちょっとこう吹っ切れた感みたいなものが出てきますよね。で、その吹っ切れた感みたいなものが出てくるって、自分の中での思考がそっちに行くっていう事でもあるんだけども。それによってなんか自分の行動とかも変わるんだよなーなんて事はちょっと感じるわけです。ってか、感じたわけです。そうすると、今まで我慢してきた事とかも、それはこう…なんて言うんだろう、自分というものに自信がない、あるいは自信がないと思ってしまっているからその事には我慢しようとか言及しないにしようかなーなんて思ってた事が、いや自分という人間も捨てたもんじゃないだろうと思うとすると、その捨てたもんじゃないと思ってる僕が違和感を感じているものだったらば、それは違和感として表明してもいいのではないかな?みたいに、なんか思考が僕の中で変わって来てる…うん。なんかすごいこの6月って僕の中ではそういう風にそれを前向きって言うのか、なんか自分の弱さを見せていくっていう自分がいいなーって思っていたんだけども。今日のタイトルで言うと、自惚れってのは前の前で言ったとするならば、自惚れると言うより強がってみようかなってちょっと思ったっていうか。うん。
で、多分なんだけど、タレントさんってみんな強がってんですよね。本当はすごい弱い人間かも知れないし…みたいなことが多分あると思うんだけど。でも自分の作品が、じゃあ本当はすごいものなのか?すごくないものなのか?なんてのは──、すごい、すごくないってものはそもそも主観でしかなくて、客観的な言葉ではないわけだから、これはすごいんですよ!ってやっぱり思ってないとやって行けないんだろうなーって思った時に、僕なんかは一応クリエイターの端くれなんだけど、端くれとか付けちゃってるところに謙遜なのか自信のなさみたいなものなのか?ってあるんだけど、いやいや、自分はすごいクリエイターなんですよって強がってみるという。この強がるってことがなんか最近まで、あるいは若い頃って、強がってるのって恥ずかしいなーとか、恥ずいなーみたいな思いがあったんだけど、むしろ必要なことなのではないかな?なんて、ちょっと思ったりするわけです。
Abema prime の番組に出演した
で、またそこがちょっと僕の中では繋がっちゃうんだけど。っていう風に思い始めたら──ちょうど数日前に、放送自体はこの前、一昨日、金曜日の夜中にですね、Abema prime、ひろゆきさんが出ている Abema prime の番組で、テレビ局を辞めたフリーの人間、日テレ、TBS、フジテレビ、NHK、テレ朝を辞めた人間が座談会をやるんでっていう企画に出演しませんか?っていう依頼のメールが舞い込んで来たわけです。で、そういうのって、まあコロナ前って言うか、僕は2017年にフリーになってからはなんかそういう話って結構来てたんだけども。僕の時系列で言うとここ数年はなんかコロナだからなくなったってのもあるし、なんか僕にそういう場を、出してもいいやっていうのって、そんなになかったんですね。だから自分の中では発信してますけどね。それは東洋経済オンラインだったりとか、さっき言ったメルマガだったりとか。このICUCてものだったりとか。まあそういう風に自分ではやってるけども、他者から求められてるのか?って言うと決してそうではないんじゃないかな?っていうところの、またこう…自惚れの逆っていうか。まあそんなことを思ってたんだけど。ちょっと自惚れてみようかな?ちょっと強がってみようかな?って思ってみたところ、…そうすると、そういう仕事がやってくるんだなっていうことは何か不思議なんですよね。
で、まあやって来て。で、見て頂ける方、なんか数日間見られるらしいんですけどね、Abema prime ね。その他局の方も含めて、だから5人、5局の方が出てて。アナウンサーさんがいて、ひろゆきさんがzoomでパリから参加して、1時間半くらい喋ってますけど。はっきり言うと僕が一番喋ってましたね。で、なんか当然アナウンサーの方がいるからその人が回しをしているけども、うん。まあ台本を見ても、その回しを見ても、もっと深いところ突いた方がいいなって思うこととかが、やっぱり自分としてはプロだからあるわけです。そうするとそこについて語ろうみたいな時に僕はいちいち茶々を入れてたし。台本上は今この人が喋るって番だからって、その番の人の話を邪魔するってことはしちゃいけないのは当然分かってる上で、その方の話をより面白くするために茶々を入れるとか、あるいは論点を付け加えるとか、そういう事を結構、自分の中ではその90分の中でやってみたところ──。で、まあ、やった後、やり遂げたなーなんて思いながら結構見返してみたら、結構頑張ってるし、結構面白いんじゃないかなって思った時に──うん、なんかその自分がそれをやれるスキルがあるってことは実は強がりでも自惚れでもなく、ある一定の才能と言うと語弊があるけども…語弊があるけどもって言ってる段階で自惚が弱いんだけども、そういう能力はやっぱりあるんだなってことをなんか僕はちょっと確信しましたね。で、これおが面白いわけですよ。
確信したって言うのは、という様な思いの方が先にある、強がってみようとか、自惚れてみようと思うと、そういう仕事がやって来て。実際そういう結果を残せる。で、残した後に翌日関係者の方からやっぱりメッセージが来て。もう角田さんがいて助かりましたと。うん、社交辞令な様な気もするけど社交辞令じゃない気がします。自分で放送を後で見てみたら確実に僕がケミカルというか化学変化を起こさせる起爆剤になっていたんじゃないかなと。適度にひろゆきさんにツッコむしね。ひろゆきさんとの会話の中でホリエモンと今バトッてるじゃないですかって言ってみたりとかね。そういうことをちゃんとやれてるような気がする。うん。強いて言えば僕にもうちょっと回させて頂けたら、ちょっと途中で脱線して、話の本筋じゃないところで盛り上がるみたいな感じになってるなーって思ってるところとかも、もっとテレビとネットのこととか、テレビ局のビジネスモデルとかをもうちょっと面白おかしく、より深く、話せたんじゃないかなーなんて思いもあります。だからポテンシャルとしてはもっといけたんじゃないかなーみたいに思います。なんかそれってそこは自惚れてみてもいいんだな、強がってみてもいいんだなって思います。
思いが先か?行動が先か?
あ、今コメント頂きましたね。「確かに角田さんが一番喋ってましたね。バラエティ番組の人らしい、出るためのスイッチONした角田さんだったなーと思いました。」そうそう、スイッチONした感じがするんです、うん。今のスイッチONって彩さんからコメント頂いたのはすごい僕の中ではすごい言い得て妙と言うか全くその通りで。
元々ONにしてたんだけど、なんかコロナもあるしOFFってたんだろうなっていう、自分の中で。うん。で、それがね、例えばコトブキツカサとやってる寿司特ってやつだったりとか、東京画廊の山本豊津さんとやってる豊津徳っていうところだったりとか、例えばちょうどそのさらに2日前の水曜日、今週の6月22日には大阪で吉本新喜劇の佐藤太一郎ってのとやってたトークライブ陽太っていうのを久しぶりにね、コロナで止まってたものを久しぶりにやってみたんだけども。うん。やっぱり僕は…今日はそんなに喋らないですよーなんてオープニング言ってたんだけど、結局太一郎に喋りすぎですってツッコまれる。つまり吉本新喜劇のタレントさんにツッコまれる意味では正しいツッコまれ方をしてるぐらい正しく喋っていたんじゃないかなーなんて思うんですけども。うん。まさにスイッチON出来たのかなーなんて思うわけです。
そうするとね、弱さを見せるって事が僕の中ではすごい…僕の中での誠実さの表れだったんだなーとも思うんだけども。それにこう…弱さ、フラジャイルみたいなものの呪縛っていうかに自分というポテンシャルみたいなものがだいぶ抑制され過ぎていたみたいなことなのかなって…うん、今は感じる。少なくとも先々週ぐらいまでは感じてなかった。うん。
なんか瑣末なこと、ちょっとした悲しいこと、ちょっとした辛いこと、ちょっとした憤りみたいなことに関して過敏に反応しすぎていて。でもそれって結局自分の中での能力の無さなんだなーみたいな風に、なんかこう自分のポテンシャルと自分の環境との関係の中で自分の方に非があるように思い込もう、思い込もうとしていたっていうか。うん。で、本当はそういう人じゃない人だったらばそういう風に思い込もうとすることって社会の中での潤滑油にもなるし、献上の精神とも言えるし、特に日本というすごいしがらみが多いところだと実はそういう風に振る舞う、あるいは考えるってことは一定的に大事なんだとは思うんだけど、なんかそれに拘りすぎていたって言うか、束縛されすぎていたんだなってことをなんかこう…思ったわけです。
そうするとなんか自分の──、面白いんですよ。その、という感じで自分が例えば金曜日の夜の Abema prime なのか、水曜日の陽太なのか、そういうところで自分がスイッチONした状態をやったから自分は出来るじゃんって思ったとのか…というよりも、自分は出来るんだ!って思ったらそういう仕事がそういう結果を残せてるっていうことなんだなって思うと、思いが先か?行動が先か?ってことなんだけど、そこってやっぱりお互いがお互いをフィードバックしながらそっちの方向に行くから、それに合わせて思考もそっちに行くし。というか、その行動を招くためにはまず思考がそうなっていないと行かないんだろうなって思ったりするわけです。うん。
なんかそれってこの6月の今日は26日ですけど、うん、なんか昨日、6月25日とかにはなんかちょっとそういう事を気付かされた感じがします。うん。もう迷わない!…っとまで(笑) 断言できるほどその感じがあるかどうかは分からなくて。また自分が落ち込む、凹む時には…、凹んでしまったら、やっぱり違うんだよ、自分なんか自惚れるほどの存在じゃないんだよって思ってしまうことがあるかも知れないけども、現時点での僕は…うん、スイッチONのまま行ってみようかなってちょっと思い…ようやく思い始めましたね。うん。で、僕がそのスイッチONをやっていることで、例えば周りなのか、周辺なのか、そういう所と軋轢があったりすると、今までだったらその軋轢の方に自分を合わせて行って、むしろスイッチOFFにしちゃおうみたいなところがあったんだけど。そんな軋轢みたいなものがあることを前提で自分はスイッチONのまま行ってみようってちょっと…思う。で、それが過剰に自惚れてるとか、過剰に強がっているんじゃないかってことかも知れないんだけど。それも、まあ言うても50年ぐらい生きてるんで。なんかそういう風にやっても大丈夫なんじゃないかなって、社会との折り合いというか、社会との関係性において、それぐらいの事を自分がやっても、もう大丈夫な年代だろう、むしろ遅すぎるだろう?!そこに気づくのが!って。ちょっと、ちょっとだけ思えている。なんかそれが今日僕が感じていることかなーなんてのは思います。
悲しい思いはしたくないんだ
まあここに至るプロセスというものでは喋れる事も喋れない事も含めて色々あるんだけどね。喋れる範囲でギリギリ言うとね。例えば今、水曜日、大阪の大学に授業に行ってるんだけども。まあ4月からやっていて、このYouTubeでも適度に話したかも知れないけども。なんかね、初めはちゃんと聞いていた学生もね、僕の喋りに退屈なのか寝始めたりとかね、私語が多くなったりしてね。まあそんな事どうでもいいじゃんって思ってたんだけど。まあ、あることがきっかけにどうでもよくないんだな、やっぱり…って思って。それが6月22日の水曜日だったんだけども。
結構僕がキレたんですね。で、その時に言ったのは、別に僕は教育者ではないので教育的にあなた達を高めたいからこうだみたいな事を言うほどの教育者じゃない。ただ事実として、僕が一生懸命喋っているのにそれに対して一生懸命聞いてくれないっていう態度自体は悲しくて。その悲しいと言うことに僕はもう耐えられないから嫌だって言ったんですよ。うん。何で僕の方だけ耐えなきゃいけないんだっけ?って。うん。だから別に僕の話を聞いてすげぇなと思おうが、下らなねぇなと思おうが、そんな事はあなたの中で処理して欲しいんだけど。僕という個人が少なくとも一生懸命やってる時に、もう悲しい思いはしたくないんだよねってことを授業で言いました。んふふ(^^) そんな事を言う先生っているのかなーなんてちょっと思うんだけどね。でも事実としてそうだからね。
で、それがメディア論だったりするからね、実はメディアってそういう媒介って意味で言うと、Aというもの…それはAが例えば教えてる方で、Bっていう方が学生だったりすると、AとBの媒介、メディアっていうのが授業だったりすると、その授業という場でAとBがインタラクティブにやり取りしていな限り成立しないんだと思うんですよ──っていう、まあメディア論の話に、ただ自分の事を言うよりはメディア論の話をしたつもりではあるんだけど。一方で自分がね、Aとしてね、独りよがりにやっていて。Bというものに刺さらないってことはやっぱりあるし。ただ少なくともBという方がAというものに働きかけることで、Aというものがより活性化していくってことがあって。で、BというのもAからの一方的なシャワーを避ける、あるいは一生懸命聞く、あるいは寝る、あるいはむしろ反発して私語をして聞かないみたいな、様々な対応パターンがあるとは思うんだけど。少なくともそこを、こう…、Aが投げたボールをBが受け取って、やっぱりAに投げ返すっていう事が必要なんじゃないかなと。で、それを投げ返してくれるからそのボールを取ったAは再びBに、更に面白い、更に興味のあることを投げ返せるとすると、Bという方が投げ返さないっていう場は僕の中では耐えられないなって話をしました。
つまり自分の弱さみたいなものを語ってみたって意味では(笑) この知的好奇心向上委員会と一緒ではあるんだけども。そういう場で弱さを語っちゃいけないんだよなっていう弱さからの脱却っていうか。うん、なんかそれぐらいはもうしてもいいんじゃないかなってちょっと吹っ切れたんですよね。
で、そういう風に吹っ切れたらね、まあほとんどの学生がどう思ったかは知らないけども。数人はね、すごい共鳴してくれたことがあって。で、共鳴してくれて、その共鳴してくれたって事を僕に教えてくれた人が数名いてですね。それは素晴らしく勇気を貰いましたね。うん。
だから自分の弱さというものを出す強さ、というか。強がってみるというか。そういうことって僕の中では稚拙だし、なんかちょっと上品じゃないよなーみたいな風には思っていたんだけども。実はそういう強さ、強がってみるみたいな事でむしろ自分の訴えかけている言葉が、Aという人間である僕が訴えかけた言葉がBに刺さって、Bの方が受け止めてくれて、また投げ返してくれたっていうのは、実は”弱さがあるから弱いまま黙ってるんだよねーってことよりも、数倍価値があることなんだな”ってことが分かりました。まあ皆んな気づいてんのかも知れないけどね!僕が気づいてないだけなのかも知れないです。うん。あるいは気づいていたけども見えなくなってきてしまった。あるいは見ないことにしようと思っていた。なんかそういうところもあるのかなーなんて事をちょっと思いますけどね。ただそれを見てみた方がいいなとも思ったし。うん。
表方としての気概
この思いがね、僕の中でコロナ明けというかね、50代になった自分というものの新たな生き方の形になるといいしね。生き方というか働き方とも言えるし。自分のスタンスみたいなことかも知れないし。だからずっとこのICUCというのは自分の気持ちとかその時の行動とかの、なんて言うか、アーカイブだみたいな話をしていたんだけども。今僕が思っているのは、せっかく mireva channel ってのをやっていて、寿司特ってのもやっていて、豊津徳ってのもやっていて、ICUCってのもやっていて、考具の加藤昌治くん、高校の同級生とあんちょこ辞典のあんちょこ通信っていうお悩み相談会ってのをやっていてい。で、適度にね、MOVING DIVERSE ってことで僕が移動しているところのドキュメンタリーみたいなのも配信したしていて。で、今度さっき編集が終わったんですけど A to B to Cっていうのものを来週UPしようと思っていて。…やり過ぎなくらいやってるのに、それが全部自分の弱さが、こんだけ弱いんですよって言ってるのって…ダメじゃん!っていう事はちょっと、ようやく、分かった気がします。その角田陽一郎という人間をどういう風にしていこうかなって時に、うん、なんか強がってみようかなってやっぱりちょっと思いましたね。強がってみようかなと思いましたねってことをここで表明してるのって実は弱さな気もしますけどね、うん。でもなんかそういう事で落ち込む、傷つく、憤るみたいなこととかってあると思うんだけど。それはお互い様だしね、うん。なんかそういう自分の中での変化みたいなものがね、すごくあったのが先週でしたね、うん。なんかそんな思いみたいなものって、うん、なんか自分がこれだけ弱くなっちゃってるんだよってことを表明していればいいんだよっていうピュアな感じっていうのを大事にしてきたつもりなんだけども。それよりも自分という人間が強がってみて表出できる自分の能力と言うか、自分のセンスと言うか、自分の行動みたいなものの方にもし若干でも価値があるならば、そっちにベットしてみようかなって思ってるってことかも知れないですね。
──気づくの遅っ!って事なんですけどね。でもそういう事ってね、…今ね、またメッセージ頂いてますけど。寿司特やってるコトブキツカサさんがね、よく角田は…「裏方から出役になれたってことか。」みたいなこと頂いてますけども。そうそう、裏方でいいやって思ってることって、裏の大変なこととかの弱さみたいなものに埋没してる訳だから、そんな出役として強がることは無理なんだよ!みたいなことを存外に語っていたという意味で僕は裏方だって言ってたんだと思うんだけど。このICUCですら、少なくとも自分が考えを表明しているってことで言うならば、表面なわけですよね。うん。だから裏方と言うよりは表方としての気概みたいなことが、もしかしたら弱さを表明することというよりも強がることなのかも知れないし。ま、強がり過ぎてもポキッと折れちゃう可能性があるなーなんて事を思いながらも、そうならないぐらいの調整ぐらいはもうそろそろ出来る年齢なのではないかなーなんて事を思っている…ってことかも知れないですね。うん。まあ、強がってみようと思います!んふふふふふ(^^) それが上手く行くかどうか分からないけども…っていうところがまた弱がってるかな?まあそんな感じで今日のICUC知的好奇心向上委員会は終わりにしたいと思います。また来週よろしくお願いいたします。
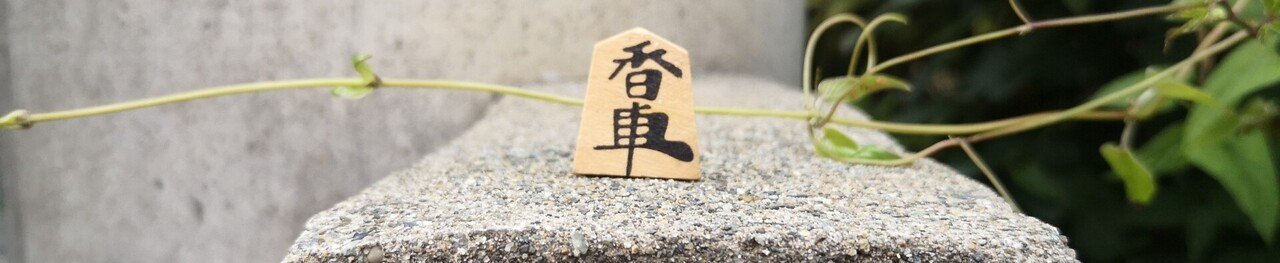
文字起こし後の文字寝かし
(好き勝手に思った感想を書き残しておくことを文字寝かしと言うことにしました)
自惚れてみようと思う過程。
ICUC-113_2022.6.11【人生の潮目が変わるとき】では、資格で実力は測れないから不要じゃない?みたいなことから、資格を持つ事で自信が持てるかも?まずは博士論文を書いたという自信を持ってはどうか?という、強がる根拠のような話を「潮目が変わる」という表現で話していた。
ICUC-112_2022.6.5【楽しいこととつらいことは同時に起こる】では、小さいマイナスに対して徒労感で疲れてしまうのは、大きな事が出来てないからでは?フィクションで生きてるとすると、そこが自分のリアルであり、じゃあそこで起こったマイナスは夢幻かも?という話を。
ICUC-111_2022.5.29【新しい生き方、世界に自分をモデレートする】では、マキシマムな動きを連想する肩書きから、ミニマムな動きに合う肩書きに。他人をいい意味で意識せず、でも世界の変容を受け入れようという話だった。
自惚れという単語がはっきり出るのは、DIVERSE vol.99 2022年6月14日Full Moon『自惚れのススメ』だけなんだけど、自惚れてみようと思う過程はずっとICUCに残っている。…というかICUCはコロナ前のスイッチON状態から誕生し、スイッチOFFからONの様子までが動画で残っている感じ。なんだかアーカイブの良さを実感できた。本当なら自分の動きをアーカイブから知ることがベストなんだけど、資格って不要では?と似た感覚で、自分の変化ってそんなに見る価値ある?って感覚で。出来るものは真似っこしたいんだけども、Facebookの○年前の今日が関の山かも…。
弱さを見せられることについて、単純に好感が持てる。角田さんに対しては特に。嘘がないという点と、心を開いてくれていると感じる点で。逆に弱さを見せない事に対しては良い意味では弱音を吐かず頑張っていると思うし、悪い意味では本心を隠して嘘をついているという感覚がある。
虚勢って言葉は面白い。虚(うつろ)なのに物事を勢いで進めようとするってことだよく分かる。私が演技や演出という言葉をちゃんと理解できないまま嫌う原因として、この弱いのに強く見せる、無いのに有るように演技する、演出する、つまり嘘をついている、騙しているというイメージが強い。過剰包装なんかも環境問題というより包装で中身をよく見せようとしている感覚の方が強いんだけど、最近なんとかいい意味で演出とは飾るというイメージが出来始めた。化粧や服や、好きな人に贈るプレゼントの包装も演出なんだよな、と思い始めて。
好感が持てると書いたけど、鬱陶しいこともある。私は弱いんですと言われると、かまってちゃんとか、この優しい言葉をかけて欲しいという裏があるような。努力したかどうかはともかく言い訳してる様な。私は大人になって重い女という意味がやっと分かり、さらにそれが自分のことだと分かかり。さらに最近になって自分は弱いんです話をしがちだってことを自覚出来たから、嫌な事があったり疲れた時ほどやらかさない様に気を付けるようになった。
すごいものが出来た。自分で満足いくものが出来た。でも、すごいいいものですって言いにくいのは日本人だからなんだろうか?映画なんかを思い出すと、海外だからって日本と真逆ってわけでもなさそうだけど。
私の”飾るという言葉による演出のイメージ回復”はものづくりから出てきた。上には上という言葉は三すくみの形を取るもので自分が頂点になる事はないから、少なくとも手を抜かずに作った、現時点で満足する出来だってことで、作ったものに対して自信を持つしかない。ならば、作ったものに服を着せてやるくらいのことはして送り出さなきゃ逆にダメなんじゃないか?と思う様になって。作品は子供って言い方は嫌いだけど、思いとしてはこんな感じかも知れない。角田さんなら、例えば本とかに対してそんな思いってあるだろうか?…あるな。「天才になる方法」の表紙なんて一等嬉しそうに飾ってた。
AbemaTV。正直言うと、ひろゆきと?…角田さん大丈夫か?と思って見た。水曜どうでしょうD陣のYouTubeにひろゆき登場回があるけど、面白かったことを思い出した。
AbemaTVでは角田さんとしてはもっと深い話を突いた方がいいなってことだけど。台本を見た時点で一目瞭然なのかもだけど、番組として話の深度はどのくらいにしたかったんだろう?と思いつつ、それぞれ個として話しつつ、番組としてのまとまりを崩さないって大変だと感じた。
それにしても出演スイッチONの角田さんを久しぶりに見た気がした。でもイベントなどの登壇とはまた別のスイッチだった。スイッチのON・OFFって自然とやれるけど、種類は多いし出力の幅も広い。自然とON・OFF出来ない時があって、それが自分が無意識に決めてしまった思い込みなんだと思う。
角田さんはコロナでスイッチONの機会が減った。言い換えればOFFして過去から未来まで内省してみた期間で、それは鬱々とすることも多くて大変だったけど、そろそろONに、内省から今に帰ってくるんだと思った。
大学の話。あとで刺さったってことを言ってくれた学生さんは、角田さんが少しでも悲しまない様にと思ってくれたんだろうな。もちろん共感したという事実をちゃんと伝えたかった部分もあるだろうし、授業の内容を実践し、BとしてAにボールを返しに来てくれた。お喋りした学生さんがいた事は、後でわざわざボールを届けにくるほどの人がいるってことを知るための出来事だったんだろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
