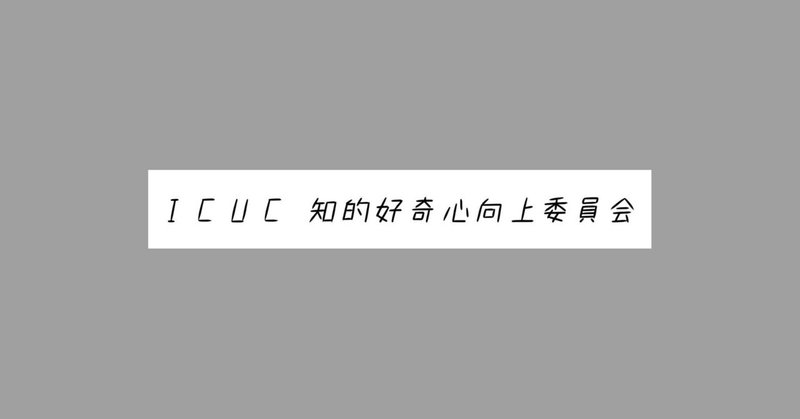
ICUC-121_2022.8.07【どんなヒトだってモノだって結局、何でもいいんじゃ無いだろうか?】ICUC知的好奇心向上委員会
【ICUC知的好奇心向上委員会】の私の知的好奇心の向上&趣味の文字起こし。I see, You see ! Intellectual Curiosity Update Committee !
角田陽一郎121「どんなヒトだってモノだって結局、何でもいいんじゃ無いだろうか?」ICUC知的好奇心向上委員会
どうやって創っていいのかわからなければ先人の模倣から入ればいいというアドバイスをよく聞くけど、ぶっちゃけ自分には若い頃からよくわからなかった、やっぱパクってるような気がしてて。でも最近ようやくその意味がわかった。むしろそもそもあらゆる創作が模倣なんだということが。それでいいのだ。
今日揉め事が起こって、その大会社の代表に電話したら、何回も事情を説明して担当部署に繋ぐの長く待たされたんだけど、廻された先の担当がなんと知り合いという奇跡。瞬時に揉め事は解消された。つまり揉め事は、揉めてる内容如何よりも、関係性の強弱で起こる。
これ外交も政治もそうなんだろうな。
ちょうど昨年の今日はこう呟いていた。
「パズルはうまくはまらない」
それぞれのピースがカチャカチャ全部はまんないと人生はうまくいかないとして、だいたいのことは、だいたいうまくはまんない。何処かが欠けていたり、何故かピースが余ったり。はめるのに時間がかかったり、時間かけてたらどんどん壊れていったり。ならばピースをはめない人生をもう進むしかないな。
でも先日は、こう書いた。
「自分も貴方も世界というパズルを構成する1ピース」
世界というパズルを構成する1ピースである僕が、あなたが、でもそこに今、此処に存在しているから、この世界というパズルは、ある情景を形作っているのです。
つまり想いなんて容易く反転するものなのだ。
モノコトヒトに拘る必要は無いのです。
動画の内容(+文字起こしメモ&感想)
砂浜から
おはようございまーす。ICUC知的好奇心向上委員会でございます、と。今日は海に来ているので、せっかくなんで海で喋ってみようかなーなんて思っております。先々週?先週?海で喋ったんですけどね。あれは本当に急遽喋ったものですから。急遽喋ったからなんだって話じゃないんですけど。あの…結構ノイズが激しかったかな。まあ今回もそれで解決するかどうかは分からないですけどね。まあ話してみようかなーなんて思っています。
これ、あれなんですよね。海をこういう彼に背にした方がいいじゃないですか。海を背にするということは浜の方にこの斜めになってるから、今僕座ってんですけど結構これキツイッすね。なんかね、言ってること分かります?斜めの感じが座っている角度と合ってるといいですけど、合ってない結構…これで30分喋れるのかなーなんて思いながら。こっちからは陽が当たっているしね(笑) とか思うんですけど、まあやってみますか。ほら、こっち行くと逆光になるでしょ?色々こう考えるとこの辺がいいんですけど。はい。
模倣することに抵抗がある
えーと。今日8月7日ですかね。8月7日。あの、今日はね、ずっと執筆を…執筆しようかなーと思って。まだ執筆が出来てないんですけど。出来てないんですけど、執筆が大丈夫だなーって思う予感がだんだんして来てるって事がちょっと僕の中では面白いなあと思うんで、今日その発見を話そうかなーなんて思ってるんですけど。ちょっと昨日だっけな?一昨日だっけな?Twitterに書いたんですね。インスタとかに。なんかね、ほら、何か作品を作る時。僕の場合はじゃあ文章を書くとき自分の尊敬するとか大好きな作家の文章を1回写してみようとかよく書いてある、アドバイスしているのってあるじゃないですか。だからつまり模倣してみようみたいなね。作家の文体をみたいな。結構見るんですけど。なんていうか自分の中では…と言われても、もうずっとね、本、なんだかな言って10何冊出してるんですけど、何かすごい抵抗があったんですよ。だって模倣…やっぱパクりになっちゃうじゃないかみたいな。
テレビのバラエティってそういう意味では色々そういうことをやるときありますよね。各局のものをパクるというか。だから僕で言うとそれこそ昔ね、あの…法律…法律相談所?日テレのね。っていう時に法律を相談する番組をちょうどやってる時にフジテレビで、みのもんたさんで「ザ・ジャッジ」っていう法律、やってたんですよね。「行列が出来る法律相談所」と「ザ・ジャッジ」って言う企画があったんですよ。ちょうどその時金スマを僕やってて。で、なんかそれをパクッたら面白いよねって言って。こういう時にはこういう法律的な解釈ができますよってコーナーをやったんですけど、そのコーナーのタイトルに「行列の出来るザ・ジャッジ」って付けたんですよね。
いやでもそれって、この企画はその人気番組「行列」のパクリだし、フジテレビの「ザ・ジャッジ」のパクリだよって堂々と言うことで、まあ1個のバラエティ的なエクスキューズと言うとあれだな、それで笑えないよと言われたらあれなんだけど、少なくともそれをやっていることの意味みたいなものを自分で作ったんだと思うんですよ。だからそれって一周回って模倣じゃないというか、パロっているっていう感じ。
で、それは…それは大丈夫なんですね、僕の中ではね。だから僕が書いた本とか文章とかのタイトルとか1節とかが、これはこの音楽にオマージュしていますからその音楽と同じ名前にしてますよとか。例えばそのその小説その作品の一つをなんとなく名前が似てますとか実際僕の水道橋博士のメルマガで、メルマ旬報で連載しているタイトルは毎回著名な作品、著名な小説の名前からバラエティプロデュースと名付けて書いたりもしたりしてるんですよね。
だからそういうのは全然大丈夫なんだけど、なんか自分が作る時に自分の好きな作品を模倣してみようって、それとはまた全然別レベルじゃないですか。だから何かそういうのって昔から抵抗があるわけですね。
模倣することに腹落ちする
そうなんですけど。それをこう実際にやってみてなんか最近…、まさに小説を書かなきゃいけないから書いていると、やっぱりその先人達というか自分がこういうものを書きたいんだよなーっていうものがあるわけですよね。で、それって比較的若い頃に読んでいる作品なわけですよ。で、多分若いころに読んでるからその作品を自分もやってみたいとかね、自分もそういう作家になってみたいとかね。そういうような思いがあるからその作品みたいなことを書きたいと思ってるわけじゃないですか。
なんだけど、さっき言ったようにそれを模倣するのは嫌だと言う思いもあるわけですよ。そうなんだけど、本当にここ先日むしろ今夏休み期間なんでこの夏休みにそういうのを改めて読んでみたんですね。つまり若いころ目にしていたものを改めて読んでみる。そしたら「あぁ、そうそう。こういう感じだったよな。」ってこともあるんだけど、若い頃に感じたその衝撃というののリフレインもあるんだけど。…これ後誤解を招いかないように言うと、”この程度でいいんだ”ってことも気づくんですね。この程度でいいんだっていうのは”そんな大した作品じゃないじゃん”じゃなくて、あらゆる作品ってこの程度なんだなってちょっと思えたってことなんですよね。
それが若い頃は実際自分も本を出したことないし、これ別に今小説、本の話だけで言ってるけど、同じように映像作品もそうだし、もしかしたらアートとかもそうかも知れないし。もしかしたらミュージックってのもそうかも知れないけどね。そういうものって若い頃最初に受けた衝撃はこんなのどうやって作ってるんだとか、こんなんどうやって描いたんだとか、こんなのどうやって思いついたんだ、みたいなのの塊じゃないですか。その衝撃のもとにその人たちの作品の虜になったりファンになったり、自分の脳内を形成されていくわけですよね。
で、その思い出補正されているというか、その思い出みたいなものを改めて読んでみると、その思い出はリフレインされるところも当然あるんだけども、それよりも「あ!なんか作り方わかるな。」とか、なんなら書き方は分かるなというか。そっかこういうやり方でやってるんだなっていう。つまり自分が歳とって作品を作る、なんなら文章を書いていることの一つの、一つのメリット。海とも山とも分からないから書けるっていうものが若い頃はあったかも知れないけど、逆に海とか山とか分かる、海とか山とか気付いたことで生み出せるものがあるんだなってことに気付くと、その過去にじゃあ自分が見習いたい、模倣したいと思った作品を今改めて読んでみると、うん、そのシステムは分かったというか。そのエキス…システムって言うとまたちょっとあの冷たいかな?そのエキス、その本質みたいなものが見えたなーって思った上で、その作品のあり方とかを自分が模倣したとしても全然パクリにはならないんだなって。やっと気づきました。毎回これがね、気づくのが遅いなーっていつも思うんですけど。
で、多分そういう、じゃあ小説教室みたいな本とかね、映像を撮るものとかね。そういうものを書いてらっしゃる方っていうのはきっと僕が言ったこととかも当然理解した上で。だから若い人よ、と。あるいは若くなくてもこれから始める人よ、と。まずは模倣から入ったらどうですか?ってアドバイスしてたんだなってことがわかるわけです。それが僕がそのアドバイスをしてほしい年齢の時は全然そのアドバイスっていうのは自分には刺さらなかったんだけども、自分がその年齢ぐらいになる…まあキャリアになるというかキャリアなんか全然ないんですけど、その立場ぐらいに近づいてくると、その人たちがそうアドバイスしている理由がやっと腹落ちするっていう。この事実、面白いなーと思いました。
どっちでもいい
だからこの話から演繹出来ることで言えば、若い人たちはその先生とかね、師匠とかね、あるいは尊敬する人とかがアドバイスすることとかを聞けるかどうかというとやっぱり本質は聞けない、あるいは聞かなくてもいいんじゃないかな?ただそういうアドバイスとかをする人はその立場になった上で今自分がアドバイス出来ることと言えばそれだよっていう、思ってることっていうのはやっぱり、うん、1個の真実ではあるということが分かりますよね。1個の真実という事では分かるんだけども、それを採用するか採用しないかというのはそのアドバイスを聞いた方側に主導権はあるわけで。だからそれをこう採用しようが採用しまいがは勝手ですよ?勝手だけども。で、僕は何かたぶん、採用できなかったのがやっと採用してもいいのかなって思えるようになったというか。
でね、これ採用した方がいい、あるいは採用しない方がいいって話じゃなくて、そのアドバイスを採用するもしないもその人の人生次第だから、つまりどっちでもいいんですよね。このどっちでもいいんですよねって感覚って、なんか言語化すると、さらに言語化すると、何か良い作品と出会おうが悪い作品と出会おうが、どっちでもいいんですよね。って話はこのICUCではよく言ってるんですけど。これ人間もそうだなって、やっぱり最近むしろ思うんですね。
例えば僕のことが好きな人がいる、あるいは僕が好きな人がいる。僕に、相手に、いるとするじゃないですか。それは別に親族だろうがね、友人だろうが、恋人だろうが、そういう好きな人ってのがいますよね。で、一方で、そんな馬が合わないなー、なんなら嫌いだな、苦手だなーみたいな人っているじゃないですか。それってなんなのかなーと思ったときに、やっぱり相性みたいなものはあるし、その出会いの…出会った感じというのもあるし。その出会いの中でどういう経緯があったか?プロセスがあったか?みたいなことってやっぱりすごい大きいんだと思うんですね。そういう感情を抱くか抱かないかっていう。で、そうなった時って、例えばその人の相性あるよねとか、合う合わないあるよねとか、性格が良い悪いてあるよねって言ってるほど固定的じゃないんじゃないかなってちょっと思うというか。
だからさっきの模倣する模倣しないみたいなアドバイスを僕が採用したか採用しないかっていう意味で言うと、僕は昔は採用しなかった、あるいは出来なかった。若い頃は。なんだけど、今は歳食うとなんかむしろ受け入れられる。むしろ採用したい。なんなら模倣しようと積極的に思うっていうことで、今なんか僕は模倣しようと思っている作品を色々こうを読んだりしているわけですね。
すごい勉強になる。そうするとやっぱりなんか自分はそのパターンを自分なりにこう作ればいいんだっていうのがなんか見えてきてて。だからまだ原稿全然書いてないんだけどなんかちょっと安心出来てるようなところが若干あるんですよね。うん。
という風に変わるわけです、自分の考えとか思いって。そうするとその…例えばね、だから恋人で言うと、この人じゃなきゃダメなんですみたいなのってまああるし。実際あるし。それがストーリー…小説だろうが、漫画だろうが、映画だろうが、この人のために!みたいのってたくさん、たくさん、あるじゃないですか。でも本当にその人じゃなきゃダメなのかなと思った時に、たまたま出会ったという意味では、その人と出会ったという価値はすごい尊いものなんだけど。じゃあ…その人が仮にAさんだとして、Bさんと出会えばまた変わるんだよなって。そのBさんが変わるというのは恋愛で言うと…どんどんもう、なんか次から次へと、とっかえひっかえしてるのねみたく思われるけど。友人だってそうだし、会社、今の話って会社とかだってそうだと思うんですよね。
家族ってのは変えられないからまたそこはそこであるドラマを生むんだと思うんだけども。そういう人とくっ付く、そういう人とくっ付かない。その人に好感を持つ、あるいは持たないって事って、そういう意味でなんでもいいんだなっていうか、誰でもいいんだなって僕は何かちょっと思えるようになってきました。
誰でもいいんです、僕は別に。って言うとすごいその相手の事を軽視している、あるいは薄情だっていう風な聞こえ方に聞こえるんだけど、なんか僕はそういうことでもなく、誰でどんな方でも、僕と出会ってしまった、アクセスしてしまったっていうような意味では、なんかその人が僕のことを嫌いだと言われたらそれはそれでアリですけど、何かご縁があるっていう意味ではね、そのご縁の中にこそ実はその人のとの相性とかその人との愛情とか、そういうものがあるんじゃないかなーなんて思うわけです。
パズル合わせ
それって人もそうだし、さっきも言いましたけどそういう会社もそうだし、仕事なんていうもみんなそうだしね。なんだったら住む場所とかね。今ここに行くのか行かないのかなんてね。学校とかもそうですよね。自分の志望じゃなかったとかさ、自分の志望だけどさなんか入ったら違ったとかさ。でもそういうものって、さっきのアドバイスで言うと、その時の、22歳の僕には分からないとか、42歳の僕には分からないとか、35歳のあなたには分からないでしょうとか、そんなことのパズル合わせでしかないのかなーなんてちょっと思ったりするんです。
だから僕は何かそういうの、このICUCでは何週間前とかに、いい作品ばっかりに、良い出会いばっかに、自分がこう満たされてしまうことってなんかむしろ何か間違ってるような気がしてて。なんか悪い出会い、この作品つまんなかったなーとかもあるし、この人と出会ったことですごい失敗したかなーなんて思うことも含めて、出会いっていうのは価値があるんだなってちょっと思ったりすると、そのモノとかコトとかヒトに出会うこと、あるいは別れる事っていうのはそれでいいんじゃないかなって言うふうに感じたりするわけです。これって何か僕の中ではんちょっと面白いんですよね。
何週間前にね、それこそ釈徹宗さんという宗教学者の方とね、トークイベントした時に「幸福というのは幸福を求めないことが幸福だ」って言われて。すごいなるほどなーと思ったって話はしたと思うんですけど。そういう風に思っていくと何か良いヒト、良いモノ、良いコトを追求するということが、言うてもその幸福を追求するということの言い換えでしかなくて。それをやってると結局その人生ってなんかむしろ虚しいんじゃないかなっていうふうに思ったりするわけです。
だからまさに本当に、今日たまたまTwitterで見たひろゆきさん。2チャンネル創設者のひろゆきさんがリツイートしてたやつで、何だったっけな?ハーゲンダッツのアイスを死ぬほど食べたらハーゲンダッツのアイス美味しくなくなっちゃったって書いてるツイートがあったのかな。あんなに好きだったのにあんなに高級なのにって書いてあって。それってあるよねっていう。そうしたらひろゆきさんが美味しいものばっか食べない方がいいって書いてあったんだけど。いや、だからって、それって別にまずいもの食べろって意味じゃないんだけど、なんかその時にある食事もね、作品もね、それこそ人間もね、その時その時のやっぱり出会いなんじゃないかなーなんて思ったりするわけですね。
1年前のパズルをアップデート
でね。そうするとまたちょっと面白いなーと思うのは先週ね、あの、それこそ新月だったからってのもあるしメルマガでも書いたんだけど、世界というパズルを構成する1ピースなんだということを僕が書いたわけですよね、自分というのがね。だからなんかどんなに世界というものが複雑ででっかいもので、自分というのがどんなに些末で小さいものでも、そのピースというものがカチャッと嵌るからその世界っていうのは成立しているんだってことを書いたと思うんですけど。
そしたら昨日?一昨日?忘れちゃった。まあつまり先日、Facebookでね、ほら、過去の書いたこととかが自動で上がってくるじゃないですか。今日は何の日的な。そうしたらちょうど一年前に書いてるんですよ、この世界はピースがはまらないって(笑) うん、何て言うんですか?嵌めようと思ったピースが足んないし、いや、なんならピースが余ってるし。凸凹がなんか間違ってるし、うまく嵌んねぇもんだなと。この世界ってのはガチャガチャ上手くいかないもんだなって、去年書いてるんですよ。そんなこと…すげー忘れてるんですけどね。
すっごい忘れてるのに去年はこの世界をピースで例えて、ピースが嵌んない世界にイライラ、何なら悲しみを覚えているのに、もう一年経ってそんな世界にむしろ僕はそのピースとして嵌ることが大事なんだと思ってるって。もう…もしかしたらその世界というパズルっていうメタファーは一緒でも、1ピースを構成する僕というメタファーがもう僕の中で変わっているってことですよね。
少なくとも去年それを書いたときには僕という1ピースってあるカタチを…こうピシッとあって、それを嵌るところを探してたみたいな。それって職場だったり、人間関係だったり、なんか自分の作るものを…とかね。そういうものをどう嵌めていけば自分のピースが嵌るのか…嵌んねぇな。むしろ僕の嵌る相方とか、僕が嵌る隣は何なんだ?ということをずっと探してるっていうような意味なのかもしれないけど。数日前に世界を構成する、世界というパズルを構成する1ピースだって僕が書いた時には、その時には僕の中では結果的に僕はここにいるところのパズルに僕を当てはめればいいんだっていう。空いてるところにね、カチャッと。っていう風に僕がその出っ張りとか引っ込めを、引っ込んでいるところと出っ張りを、なんかその合わせるって言うとすごい窮屈に聞こえるんだけど、ただカチャッて嵌ることの方の快感の方が実は窮屈さよりも快適なんじゃないかってことをたぶん僕は思ってるからメタファーとしてそういうことを言ってるんだと思うんですよね。
これってね、”ね”って…何が”ね”なんだけど。面白くないですか?ってことです。その時思ったこと、それは20年前に思ったこと30年前に思ったことみたいなことと変わるのは当然で。で、当然変わらない自分みたいなものも本質となって、その中で更新されていく、…アップデートされていく。おお?!知的好奇心向上委員会をアップデートコミっティて言ってたところがなんかリンクしてる感じしますけど。そういう風にアップデートして行くわけだから、考えとかね。そうするとそれこそ何十年か前にその作品を見て感じたことっていう気持ちも、その時の気持ちを大事にしながらアップデートしていくし、それって人間関係とかもね、それが恋愛なのか友情なのか、そういうものもその時そう思ったということを超えて、やっぱりアップデートされていくんじゃないかなーなんて思ったりもするわけです。
なんかねえこれってすごい面白いなーなんて思ったりするんですね。自分が”こう思う”とっていう思いってまあ、あるじゃないですか。それを相手に伝える。相手としてはどこまで理解するのかというのは相手次第なわけで、その時にその相手が僕に例えばちょっと共感とか好意があれば受け入れやすいですよね。あるいは否定するにしてもまあまた角田のその性格だからそういうことを言ってんだよねみたいな。本質的な否定というよりはその度量があった上での受け入れが出来るわけですよね。
ところがそういうのが無いければあいつ何言ってんだって話になるし。いや何ならキモいって話になるし、なんだったら酷いみたいな話になるし、なんら誹謗中傷だみたいな話まで行くって考えると、なんかそれってそのもの自体に果たして良い悪いとか…好き嫌いも含めてあるのかな?っていうか。その時のタイミングとか関係性において好き嫌いっていうのが作られてアップデートされるし、その中で自分のある意味尺度というか考え方と照らし合わせて、それが良いものだと考えたりとか、あるいは何か良くないものと考えるとか。そういうことなんじゃないかなーなんて思ったりするわけですよね。
関係性をどう構築するか?
いやこれ、面白いですね。ちょうどね、何曜かな?金曜日かな?またTwitterにも書きましたけど。…よく書いてますね。あの、ある企業とちょっと揉め事が起こったんですよ。ある企業と揉め事が起こって。で、このままではやばいからと思ってその企業の大代表というんですか?電話を…当然メールのやり取りとかもしてんだけど、ちゃんと届くか?っていうのと、お盆休みに入っちゃうとすげー時間かかるだろうなと思ったんで、とりあえず大代表にかけてみたんですよ。
で、そうすると代表、電話の交換の方が出るじゃないですか。その方に僕はこれこれこういうことで、こういうことで…って説明するんだけど、その説明がなかなかハードな説明だから、代表の一般の方には分からないですよね。分かんないんだけど説明せざるを得ないのはご説明するじゃないですか。だから…あなたにそれを理解してくれと言ってるんじゃなくて、ええと…あなたがここだと思うしかるべき部署に1回まわしてくれと。その専門家に説明したら伝わると思うんでっていう話をして。でもこの部ですか?あの部ですか?と。いや、それはお宅の取り決めでその部になっているわけだから僕には分からないけども、その担当、僕が今悩んでるこういうことの揉め事があるところの担当の部署に繋いで頂くしかないんです、みたいなことをもうかれこれ…もうなんか何分もやりとりしたわけですよ。
で、結果、繋いで頂けたんですよ。で、繋いで頂いて。で、最初に名前を角田ですと名乗ったら「え…角田?さんって、何とか何とか?」って言って。えっ…あ!って。奇跡的に知り合いだったんです。ああー久しぶり!みたいな。いや、これで、こういう事があって困ってるんですよって言ったら、それは困るよねーっつって。ちょっと待って調べるからって言って。色々こっちが事情説明して、もうだから直電の電話をもらい、メールアドレスに…いや僕らが今こうなってるこういう事をっていうのを送ったら、ものの30分で解決!うわぁ~解決じゃーん!と思ったんですよ。
そうなったときに物事が解決するかしないかってその問題の大きさやなんか複雑さみたいなことで決まるなーって思うんだけどでも実はそこに関係性があれば解決しちゃうんだなって。ある意味ちょっと嬉しい反面、拍子抜けしたんですよね。
で、これってたまたま僕はあるビジネス案件でしたけど、外交とか政治ってこういう事ばっかなんでしょうね。この人を通せば通る、この人を通さなければ通らないみたいなね。だから例えばで言うとねオリンピック問題で元電通の方がね、今捜査を受けて。で、あの方が正しいか正しくないかなとか全然分からんけど、少なくともあの方がいたから通る話っていうのがあって。まあその通すためのお金がかかる・かかからないという違法性は分かんないですけどね。でもこの方がいたからトヨタカップが出来てとか、オリンピックが入ってきてみたいなことは一方で事実としてある中で、そのコネクションがあるという能力をどう評価するかというのは凄い難しい問題だなーと思いました。
つまりそれこそ政治なんて…というコネクションがない人にも人権は平等だからみんな公平にやらなきゃいけないと言いながら、結局そういう知り合いがいるから…なんて言うんでしょう、知り合いがいるから有利にするみたいな。明らかに賄賂性のある話になるまでもなく、コネクションが繋がらないというレベルで、もう今みたいなね、僕がやったみたいなケースがあるとすると、それって実はその能力とか中身の内容云々という話もあるけども、実はどういう関係性を構築していく事の方が…事の方が言うと語弊があるな、ということがすごい重要なんだなって。やっぱり実感するわけですよ。
で、そうすると実はその、もしかしたらじゃあ経済的な利益を上げるとかね、もっとベタで言うと人間的に快適に生きるとかね、さらに言えば世界を平和に維持するって、実はそういうコミュニケーションのネットワークをどれだけ維持出来るかっていうことで、その問題が問題にならないように、つまり戦争が戦争にならないようになるとかね。まさにそういうことをやっているときにね、あの、ペロシさんが台湾に行ってて、中国はミサイル撃ってくるとかみたいな話をしたときだから。そういうのってで結局外務大臣の会議でなくなっちゃったりしましたけど、実はそういう時に話せる人をどれだけ持っているか持ってないかみたいなことで、実はその国益みたいなことの実務的な、実的な利益というか、中身以上に重要なことなんだなーなんていうことを改めて実感したってことです。
そう考えると、まあ、まとまってるかまとまってないか分からないけど、何でもいいというものにどう自分がアクセスするか?コミュニケーションするか?ということが、その自分の考えをどう人生にフィードバックするか?しないか?ということと関係しているんじゃないかなーなんて思ったりもします。ということで、また来週。

文字起こし後の文字寝かし
(好き勝手に思った感想を書き残しておくことを文字寝かしと言うことにしました)
海を背にすると地面が斜め。つまり話しながら腹筋運動ができてしまう。
私は全部が中途半端になってしまうのでながら運動は性に合わないので、運動するならちゃんと運動の時間を取ることにしている。10年ほど前に10kg減量出来た時は、スポーツクラブ等だといちいち外で運動できるように着替えて外出しなきゃならないのが嫌で、食事と自宅運動と散歩のみだった。今は逆に運動屋さんへ行く方が性に合っている。つまり着替えている。自主的に人と会おうとしない私にとって、実はある程度人と会うことがメンタルの維持にいい事が分かったから続いてるんだろう。変わりそうにないモノも変わっていく。変わってほしいモノはあんまり変わってくれない気もする(笑)
模倣って良いのか悪いのかどうもよく分からなかったけど、今回ちょっと分かった気がする。
まず模倣と真似の違いは、外面だけ似せるのが真似、細部まで似せるのが模倣という解説があった。なるほど。物事を始めるのに真似から入るということは多いけど(例えば子供がアイドルの真似をして歌って踊るとか、変身して怪獣(=父親)を倒すとか。)、その物事で仕事をしようとか、そのものの質を高めるためには模倣することが大事なんだろう(同じキャンバスと筆と絵の具で同じ絵を描くとか、同じ場所と道具で同じ写真を撮るとか。)。模倣するというのはそのものの本質を捉えると言い換えることが出来るかも知れないし、いわゆる型の習得作業かも知れない。
それからオマージュ、パロディ、パクリの違いという、ありがたいセットの記事があった。
オマージュ
真似る対象に尊敬の念があり、元の作品のままでなく独自の解釈を表現する事。
パロディ
真似る対象に愛情があり、元の作品を茶化す。
パクリ
真似る対象に敬意や愛情はなく、元の作品をそのまま真似る。盗用や盗作。
そっか。模倣や真似は行為そのものを指す言葉で、その行為が行われた経緯、尊敬の念や悪意の有無でオマージュ、パロディ、パクリと分けられるんだ。贋作もパクリに入るかな。パクリの解説には盗用や盗作とあったけど、私はパロディを指す部分もあるように思う。オマージュの解釈の表現は習得した型の型破りという事もありそうだ。
模倣が盗作だと言われるか否か。パロディはしっかり茶化されているから盗作と言われることはないけど、オマージュの場合は盗作だと言われる事があるのは、独自の解釈の表現が未熟だってことなんだろうと思う。言われてみれば確かにこの解釈の表現が無ければ盗作としか言えないし、パロディは茶化すことが目的なので、茶化すという独自の解釈が作品に濃く出るからパロディと分かりやすいんだ。
日本は自分が所有するものに対しては贋作、本物ではないもの、偽物ではいけないという意識がしっかりあるけど、パクったことを”参考にした”と言う人が多いと聞いた事がある。父が「日本は外国の製品を上手に真似た上に性能を高くするから、外国は物を見せるのを嫌がるんだ。」と話していた事も思い出した。そもそも日本人は模倣の技術は高い。自分なりの解釈というのはその作品を元にさらに上を目指す事も含まれていると思うけど、粋じゃない見栄の張り方とか、簡単に儲けよう、簡単に注目を浴びよう、努力や研鑽は面倒だと思えば、いくら尊敬の念があったとしてもそれを表現する技術が不足して、オマージュです、いや盗作だ、の問答になるのかも知れない。
「行列の出来るザ・ジャッジ」みたいなパクリと分かる名前。テレビ局同士だと…たぶんパクられた!と怒ることより、ドヤ顔でパクりたいほど面白かっただろう?と言ってそうだ。自分なら出来ればパクられたと怒るよりドヤ顔をしたいと思うけど、自分が手塩にかけたものがパクられたとき、どんなことを思うだろうか想像出来ない。ドヤれるほどの余裕を持てているといいな。でも盗作だったら盗作だときちんと言えることも大事だ。取り越し苦労だけど。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
