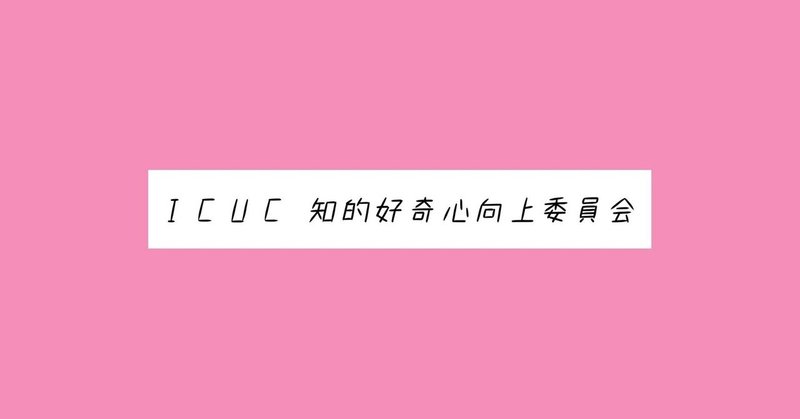
ICUC-077_2021.9.12【小説を出版してみてわかったこと:表現の”拙さ”という価値と新しいOS】
【ICUC知的好奇心向上委員会】の知的好奇心の向上&趣味の文字起こし。I see, You see ! Intellectual Curiosity Update Committee
新刊図書
『AP アシスタントプロデューサー』角田陽一郎著エパブリック
『仕事人生あんちょこ辞典』角田陽一郎/加藤昌治(ベストセラーズ刊)
角田陽一郎77「小説を出版してみてわかったこと:表現の”拙さ”という価値と新しいOS」ICUC知的好奇心向
アカデミック(A)とビジネス(B)とクリエイティビティ(C)の結節点
まずは膨大なやるべき思考を脳内マッピングしていかなくては!!
それは、ボクが、この歳で学生であることと、バラエティプロデューサーであることと、映像や小説を産み出して来た(行く)ことは、全て繋げることができることへの無限の拡張性。そしてそれを繋げることができることの、自分の(もしかしたら世界で唯一の)オリジナリティの可能性。
その拡張性と可能性を内包したOS [オペレーティングシステム]を新たに創造すること。
このクリエイティビティに人生を賭けてみたい。
動画の内容(+文字起こしメモ&感想)
効率が悪いものにどうコミットするか?
おはようございます。ICUC知的好奇心向上委員会でございます。バラエティプロデューサー角田陽一郎です。よろしくお願いします。えーーと?9月12日でございます、と。ICUC知的好奇心向上委員会というのはですね、そいういう名前でやっておりました、CAMPFIREでね。ま、オンラインサロン的なもの。それをこう何となく、去年のコロナ騒動が今でも続いておりますが、コロナから何となく自分が思ってることを30分ぐらい喋ってみようかなーってことをやっております。そんな中ですね、自分の日々思ってることとか感じてることを喋るという風にだんだん移行しておりまして、果たしてそれが知的好奇心の向上に繋がってるのかどうかは(笑) 甚だ疑問なんでございますが。まあ、そんなん感じでやっております。
8月18日に私の『AP』という小説…今あるかな?手元にあるかな?ないか。まあいいや──が、出ましてですね。その時にSMAPのお話をしたりした、コトブキツカサとやっている番組が結構バズったりしまして。で、バズったりして、そのバズった直後にこのICUCでも小説を書くと言うことと推し、SMAPだったらSMAPのことを推している方の熱い気持ちみたいなのを喋った回も結構視聴数が行ったりしてですね。ほぉー!と思ったりして。
で、その次は電気グルーヴの話をしたりとか。フジロックで観てすごい癒さ…ボクの中では癒されたと言うよりなんかちょっと立ち位置を見させて頂けたなーと思う話をして。そしたら通常回くらいの視聴数に変化し。
で、先週は演劇。藤原竜也さん主演の「ムサシ」について語らせて頂いた…。でも別にそれだけ語ってるわけじゃないんですよね。ぐにゅぐにゅ、ぐにゅぐにゅ、単純にボクが今思ってることをまるで渦の様に語ってるから、そのトピックだけではないんだけども、語ってみたところ、むしろそれは視聴数が悪くて、普段より。なるほど!と思いました。
そっか。だからこれちょっと面白いんですけど。分析するとその先週、先々週も言ってたんですけど、このICUCで喋った回にどういうタイトルを付けるのか?ってことってあると思うんですよ。で、さらに1ヶ月前、2ヶ月前とかは結構写真入れたりとか、ちょっと編集も…凝ってはいないけども、やれるだけやってみたりしてたんんですけど。あとはサムネイルをいちいちちゃんと作ってみるとかね。うん、それもそんなに大差無いなーなんて思って。むしろ今は感じたことを喋った後すぐ出す方がいいかなーなんて思ってね。むしろ喋ることを結構車の中で喋っちゃったりして。それをそのままiPhoneでアップするとかね。そういうことをやったりもしてますけども。
そんな中でSMAPの件があったので、やっぱりタイトルみたいなものは大事だな…、いや、昔から大事だなと思ってるんですけど、大事だなーなんて思ってやったんですけど。仮に「ムサシ」って回が悪かったとして、でも藤原竜也さん大人気じゃないですか。で、演劇というものはやぱりすごい…すごい狭いものなのかなーなんてのもちょっと思います。だから「ムサシ」のことは見なくていいやって思われたこととかもあるんだろうな。でも「ムサシ」の話は30分の中のほんの2割3割程度なんですけどね。
…と思ったりした時に、ああ、思ったことをどれだけタイトルに込めたりするといいのかなー?ってことと、毎回毎回トピックがぐるぐる回ってるというのは、ワントピックについて5分で語るみたいなこととかの方がね、YouTube向きだって言われている中では、すごい効率が悪いんだろうな、と。うん。効率が悪いものにどうコミットするか?みたいなのが一番知的好奇心なのではないかなーなんて思うんで、別にこのスタンスを崩そうとは思わないんだけど、でもなんか今思ってるのはこのICUCもそうだし、豊津徳もそうだし、寿司特もそうだっし、そんなにつまらなくないのではないかな?とは思っております、と。
だからまあ、この男が嫌いだって…、このおっさんのうだうだ喋ってるのがもう嫌いだって言う方はそもそも駄目だと思うんだけど、そうじゃなくて、誰が喋ってるかは置いといて、その話の中身みたいなものに興味があるという方にとっては、なかなか深い話してんじゃないかなーって、いつも思ったりします。
それは自分がね、15冊くら本を書いてるけども、本の中身もそうなのではないかなーなんて思ってて。色んな体の…、「最速で身につく世界史」とか「、人生が変わるすごい地理」とか、「「好きなことだけやって生きていく」という提案」とか、「運の技術」とか、「出世のススメ」とか、「読書をプロデュース」とか、「天才になる方法」とか、色んなこと書いてますけど、その辺のビジネス書とか自己啓発書よりはちょっとユニークな気づきのポイントを入れてるのではないかな、と。それはまあその本を書いてた「仕事人生あんちょこ辞典」ってのもそうなんですけどねって思ったんです。
行間を読む必要がないサプリみたいな本
そう思った時に、これ誰って言っちゃうと本当に悪口みたくなっちゃうから嫌なんで、すごい…すごい何冊も本を出してる著名な方のビジネス書みたいな、自己啓発書みたいなのが、ちょっとタイトルで惹かれて買ってみたんですよ。で、パラパラ読んでみたんですけど…。何が言いたいかって言うと、ビジネス書みたいなものってその著名な方が書いてないものを多いじゃないですか。昔だったらゴーストライターって言ったりね、今はブックライターって言ったりしてて。
で、そうするとその方が語っている内容みたいなものが価値あるかないかって言うと、すごいあると思うんです。その方がやっぱり有名な方だから、その著名な方が著名にいるという立場まで行ったのは何故か?とか、そこを維持してるのは何か?という、(──ドッドサッ)経験値とかね。何か落ちたぞ?(笑) 経験値とかね。そう言うものとかが分かるという、トピックが分かるという意味では分かります、その本、すごく。で、それでいいんだって言う人にはそれでいいのかなーなんて思ったんだけども。
これ自分がやっぱり小説を書いてみて分かったんですけど、やっぱり文章というか伝えること、伝え方にやっぱり意味があるなーと思った時に、全部とは言わないまでも、ブックライター、ゴーストライターの方がその方の思いを…喋りを聞いて、聞いたものを文章にまとめてるののまとめてる文章ってのはよく言えば分かりやすい。悪く言えば個性がない。うん、…ものになって、なんかね、その…たまたまその本というか…そう考えるとだからボクは元々言ってるビジネス書とか自己啓発書をこんなに自分が書いてるのにも関わらず好きじゃないって言っている意味が分かりました。つまりね、そこに書いてあるコト、モノの、情報という意味での意味はあるんだけど、その表現する、表現、Expression、というか Express がなんか陳腐だなーなんて思っちゃったんですね。
だからそれこそ速読できますよね。ああ、そういうこと書いてんのねって。この方はこのトピックについてこういうことを書いてるのね、こういう風に思ったのね、こういう風に行動するのね、ってことさえ分かってしまえば、文脈上に行間を読む必要もないし、その文章に深みがある・ないみたいなことって気にしないで読めるんだなって思ってしまったというか。
で、その思ってしまったって意味で言うと、いま自己啓発書だビジネス書だって言ったんですけど、もしかしたら論文みたいなものだってそうですよね。むしろその感情というよりある研究対象についてどのように掘ったか?ということをむしろ客観的に書いた方がいいわけですよね。だからその客観性みたいなものを高めれば高めるほど──、それで味のある論文ってあるんですけどね(^^) うん、それはそれで、そこまで行ったらやっぱり巧みというか職人のすごさみたいなことだとは思うんですけど。そこまで行ってないものがほとんどだとすると、なんかビジネス書とか自己啓発書と同じ、同様なつまらなさを感じてしまう。だからその研究対象について深く堀り下げてるということには価値があるんだけど、その文章を味わうと言う意味で言うとなんかサプリを取っているみたいなものなんだなと。
だから速読とかをすごい勧める人とかはいて、ボクは速読じゃない方がいいという話は「読書をプロデュース」って本でもね、言ったんだけども。速読でも読める本があるんだっていうことは事実だなってことに今更気づいたわけでもないけど、その著名な方の本を読んだ時にトピックとしては面白いのに、読み物としては全然面白くないっていう感覚。これってなんかすごいボクの中では新たな…知的好奇心なのかどうか分かんないけど、知的好奇心とはもしかしたらその相通ずるところがあるし、実はその知的好奇心を阻害するようなものなのではないかなと思ったという風に、思います。
拙さの表現
じゃあね、じゃあボクが書いた小説『AP』というものがすごい文章なのかって言われたら全然そんなことないんです。全然そんなことない。うん。全然そんなことないんだけど、全然そんなことないんだよって事を一作目で書きたかったっていう思いがちょっとあるんですよね。
これって…言ったっけなぁ?ICUCで言ったのか、寿司特で言ったのか、周りの人に言っただけなのか分かんないんであえて言っちゃうと──。第一項が上がったあとね、小説『AP』が。上がった後に、当然編集者さんからね、ここの文章をもっとこうした方がいいですよね、ああした方がいいですよね、みたいな言葉を頂いたわけです。で、当然直した方がいいところは直した方がいいけど、ここの文章ってもっとこう短くできますよね?とか、もっとこう説明が足りないですよね?とか、説明が重複ですよね?みたいなものとか貰った時に、そうだよなーと思ったんだけど、なんかそれを直しすぎて洗練された文章になっちゃて果たしていいのかな?って、ちょっと思ったんですよね。
どういうことかと言うと…、そっか!この前の加藤昌治さん、「あんちょこ辞典」を一緒に書いたね、「考具」の加藤昌治さんとのトークの時に言ったんだっけな。あれはクローズドなのでここで喋っちゃうとすると──これもクローズドくらいの人数しか聞いてないかも知れないけど(笑) 司馬遼太郎がね、「竜馬がゆく」っていうのでブレイクするわけですけど。あれってまだ司馬遼太郎さんが若い時に書かれた文章なんですよね。だから司馬文学とか司馬文体とか言われるほど文調が独特なものがあるけども、やっぱりまだ初々しさがあるわけですよ。その後たくさん作品をやって──「翔ぶが如く」とかあって、そのあと「坂の上の雲」なんてのはむしろ老境に差し掛かった司馬さんが書かれたものだと思うんだけども。司馬文体が洗練された感じであるわけですよね。いきなり著者が入ってくるみたいなことも既に自然みたいなね。今は日露戦争の話なのに著者は…とかってパッと出てきちゃうみたいな(笑)こともむしろ司馬さんだからいいみたいな、独特のすごさみたいなものがあるんだけど。
「竜馬がゆく」ってまだそこまで行ってない気がする。でもやっぱりここまで話題になってしまったというすごい文学だし、むしろ坂本龍馬という歴史人物を再発掘したという意味ではすごい価値のある小説だと思うんですけども。それって坂本龍馬自体も志半ばで殺されてしまう、30代前半で。32とかでしたっけ?で、殺されてしまうという意味で言うと、若気の至りみたいなのが満々あるわけですよね。で、もしかしたら明治維新というものだって近代国家に生まれ変わるための若気の至り、日本の。で、今もしかしたら日本が苦しんでるのってのは若くなくなってきてしまって、若気の至りがやりにくくなってるっていうところがあるとは思うんだけども。その若気の至りというのを描いている青春小説の文章が洗練されていると若気の至り感が伝わらないのではないかな?と、ちょっと思っってたりもするわけです。
だからあれはやっぱり青春で駆け上っていく坂本龍馬みたいなものを速書きというか拙い書き方で書いてしまったいるということに、その拙さという表現方法も含めて青春っぽさというか、うん…挫折までも含めて、それを乗り越えて行った明治維新みたいなものを含めて描かれているのではないかなーって思った時に、ある文章が洗練されればされるほど良いということは果たして良いのかな?って思っているってのがあるわけです。
で、自筆『AP』という小説はボクにとっては処女作、童貞作(笑) なものでございますから、なんて言うか歳はもう超いい歳なんですけど、その拙さみたいなものがむしろあった方が。で、なおかつ主人公のAPの女の子は25歳、三崎美南ちゃんっていう女の子になっておりますが、AP3ヶ月目の話という意味では全然わけが分かっていない中、ぶっ飛んだ人達と業界でやっていくということだとすると、その彼女の思考とか彼女の行動自体も拙いわけで、その拙さってのが文章全体でも拙さで溢れているということで、もしかしたら…。
それでもね、1章から6章まで書いてるから、どんどん進んで行って6章くらい書いてる時には一応1章から書いて行ってるんで、なんて言うか…ボクの中でも1章書いてる時よりは若干洗練さが出てるんだと思うんですよね。そういう作家の成長みたいなものも小説の中で表現としてあるということの方が、小説全体としての初々しさみたいなものが出るのではないかなーなんて思ったりもします。
プロセスは速読じゃ読めない
それってね、村上春樹さんで言うと。ね、最初の第一作は「風の歌を聴け」ですけど。その後洗練された村上春樹文学になっていく縁はすごくあるんだけど、やっぱりちょっと初々しさをボクは感じるんですね。ボク実は村上春樹さんは2作目の「1973年のピンボール」から読んでるわけですけど、だから思ったんです。ああ、なるほど、こういうものなんだと一瞬で惚れてしまったんだけども、そこから戻って「風の歌を聴け」を読んだらむしろ無骨さを感じたわけですよね。
でもあれって「風の歌を聴け」を出してデビューして、認められて、賞を取って…賞を取ってないのか。認められて。で、二作目を書きましょうってなった時に、一作目から二作目を書くっていうのと、ゼロ作目から一作目を書くっていうのには意味が全然違うわけですよね。ゼロから1にするという行為をしたときの拙さ。拙さと言ってしまうとマイナスに聞こえるけども、実はその熱い想いみたいなもの、迸り感みたいなものが過剰に出ている感じ。で、二作目って、二作目が出たから発注が来てるわけで。その発注が来てるという余裕感。でも一作目を超えなければいけないというプレッシャーみたいなものの中で洗練されていく二作目、三作目、四作目という。
三作目で今度方針を…なんて言うんですか、サザンオールスターズで言うと「いとしのエリー」というか。つまり今までやった一作目、二作目とは違う部分を出さなと…みたいなこともあるのかも知れないけど。考えると色々あると思うんですけど、そういうような展開ってその小説自体の作品が描いてることというのもあるし、著者が描いている著者の人生が描かれているという意味ですごい面白いなーって思ったりするんです。だからその拙い文章とかもしかしたら洗練された文章になって行くプロセスみたいなものも楽しむってのが、なんか、本を読むことの1番の──、むしろそのことって速読じゃ読めない気がするんですよね。だからゆったり読む。それはもしかしたら映画とかもそうかも知れないし、音楽とかもそうかも知れないし、アートとかもそうかも知れないんだけども。そういうことに意味があるのではないかなーなんて思うわけです。
で、一方で。やっぱりそのブックライターの方が聞き書きで書いているものって、ある意味そこのクオリティは読みやすいというところは担保されてるみたいな意味で言うと担保されてるんだと思うんだけど。そこに拙さから成長して行くという過程が見えないというのがなんかすごく退屈なんだなーって思うってことになんか気付かされたわけですね。
まあ、どっちでも良いんです。どっちでも良いんだけども、自分がどういうスタンスで、どういう風にそれを味わって、なおかつ生きて行くということなのかなーということに尽きるのかなとは思いますけどね。
先生に正直に話す
そんな中でね、一昨日、金曜日に東京大学の大学院、私、博士課程1年目なんですけど。月いちで面談を…指導教官、指導の教授、尊敬している教授とディスカッションをしてるんですけど。8月はちょっとバタバタしててボクがブッキングしなくて。先生からはいつでもどうぞって言われてるのにも関わらず不義理をしましてですね、ボクから…ボクがブッキングしなかったんで。8月は面談やらずに今、9月になって一昨日やってみたわけです。要するに2ヶ月ぶりにね、先生にお話して。
8月には小説が出て、9月の頭に「仕事人生あんちょこ辞典」が出たって意味ではすごく文章を書いてるように見えますし、毎日おはようございますTwitter・Instagramやってますし、なおかつ適度に note に文章を出してるということもありますし、水道橋博士のメルマガも書いてるし、メルマガ DIVERS っていう自分のメルマガも書いてるという意味で言うと、結構発信してる方だと思うんだけども。むしろ…でもその先生と会わなかった8月みたいなものってのは、ボクは8月はいつも悲しい月だって言ってるのもあり、なんか創作活動は頭の中ではぐるぐる回っていたんだけど、実際机にガンと向かってパソコンをカチャカチャッと打つみたいなことってほとんどやってないような気がします。うん…研究に至ってはそれこそ7月くらいに喋りましたけども、英語が出来なかったという、自分が英語が達人になることは無理なんだってことに気づくという挫折感の中、なんかアカデミックなものにすごい…なんかこう…自分が離れていたところがありますね。
で、一方で「三体」を読んだりとかしたという意味で言うと、なんか小説みたいなものが書きたいな──、書きたいなーとか言いながら8月中に書きますって約束しているものも書いてないって意味ではトータル書いてないんですね。だからアウトプットが出来てるようですごい出来てなかった8月なわけです。で、そのアカデミックへの悩みというか、なんつーんだろうなー、自分の喪失感みたいなものがすごくあって。なんかね、全然出来なかったんです。
で、そんな話をですね、久しぶりに先生と話したものですから、そういう風にぶつけてみたわけです。もうなんかボクのアカデミックなものに対する倦怠感、喪失感みたいなものがありますみたいなことを正直に。で、そうしたら先生からも、そう言いながらも角田さんこんなことやってるじゃないですか、あんなことやってるじゃないですか、みたいなことを色々ヒントを下さって。で、下さった中でね、そのことをボク文章で書いてあるから読まさせて頂くと、、、
今日は久々指導教授とディスカッション。自分の研究領域とビジネス領域と創作領域の結節点について鋭くアドバイスいただく。自分のアカデミックなモヤが一気に晴れ渡る爽快感。まずは膨大なやるべき思考を脳内マッピングしていかなくては!!
それは、ボクが、この歳で学生であることと、バラエティプロデューサーであることと、映像や小説を産み出して来た(行く)ことは、全て繋げることができることへの無限の拡張性。そしてそれを繋げることができることの、自分の(もしかしたら世界で唯一の)オリジナリティの可能性。
その拡張性と可能性を内包したOS <オペレーティングシステム>を新たに創造すること。このクリエイティビティに人生を賭けてみたい。
っていう文章を書いたんですけど。何が言いたいかって言うと、全然アカデミックな研究をやってませんよって先生に白状したところ、「でも角田さんは仕事、ビジネスでこういうことやってるじゃないですか。」ってことは先生には何となく報告してて。で、なおかつそれとは別に創作というのは──元々番組は作ってますけども、小説みたいなものとかいうのをやって行く中で、クリエイティビティがあるものをやってるわけで、それってのは「研究の対象の一つにはなるのではないですか?」と言って頂けて。何となく色んなものをミックスした方がいい、メディアミックスだけじゃなくて色々…思考ミックスみたいなものがいいと言っておきながら、そこはそこ、これはこれと分けてたんだけど、なんか先生と話してるうちにその結節点が見えたと。
結節点の無限の拡張性
そうするとアカデミックなもの、今、学生という身分、立場の、アカデミックな領域と、バラエティプロデュースっていうビジネス、エンターテイメントビジネスの領域と、小説、なんならそれをドラマにするというクリエイティブな側面。アカデミックA、ビジネスB、クリエイティブC、このABCの結節点みたいなものが出来たなーと思った時に、この結節点ってすごい拡張性があるなーと思ったんですね。全て繋げることが出来る、その3つを区分しないということが出来る、無限の拡張性を感じたんです。
無限なので、なのでまずは膨大なやるべき思考を脳内マッピングしなければいけないってのは、無限に広がってしまうものをどうマッピングして思考のデザインをするか?みたいなことを考えなきゃいけないんだよなーって意味で言うと、膨大なことを考えなきゃいけないし、それを実際カチャカチャやらなきゃいけないんだろうなって思った──ということがありますし。その3つの領域を繋げられることはやってる方はいるけど、もしかしたら世界で唯一の、オリジナリティを生む可能性があるのではないかな?と思った…うん、それが自分、角田陽一郎という人間、自分のオリジナリティとも言えるし。その3つの結節点を形にした時になんかすごいオリジナルなものになるのではないかなと。
ずーっとオリジナルなものがないなーと思いながら生きてきた──、それはコンプレックスとも言えるし、諦めとも言えるし、いつか生み出すぜっていうモチベーションにもなってたのかも知れないんだけども、なんかその最初の一歩みたいなものが先生と話しててちょっと見えたんですね。うん、じゃあ何やる?って言って、それが金曜日で、土曜日、いま日曜日の朝で、なんかね、こんな珈琲を淹れて飲みながら、じゃあその結節点を考えてみるかーなんて思いながら。せっかく久しぶりに涼しいから海でも行ってみようかなーと思ったら、天気が悪いからやめるかーなんて空を見ながら思いながらも。うん、その結節点をちょっと探ってみるか!っていう風に思考の日にしようかなーなんて思っていたので。まずはそんな思いをこのICUCで喋ってみるのもどうかなーなんて思いました。という意味では久しぶりに知的好奇心が向上してきた(笑) 自分みたいなものを知的好奇心向上委員会で…一応、委員長なのかなボクは(笑) そういう意味では一人でやってるので知的好奇心向上委員会の委員長として喋ってみるのは、知的好奇心向上宣言とでも言いますか。なんかそんなものかなーなんて思いました。はい。
戦隊モノと怖い映画
あとね、本当に色々話したいことあったんです。今日、戦隊モノ見て。日曜日の朝ってやってるじゃないですか、戦隊モノ。で、戦隊モノをパッと点けて見てたら、自分はちょうどゴレンジャー…だから戦隊モノの第一作目ってまさに世代なんですよね。幼稚園の年長組くらいだから一番ハマった時代で。そこから戦隊モノってぐーーっと、ずっと続いてるなーなんて思ってて。
ゴレンジャーなのでああそうかそうかと。で、色々思い出して。そしたらゴレンジャイって言うね、ダウンタウンの「ごっつええ感じ」フジテレビでやっていた…だからゴレンジャイっていうネタがあるんですよね。そのネタがあると思って…YouTubeにあるかなーと思ったらあったんですよ。で、あって、それ見てたらシリーズもので本当くだらなくて、ケラケラ笑いながらダウンタウンの二人と今田耕司さん、東野幸治さん、130Rの板尾さんとホンコンさん、あとYOUさんと篠原涼子さんが出てたりしてて。すっごい面白かったんだけど。
一方でね、今じゃ描けない様な差別用語、セクハラ用語、セクハラ行為、みたいなものがたくさんあって。うん、でもそれがあったから面白かったのは事実だなーなんて思いながらね。あー、表現というものってのが…今あれ、あのクオリティで地上波でやることは無理なんだろうなーと思うわけです。「お子様が見てるから駄目だよー!」って突っ込むためにお子様に見せちゃいけないものを見せるっていう、うん。それって百歩譲って大人の嗜みなんじゃないかなーなんて思ったり。その大人の嗜みが見せられないとしたら、あらゆるコンテンツは幼児化してしまうのではないかなーなんてことを思いながら見ててね。うん…そこって、でも今表現しちゃいけないことは事実なら表現しちゃ駄目なわけで。駄目って言うか駄目って言われるから表現しないというよりは、自分のプライドとして矜持としてしないっていうのってのはありかなーなんて思いますよね。
あと一方で映画の「OLD」っていうのを観てきたんですね。シャラマン監督ね、「シックスセンス」の。相変わらずな、またオリジナルな、独自な脚本でしたけど。すごい怖いわけですよ。そのビーチにいると何分で1歳年取るみたいな感じだから、もう夕暮れには死んでしまうくらいの歳の取り方をしてしまうという謎のビーチに囚われてしまった何人か…みたいな話なんですけど、それ以上は、ここまでは予告編で言ってるんで観る方は観て頂きたいと思いますけど。ボクはすごい怖かったです。すーんごい怖かった。なんかむしろ普通のホラーよりもよっぽど怖かったなーと思って。
うーん、と思うんだけど、ふと気づくわけです。それで「わぁ、そんな急いで歳取っていくの嫌だなー」って風に思うことが超怖いんだけど、パッと我に返ると…だってもう9月も半ばですねとか、8月も終わっちゃいましたねとか、今年ももうあと3分の1ですねとか4分の1ですねとか言ってるのって…同じことですよね?だからあのビーチで行われている時間感覚っていうものは実は今、現代の、現実の世界でも時間が過ぎて行くこととなんら変わらないじゃんと思った時に、ああ自分は死に向かってるんだなーなんてことに気づくと、あの作品の怖さみたいなものは実は現実の方が怖いじゃんって気付かされるって意味で、すごい…面白いというか興味がありますよね。
ってことも思いました。はい。で、さて。タイトルどうしようかな?と思った時に──だからゴレンジャイとOLDっていう風に書いてみてもいいけども。でも、なんか、拙さをどう表現するか?みたいなことかも知れないし。…うん。ああ、あとね。もう1個、巨匠っているんだっけ?この世界に…って話をしようと思ったんだけど、それはまた来週にしようと思います。
はい。そんな感じで知的好奇心向上委員会でございました。みなさままた来週よろしくお願いいたします。

文字起こし後の文字寝かし
(好き勝手に思った感想を書き残しておくことを文字寝かしと言うことにしました)
巨匠っているんでしたっけ?これ来週聞きたい。もし来週そんな気分じゃなかったら寿司特でもいい。聞きたい。
果たして知的好奇心の向上に繋がっているのか。私はやっぱり繋がっていると思う。そもそも毎回ちゃんと知的好奇心に繋がったか?よりも、知的好奇心への配慮があったことの方が大事、視聴者も角田さんも。それは知的好奇心向上という名前が付いてる以上、毎回自動的に「知的好奇心の向上」に思いを馳せているから心配ない。
角田さんは豊津徳でも言っていたプロセスこそが大事であり面白いところとするなら、角田さんの日々のぐにゅぐにゅぐるぐる思考こそ大事な見どころ、面白さということになる。実際それを目的に聞いてる人もいる。この人すごいなーと思ってたけど、こんなにぐるぐるしてるんだ?!と。知的好奇心って”知りたいと思うこと”だから、30分、──2倍速で観てるなら15分?ぃゃぃゃ角田さんのお喋りは二倍速は(文字起こしが早く出来るかとやってみたことあるけど)ツラい。ゆっくり映画の話をしてくれるコトブキさんでも1.5倍くらいが限界。これではサプリをコーラで飲んでるようなもの。まあ倍速だとしてもこの長さを視聴してるということは好奇心は働いている。それって角田さんの言う「効率が悪いものにどうコミットするか?」ってことなのかな。
ムサシの回の視聴数、本当だ…100回いってない。時々100回未満の回ってあるけど、なんなんだろう?毎回確実に観ている人がおおよそ100人で、その他の人は流動的みたいな?
noteは最近タイムラインの表示アルゴリズムが変わって、今まで見たこともない人の投稿がズラッと並ぶようになった。で、それはICUC文字起こしにも変化があって──ビジネス系というか、例えばアカウント名に最強サラリーマンとか月商1億とか書いてるような人のタイムラインに文字起こしが出ていると思われ、最初に♡を付けるのはそんな方々だったりする。正直心中は複雑なんだけども。YouTubeで表示される・されないはやっぱり多くの人が関心を示しやすいタイトルなら多くの人の目に入るんだろうか?
竜馬…龍馬??坂本龍馬記念館サイトに書いてあるものを読むと、龍は画数も多いし「りゅう」と読むので、良馬と書く人がいた。姪への手紙で本人が「りょうま」と書いているので龍馬で「りょうま」と読むことが分かる。龍馬が主人公の小説「汗血千里駒」で「りゅうま」と振り仮名を打ったので「りゅうま」と呼ぶこともある。龍の新字体が竜で、司馬遼太郎の「竜馬がゆく」で竜馬という表記が一般的に。小説の中の架空の”りょうま”だから竜馬にしたという話があるそう。
あくまで小説、架空の話。だから竜馬。これはなんかカッコいい。史実で作品のリアリティを支え、その上にドラマを展開させたんだろうな。読んでみようかな。
結節点の無限の拡張性。拡張の起点、最初の一歩みたいなものが先生と話しててちょっと見えた。──最初の一歩とは小説の話で出てきた0→1と同じだ。A×B×Cの話、最初に角田さんがSNSに書いたのは8月?7月?もう少し前だったか?確かにどこかで見た。最近のICUCは撮ったらすぐ出すと話してるけど、これはたぶん角田さんの想いの撮って出しVer.SNSだったんだ。つまりゼロ前、準備の7とか8くらいで、先生との話で9まで来たので次のステージに繰り上がり、いよいよ0から1を成す。
A、B、C、3つを接続したい想いはSNSで撮って出した通りで、AとB、AとC、BとC、2つ接続してるものは既にあるものを見たりして想像できていた。で、A、B、Cを一旦バラバラに捉え単体を見直すという作業が準備の7くらい?時期的には8月くらい?そんな感じだったんだろうか。考えて考えて倦怠感や喪失感しか持てなくなった時、この話を思い出そう。
角田さんはプロセスを見せた方がいい、プロセスを含めて作品となって面白いんだと言っているけど、じゃあ角田さんが見せてるプロセスとは具体的にどれ?ということをずっと思ってた。何と言うか、プロセスは見てるんだけど名前のない感情みたいで、これだと捉えきれてなかった感じがする。角田さんの「未だ何に成るか分からないぐにゅぐにゅの思考。ぐるぐるの想い。」これがプロセスだ。ただ「未だ何に成るか…?」だから、おそらく本人だって全部は分からない。成した後だったらこの部分がこの作品のプロセスだと言えるんだろうけど。これは何かいいものを見つけられた気分だ。
戦隊モノ。私が何となく覚えてる一番古いものはサンバルカン。これが黄色はカレー好きというキャラを確立したと聞いたことがある(Wikipediaにもそう載ってて驚いた)。次にOP曲の戦隊名の部分のメロディーだけ記憶にあるゴーグルファイブ。次にOP曲をもう少しだけ多めに覚えてるダイナマン。爆発!爆発!科学戦隊ダイナマン♪だ。それ以外は何も覚えてないけど。
サンバルカンは赤青黄で、後の2つはどちらも赤青黒黄桃の5人だったらしい。次のデンジマンは覚えがないけど、赤青緑白桃だったようで、覚えてはないものの、白と緑を見た記憶はここなのかも知れない。弟が持っていたが弟はまったく覚えていないらしいトレーラーが連結できる玩具、これはどの戦隊モノだったんだろう?
日曜の朝のシャイダーは何モノなんだ?検索してみると、これは宇宙刑事モノという括りだった。ギャバン、シャリバン、シャイダー、私が5歳~8歳の時の放送。先の戦隊モノと同じ時期だけど、どの刑事も違いは全然分からない。大人になってから見てみると…ストーリーの面白さとか分かるのかも(と思いはするものの、さあ見てみようかなとならないなー。)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
