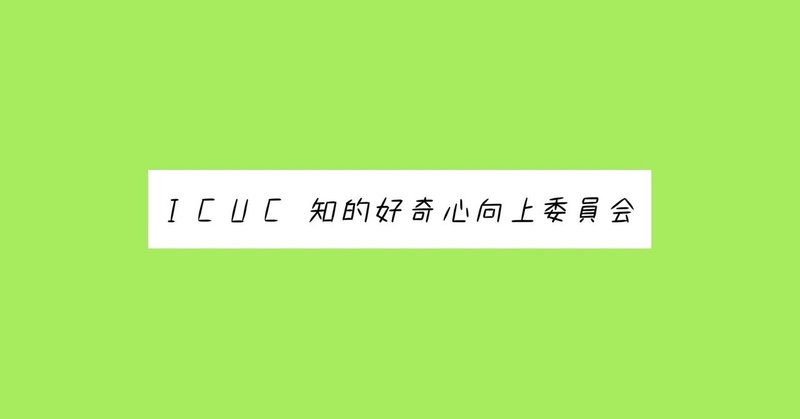
ICUC-090_2021.12.12【推理小説の話】
【ICUC知的好奇心向上委員会】の私の知的好奇心の向上&趣味の文字起こし。I see, You see ! Intellectual Curiosity Update Committee
今週の本
アンソニー・ホロヴィッツ
『カササギ殺人事件』
『ユウガオ殺人事件』
(創元推理文庫)
週末の深夜、普段はなかなか読めない傑作推理小説を夜通しかけて一気に読む。何度止めようと思っても続きが気になって止められない。朝方、薄明るくなる頃に謎解きが始まり、突然陽の光が射すとともに、犯人がはっきりと見えてくる。この読書の至福。
アンソニー・ホロヴィッツ 『カササギ殺人事件』 『ユウガオ殺人事件』(創元推理文庫)
動画の内容(+文字起こしメモ&感想)
数字減少現象と千日周期
どうもー。バラエティプロデューサー角田陽一郎でございますぅ〜。…なんか光がすごいな(ライトの位置を調整する)あ、これで大丈夫か。はい!ということとで、ICUC知的好奇心向上委員会を。なんか最近ライブでやっちゃおうかなーなんて思いながら。でも今日は土曜日ですけどね。土曜日にやるの初めてかなぁ?ライブでは。うん、なんか、今日はなんかやっちゃおうかなーなんて思ってやっちゃってます。(笑)やっちゃおうかなーと思ってやっちゃってるってのも変ですけどもね。はい。あの、音って聞こえてるのかな?まあいっか。
なんかね、最近ね、…最近でもないんだけど、ボク…人気ないです。うっふっふっふ!いや、人気ないというか元々ないんですけどね。元々ないんだけども、なんと言うかICUCとかも一時期より視聴数とかが減ってるわけですよ。それってなんかコトブキツカサとね、寿司特ってのをやってるしとか、あとは何だ?Twitterとか、インスタとか、なんかね、分かるんですね。なんとなく、こう、数字がね、減ってるのが。
で、それってなかなか──いや、あの、そもそもそんなに多くないから、そのことを気にしてると言うより、気にしてないと言うと嘘になりますけど、「あ、なるほどなー」って思えたりするわけです。それってすごい自分のことは棚に上げて人のことを言うとすると、なんか数年前とかって結構メディアに出てた人なのに「あれ?なんか急に出なくなっちゃったなー」みたいな風に思う人っていませんか?なんかね。そういう様な人ってこちらから見ると…こちらってどっち側だ?だからその…当事者じゃない方から見ると、「あぁ、なんかあの人って居たけど、最近居ないねぇ」みたいな。「何やってるんだろうねぇ?」みたいな感じの人っているじゃないですか。で、ボクもそういうことを感じる人って色々いるわけですよ。
なんだけど、そういう人って時々ソーシャルメディアとかで見てると「ああ、なんだ。全然違うことでご活躍されてるんだね。」みたいな人ってのも結構いるんですよね、うん。つまり情報にアクセスしてるか?してないか?ってのは、その人自体が情報を公開してるか?してないか?ってことと、一方でその情報を受け入れてる方が見てるか?見てないか?と言うかね、そういう様な差ってあると思うんですよ。で、それって一つはそういう感じで何かパッと世に出るとそれがずーっと続くのか?あるいは続かないのか?みたいな事ってのもあるんだろうなーとか思うわけです。で、その時に…何て言うんだろうな、一般的にその人がちょっとこう話題になって、その話題って何年持つか?みたいな話って、何にもないと何となく1000日って言われてるみたいな話ってボク前もしたと思うんですけど。──確かあれなんだよな、(アイドルグループの)SPEEDってちょうど1000日だったんですよね。だから1000日って…2年と9ヶ月で1000日なんですよ。そう、だからなんか会社とかサービスとかそういうものも何となく1000日続くと次の1000日があるみたいな事とかは言われてて。それって実際ボクがgoomoって会社を2009年に立ち上げるんですけど、やっぱりね、1000日ぐらいで終わりましたね。4月に立ち上げて1年経って2年経って、ちょうど1月くらいで1000日だったんですよ。そこで最後の1月2月3月みたいなのが行ければ3年になるんだけど、大体その前に4月までに打ち切り決定みたいなねことってよくあるんですよね。番組とかもそうなんですけど。うん、まぁみたいな事とかあるじゃないですか。と思った時に、その人が新しい事を初めてそれが…メディアでって言うか、社会でと言うか。なんか新しいことをやってるよねーっていうのが耳目に乗ってるのって1000日くらいなんじゃないかなって思うんですよね。
で、そう考えるとボクは2017年にTBSを辞めて。厳密に言うと2016年の12月31日に辞めて、2017年からフリーで活動してるんですけど。2017、2018、で2019年の…えぇーと、いつぐらい?ぅん?2017年、2018年、で2019年のちょうど秋ぐらいに1000日を超えたなーなんて思ってて。で、そこから経ってると今度は…2019年でしょ…2020年、2021年って考えると、間もなく2000日目になるんですよね。うん、間も無くと言うか…ちょうどボクは大体1000日って2年と…何ヶ月?ぅふふん(^^;)…えぇっと、2年とぉ〜…9ヶ月、とかだとすると、倍だから4年と(笑)5年と6ヶ月。5年半くらいでちょうど2000日って考えると、次の2ターム目なんだよなーなんて思うわけです。うん。
LIFE GOES ON 千日
そうするとちょうど5年半ぐらい経ってるって感じになると、あと…だから…この半年くらいでちょうどボクは次の1000日目なんだと思うんですよね。そうすると2017年からの1回目の1000日目は乗り切ったんだけど「あ、2回目の1000日ってなんか乗り切れない様な気がする」って言うか。その乗り切れないってのは別にネガティブに言ってるわけじゃなくて。バラエティプロデューサーみたいな肩書きで何かをする時に、それの新規性とかね、それで例えばこのICUCもそうだし、動画をやってみますとか、あるいはなんかプロデュース塾をやってみますとか、そういうのってのが「ああ、あの人またやってるのね」とか。つまり新しく見えない。良くも悪くもですよ、新しく見えればいいってことでもないんだけど。みたいなことを最近感じるんですよね。だからなんかこうバズってもいないんだけど、バズらないまま新規制が無くなっていくっていう感じって…それがダメって言ってるとか、悪いとか良いとかじゃなくて、そういうものなんだよなーなんて思ったりするわけです。
一方で、そんな事とか全然気にせず、LIFE GOES ON と言うか。人生ってのは続いていくわけですよね。だったらそんな事を気にせずどう生きていくのか?ってことだけ考えてれば別に良いんだと思うんですね、それぞれが。で、そんな中でじゃあボクは次の3000日目なんだっていう、この3000日目を何をやって行くのか?ってことを考えた方がいいんだろうなーなんてことを思った時に、最近の数字が伸びない感じって、ああ、なんか、そうそうそう、2000日目の耐久年数が終わってきてるんだろうなーなんてことを何となく感じますね。
でもそれって何回も言ってますけど、別に悪い事と言うより、自分の生き方を変えればいいんだろうなーなんてのも思ったりするわけです。で、そんな中でね、その自分がね、一緒にTBSを辞めて一緒に仕事している人とかもいるんだけど。その人とね、この前お茶してて。で、最近の仕事の分析とかもしつつね。お茶しててって言うのもあれなんですけど、つまり──前はね、しょっちゅう会ってたんだけど今はリモートだから、リモートでは会議はなんだかんだ言って週1、週2くらいではやってるんだけど。色んな案件をその人と。面と向かって会うのってね、なんか領収書を渡すとかね、判子をもらうとか、そういう時が多いじゃないですか。で、たまたま会ったんで、自分がね、今こんなことやろうとしてて、こんないい事があり、こんな悪い事もあり…みたいなこととかも話してると、一緒にやってるパートナーの人がね、「角ちゃん、あれだよね。」って。「もっとブレイクしてもいいよね。」みたいな(笑) つまり、見れば面白いし、話してることとかもその辺の話してる事より面白かったりもするかも知れないんだけど、なんかいまいちブレイクしてないよねみたいな事を、むしろパートナーだからね、冷静に言われたわけですよ。「ああー、そうかぁ。ブレイクしてないんだ。」みたいな。
で、またこれ、ブレイクしてないって言うとまた話がややこしいんだけど。ブレイクしたいのか問題ってのもあるからねっていうのがあるんだけど、うん。ボクとしては別に自分が食っていけるレベルでブレイクしてる、あるいはしてないでいいので、別にそれはそれで、つまりいいなと思ってやって来たんだけど。それもじゃあ自分が作ったコンテンツ、それが番組でもいいし、書き物でもいいんですけど、そういうものが全然見られなくていいのか?って言うと、やっぱり見られないよりは見られる方がいいし。このYouTubeだって、それこそコトブキツカサとやってるやつとか、山本豊津さんとやってるやつとか、加藤昌治くんとやってるやつとかだってね、それは当然見られた方がいいわけですよ。でもそうすると見られるように作るのか?みたいなことを考えると、前も言ってますけど、こんな感じの30分だらだらと喋ってるのって、まあ奇特な人しか(笑)見てないですよねぇって、奇特な方って今見てる方に言ってる様で、すごいすまない様な気もちょっとだけするんですけども。うん、でも、まあ、これはアーカイブだからそれでもいいよなーなんてのも思ってるわけです、うん。
一方でね、小説『AP』は書きましたけど、あれは本当にドラマ化したいよなーなんて思ってるし。今日もね、今日は比較的ここにずーっと閉じ篭ってたものですから、今もう1個書こうと思ってる小説が、発注が来てるやつがあるんですけど、それがね…今年の夏までに書くって言ったのに、もう冬来ちゃったんですよね…うふふ。それがまだ書いてなくて。で、それも今日、やっと、そのフォルダを作りましたね。これ…こんなこと言ったら編集者さんに怒られちゃうなぁ…パソコンの中に、うん。これから原稿を溜めていこうと、やっとその段階まで来たと言うか。いやでも来たと言ってもね、すごい迷ってますね。この迷ってる時って面白いですよね。自分は文章を書けるのか?書けないのか?みたいな。うん、なんかそんな事を思ったりもしますよね。
で、そんな中ね。昨日とかはここに篭ってたんですけど。篭ってたけど実は2時間…3時間、4時間…5、6時間ぐらいオンラインミーティングとかやってたから、全然篭ってた感じじゃなかったんだけど、そんな中でね、書き物もしなきゃなーなんて思いながら、なんだかなーと思ってたんで、今日は読書の時間にしちゃうかと思って、昨日の夜、読書をしたわけですよ。それが、こう、推理小説だったんですけど。なので今日は…持てるかな?じゃーん!この話をしようかなーと思っております、と。
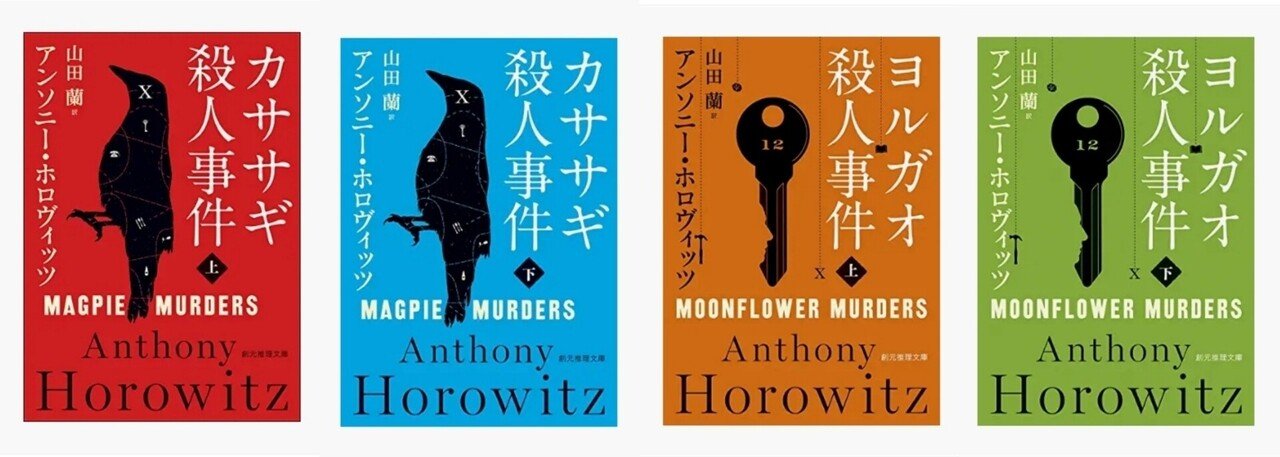
止められないミステリー
ね、これ。本っ当に…。アンソニー・ホロヴィッツのですね、最初の方はこっちですね、「カササギ殺人事件」ね。これすッッごい面白いんですよねぇ。で、今年の秋にその第2弾というか続編、続編と言っても全然繋がってないんですけど、繋がってるんだけど事件自体は繋がってないという「ヨルガオ殺人事件」があって。今この上下巻なんですけど、まぁ、まあまあ、これくらいの厚さがありますよね。これぐらいの厚さがあるんですけど、あのー、まあ、あれですよ、まあ…面白かった(^^)!!うっふっふっふ!これまたミステリーの話ってなかなかするの難しいと言えば難しいですよね。で、だから本当に読んでる場合じゃないんだよなーとか思いながらもちょっと…。これ(「ヨルガオ殺人事件」)は数日前に読み始めて。カササギを見たのはちょうど2年前ぐらいだったのかな?で、だからちょうど2年後って設定なんですけどね。で、ヨルガオ見てたら、なんか面白くて止められなくなくて。で、昨日の夜、下巻に突入したんですけど。そしたらずーーっとずーーーっと読んでて、もうね、これ、ずーっと読んでたら朝になっちゃうじゃないですか。で、朝になっちゃったらその日の朝、眠くなっちゃうからその日が1日ボロボロになっちゃうから、どうしようかなーとか思ってたんだけどね、オモロくて止められないんですよね。オモロくてと言うか続きが気になっちゃってね。また良くできてるんですよ。それで本当にね、基本ボク本は寝ながら読んでるんで。寝ながらこうずーっと読んでて、で、もうこの辺まで来て、朝5時だ?!みたいな。6時だ?!みたくなって。あぁぁ、犯人が?!あぁ、犯人が!犯人がぁぁ!!って言ってたら、もう…ちょうど薄暗い中で夜中読んでるわけだから、薄暗いじゃないですか。…今日なんか目が眠そうだな。本当にずっと読んでたからだと思うんですけど。そしたら、もう、犯人が分かった瞬間になんか太陽がちょうどパーッと出て来たんですよ。なんかそれがすごくてね。ああ、なんかだから夜通し、やっぱり気になって気になって止められないっていう読書体験ってのはすごくいいもんなんだよなーなんて、改めて思いました。
うん。でね。ボクはミステリー小説をすごい読んでる人よりは全然読んでないですよね。マニアじゃないですね。ただやっぱり基本は大好きですね。アガサ・クリスティーのポワロシリーズは全部読みましたね。ポワロシリーズって何個あるんだっけ?30個、40個ぐらいあるんだけど全部読んでて。「スタイルズ荘の怪事件」からね、ずーっと順番に読んでいって、最後が「カーテン」ってやつなんですよね。ボク最後の「カーテン」って言うのって、たぶんカーテン・コール、カーテンが閉じるって意味のタイトルで「カーテン」ってのがポワロシリーズで一番最後なんですけど。それ読むとね、ポワロともう別れるの嫌だなーなんて思って、最後にそれだけ読まないでずーっと20代の時読まないでいたんですけど。ちょうどね、20代の終わりぐらいにね、フィジーに行ったことがあって、休みで。フィジーに行ってもプールサイドに「カーテン」持って行って、その海のところのプールサイドで「カーテン」を最後に読んで、ポワロを終わりにしようって決めた、20代最後にポワロと別れようと思って読んだみたいなところありますね。
でね。この「ヨルガオ殺人事件」、ここにかいてありますけど。「アガサ・クリスティへの完璧なオマージュ イギリスのホテルで起きた殺人 謎解きが二度も味わえる、至高の犯人当てミステリ!」ってかいてありますけど。いや、もうねぇ、本当に。だからその、アガサ・クリスティとかが好きな…なんて言うんですかねぇ、人にはねぇ、もうこれは止められない。良くできてるわけですよ。また…すごいですね、良く出来てる以上…言っちゃうとね、ネタバラシになっちゃうから言いたくないみたいなところがあるんですけどね、うん。
日本の推理小説とボクの夢
一方でボクね、日本のミステリーってそんなに読めないんだよなぁ。嫌いじゃないですよ、全然。ドラマとかだと「古畑任三郎」とかやっぱり好きでしたけどね。だけど…なんかね、やっぱり、なんて言うんでしょうね、宮部みゆきさんとかもすっごい良く出来てるじゃないですか。だけどやっぱり怖いんですよね、リアルで。うん。ところがアガサ・クリスティとかね、このアンソニー・ホロヴィッツとかって、イリギスのとある村で、洋館で、人が死ぬとかね。全然リアリティないじゃないですか。まあ、つまり自分の人生とかけ離れてるから。だから本当に作り物として読めるっていうものの面白さ。最後にはね、関係者が集まって来て、それに一人づつ容疑を晴らして行って「犯人はあなたです」って言う感じとかね。すごいいいじゃないですか。
ボクは「さんま・玉緒の夢かなえたろかSP」っていうのをね、「あんたの夢をかなえたろかSP」ってTBSでやってますけど、あれをずーっと20代の時から30代の半ばぐらいまで演出、ディレクターやってたんですけど。あれっていつも…ちょうど今の時期、あれは1月オンエアだから12月の時はね、夢を叶えまくるわけですよ。で、該当インタビューをしてね、夢がある人をインタビューして、あなたの夢はなんですか?って聞いて、夢を叶えるんですけど。その会議をやってると時にスタッフとどんな夢がいいんだろうね?と言って、もうスタッフみんな、2〜30人いたんですけどね、その会議に、すごい深夜にやってるんですよ、それぞれ叶えてほしい夢を言ってってみようか、みたいな(笑) 今でも覚えてるんですけど、ある時あったんですよね。ボクはまだ総合演出じゃなかったかな?総合演出の人間が一人づつ言ってってみようぜって。どんな面白い夢が僕らから出てくるかなー?みたいな事があって。誰々君がこんな夢がいいです、こんな夢がいいですって言って。で、ボクの番に来て「角田は?」って言われたんで「ボクは探偵になって、孤独な閉ざされた洋館で殺人事件が起きて、そこに泊まってなきゃいけなくて、容疑者が7人いたりして。その7人の中で、最後に集めて「犯人は、あなたです!」って言うのをやってみたい。」って言ったことがありますね、夢で。うん。
…ああ、日本のやつ苦手だって言ってたけど、「金田一耕助」ボク全部読みましたね。それはちょうどね、25歳くらいの時ですね。ADやってて2年目の時にADが辛くてね、もう辞めてやろうと思ってね、嘘の診断書書いてもらって、TBSを3ヶ月ぐらいサボって休んでたんですよ。もう辞めようかなーなんて思って。その時に「金田一耕助」シリーズ、「悪霊島」とか「獄門島」とか「病院坂の首縊りの家」とか「悪魔の手毬唄」とか、あれも全部読んだなー、うん。
いつかはね、ミステリーみたいなの書いてみたいなーと思うけど、ミステリーは書けないだろうなー。緻密さが必要じゃないですか。あの緻密さって本当にね、それこそボクは論文を書いてて、小説も書かなきゃなーなんて思ってるんだけど、緻密さ…難しいんですよね。うん、緻密さ難しいんですよねって馬鹿っぽいけど、言い方が。緻密さ難しいんですよ。それをどう担保するか?みたいな。なんかね…映像やってるからかも知れないですね、自分は。映像ってカメラで撮ってるだけで、そこに画面に色んな情報が入ってくるから、ある意味、緻密さって自動的に出てくるんですよね。だから映像の情報量をあとでナレーション、編集で、どうカットして、ナレーションでどう組み立てて行くか?みたいなことだとは思うんですけど。パソコンに向かってね、文章を書いてると文章しかないから、その文章に緻密さを与えるのって自分しかいないんですよね。だから映像とかって外にあるものを撮るっていうのがあるけど、文章ってね、本当に自分でこうカチャカチャ打ちながら緻密さを出さなきゃいけないとなるとね、その緻密さが出てくるのって、やっぱ自分の脳内からじゃないですか。そうすると自分が緻密じゃないんだなってことがすごく分かると言うか。でもこれは、まあ、一概にミステリー、推理小説だけじゃなくて、あらゆるジャンルの文章もそうだとは思うんですけどね。うん。
で、それがね、この、本当に、アンソニー・ホロヴィッツ…またアンソニー・ホロヴィッツさんって、なんかあれらしいですよ?三谷幸喜さん的な感じですよね、なんか話を聞くと。
イギリスを代表する作家。ヤングアダルト作品〈女王陛下の少年スパイ!アレックス〉シリーズがベストセラーに。また、人気テレビドラマ『刑事フォイル』の脚本、コナン・ドイル財団公認のシャーロック・ホームズ・シリーズの新作長編『シャーロック・ホームズ 絹の家』などを手掛ける。アガサ・クリスティへのオマージュ作『カササギ殺人事件』では『このミステリーがすごい!』『本屋大賞〈翻訳小説部門〉』の1位に選ばれるなど、史上初の7冠に輝く。さらにホーソーン&ホロヴィッツ・シリーズ『メインテーマは殺人』『その裁きは死』でもすべてのランキングで1位に選ばれ、3年連続で年末ミステリランキングの完全制覇を達成した。
そうそう。だからなんかそういう本当に色んなジャンルのことを、007のパスティーシュなんかもやってるって書いてありましたけど。なんかね…良く出来てます。自分が映像だからですかねって言ったのが恥ずかしいというか、だって脚本とか書かれてる方ですもんね。つまりどれだけパズルを埋めていくのか?いかないのか?どれだけ説明するのか?みたいなことが、その勘所みたいなところがすごい分かってる方なんでしょうね。で、分かってて、現代の話なのに1950年代とかね、戦前、40年代ぐらいのアガサ・クリスティっぽさが…1930年代とかか…出てくるんですよねー。すごいなぁ、本当に。いやいや、もう(画面に本を)見せてるだけですけど。だからなんなんだってわけじゃないけど、うん。
昭和歌謡と海外推理小説
だからね、今日のICUCはいつにも増してそんなに中身が無いので。中身が無いというか中身はあるんですよ?あるんですけど、いつにも増して散乱してるから、あれですかね?また視聴数は行かないでしょうね…んっふっふっふ。ちょっとあの、コメント頂いてるんで読むと。「外国というリアリティの薄さって、寿司特で仰ってた昭和歌謡の歌詞の良さと同じですね〜」ああー、そうかそうか、なるほどね。そうそう、寿司特ってコトブキツカサの番組で言ってたんですけど、今、現代の曲ってみんなシンガーソングライターでしょう?だから昔の昭和歌謡ってさ、この前四国まで自分の車で運転して行ったから、運転中Spotifyで結構聞いてたんですよ、昭和歌謡。あの…すさまじくいい曲多いですね。ストーリー性があると言うか。それって例えばですよ、中森明菜さんが歌った「北ウイング」って歌って、別に──♪「Love Is The Mystery」 でしたっけ?♪「わたしを呼ーぶの〜」って、わたしを呼ぶのの”わたし”って中森明菜さんじゃないですもんね。ところがヨアソビとかね、あいみょんとかの歌って、なんか自分達のことじゃないですか。その差ってリアリティの無さが有るからこそのストーリー性の担保みたいなものとか、普遍性って出るんだよなーって話をしてて。一方で、今の曲が全然悪いって言ってるわけじゃなくて、いい曲すぎるってボクは表現してるんですけどね。なんかこう、みんなメロディもいいし、想いもすごい…想いというか詩。でもなんかこう「銀座の恋の物語」的なね、なんか軽さみたいな。野口五郎さんの「19:00の街」とかね、大橋純子さんの「シルエット・ロマンス」とかね、高橋真梨子さんの「桃色吐息」とかね、なんかね、いいんですよね、聞いてると。あのリアリティの無さみたいなものってリアリティがないからそのストーリーに入れるってあると思うんですよね。これが全く…この本も全く一緒ですね。つまりストーリーの無さ…無さじゃない、リアリティの無さ。いや本当はあるのかも知れないんだけど、ボクはイギリス人じゃないからイギリスのリアリティが分からない感じ。そのウキウキ感、楽しさみたいなのってあるよなーなんて思いますね。うん。
いやぁぁ、でもなんかすいません、本当に目が眠そうなのは、単純に本当にもう、朝もう、徹夜で見ちゃったからいけないですね、うん。読んじゃったからですね。徹夜で読んで、うん、でも、久しぶりにそれやって楽しかったなぁ!今年それやったのあれですね、ミステリー小説で言うとそれでしょ?あ、でもこの前の亀山郁夫さんの、先週言ってた「ドストエフスキーとの59の旅」も1日で読んじゃったけど。でもあれは夜通しじゃなかったな、うん。あと夏に読んだ「三体」ね。「三体」も夜通し読んじゃったな。だから今年読んだのが「三体」と「ヨルガオ殺人事件」ですね。うん…でもなんかね、そう考えると、ボクTwitterに書いたんですけどね。Twitterというか文章にね。じゃあ最後にそれを読んで終わりにしようかなーと思うんですけど。結局ね、今レコメンがないと読めないとか読めるみたいな話とかってよくあって。レコメンされると売れる・売れないみたいなのがあったりして。で、なんかね、今自分が思ってることを書くとすると。
観たい作品がある。
読みたい本がある。
その中で、どれを観るか?何を読むか?若い頃は話題になってるのを観てたし、読んでたかな。
つまりそれは、無意識に自分よりも、他者を、社会を気にしてたんだと思う。
今は、自分の人生が欲してる作品を観るし、読もうと思う。
どうせ全てにアクセスできるわけないのだから。
そういう意味で言うと、ある作品への他人のオススメや世間の評判を気にしなくなった。
自分がその作品を知った瞬間の自分のインスピレーションで、観る作品や読む本を、自分が選ぶ至福。
その作品に出会うためにいろんな情報には触れるけど、その中での他人の感想には興味も無いし、あまり意味も無い。
さらに言えば、自分が見たり読んだりした作品への他者の感想を後から知ることで、その他者の嗜好や思考や志向が見えてはくる。
そこに感動したのか?
そこに興味があるのか?
そこは理解しないのか?
でもそんな他者の感想は、その作品自体や、それを自分が経験する至福の価値以上のものではないのだ。
その作品と自分が自分で出会うこと自体が、自分の人生の至福の瞬間なんだと思う。
その至福の瞬間を他人に奪われるのは、至極もったいない。
っていうね、文章を書いたんだけど。そう、だからね、このボクのICUCでお薦めしてるから読むとかじゃなくて。お薦めしてるか?してないか?じゃなくて、やっぱりこういうのを見て、見た時に「あ!これはちょっと…」別にいいんですよ、これ4つあって(カササギ上下巻とヨルガオ上下巻)、ジャケ買いとか、綺麗だなー、だから見ようかなーとか、そんな自分のインスピレーションでね。でも別に…でも自分は読まないなって思うなら読まないでもいいと言うか。そういう様な自分の中でのインスピレーションで物事に触れていくというか、出会う。その出会うっていうのを他人のレコメンでやっちゃうと、その出会うということの一番の良さがなくなっちゃうのが勿体ないなーって思ったっていうことを思いました。はい。そんな感じで知的好奇心向上委員会でございました。また来週よろしくお願いいたします。

文字起こし後の文字寝かし
(好き勝手に思った感想を書き残しておくことを文字寝かしと言うことにしました)
数字減少。数字数字言わない!と言いつつ自分が生きていけるだけの数字は持っておくというのが角田流フリーランスの極意(?)。どなただったっか忘れたけど、TBS辞めるならSNSの数字を持っておいた方がいいと助言頂いたのでそうしてると記憶している。その理論を角田さんが回し続けた結果が思はぬ展開を見せている、とか?例えばフリーランス方程式があって、nにフリーランスで生きる人を代入していったとき、角田陽一郎を代入すると「あれ?」と。じゃあ角田さん死んだの?というと、逆に36個も仕事回して元気じゃねぇか!みたいな。
SNSから仕事に繋がること、特に著書やイベント開催ではSNSの数字がある方がいいと聞いたけど、今ある36個の仕事のうちSNSあってこそな仕事の割合って1000日周期の1ターム目と2ターム目で違ったりするんだろうか?最近は「SNSで知りました」より「〇〇社の社長さんから聞きました。うちのプロデュースもお願いします!」みたいな。いやでも、やっぱり私にはSNSは販促、量を売る部分に必要なのは変わらないよな…としか想像できない。どうなんだろうか。
私が「仕事が軌道に乗る」という言い方を意識したのは「魔女の宅急便」だったな。当然だけど軌道から外れることもある。今いる軌道より1つ隣の軌道がベター、2つ隣の軌道がベストとか、つまり軌道に乗せる努力と、維持する努力と、乗せ続ける努力はちょっとづつ違う。
2017年1月1日を1日目として、1000日目は2019年9月27日。2000日目は2022年6月23日。あ!っと思ったけど…惜しい。2019年9月27日(金)じゃなくて、29日(日)がICUCの初回だった。先週は「そうだ、目に付くところに書いて貼っておこう!」と収入が安定したらギターを習いにいく(父のギターが弾けないから)、それが出来たらピアノを買う(才能があると言われたのにやめた後悔)と書いて貼ったけど、何かしらの1000日目も書いて貼った。次をどうしようと思っていればそのことを、特になければそこまでの1000日を振り返る目安に使おうと思う。
ブレイクした角田さん…を、想像出来なかった。今だって遠いのに更にさらに遠くなるから嫌だという気持ちもふんだんに盛り込まれてるとは思うものの、角田さんらしさという点で、表舞台で誰もが知ってる有名人という感じがなんとなく似合わない気がどうしてもする。パートナーさんの仰るブレイクとはどんな状態を指していたんだろうか?私の思うブレイクとは違う気もする。
奇特な方。そう言われるのは嬉しい事だと思うのは、私が角田ストーカーだという自覚の上にだけ成り立つんだろうか?”変な人”も褒め言葉だと思ってるからどうにも分からん。
リアリティがあるから怖くて読めない。日本歌謡の話を聞いたのは「寿司特」じゃなくて「あんちょこお悩み相談会」だった…いや、両方で言ってたか?
子供の頃は近所の自衛隊の基地へ降りる飛行機の音が大きく、「はだしのゲン」と「火垂るの墓」の影響だろうけど、空襲を連想し、私の前世は戦争で死んだ人だと思ってたほど。現在は空軍の飛行ルート近辺、機種が違うことあるかもだけど音にはすっかり慣れた。音というリアリティ。戦闘機(現在、主に米軍)より輸送機(昔、主に自衛隊)の音の方が怖いという、リアル内で起こる誤差。
今でも日本軍が出る映画は見てみようと思えない。硫黄島とかゼロとか。外国というリアリティの無さから「プライベート・ライアン」なんかは妹が初っ端で嘔吐しそうで離脱したと聞いてたけど観れた(でも「プライベートライアン」「ブラックホーク・ダウン」「ミスト」はもう観ないリストに入れた。)
逆に、昔は怖かったけど今は読んでみたい本があった。「三びきのやぎのがらがらどん」、おそらく話より絵が怖かったんだろうけど、今見るとかなり好みの絵だった。内容は明後日辺りに確認できる。
先週の話題「ドストエフスキーとの59の旅」はピンと来て読んだらプロローグでノックアウト。面白い。平たく言えば亀山さんの思い出話なんだけど、それでなんで面白いんだろう?全然分からないけど面白い。それから角田さんが画面に出していた安岡治子(翻訳)「白夜/おかしな人間の夢」。この絵が嫌だから買いづらいという方もいるようだけど、私は光文社古典新訳文庫の表紙だけ並べて眺めたい。急に「そうか!画集を買えばいい!」と思い、望月通陽さんの画集を探した。買ってみた「せんはうたう」は最高だった。点・線・面の線だけが持つ自由と可能性をうたってた。他にもいくつかあるようなので買い足して行こう。去年「つつんで、ひらいて」という映画を観たけど、本の装丁はアートというか収集というかで結構見逃せない。
自分のことを歌うシンガーソングライターと、リアリティの無さで普遍性を担保する昭和歌謡。確かに!と思うと同時に「ドストエフスキーとの59の旅」や「生物と無生物の間」の面白さはリアリティとは違うのか?でもリアリティだとすると矛盾する気がする。でもどこがどう矛盾してると上手く説明できない。想いの発し方、飛ばし方の違いだろうか?
リアリティがないからそのストーリーに入ることができる。リアリティのあるストーリーには寄り添うことは出来るけど、同調することが出来ないかも。同調というのは、自分が主人公に成り代わるのではなくて、世界観の内に入るとか浸れる、体感できるという感じ。
緻密さは自分の脳から出て文章に。これは”ボクは学者に向いてない”と同じところに行き着くだろうか?思考することは楽しい、リアルな移動も材料としてはある、だけど創作そのものは一点集中で深〜く深〜く。
YouTubeでアインシュタインが思考実験だけで理論を構築したとか、「ラプラスの悪魔」「メアリーの部屋」の話を見た。アインシュタインの一般相対性理論は日食で実験出来たことで証明されたけど、思考実験の方はその名の通り思考のみ。この思考実験にストーリー要素を足すと推理小説が出来たりしないんだろうか?角田さんは思考は楽しいと仰ってたし、小説も書いたから、あとは思考で実験をするようになったら、ミステリーが書けちゃったりしないもんだろうか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
