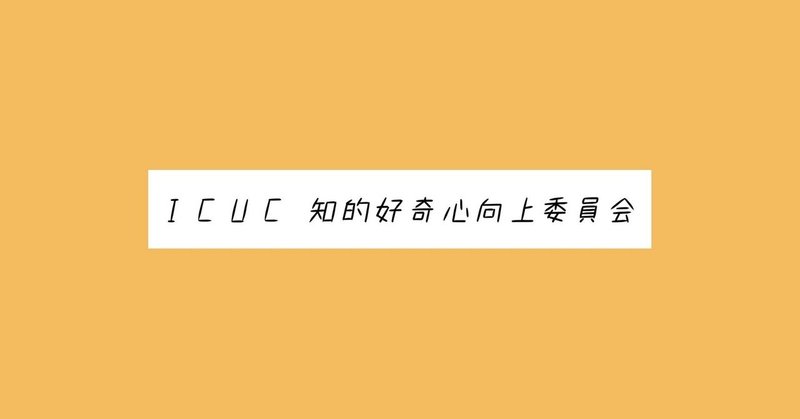
ICUC-118_2022.7.17【この世界を、果たして自分が(自分なら)どう解釈interpretするか?】ICUC知的好奇心向上委員会
【ICUC知的好奇心向上委員会】の私の知的好奇心の向上&趣味の文字起こし。I see, You see ! Intellectual Curiosity Update Committee !
角田陽一郎118「この世界を、果たして自分が(自分なら)どう解釈interpretするか?」ICUC知的好奇心向上委員会
自分を求めてくれる人や組織や社会があるということは、なによりも幸せなことなのかもしれない。
自分が求めている人や組織や社会があることよりも、実は何倍も。
求めるのではなく、求められること。それを他者に要求するのでもなく、自我の欲望に執着するのでもなく。自分の使命をただ果たすこと。
動画の内容(+文字起こしメモ&感想)
海が気持ちよくて
おはようございまーす。ICUC知的好奇心向上委員会でございます。えー、私いま海に来ております。はい。えーと、本当はね、海で収録しようなんて思ってもいなかったんだけど、今なんか気持ちいいから撮っちゃおうかなーなんて思って単純に動画を撮ってます。なので、ちょっと、撮影の棒も持ってきてないから、結構手が入っちゃったりしたらごめんなさいって感じなんですけど。…これちゃんと撮れてるのかな?これアレなんですよね。30分話したのに撮れてなかったら悲しいなーなんて思いながら。でもやってみようかなーなんて思いました。ああ、こっちの光にするとちょうどいい感じになりますね。
えーと、今ですね、海に来て。なんか、気持ちいいですね。なんかこう足で…やっておりますが。今、足見えたかな?自分の出てるお腹だけが見えた気もしますが。なんか、ずーっとね、昼ぐらいまで雨降ってたんですけど、雨が止んだみたいなので。で、陽が出てきたからちょっと海に来てみようかなーなんて思って来ております。
あのー、なんだ、こう言う感じでずーっと海にいると。ずーっと海にいるとって言うか、海の中に入ってると、あれですね、何話していいかとかがよく分かんなくなりますね。んふふふふ。うん。そんなこと、話すってやっぱりいちいち色々考えるところだから。なんか考えるってことがなんか…、う~ん、なんて言うんだろう?考えなくても考えてるというか。う~んと…つまり論理的に考えるということじゃなく考えてるというか。なんかそういうのが…なんとなく、こう…散歩しながらだと…そういう気分なのかなーなんて思っております、はい。
どこから話そうかなぁ。今日はね、自分の気持ち的なことの変化みたいなことで、ずーっと先々週から第二章って言ってたらね、なんかこう自分の想いというものをもうちょっと…自分勝手にではなく、何て言うか、他者の為に自分の想いというものを…使うっていうとアレだな。自分の思いというのを表出してみようなんてことを先週言ったと思うんですけども。そんな中でね、感じた事を喋ってみたらいいかなーなんて思っております。
松井守男さんを知る
あのー、なんだ、なんかね。先週もまたちょっと色々自分の中で思ったことがあるなーと思ったのは。うん、あの、松井守男さんっていう方ね、僕ね、知らなかったんですよね。フランスのコルシカ島に住んでいる日本人のアーティストなんですけど。先月亡くなっちゃったんですよね。で、先月亡くなっちゃったんで、追悼ということで教育テレビの日曜美術館で再放送してたんですけど。たまたま観たんですよ。そしたらえらく感動してしまってね。うん。で、その松井さんって光の画家と言われてるんですけども。若い頃パリに留学で行くも、なんとなくいじめにあったりして。なかなか上手く行かなかった時にピカソに、晩年のピカソに出会うんですね。で、晩年のピカソと最後の数年ぐらいは結構一緒に過ごしたという方で。で、その中から色んな想いみたいなことを貰うと。
なんだけど、ピカソってのはね、30代半ばでキュビズムっていうのを生んで、一役スターになるんだけど。松井さんって方はね、全然やっぱり鳴かず飛ばずで。すごい才能あるのに…と思って、もう40ぐらいの時かな?もう遺言っていう作品を作るんですよ。もう、これ描いたら死んでもいいや!ぐらいの気持ちで。で、その遺言っていう作品をパリで、すごい大きいキャンバスなんですけど、面相筆っていう一番細い筆で、それでもう2年ぐらいかけてちまちま、ちまちま、ちまちま、描き続けるんです。それで描き続けたらね、出来上がった作品、それが世の中で認められて、彼はそこから大活躍していって。
で、フランスにずーっと居るんだけど、日本の国籍を失わないままね、フランスでずーっと活躍して。で、55歳の時って言ってたかな?だから今から20何年前だと思うんですけど。コルシカ島に居を構えてね。コルシカ島ってナポレオンが生まれた地中海の島だと思うんですけど、その光がすごい綺麗で。その光を感じるアトリエで創作活動をしながらアーティストをやっているという方だったんですけど。まあ、ドキュメンタリーはね、その方がコロナでコルシカに帰れないから瀬戸内海の島でインスタレーションというかをやったり、神社の襖に絵を描くみたいなことをやられてたんですけど。まあ、めちゃくちゃ、素晴らしい。うん、そのドキュメンタリーも素晴らしく面白かったし、その松井さんていう方がね、描きながらですね、ぶつぶつ言うんですよ。「さあ来たぞ」「降りてくるぞ」「降りてきたぞ」「いいぞ」「来たぞ来たぞ」って。そうするとね、光で描いて、ずーっと線を描いてるんだけど、そこに龍が表れたり、そのまま見てた、デッサンしてた木々みたいなものがその光の線と共に表れたりとかね。なんかそういうのがすごく、すごく、よかったんですよ。
で、そんな方のね、生き様というかをテレビで知って。で、松井さんの本買って。読んだらね、素晴らしくよかったです。うん。なんかね、出来ればお会いしたかったですね。亡くなってからその方の存在を知るってのはね…。まあ、例えばね、ピカソなんてのはたぶん会えないだろうなーとか思うんだけど。僕がね、例えばテレビ局に入って最初に悲しかったのは寅さん、渥美清さんが亡くなったの…95年とかだと思うですけど。96年?95年だと思うんだけど。僕は「男はつらいよ」が好きでね。山田洋次監督に憧れて東大行ったもんですから(笑) で、そのままエンターテイメントに行ったんで、いつかは山田洋次監督とをお会いしたいし。渥美清さんとなんならお仕事をするというのが1つの夢だったんだけども。そういう、もしかしたら会えたかも知れない方と会えないというのは、すごい忸怩たる思いがするんだなーなんてことを感じたりもしたんですけどね。うん。
で、その松井さんのね、本を読んで。なんか松井さんが考えてるアート思考というか、アートというものが例えばフランスという国の文化を創ってるのは当然なんですけど。文化だけでなくて、アートがあるからこそフランスというのはパワーというか国力を維持していると。うん、それがなんか、なんて言うんでしょうね。例に出してたのは、もしなんかね、国がやばくなったらどうすんですか?ってあるフランスの政府の高官と話した時に、その時はモナリザうっちゃえばいいんですよって(笑) 言ってたと。うん。つまり国力、経済力、まあフランスも全然ある国だと思うけど、その経済力、軍事力異常にフランスというのがパワーを持ってるのは、実はたくさんのアーティストとアートの作品という物をすごい大事にしている国だから。うん、という事を仰っていて。それを、なんかね、日本人ももっとそういう意味でアートを大事にした方がいいんじゃないかなんてことを仰っていて。それはね、僕が東京画廊のね、山本豊津さんと豊津徳ってのをやってますけども、毎月ね。豊津さんも常にそういうことは仰っていて。うん、なんかね、アートというものが悪い意味じゃなくパワーなんだなってことをなんかすごい教えていただけたというかね。
絵に光を描く
あとね。これはもう、全くもう、なんて言うんでしょう?あのー、手前味噌なんですけど。僕もなんとなくね、絵を最近描いたりしてて。で、僕はあの、本当に去年描き始めたばっかなので、全然下手くそなんですけど。何て言うかこう…抽象画と言うか、厳密に言うとデッサン力とかが死ぬほどないので何描いても抽象画になっちゃうだけなんですよね。なっちゃうんだけど、その抽象画を描いてる時にやっぱり僕がすごい大事にしてるのは、それをこうやっぱり色というか色彩、つまり光で表現するということがすごく大事なんだよなーなんて素人ながらに思ってて。その光をどう描くか?っていうことだっていう風に、もう、誰に教わったわけでもなく思ってたんですけど。その松井さんもそう仰ってたし。松井さんをピカソがね、ある意味直感で認めてくれたのは、その光という話をしたからなんですって。うん、だからその光というものの、なんて言うんだろう、ありがたさと言うか、恩賞というか、素晴らしさみたいなものというのを描きたいと思って松井守男さんは絵を描き続けて。で、そんなレベルは遥かに及ぶか及ばないかとかはむしろ関係なく、僕もアートって結局光なんだなーって思ってるということを、うん。
あとね、松井さんが、さっき言いましたけど、描いてる時にぶつぶつぶつぶつ言いながら描いてるんですけど、別に僕もぶつぶつ言いながら描いてんのかどうか(笑) 意識してないから分かんないんだけど。絵を描いてる時にはなんかそういうことを感じられるというのはすごい、うん、面白かったです。
歩歩琳堂画廊へ
で、そんなことを感じながらね、水曜日に…火曜日か。火曜日にはですね、神戸の本町にある歩歩琳堂画廊(ぶぶりんどうがろう)という画廊で、現代アーティストのイケミチコさんという方がね、個展をやってるんで。で、この mireva channel に置いてありますけども。イケミチコさんのアトリエにね、1ヶ月前ぐらいにアトリエに行って、生配信させていただいたんだけど。せっかくなんで、じゃあ個展、実際に個展をやっているところにお邪魔しますよと言って個展先からね、配信をさせて頂きました。
イケミチコ展-CRAZY
「現代アーティスト・イケミチコさんの秘密のスタジオ訪問」イケトーク MovingDIVERSE#6
で、そこでね。歩歩琳堂画廊のね、オーナーの川辺さんっていう面白い女性、あえて面白いおばちゃん。おばちゃんと言っても僕と大して年齢違わないんですけど。まあ僕もオッサンなんで。面白い関西のおばちゃんと知り合いになってね。なんかすごいアートの話をとかをたくさん話してたら、なんかすごいすごい…うん、面白くてね。で、そのまま飯でも食いに行きましょうって言って、食べに行って。で、吉村さんっていう、またこの方もね、神戸在住の素晴らしいアーティストなんですけど。そのアーティストの方を紹介して頂いて。で、その方と一緒にご飯を食べたりとかね。
なんかそんな風に──だからその日、松井さんの本を読んで、新幹線の中で。で、神戸元町でイケミチコさんの絵を見ながら配信をして。画廊さんとお話をして。吉村さんっていうアーティストの方と知り合いになってね。で、またすごいいいアトリエを神戸の海に持ってらっしゃるらしいんですけど。今度遊びに来てくださいっていうんで、もう「行きます!」みたいな。そんな感じの火曜日でした。はい。
副学長とご飯、指導教官と面談
で、水曜日。翌日水曜日、僕は毎週大阪の大学で非常勤講師をしてて。で、そこで講義終わりにね、副学長の先生とご飯を食べに行ってですね。で、またその副学長は田中雅一先生というんですけど、もう文化人類学の(※)てね、もうお話がすごい面白くて。なんかそのアートというものとアカデミックというものっていうののエロさみたいなね。エロティックなものにドキドキと感じながらね、そういう時間を過ごさせて頂いたんです。はい。
※聞き取れませんでした。
で金曜日にはね。久しぶりに東大の、僕は今大学院博士課程でいますんで、月一で指導教官の中村雄祐先生という方と面談してるんですけど。なんか久しぶりに、また1ヶ月ぶりにお会いしてね。で、一応指導教官なんで僕の博士論文をどういうことを書くか?みたいなことを基本は色々ディスカッションをする…ということになってるんですけど。僕が全然書いてないからっていうのもあるし、なんか色んな事を…。
それこそね、1ヶ月半くらい前にはバラエティプロデューサー引退するか?なんてことも言ってたぐらいですからね。そんな中で全然進んでないからかも知れないんですけど、いつの間にか身の上相談というか、お悩み相談会みたいな感じになっちゃうんですけど。すごい中村先生ってのはめちゃくちゃクレバーな方なんで、その相談にダイレクトに答えるというよりも、ならば角田さんはこういう研究をすればいいんじゃないですか?っていう研究の骨格というかね、ストラクチャーを提案して頂けるんですよ。そうすると、ああ!なるほど!僕が何となく、たぶん頭というより感性で思ってたテレビとかメディアとか、ソーシャルメディアとか、マスメディアとか、テレビとか、コンテンツとか、ビジネスとか、そういうものに感じていたものがね、そのストラクチャー、構造がピピーッっとハマることでマトリクスが出来てですね。そのマトリクス上で研究していくと、もう書けてもいないのにその論文はきっと素晴らしい論文になるのではないか?と。書けてもいないのに。なのでむしろそれを書かないとやっぱりまずいんだなって気持ちにさせて頂ける。そう、で、それって僕の悩みにダイレクトに答えて頂いてるわけではないんだけども、そのストラクチャーというか、マトリクスを提示して頂けるだけで、ああ、なんか書けそうな気がするかどうかは分かんないんだけど、少なくともその博士論文を書かなければいけないんだなっていう。それこそね、Mission From God と言うか。神の使命みたいなものを感じさせて頂けるわけなんです。
だからそれはね、その先々週に大阪のスタンダード・ブックストアでトークイベントで対談させて頂いた浄土真宗の僧侶で宗教学者の釈徹宗さんとのお話のなかでね。なんかこう感じた Mission From God みたいなものの1つとして、やっぱり僕がこの歳で東大の文化資源学にいるということは、やっぱりその文化資源学に居る中で、僕が今までやってきたテレビとかメディアとか、そういうものをやっぱり一度体系化すべきなんだなっていうのが Mission From God なんだってことに、なんかすごい気付かさせて頂いてですね。なんかすごく、すごく、勇気を頂いたんですね。うん。
森鴎外記念館
で、そんな中ね、本郷に来てたんで、前々から行こうと思ってた、友人から教わってて。これ面白いから行ったら?って言われてたんですけど。森鴎外の記念館にね、千駄木、谷根千の千駄木にあるってことは東大からもう5分ぐらいのところにあるんですけど。僕行ったことなかったんですけど。そこで特別展をね、平野啓一郎さんとかが監修して、「読み継がれる鴎外」っていうのをやってるって言うんで、まあ、行ってみました。
それでね。その展示も面白かったんだけど、鴎外の人生というのをすごい…幼少期の頃からね、亡くなる60歳。ちょうど60歳で亡くなって。今年亡くなって100年、だから生誕160年ですね。で、ちなみにその文学館ってのは生誕150年、つまり10年前に元々鴎外が住んでいた観潮楼っていうのかな?なんか千駄木なのに2階からは東京湾が見えたらしいんで、潮を観ると書いて観潮楼っていう名前を付けたそこに30年ぐらいいた鴎外の家。そこの跡地。そこはもうたぶん震災とか空襲…震災じゃないか、戦災か。戦災でもう焼けちゃったらしいんですけど。そこに博物館が、文学館が…記念館か、が建っていて。すごい美しい建物でした。コンクリート打ちっぱなしの。うん。
そこでその展示を見てね。僕、鴎外がすごい好きで。でもすごい好きって言っても全然全部読んでるわけでもないしね。で、鴎外で言うと「渋江抽斎」っていうね、作品があって。すごいそれは評価も高いんだけど。僕が浪人時代…浪人時代じゃないや、大学の先生だ。大学のフランス革命の専門家の遅塚忠躬先生って方の授業を受けてる時にポロッと仰ったんですよ。「渋江抽斎」を読んだらすごい面白かったと。で、大学3年生の僕はね、そんなに面白いってんだったら読んでみようと思って読んでみたら、最初の1ページぐらいで挫折するというぐらい全然面白くなくて。この話、前も話したかもしれないけど、すーごい文語体でね、文語調で。文語調の…だって「舞姫」とかも「石炭をば早や積み果てつ。」って文語調だから、まあ古文みたいな感じじゃないですか。すごい読みづらいなーと思って、全然読めなかったんですけど。ただその先生は死ぬほど面白いって言ってて。で、そうかーと思ってそれこそ今から10年前ぐらいに。40ぐらいかな?読んでみたんですよ。そしたら、まあ、面白くてね。その辺から僕はなんか鴎外という人がすごい興味を持って。で、鴎外ってのはご存知の通りドイツに留学してるのはお医者さんでね、ドイツに留学して、女性と恋に落ちるけど、女性を振って日本に戻ってきてすぐ結婚しちゃうってことで、すごい女性蔑視な人だなーと思われてるんですけど。その展示にもあったけど、その中の動画でも森さんっていう鴎外の詳しい方が仰ってたけど。すごいフェミニストなんですよね。樋口一葉とか与謝野晶子とかをすごい推してたりとか。つまり才能のある人をすごい推挙するっていうことをやってるわけなんですよね。で、その鴎外も軍医としてはそんなに成功しなかったなーなんて思いがあったりして。で、一方で色んな作品を書いてるんだけども。なんかその時に自分は翻訳ばっかりやっててちゃんとした小説を書いてないっていう恨み節を言ったりね。九州の小倉に転勤した時には自分は出世街道から外れたとかね。すごい悩んでるんですよね。
50歳で小説を書く
で、そんな中で適度に軍医として出世しつつ。適度にしか出世せず。で、そんな中で50歳の時に明治天皇が崩御されて。で、その時に乃木将軍が殉死、切腹すると思うんですけども。その切腹というのにすごい感極まって。…感極まりますよね。自分もそういう立場にいると言えばいるわけで。で、その時に殉死というのをテーマで小説を書いてみたいと思ったんですよね。そこから彼のほぼその記録というかを…色んな歴史のね、記録というか。江戸時代とか。主に江戸時代が多いんですけど。そういう時にあった記録というのを丹念に丹念い調べながら。「渋江抽斎」もまさにそうなんですけど。ただ日記のように書き連ねていく歴史小説というか。その、うん、ルポルタージュ的な小説というか。そういうものが生まれたんですね。
それがまさに鴎外が50歳の時に。で、僕はその50歳の時に鴎外がそういう風にある意味覚醒して60歳の残りの10年、彼は歴史小説を書き続けるんですよね。歴史ルポルタージュと言ってもいいのかも知れないけど。そこに「山椒大夫」とかね、「雁」とか、色んな傑作が生まれていくわけです。で、それをね。それこそ僕も40の時に「渋江抽斎」を読んで。で、自分が42で本を出すようになって。そこから自分が何となく個人の名前で生きていこうと思って、その後TBSを辞めてね。でも、いつしか小説は書いてみたいなーと思っていたものですから、鴎外が歴史小説を書いたという50歳、少なくとも50までにはどんな形でもいいから小説を世に出したいなーってずーっと思ってて、思ってて。で、去年、51歳になった翌日に出したので。50歳の内に小説を書くという夢は叶わなかったんですけど。まあ、厳密にいうと2日か、2日?1日?叶わなかったわけですが。そういう叶わなかったのも自分らしいなーとか思いながら。「AP アシスタントプロデューサー」という小説を出させて頂いたというのはなんかすごい栄誉を感じるわけです。
で、その中でね。例えば「大塩平八郎」とか…鴎外の小説ね。あとそれこそアンデルセンの「即興詩人」。で、「即興詩人」とかも昔ね、読んでみようと思って挫折したわけです。文語体で難しいなーと思いながら。で、安野光雅さんという画家、鴎外と同郷の津和野出身の安野光雅さん。ちなみに安野光雅さんは僕がやってた「オトナの!」って番組にご出演頂いたことがあるので、お会いしたことがあるんですけど。安野さんも数年前にお亡くなりになっちゃいましたけども。安野さんが口語訳の「即興詩人」を出版されてて。それは僕もね、本持ってるんですけど…さっき本棚で探したんですけど…見つかりましたけど。やっぱり読んでないんです。で、そうか、でも「即興詩人」ていうのは本当にすごい本で。鴎外はそれを9年かけて翻訳するんですけど。なんかずーっといつも持ち歩いて読みたい本だって、その特別展「読み継がれる鴎外」の中で書かれてる方がいらっしゃって。そんなに素晴らしい本ならば、素晴らしい作品であるならば、ちょっと難しくても僕もちょびちょび読んでみようかなーなんて思って。青空文庫にね、今や「大塩平八郎」も「即興詩人」もあるから、まさにこのスマホでね、読んでみてるんです。そしたら昨日も夜遅くまで読んじゃったんだけど、確かに面白い。面白くて、やっぱり「渋江抽斎」の時に若い頃読めなかった文語調っていうのが今はすごい気持ちいいなーと思ったっていうのと、その文語調の気持ちよさっていうのをすごい感じてしまうと、むしろ口語で「即興詩人」を読むのが勿体無いなーなんて思うほどにね、鴎外の文語調の美しさっていうのが分かりますね。まだ第一章、二章くらいまでしか読んでないんだけど、ちょっとこう、数日かけて読んでみようかなーなんて思っています。
マニア・マニエラ
だからそんな感じでね、松井守男さんの感じ。絵を観て、それで森鴎外の文章を読んで。で、まさに土曜日、昨日だったんですけど、ムーンライダーズ。ムーンライダーズは僕の大好きなムーンライダーズが Billboard Live で「マニア・マニエラ」っていう1982年に出たアルバム。発売しようとしたら難解すぎると言われてレコードで出ず、カセットブックと当時まだCDプレーヤーなんかみんな持ってない時代にCDで発売されるといういわく付きの作品があるんだけど。すごい名盤があるんですけど。その「マニア・マニエラ」再現ライブをやって頂いてね。もうすごい興奮しながら見てたんですけども。いやぁー、凄まじくかっこいい!元々すごい名曲揃いのアルバムなんだけども、それを今風の解釈というかね、そのメンバー6人+スカウトの澤部さんと佐藤優介さんがいらっしゃるから、今やムーンライダーズは8人体制なのかも知れないですけども。moon の o が2つ多くて moooonriders なんですけども。その8人の演奏する「マニア・マニエラ」がめっちゃめちゃかっこよくてですね。
で、その松井守男さんの光というアートで、森鴎外が小説というのを歴史事実で書くっていう事と、そしてムーンライダーズが「マニア・マニエラ」というアルバムを30年ぶりにライブで再現するっていうのを聞いてる時にね、なんか僕としては、”そうか、この世界っていうのは解釈なんだな”って。解釈って interpret,、interpreter のね、interpret。つまりこの世界ってのは解釈なんだなってことに、なんか僕ね、ビルボードでムーンライダーズのライブを聞いてる時に突然南風が走るような気分で感じてしまったわけなんです。いや、解釈なんだってことは何となく頭ではわかってたんだけど。本当に解釈なんだなと。で、どのように解釈するか?っていう話ってことは、突き詰めれば仮にこのネタ大したことないなーなんてことはあったとしても、それを解釈次第では遥かに面白くなるわけですよね?くだらないと思ってるものも自分の解釈次第で遥かに価値のあるものになる。そうするとなんか僕はテレビのプロデューサーや自分の本を書くときに、ある種のネタ探しというか、面白いものというか。なんかネタになるものをずーっとずーっと探して探して探して半世紀経ったんだけど。ジブはそんな風にうろうろ探すというよりも、実はそんなものはすでにここにあったんだなっていう。自分の周りにあったんだなと。あらゆるものが。そのあらゆるものを自分がどのように表現するか?つまり自分がどのように解釈するか?どのように interpreter になるか?そういう事でしかないんだなって事に気付かされたわけです。なんか僕はね、すごい…これをね、それこそ第二章って2週間前に言いましたけど、なんか解釈なんだ。創作とは解釈なんだってことがはっきり見えた感じを今日は海で語らせて頂きました。ICUCまた来週よろしくお願いします。

文字起こし後の文字寝かし
(好き勝手に思った感想を書き残しておくことを文字寝かしと言うことにしました)
お腹も見えましたけど、ちゃんと足も見えました。足が海に入ってるだけで何とも涼しげに見えるのは不思議、実際は暑いのに。多少は足から冷えた血液が巡って涼しくなるだろうか?
壁紙を寒色にすると冬は暖房を付けていても寒いと聞いたことがあるけど、色だけじゃなく気持ちがいい景色だと快適な気になるんだろうな。あ、風鈴もお化け屋敷もそうか。
海に入っていると何を話そうか分からなくなる──は納得。海にはリラックスというかデトックスしに来てるわけだから…そうか。同じ”出す”でもアウトプットとデトックスは別物ってことだ。文章とか論じることに海は不向きかも知れないけど、その人の自然な話を聞ける機会にはなるんじゃないか?
歩歩琳堂画廊からイケミチコ展のライブ、面白かった!この動画は展示をじっくり観た後に聞きたい。自分が最初に思ったことを間違いとして訂正せずに、オーナーの考えとイケさんの考えを聞くのが一番楽しいと思う。オーナーさんも、イケさんも、それぞれ展示や作品に込めた想いが口から溢れ出る。それがすごく羨ましい。私には”想いが元になって手を動かす”ということがないので。私は「想いがある作品が良くて、想いがないものは悪い」と思っている。それが合ってるか間違ってるかは分からないし、ただの無いものねだりかも知れないけど。ただ、思いがないから自分はダメなんだと言い聞かせてるのは良くなさそうだな。思いが言葉にならないだけだったらいいなと思いつつ、想いがあったら気付ける様にしておくことと、思いが生成されるだけの勉強を疎かにしないように。
イケさんは嫌がるかも知れないけど、イケさんという人は可愛い、すごく愛らしくて、物事に対する姿勢がカッコいい。自由に生きてる!って感じがすごくカッコいい。
中村先生はいつも悩める角田さんを救ってくれる。釣った魚をくれるんじゃなくて、釣りの仕方を教えてくれるんでもなくて、釣り方をひらめくようなものを見せてくれるという感じ。中村先生は角田さんのどこをどう見ているんだろう?
「授人以魚 不如授人以漁」人に魚を授けることは、漁の仕方を教えるに及ばない。これを思い出したんだけど、ずっと太公望の言葉だと思ってたら老子だった…。太公望といえば釣りというのは、作者を忘れたけど漫画で知ってただけで。漫画の中では真っ直ぐの針を水に垂らして考え事をする場面だったけど、歴史上の太公望にもそんな話があったのかは検索するもヒットせず。「覆水盆に返らず」が太公望の言葉だったことと、太公望は釣り好きの代名詞にもなっているので検索しても釣り堀ばっかりヒットすることを知れただけでよしとする。
中村先生の解答で方向が分かるとか、モノにできるのって、実はすごいことなんじゃないかと思っている。もちろん中村先生の的確さはあるだろうけど、私が聞いてもへぇ~!で終わるんじゃないか?
森鴎外…私のイメージはなんか国語の教科書に出る歴史上の人物ということから、給湯流作動ラジオ「#69 森鴎外の本業知ってる?職場でマウント取りまくり・クラッシャーだった森鴎外…彼が抱えてたコンプレックスとは!?」で塗り変わったままだ。戦死者より脚気による病死が10倍だった当時、鴎外は脚気は微生物のせいだとしたため陸軍は白米食を続け、海軍は麦飯を食べたために脚気を減らせたことについて、ナリワイの伊藤洋志さんとお話しいる回。半休さんの鴎外を絡めとる思考回路が面白い。
今回思ったのは、失敗が言い継がれるのはいわゆる有名税みたいなものかな、と。軍医でありながら作家して名を残せるってすごいことだし。脚気の他に、爵位がもらえるんじゃないかと思って病床で羽織袴だったとか、なんというか、見栄をそのまま見せてしまうような人だっとすすると、慕う人も多かったんじゃ無いかと思う。
マニア・マニエラのマニアは熱狂的、マニエラは手法、個々や民族や文化特有のやり方というものを指したイタリア語とのこと。曲名だとばかり思ってたらアルバム名だった。ムーンライダーズ特有の解釈と表現の手法が当時の文化的な解釈と合わないことが分かっていたからマニア・マニエラって名前になったのかな?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
