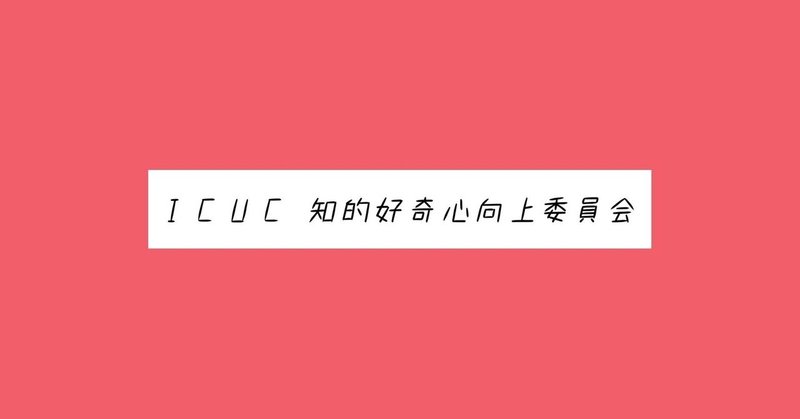
ICUC-099_2022.2.13【民藝運動と文化資源学、ボクがやりたいこと】
【ICUC知的好奇心向上委員会】の私の知的好奇心の向上&趣味の文字起こし。I see, You see ! Intellectual Curiosity Update Committee
今週の本
ーーーーー
角田陽一郎99「民藝運動と文化資源学、ボクがやりたいこと」ICUC知的好奇心向上委員会
動画の内容(+文字起こしメモ&感想)
99
おはようございまーす、おはようございます。知的好奇心向上委員会バラエティプロデューサー角田陽一郎でございます。2月13日、3連休の最後の日曜日の朝にライブ配信しておりますが。なんか3連休結構篭ってるんでね、今日も頭寝ぐせモードで。これもいいんじゃないかなと思って寝ぐせモードのもやってみようかなーなんて(笑) クルッてなってますけど。…なんで寝ているとこうなるんでしょうねえ?不思議ですよね。なんですけど。まぁこんな寝ぐせでやってみようかなーなんて思っております。あのー、あれですよね。緑の髪にして、だいぶ色落ちてきたんですけど。緑の髪のいいところは寝ぐせしててもファッションでやってるんじゃないかな…寝ぐせしてても??寝ぐせになっててもファッションでしてるんじゃないかなって思われがちな、うふふふふ、ところはあったりして。それはいいなーなんて個人的には思っております、うん。どういう個人的かよく分かんないんですけど。
あのー、なんかね、ICUCも今日なんと99回目?99回目なんですね。すごいなー、99回もやってるんだな何気にいってるんですけど。前回はね、「通常運転のダメさ加減」っていう話をさせて頂いたところ、そんなにいつも視聴数って良くないんですけど、先週はさらに良くなかったんです。なるほど、と。で、まあ色々、色々考えてみるとその中身がどうこうとかは置いといてですけど。んふふ、置いといたら考えてないだろ!なんですけど、置いといてみると──ああ、彩さん「さっき起きました。おはようございます。」そうですよね、もう、3連休ですからね。ゆっくり寝ましょう。んふふふ。あのー…あ、そうそう。何がと考えてみると、ダメさ加減みたいなYouTubeって見たくないんだろうなとかちょっと思いますよね。ネガティブなこと。これね、ボクね、周りの人に2名ぐらいに言われたことあるんですけど。結構角田さんこのICUCって自分の苦しみというか暗さみたいなものをすごく表に出してますよねと。で、なんかもうちょっと…だからこの例えばラジオとか出た時とかはすごいエンタメ的に喋るじゃないですか?と。わちゃわちゃと。ワーワーと。まあ一人で喋ってるからそうならないんでしょうねーとも言われましたし、…うん、そうかも知れないですね。だから一人で喋っていると、で、こういう感じで自分とこのスタジオに篭ってやってると、なんかそんな感じでどんどん静かになっていくんでしょうね。でも本当は角田さんってもっとワーッて喋れるじゃないですかみたくなったときに、ワーッと喋りゃいいじゃないですかって。じゃないですかー見たくなった時に、ワーッとは喋ればいいんじゃないですか?って。2人ぐらいに言われたことあって。ああ、それほど、と。そりゃそうですよね。それって人の動画とかを仮に見るって、それのある意味…まあハウトゥーもんなのか知的生産術なのかは分かんないけど、なんかそういうようなところもあるし。単純にエンタメとしてね、見てて楽しいから見るっていうところもあるんだろうなと思うと、なるほどなーと思いました。でもそうするとまた私の問題なんですけど、早口になってくるんですよね。早口。早口でいいのかなーなんて思っているところも若干あるわけですよ。で、早口をやめて、なるべくゆっくり喋ろうとしていると結局ゆっくりになるとなんかボソボソ喋るようになっていくと。じゃあそれでいいんじゃないか?とも思いつつ、今日は寝ぐせのままっっふっふっふ、やっておりますという感じでございます、と。
テレビの画作り
みなさんの地域はどんな感じなのかは分からないですけれども、ここ関東の海は側はですね、雨。また雪になるかも知れないと言ってますね。ああ、明日はラジオなんで東京に行かなきゃいけないんで、だったら今日中に東京に行っていた方がいいのかなとか。行けなくなっちゃったら…ボク基本車移動なので、行けなくなったら困るなーと思いながら今迷っております、と。なので今日午前中にこれ撮影者しちゃおうみたいなことなんですけどね。
3連休初日の金曜日もなんか雨…じゃなくて雪か、雪になるっていう風になってたじゃないですか。そう、だから木曜日ですよね、ちょうどね、だから10日の日か。10日の日が雪になるかもみたいな感じだったから、ボクは都内で案件が、要件があったんですけど…止めようと。止めようと思ってずーっとここに篭ってました。そしたらね、そんなに翌日、雪はぜんぜん積ってなくて。そう、だから金曜日は都内で要件があったんで行ってみたんですよね。全然もう、むしろ普段の3連休の初日より道路が空いているというかね。皆さんが多分遠出しないようにしてたからだと思うんですけど。で、つまりどういうことかと言うと、その前の1月に雪が降った時にはすごい交通麻痺してしまったから今回は過剰に、ある意味過剰に気を付けて下さいね!気を付けて下さいね!っていう風にやってたところ、スカされた感じでそんなに積もらなかった、降らなかったってことだとは思います。なので、今日もねこの後どうなるのかはちょっと今空を見てると、前の窓があって見えるんですけど…大丈夫かなー?雪になっちゃうじゃないかなー?なんていう、ちょっとドキドキしながら見てはいます。はい。
それでね、何が言いたいかっていうと。これ…悪く言うわけじゃないんだけど、木曜日とか金曜日…木曜日か特にね、だからその雪の降る時の「今日は雪降りますよ!」という感じで各局が、テレビ局が報道してたじゃないですか。でもなんとなくこう渋谷とか新宿とかですごい雪が積もっているような映像を見せたいんだろうなーなんて思いながらもそれを見せられなかったというか。実際降ってないからね、だったじゃないですか。まあそれはいいじゃないですか。で、そうするとたぶんそのテレビ局のスタッフは考えるんでしょうね、なんか絵面として雪がある映像を映さなきゃいけないよなーみたいな。ってことでたぶんどのテレビ局も箱根に中継出したりとか箱根の映像を出してこちらは積もっていますとか、お土産屋はもう閉まりましたとか、ロープーウェイがどうですって、インタビューとともにね、箱根の映像をすごく写しましたよね。
で・も・ね、って話なんですけど。箱根って都心に雪が降るか降らないかにかかわらずいつもそんな感じですよね。いつも路面凍っててやばいなーと思いながらとか──ボクは九頭龍神社に毎月お参りいに行ってたことがあるんで、むしろ全然報道されてなくて都内ではすごい明るく晴天だったのに箱根に行ったらすごい雪交じりの道で「大丈夫か?俺…ちょっとこれ運転厳しいんじゃないか_」って焦った事って結構ありますよね。つまり箱根って元々デフォルトで雪降ってんじゃないかみたいなイメージがボクの中にあるに、こういう時に都心とともに箱根を出して雪の映像を見せて「さあこれから積もります」っていう煽ってるのって、煽っているという意識はないにしても…、つまり画作り。雪の報道だから”雪を見せる画作りをしなくちゃいけない”っていう制作現場の意図が、ボクが制作現場にだからすごい見えるんですけど、で、箱根の映像を報道するわけですよね。ところが都心はそんなに積もってないんだったら、箱根ばっかのことをやってても、あれ本当は報道でちょっと、若干、過剰というか、間違ってるとは言わないけどもおかしいんじゃないかなーと思って。箱根の映像ばっか出るからさも…と思って渋谷は全然積もってないじゃん!みたいな話になっちゃうっていうか。だからそこを過剰に煽る必要もないし過剰に軽視する必要もないんだけど、現場ってやっぱり画で考えていくんだと思うんですね。だからやっぱり雪でヤバいですっていう時は雪が降ってる街の画を撮れみたいなような発想が多分テレビ局の人、報道の人、制作の人とかにもあるんだろうなーってすごく感じてしまって。だから木曜日にボクが一番思ったのは箱根の映像ばっか出さなくていいんじゃないかなって言う。箱根は雪が、雪が!雪が!!みたいな。すごく思ったというか。それって…これね、自分がテレビ局にいたから分かるんですけど悪意ないんだなー、たぶん。本当は画作りとかだけ考えてるんですよね。だからある意味ピュアなんですよね。雪が降るっていう報道するときに雪の映像ないとダメだろ→箱根だっていう。そこにこうね、そんなに悪意もないし、騙すつもりなんて毛頭もないんですけど。実際騙してないしね、だって箱根に雪降ってるのは事実だから。でも都心に降ってない時、積もってない時だって箱根降ってるじゃんってことをボクは言いたいんですけど。だあから箱根は雪が舞ってるのっていうのをフューチャリングスし過ぎるのってすごい問題なんじゃないかなって思ったと。
これって、こういう現象に名を付けたいなーと思いましたね。悪意はないんだけどそれをこうそういう風に見せることで結果的に誤解を招く。で、誤解を招くと言っても別に、その…、いいんだけど、うん。で、尚且つこれね、震災以降とかにやっぱりこう津波みたいなことがあったからか過剰に命を大事にしてくれるみたいなとこあって、言い方として。で、どっかの報道で見てたら「転ばないで下さい。命を守る行動を優先してください!」って言ってたけど、転ぶ転ばないって、いや、そりゃ転んで頭を打ったら確かにね、命に別状はあるかも知れないし、体の不自由な方とかね、お年寄りとかみたいなことを考えるとまったくその通りなんだけど!命を守る行動をしてくださいっていう言葉を言い過ぎちゃうとまたその言葉自体が軽くなってきますよね。津波だ地震だならまだ分かるんだけど、降る前の雪に関して命を守る行動…いやだから逆に言えば命を守る行動って言わなくても雪道でコケないようにがんばるっていうのは人間の本能としてというか、だって犬だって猫だって気をつけるじゃないですか。クマさんだって、パンダさんだってみたいな意味で。なんかそこを言語化して「命を守る行動」って言わないと命は守れなくなってしまっている我々って、あるいは…という風なスタンスの報道というか言い方でいいのかなーなんてことをね、思いましたね、3連休に向かっての1日目は…というか。はい。
民藝の100年
で、あとは今日のテーマは「民藝と文化資源学」というタイトルにしたのはですね。まさに今日までなんですけどね、『「民藝の100年」展』というのを東京近代美術館でやってて。やってるので観に行ってきました。いつ観に行ってきたんだっけなー?…火曜日に観に行ってきたんだ、8日の日に。でね、この日は本当はね、違うアート展を観に行こうかなーと思ってたんです。ちょっと時間が出来たんで。で、それって東京都現代美術館だったんですよ。ところが行こうと思ってたら民藝展って今週までじゃんと思って。行くなら民藝展だなと思って。で、民藝展って東京近代美術館なので、東京都現代美術館か?東京国立近代美術館か?で迷ったというか。つまり現代に行くか?近代に行くか?で迷って(笑) で、近代美術館。で、近代美術館の方に。現代美術館のはまた違う週に行けいいやと思って、で、近代美術館の方で民藝展観に行ってきたんです。
そしたらね、結論から言うとね、ボクの中でまたはすごい発見っていうかなんかスタンスがボクの中で見えたっていうお話を今からしようと思うんですけど。つまり民藝展観に行って来て良かったんですけど。これ図録ですね「民藝の100年」。なんとなくちょろちょろ知ってましたけど、で、そうそう、この柳宗悦さんがちょうど没後60周年のかな?というのを記念して。だから今年が別にちょうど民藝100年じゃないんですよね。民藝展2000……1925年に民藝という言葉を彼らが提唱したって言ってたから約100年なんですね、90何年なんだと思うんですけど。没後60年にやってるみたいですけどね。だからつまり民藝って皆さんが想像するこういうのとか、まさにコレもそうだしとか、なんかこういうのとか…っていうようなものだと思うんですよ。で、民藝家具みたいなものとかもあるし、だからボクらが…ボクらって年代が全部一緒ではないと思うんですけど、生きてきて、民藝的な物ってのはものはある意味巷にデフォルトであったりして。そうするとなんか自然でいいなー、なんかこう田舎っぽいなーみたいな意味もあるけど、一方でとんがってないよなーみたいなところで、なんか自分の中で民藝というものをそんなに評価してなかった自分ってのはちょっとあります。だから「民藝の100年展」ってやってたのは知ってんだけど、そんなに行こうと思わなかったのって──だって別に駒場にある民藝館行けば見れるだろうとか、長野にもなんか民藝の、工芸かな?の美術館あって行ったことありますけど。だからなんか別にわざわざ観に行く必要ないよなーなんて思って行かなかったんですけど。なので、行ってみてボクはすごい良かったっていうのは、民藝展の展示も素晴らしかったですけど、…今からもし行ける人がいたらギリギリ間に合うので行って頂いてもアレですけども。民藝運動というものを提唱したこの柳宗悦(そうえつ)、柳宗悦(むねよし)という人の生き様、生き方みたいなことは全然知らなかったので、柳宗悦という人の生き方みたいなのを知った時に「おっ!そうだったんだ!」っていうことでちょっとボクの中ではね、新たな芽吹きを得たというか、芽生えが生じたというか。
どいうことかというと柳宗悦さんってボク本当に何にも知らなかったんですけど、芸術家なのかなと思っていました。アーティストというか。そしたら東大の文学部の哲学科卒で。だから肩書き的に言うと宗教哲学者なんですね。あ、そうなんだ!と。宗教哲学者で民藝でそういう江戸時代の陶器とか…陶器だけじゃなくてね、囲炉裏を吊るすところの、吊るすところの木だけとかなんdなけど、それも展示されてましたけど、すごい…それは使ってるとただの使っているものなんだけど、それを展示すると本当にアート作品になるよなって。本当にボクも思いました。というものに入れ込んじゃったりとか、そういう民藝的なものを色々探しているうちに何かたまたま山梨って書いてあったかな?山梨でこのね、仏像(図録の表紙)、なんでしたっけ?木と喰うって書く…お坊さん、何千体も作ったね、そういうものに惹かれてしまって集め始めたりとか。それこそあれですよね、朝鮮、当時は日本領だったってこともありますけど…そうそう、木喰仏、もくじきぶつ、ね。この顔のにこやかさに惹かれてしまって木喰仏をコレクションしようとし始めたりとか。あと沖縄だったりとか。戦後だったら…戦前もそうですけど東北とかね。なんかそういう様なものに、そこを産業を振興させていくことも意味あるようなーみたいな、まさに運動になるんですよね。
民藝の編集者
だから柳宗悦さんが月刊民藝ってのを創刊したのが1939年らしいんですけど、そこには民藝樹っていう民藝の樹、民藝樹っていう絵が描いてあって。そこには美術館と出版と流通というのを絡めてやっていこうみたいな。あ、MARIAさんおはようございます。眠いですよね朝からzzzですもんね。はい、すいいません(^^) という美術館・出版・流通というものをメディアミックスして行こう。メディアミックスなんて言葉はないんですけどって書いてあるんです。で、『美の本質に迫るためには、思想や嗜好や慣習を介在させずに「直下に」物を観ることが大切であると説きました。』ね。それ以外に、『雑誌の挿絵の機能や、作品図版のトリミングの効果、さらには展覧会における陳列の方法など、メディアを駆使して物の見方を示す、優れた「編集者」でもありました。』『出版、美術館、ショップという三本柱』の活用がメディア戦略であるみたいなことをね、逆に言うと100年前ぐらいに提唱していて。ああそうだったんだ!って。
だから彼が…で、尚且つね、彼の、彼らの、民藝運動をやっている方達の服装とかも展示してあったんですけど、ネクタイとかがちょっと民藝の編みであったりとか、ちょっとこうなんか、皆さんが想像するなんかちょっと上品な学者みたいなルックスだったりするんですけどね。帽子とかも。で、そういうのをわざとそういう服装で世間に出てたんですって。だから民藝というのをファッションでも表現してた。ああー、そんなことをやっていたんだなーということに…だから何かね、例えばここに絵が飾ってありますけど、この絵の話も時間があったらしようと思ってたんですけど、これ10日の日に描いたのがこっちで、
で、こっちが2月…うん?だから…ボクから遠い方が10日の日に描いて、これ(近い方)は12日に描いたんですけど。
なんか最近絵に凝って、絵に…なんか下手の横好きで絵にハマっちゃってんですけど。元々アート好きなんですけど。やっぱり自分で創作してるというか。…そうです「少し前に、日曜美術館で観たような…」ってコメント頂きましたけど、やってましたよね。うん、それ観たかな?ボクは行ったんで観てないかもしれないですけど。うん。
で、その…自分が、あ、だから民藝運動の民藝というものの云々ということに関してはそんなにスタンスは変わってないです。民藝って面白いなーっていうことはなんとなく分かるけど、すげー好きかというより、アバンギャルドなものがボクはちょっと好きなのかなーとは思ったりはします。髪の毛緑ですし(笑) うん、なんだけど。柳宗悦さんが民藝運動というのを100年前に提唱してメディアミックス的にやっていこう、自分は編集者であるという定義で文化を見ていくというスタンスって、あれ?実はそれボクがやりたかったことだったんじゃないかな?ってふと思い出したというか。
ボクという文化資源学者
だからボクはね、いま東大の博士課程1年ですけど、それってあの東大の文学部人文社会研究科にある文化資源学っていう学問を専攻しているんですけど。あれ?それつまり文化資源学じゃん!っていうところに…んっふっふ!いや、文化資源学で民藝をちゃんと研究されてる方たくさんいらっしゃるんですよ?たくさんいらっしゃるんだけど、ボクは文化資源学でメディアというかテレビとか、ビジネスとアートとクリエイティブ、アカデミックをくっ付けるみたいなこととかを自分の中では標榜してるんですけど。民藝的なものというのをどう文化資源化していくかっていうのが民藝運動だったんだなってことに改めて、今さら、思い出されると。で、東大哲学科って仰ってて。でボクは東大西洋史学科なんですけど。そういう意味ではパイセン、先輩じゃないですかと思った時に、なんかボクが何となく去年の夏に『AP』という小説を出して、クリエイティブなものに今までテレビとか作っててもクリエイティブをやってる人間、作り手としての端くれ感が漂っていたのを、やっぱり自分の名前で今後もやっていこうみたいなことで小説をやってたりしてたときの…、でもやっぱりそれがクオリティが…クオリティというか満足出来るものが出来るのかなとか、出来ないのかなーみたいな鬱々とした感じ。書けないじゃんみたいなものも含めて、なんかそれってクリエーターとしてのオリジナリティみたいなものを出さなきゃっいけないんだろうなーっていう呪縛みたいなものがあったときに、そっか柳宗悦的な観点で生きていくっていうのはそもそもボクは好きだったんだよなっていうか。だからテレビでバラエティー作って、色んな社会的、文化的事象をどう映像にするか?それはお笑いも含めてとかいうことをやってたんだと思うし、文化資源学っていう──。
で、文化資源学と民藝運動ってちょっと違うなあと思うのは、それをじゃあアカデミックな領域でコレクションして研究してとか、リサーチしてとかっていうことよりも、ボクはもうちょっとパッシブに、…パッシブ?うん、なんかパッシブと言うかアクティブにか、アクティブにだな、逆だな…に、世界に自分がこういう考え方、モチベーションなんだ、こういう動きがあるんだっていうことを発信した方がいいんじゃないかなってやっぱりテレビマンだから思ってたっていう時に、柳宗悦パイセンはもうやってたんだって言う事を知ったっていうのがなんか勇気付けられたし。そっか、別に分のオリジナリティーみたいなものにそんなにこだわる必要もないんじゃないかなと。むしろ今、2022年にこの日本で、この世界で、このコロナがこんな感じで、東京オリンピックやってて…みたいな時に、どの様な文化的視座みたいなものでこの世界を見ていくかということを表現していく。だから評論家なのかって言われたら評論だけじゃなくもうちょっと…柳宗悦の言い方を借りればメディアミックス的なもので活動するってことでいいんだなっていう風にちょっと勇気づけられたんですよね。
でね、ちょうど100年前にじゃあ民藝運動をやってた…1920何年ということは大正デモクラシーなとこですよね。で、第一次世界大戦では戦勝国側にいて、何となく日本は先進国の仲間入りみたいな感じだけど、それがじゃあやっぱりイギリスやアメリカとかの1等先進国に比べてはやっぱりまだ全然劣ってるよなーみたいな中で、日本の今までの古い民藝的なものを再発見みたいなこととか言うようなのが一個の運動のモチベーションだったと思うんですね。だからあのー、イギリスのね、陶芸と、ヨーロッパの椅子の輸入とかもしてるんですよね。うん。だからそういう様なイギリスの皿とかの抽象的なデザインと日本の民藝はすごい似ているんだよみたいなことをそれこそセザンヌの絵からね、インスピレーションを受けてとかっていう様なことが展示に書いてあったりとかしたんですけど。そんな感じで日本の中で民藝というのをやっていくって、100年経って今の日本で…だからこう、だんだん上がって行く…上がってるけどまだ上り切れてないというポジションの、先進国ポジションの日本っていうのが100年前だとしたら、今はなんとなく…なんとなく上がってたのに下がって行って、あれ?いま先進国なの?大丈夫?もう先進国じゃないんじゃないの?って言われてるポジションの2022年の日本て、実はポジション的にはクロスで似てるところに居るんじゃないかなーと思ったりしてですね。そう思うと2022年に民藝運動的な新たな運動というものをやっているということにやっぱり意味があるのではないかなということをすごく感じたんですよね。
でね、先週、先々週…先週に言ったのか先々週に言ったのか分かんないですけど、ライフ・スパイス・プロジェクトっていうのは10年前くらい前にやってて、今年復活してもいいよなーなんて思ったということをちょろっと言いましたけど。ね?だからそれってちょっとそういう様なボクが思っていることとなんかリンクされるじゃないですか。それがね、またすごく面白いなあと思ったんです。だからあの、なんとなく1月末ぐらいからちょっと新しいモチベーションが、ムーブメント的なものをボクは考えている中で、それって、そんな瞬間に東京都現代美術館じゃなくて東京国立近代美術館の方に行ったっていうのはなんかまたそちらの方にこう呼ばれてたのかなー、…柳宗悦との出会いというかね。っていうのがすごい感じたのがこの3連休前でした。
いきものたちはわたしのかがみ
で、3連休で初日は鎌倉…じゃないや、横須賀横。須賀美術館に、これに行ってきましたね。これは「いきものたちはわたしのかがみ」っていう展覧会。ミロコマチコさんという絵本とかも描かれてる、まだお若い、ボクより10個くらい下の方の展覧会に行ってきたんですけど。これはこれでまたこの方の生き方とかがすごいね、すごい良かったですね。なんかね。うん、なんか、うん…横須賀美術館いいんですよね。前もありましたけど、すごい良くて。だから自分もね、こういう感じで絵を描いちゃってんのかも知れないです。自分が上手いとか下手とかじゃなくて、なんかこう、このミロコさんはね、自分の中の生き物みたいなものをまさにライブペインティングで描いたりとかされたりしてて。そう、綺麗なんです、すごく。で、それをやってる間に山形で美術展とかでやってる時にインスピレーションされて今は奄美大島に移住されて。3年前くらいか、そこでのある意味自然な暮らしをしていて。その中でね、織物に絵を描いたりとか色々されてて、そういう展示もあったんですけど。すっっごい良かったんですけどね。
なんかそういうような…、じゃあミロコさんみたいな生き方、ミロコマチコさん的な生き方も踏まえた上でのなんか──じゃあ現代アートが出てきてとか、構造主義が出て来て、脱構造主義が出て来てみたいな。ポスト構造主義みたいなものが出てきて。で、じゃあその後、震災があってコロナがあって、ウクライナとロシアは戦争しそうだしみたいな状況の中で、文化というかアートみたいなものの再定義みたいなことを少なくともつらつら考えている、この、今、目の前は雨ですけど、そんな中で考えている自分というのは楽しいなっていう…んっふっふっふ!楽しいなのか?!っていう。楽しいな、なのかも知れないです、でも本当に。でもそれでいいのかなーと思った時に、なんかね、使命感みたいなものはむしろないんですけど、それがすごく楽しいのかなーなんていうのは思ったりしました。…届くかな?これ、アレなんですよ、なんか…あ、届かない!…よいしょ。これ、絵を描いたんですけど、これは2月10日に描いたんですけど。これちょうど、ほら、2月10日雪だったじゃないですか。だから窓のから見てる映像みたいなものをただ何も考えずに描いてみようと思って。だから【YUKI】です、タイトル。雪。
と思って。そっか、その日に思った風景を、心象風景と重ねて描くのをやってみようと思ったんで、単純に日付だけ書くっていうのをやってみようかなーなんて思って描いてみました。で、描いてみたので、その翌々日だから昨日、2月12日はですね、こういう風に…なんかね、すごい陽光が綺麗だったんで、これはタイトル【YOKO】にしたんですけど。陽の光で陽光。
で、こう…なんか、これ…だからね、写真だとペタってしちゃうから…まあ下手くそなんですけど、でもすごい筆の感じがすごく気持ちいいなーなんて思ったりしてね。で、こうい描いて。日付書いて、2.12って書いて。十字架があって、なんかこれすごい…何だろうなーって思った時に、これなんか、なんかね、ボク絵を描くとその中に街が町が見えてくるんですけど、十字架…、ダブリンじゃん、とか。なんかね、そう思って。そしたらね、たまたま頼んでた…ダブリンといえばジョイスですけど。フィネガンズ・ウェイクが中古で、古本で買ったんですけど、ちょうど出て来た(^^) だからこの絵のタイトルは【YOKO(Lumière du soleil)Dublin 2.12】ってタイトルをつけたりとかしてるという。うん。なんかね、そんなのがこう自分の中では何か楽しいというかね。こんなことやってて、どうやって食べてくんだ?みたいな(笑) ボクは書かなきゃいけないんですけど!はい。そんな感じでございます。また来週よろしくお願いし──え?来週はじゃあ…あれ?100回目?あれ?何回目だっけ??そんな感じなっちゃうのか?!99回目のICUCでございました。

文字起こし後の文字寝かし
(好き勝手に思った感想を書き残しておくことを文字寝かしと言うことにしました)
寝癖、ものすごい絶壁になってたり後頭部がばっくり割れてると直さざるを得ないけど、今回みたいに全体的にクルクルしてるといい感じ。そのまま出てもよし、ペタッと揃えてるよりむしろ似合ってて良い。ただの私の好みだけど。色も緑が少し残ってる小麦色みたいになってきて。もっと黄色味が悪目立ちするかと思いきや、そうでもないんだなと人様の頭でちょっとした発見をした気分。
寿司特のワーワーわちゃわちゃ感はそのままがいいけど、ICUCはネガティブ角田全開でもいい。それが知的好奇心の向上にならなくてもいい。もはや音声版随想集。エンタメ的に喋るやつはseasoningとか他のところでやってるわけだし、ICUCは角田陽一郎という人の毎週の経過観察の過程のどこかで知的好奇心が向上すればいい。今や油絵という強力なメンタルケア的趣味ができたけど、喋ってみるという、若干かも知れないけどメンタルケアと頭の整理というファンの栄養素。
MissMyStopの上田さんが東京都は雪の場合全て休みという決まりがあればいいのにみたいなことをツイートされていた。そうだ、雪でロックダウンすれば、どこの道でトラックが立ち往生だとか、電車が来ないのでどこ行きのバスを待つ行列だとかで困らないんだ。県境的な場所はどうすんの?みたいなことは現実的にはあるだろうけど、篭っておくことで役に立つなんてコロナ前からあったんだなと、今さらながら。
犬だって猫だって人だって、本能として雪で転ばないように…クマさんだってに続くパンダさんだってに引っかかる。角田さんはよく動物に”さん”付けする。ヤギさん、ウサギさん、クマさん、パンダさん。結果角田”さん”が一番可愛いじゃないかと思いつつ、そこじゃなくてパンダ…彼らは雪で坂を滑り落ちては登り、滑り落ちては登りを繰り返してニュースになる生き物。野生のパンダは映像を捉えることが困難なほどだから、本当は滑るような生き物ではないだろうけど、野生の完全廃棄を思わせるのは滑るパンダの過剰報道の結果かも知れない。
「悪意はないが結果的に誤解を招くこと」で検索したら何か出ないかなとやってみると、出ない。フェイクニュースは違うし、ヒューマンエラーも違う。「熟語」を追加して検索すると、自業自得、画竜点睛を欠く、情けは人のためならず。これらもやっぱり違う。悪意なくフューチャリング過剰ということだから、点睛エラーみたいな?ことわざだと「虎を描いて狗に類す」とか「絵に描いた餅」なんかが近いかな。ことわざはその場の状況が目に浮かぶようなものが多いから、この場合だと”画雪から身を守る”みたいな?
民藝の百年展。Spotifyの給湯流茶道のラジオでも言ってたことが、見つけたPR用PDFにも書いてあった。「東京⇔地方」/「官⇔民」/「近代⇔前近代」/「美術⇔工芸」、宗悦が批判した東京都国立現代美術館という正反対の場で開催されているということがすごいのだと。「近代の眼がローカルなものを発見していくという「捻じれ」をはらんだ時代」とも書かれていて。捻れの英語を検索したら、twist、contortion、warp、distortion と出て来て、「ねじれ/ひねり/もつれ」の他に「引きつれ/こじつけ/反り/歪曲」など意味が広がった。角田さんの言う横断をせざるを得ない状況、横断するもの同士が接近しすぎる状況が思い浮かんだ。それをほぐすのか?押し離すのか?撚りをかけて一つにするか?今風に言うと異素材ミックスとかリサイクルとかアップサイクルとかよく聞くけど、それらともニュアンスが異なる。
自分の名前で生きて行くということが、いつの間にか自分というオリジナリティの確立という一点に集約されてしまって、さあそれが出来てるか?と思うとちょっと息苦しい。だけど、宗悦的な観点でもう一度見直すと、自分が生み出すオリジナリティというのは0→1だけを指しているわけではないし、それはバラエティではないなと…そういうことかな。ICUCでも発展途上人学でも本でも講座でも、天才にはなれないけど、新しい組み合わせは無限大だといつも仰っている。言ってはいるけどまさに著作内容は著者へ向けて書かれてるのか。で、今回は宗悦パイセンが背中を見せてくれた。オリジナル≒天才の様に思われがちだけど、オリジナル≠天才なんだと。まあでも圧倒的オリジナリティの発揮というのはカッコいいので、やっぱり憧れる。上手いこと組み合わせたね!という褒め言葉も場合によっちゃ嬉しくない。
角田さんの絵はすごくカラフルで、どの色もいい意味で主張しないというか、色が画面全体にある、平等にあってどれも大事なんだという感じがする。今まさにつらつら考えているところで、一筆ずつ丁寧に置き並べて、その考えの方向性は未定で。後から見て街を連想するのはそういう部分があるからじゃないかと思ったり。「若干の復讐心と自己嫌悪」があったところで爆ぜてはいるけど暗くなく、むしろカラフルなのも人柄かなと。そりゃあ筆の感じが気持ちいいだろうな。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
