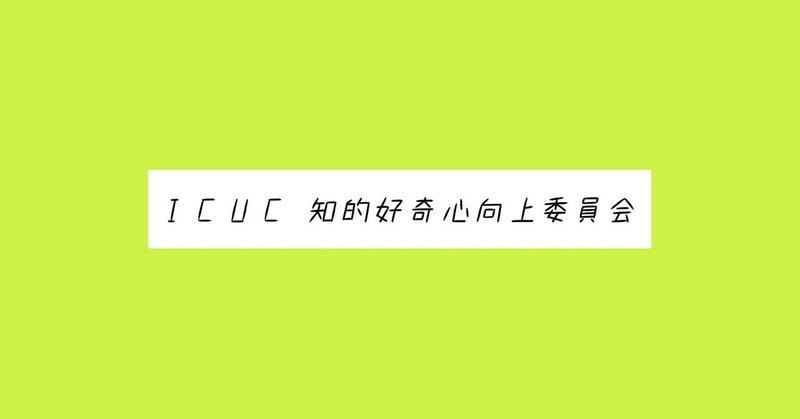
ICUC-116_2022.7.2【人生、第二章】ICUC知的好奇心向上委員会
【ICUC知的好奇心向上委員会】の私の知的好奇心の向上&趣味の文字起こし。I see, You see ! Intellectual Curiosity Update Committee !
角田陽一郎116「人生、第二章」ICUC知的好奇心向上委員会
少なくとも、世間から発注があるわけですから、その期待に応えてみようと想うのです。これは、僕にとっての半世紀ぶりの変化とも言えます。まだ51年しか生きてないので、つまりそれは、僕にとっての第二章の始まりとも言えるほどの大きな変化です。革命です。
それは、つまり、僕の人生自体の構造変化なのです。
自己肯定的に他者存在を意識する自分。
インタラクティブな生き方、考え方、創り方。今までの想いを刷新して、でも今までの経験と実績とスキルを、内に閉じ込めるのではなく、外に解放して縦横無尽に生きていく。
自惚れて、他者に惚れられて生きていく。
動画の内容(+文字起こしメモ&感想)
僕にオーダーがあるということ
どうも、おはようございまーす。角田陽一郎と申します。知的好奇心向上委員会…、今日何回目だ?何回目かよく分からないけど(笑) こんな遅くにやるの初めてかなぁ?とか言いながらこの前もこんな遅くにやるの初めてかなーっと言ってやった気もしますが。土曜日、間も無く7月3日になりそうな夜更けでございます。はい。そんな感じで今日は喋ってみようかなーなんて思っております。
で、ええーと、タイトルはですね、「人生、第二章」ってタイトルにして見ました。んふふ!はい。あの…第二章とか第三章とかってよく言うじゃないですか、人生とかで。で、僕はそう言う風に言うのとかって結構恥ずいって言うか嫌だったんですよ。うん。だからそんな事言ったって、だからつまり、何て言うんですかね?それを言ってると今のところ人生34章ぐらいまで行っちゃってるような気がするんですよね〜、んふふふふ!そう。いつもはじまりは、いつはじめてもいいみたいな話をしてるからね。なので「人生、第二章」って新ためて言う必要あるのかなー?とか。EXILEさんとかよく言ってますよね?EXILE第二章とか第三章とかね、うん。そういうのとかってたぶんあると思うんで、そんなに自分的にはそういう様な言い方はしなかったんだけど…。先週の新月の日に、僕は毎回新月と満月にメルマガを書いてるんですけども。ちょうどその満月…じゃない、新月。新月の日のメルマガがちょうどメルマガやって100号だったんですね。で、100号だから…100号という切りがいいところで…。本当はね、僕ね、もうメルマガ止めようかなーともちょっと思ってたんですよ。うん、思ってたんだけど。うん、でも、僕にそういう仕事のオーダーがあるってことは嬉しいことなので。じゃあオーダーがあるものはあるだけにね、続けてる限りは続けてみようかなーってとりあえず思い直して。100号とかちょうど区切りいいしねと思って止めようと思ったんですけど、結果的にやろうかなと思ってます。
で、じゃあその100号で何書こうかなーなんて思った時に、先週とかね…何て書いたっけ?「自惚れてみる」みたいなのおは先々週か…このICUCではね。自惚れてみるってことを言ってみたりとか、自分を認めるみたいなことをずーっと意識してなかったんだけども、意識してみようかなーって思うみたいなことを言ってみて。そうすると、なんか自分の中で、何ていうか、むしろね、ちょっとね、なんかモチベーションが上がるんですよね。で、これってすごい面白いなーと思うんです。だから、そっか、先週は強がることっていう様なことで喋ったと思うんですけど。うん、だから自惚れてみるって言ってみて、強がってみるって思ってることって、それってまだ自惚れ感が足らないよなーなんてちょっと思ったりもしてたんですね。
疎外感
で、うん、まあ、強がってみようかなって思ったっていうのは、なんなんだろう?ってこう突き詰めて考えていたらですね、これもうずーっとこのICUCも110何回やってるしって意味で言うと、僕ずーっとずーっと言ってるんですけど、自分が楽しいと思うからテレビ番組を作ってて、自分がいいなーと思うもので文章を書いたりして。つまり他者にウケようと思って番組を作った事がないって話はよく言ってるんですね。うん、まあ、だからさんまのからくりTVをやってる時とかは明石家さんま師匠に笑ってもらいたいと言うか。もうちょっと勝負で言うとさんまを笑わせるぜ!みたいな気持ちで作ってたことはあるんだけど。視聴者に…良く言うと媚びてないと言うか。視聴者にどうやれば人気が出るんだろう?って。いや、人気は出た方が嬉しいんですよ。人気が出た方が嬉しいんだけども、それを目的に考えて番組作ったことって、これ別に普通に謙遜でも、普通にこう…なんて言うんだろう?でもなく、本当に、本当にないんですよね。むしろ知ったことか!みたいな。受けるか受けないかなんて関係ないよ!ってやっぱりちょっと思ってましたね。自分が面白いと思うものを出せば、笑ってくれたら嬉しいし。笑ってくれないんだったらそれはまあ理解されないんだなでいいや!っていう思いが。自分がテレビでメジャーなものを作ってる時もそうでした。それでこのICUCみたいなことで喋ってる時も、じゃあ今YouTubeでコトブキツカサと寿司特ってやったりとか…やってますけど。そういうものも数字が気になるなーとか言いながら、どこかで分かんないつには分からなくていいやっていう様な思いがたぶんあるんですよ。うん。
で、そんな中で、そうすると、それって自分がいいなーと思うものを例えば生み出してるんだけども、結果的にそれが人気ないとすると、人の目は気にしないぞと言いながら、自分が良いと思ってるものが受け入れられないんだなって思うのってやっぱりちょっと疎外感を感じるっていう、まあわがままなんだけど(笑) だってそれはそうですよね?相手のことを思わないで作ってるって言ってるのに、相手に見てもらいたいって思うのって、すんごい矛盾。相手に買ってもらいたいって思うのって、すんごい矛盾してるんだけど。でも、矛盾してるからこそそう思ってしまうってことがあるんだなって思った時に、自分の考えや自分の想いみたいなものが他者に理解されないって思う時って、まあ、これは僕だけじゃなくあらゆる人が凹むと思うんだけど。まあ凹むわけですよね。うん。
だからなんかこう先々週から言ってる【自惚れ】とか、先週から言ってる【強がり】みたいなものってのを自分の中で…まあ、おかしいですけどね。強がってるから相手のことなんか関係ないぜ!て言ってるんだけど。言ってるんだけど、強がってるからこそそういう風に自分のことだけ考えてればいいんだぜって言ってると、ちょっと矛盾点を感じたんです。それはどういう事かと言うと、自惚れてみよう、強がってみようって考えると、でも言うても僕なんかにも仕事の発注が来るっていうかね。比較的多くとは言わないまでも、角田さんこういうのやりましょうよとか、こんなのやってくださいよとか。こんなの書いて下さいよって来るってことは、幾許かの期待感を相手が思って僕に仕事を発注してくれるわけで。そしたら自惚れてみると、あるいは強がってみると、自分ってそこそこの人間なんじゃないかって思えるなーって思ったわけです。とすると、自分がそこそこな人間だって思った上で、何かを生み出す、何か作ったものが、自分勝手に自分だけが楽しいんだぜっていうより、もうちょっと他者との接続というか、そう思うとね、うん、何かむしろそれぐらいの自分が相手のことを思ってモノを作ったらどうなるんだろうな?って考えてみるのはどうなんだろうな?って思ったわけです。
50年ぶりの意識の変化
で、これってね、さっきの「人生、第二章」みたいな話だと。つまり他者のために何かを生み出してみようって──思ったこと僕ホントに無いんですよ。…ない。少なくとも50年ぐらいない。んふふふふふ!50年ぐらいないなーって思った時に、僕いま51で間も無く52ですけど、まあいい歳してるとはいえ、まあたかだかね、50年しか生きてないという意味で言うと、50年ぶりの意識の変化なんだなと思ったんです。今まで結構…それがすごい物かすごくない物かは置いといて、色んなものを生み出してきた自負はあるわけですよね。番組とか、イベントとか、動画とか、書籍とか、映画とか、アプリとか。で、そういうものを生み出してきた時に、自分が面白いからやる、自分が面白いから書くという事をずーっとずーっとやってきたんだけど。ここに来て自分じゃなくて他者のために作ってみよう、生み出してみよう、って思ったって事は、50年ぶりの変化なので。僕の中ではそれをもう第二章って言わないと駄目なんじゃないかなと(笑) うん。だからメルマガの100号には書いたんですね。人生100年かどうかは分かんないけど、少なくとも人生50年くらい、半分くらい経ってみて、今回すごい変化が起こりました。自分のために作るんじゃなくて、他者のために何かを生み出してみようと思う。それがそう思えたことが自分の中での人生第二章なんだっていう。
はい、彩さんコメント頂きました。「僕がいいなと思う作品が他者に評価されるのは嬉しいけれど。逆に評価されないと凹みますから、防衛としての「僕がいいと思ったものを作る」だったけど。頂いた評価はそのまま受け入れてみようと思った。次に他者のために作ってみようと思った。つまり繊細な人ですね、いい意味で。」んっふっふっふっふっふっふっふっふ!そうそうそうそう。あのー繊細なのかも知れません。でも別に本当に繊細な人はもうちょっとこんな風な展開をしないのかも知れないですけどね。まあそれはいいとして。ちょっとそれも自分の中で若干謙遜してるのかも知れないけど。まあそういう事です。
いま彩さんがまとめてくれましたけど、つまり自分のことを普通に普通に考えてみたら、少なくともまだ自分がこの世界に必要ないと言われているよりは、こういう事やりましょう、ああいう事やりましょうと声をかけて頂いてるわけだから、それ相応の人間だと仮定した上で。その人間にそういう仕事の発注を頂けるのであるならば、その分のお返しをするぐらいの相手への気持ちみたいなもの──、気持ちは元々あるんだけど、中身の方も、内容の方も、こうやればウケるよなってことを…ウケるというか、こうやれば他者が喜んでくれるよなって事を本気で考えてみようと思いました。
世界の見え方が変わる
うん。でね。そう思うと──。これ僕の中での、本当に第二章だから、今までの自分と…第一章の自分と圧倒的に世界への見え方が変わってきましたね、うん。例えば今日…映画で言うと、「エルビス」ってエルビス・プレスリーの自伝的な映画が昨日から始まってんのかな?始まって、コトブキツカサ氏がすごい面白い、なんならボヘミアン・ラプソディを超えるかも知れない…上手く宣伝とかが重なればって事を言ってたので。映画パーソナリティがそこまで言うんならばちょっと観てみようかなと思って観てきたんですよ。で、面白かったです。すごい面白かった。すごい面白かったけど、これはボヘミアン・ラプソディだってそうだし、例えばビートルズのジョージ・ハリスンのドキュメンタリーみたいな映画もそうだったしとか考えると、偉大なアーティストの自伝的な映画ってやっぱりマネジメントで衝突するとか、薬物で大変になるとか、そういうのが多いからやっぱりなかなか悲しいんですよね。売れてるから悲しい。売れてるだけに悲しいみたいな。スターの悲劇みたいなものじゃないですか。
で、そういう作品を例えば今まで観てた…今までね、第一章の僕が観てると、なんかそのスターだけじゃなくて周りの人も含めて、特に自分はプロデューサーとかだからむしろ周りの人の方に感情移入しやすいんだけど、そういう人の方に感情移入して、なんかね、人生の方にズキュン!って来るんですよ。ズドンッ!と来るというか。つまりその作品の良い悪いを別にして、その作品の中で描かれている人の人生みたいなものにすごい自分を当てはめて考えてみて。なんかちょっと落ち込むみたいな。
そっか…例えばですよ?そんなに有名な、あんなアーティストだってそんなに苦労してるんだ。そこまで遥かに行ってない自分はどうなのかな?とか。んふふ!なんか映画というエンタメを忘れて、すごい自分の中に、自分の人生と重ねてしまうんですね。それって例えばアーティストの自伝的映画だけじゃなくて、例えば007とかでもそうですね。ダニエル・クレイグの最終章の…ね、ネバー・トゥ・ダイだっけ?タイム・トゥ・ネバー・ダイか?みたいなものですらダニエル・クレイグの人生に自分を重ね合わせてしまって悲しくなるみたいな、うん。エヴァンゲリオンとかもそうだしとか。うん。あるいはエヴァンゲリオンを作ってる庵野秀明監督の、ある意味、悩み、苦しみ、みたいなものとか。でもそこまでしてあれだけの大ヒット作を作ってしまうんだなーってことに対する自分との比較とか。まあ何でもいいんだけど。っていう風にすごい作品のコンテンツの内側の関係性と自分の人生を重ねてしまうみたいなことがあるんだよなーなんて思うわけです。
ところが、先週の木曜日ぐらいから第二章な私は…水曜日か。水曜日から第二章になった私はですね、今日とか普通に…エルビス観ててもなんかこの作品てこう作られてるんだっていう、もうちょっと客観的な目で見てる自分がいるんですよね。自分だったらこう作るかなーとか…。だからこの作品を自分が面白いか面白くないかと思ってる、それで良いと思うんだけど、今までの第一章の僕はそれが深すぎたんですね、うん。だからその中身の方にすごい感情移入してしまうというか。それは小説とかでもそうですけどね。ところが第二章の僕はやっぱり世間の、世間と言うか周りの一般の人が、一般というか僕以外の人がどういう風に感じるんだろうな?という様なことにすごい敏感になってるからかも知れないんだけど、ああこういうふうに描くんだみたいに、観た時に、ああすごい悲しいところもあるなーと思ったけど、その悲しいってことに打ちのめされなかったんですね。
それって僕の中ではまたちょっと衝撃的な変化なんですね。うん。で、なんかそういう風な客観的な目線で作品を見てしまうのって昔の僕だったらちょっと拒否ってた気がします。それって何か頭でっかちで観過ぎてて作品を心から楽しんでないじゃんかっていう風に思ってた様な気もするんですよね。ところが第二章の僕は…ということも分かった上でもうちょっと冷静に見ている自分がいるんですよね。うん。つまり他者のことを考えるってなんか冷静になれるんだなっていう。どれだけ、今まで自分勝手な男だったんだっていう風に思います(笑) うん…そうかぁ、やっぱり自分勝手だったんだな。うん。というのをね、すごく、すごく、今感じてます。
貢献という目線
分かんないですよ?それがこう…気持ちのこの…なに?良し悪しとか上下の移り変わってるだけなのかな〜なんてのも思って。今じゃあ上がって来たからそうなので、また下がると違うのかなーなんて思ったりもするんだけど。自分という人間の…うーん。──小沢健二、オザケンの「ある光」って歌にはね、「自分のアーバンブルースへの貢献」って歌詞があるんですよね。そう、だからオザケンさんとかが20代後半くらいの歳の時に自分がアーバンブルースにどういう、音楽業界にどういう貢献をしたのかってことを歌詞に乗っけてるんだなーと思った時に、”あ、そういうことを思ってるんだな”って当時ね、だから僕も20代に僕が聞いた時に、”ああ、そういう事を思うんだな”と思うし、オザケンというぐらいすごいアーティストでもそういう事を歌詞として書いてしまうのを聴いた時に、ちょっとね、恥ずかしくないのかな?そういう事を書いててと思った自分を今思い出しました。恥ずかしいってのは、いや、すごい貢献してると思うけど、でもそれって世界的に見てそんなに貢献してないとも言えるじゃんって言った時に、自分がどれぐらい貢献してるか貢献してないかって事を歌詞に書けちゃうオザケンってすげぇな!って当時は思ってましたね。ところが第一章の若かりし僕だとそう思えちゃうんだけど、第二章の僕、今の僕は、そうか、それが貢献度合いが高いか低いかに関わらず、貢献っていう目線が出来たってことなのかも知れないですね。
うん。そうすると今回みたエルビスって映画も、それがエルビス・プレスリーの人生を映画化したということがこの世界にどういう事で貢献してるか?とも言えるし、仮にこれがすごいブームになってしまえば、ロカビリーというかね、ああいう音楽みたいなものがファンク…ファンクではないか、まあそういう黒人音楽からの白人への、エルビスが開花させたみたいな、ロックンロールの世界みたいなものを今描くことがこの世界にどういう貢献があるか?とかね。うん、だからオザケンも当時そういう思いでそういうことを…。つまりそれは投げかけてたのかも知れないですね。僕が日本で渋谷系の王子様みたいな感じですごい人気になったという事はアーバンブルースの中でどういう貢献があるんだろうな?って彼はきっと思いながらニューヨークに旅立ったという歌だったのかなーと思うんですけど。そこにその目線というものが僕の中ではちょっと偉そうだなと思ってたんだけど。今僕はそういう僕自体がどういう貢献があるか無いかに関わらず、そういうことを思ってみよう、あるいは色んな作品のことをそういう目線で見るってなると、その作品の中で、その作品の人生にどう自分を当てはめてみるっていう見方って、その見方自体も自分勝手というか、自分の中での消化でしかなかったんだなーと思うんです。で、これちょっと注意したいのは、別にだからって貢献しなきゃいけないって言ってるわけじゃ無いですよ?別に。貢献しようがしまいがってところはあるとは思います。それはそれでいいんだと思うんですね、うん。
作品から愛情を感じる
昨日とかはね、岡村靖幸さんのライブ行って来たんです。岡村ちゃん。岡村ちゃんに行って来てね。で、マネージメントの近藤さんって方とも久しぶりにご挨拶してね。本当は近藤さんからメール頂いて、なんか、もしよろしければ来ませんか?って来てた時には、僕は単純に個人的に行きたかったからもう自分でチケット取ってたんで、今回は自分のチケットで行ったんですけど。でもせめてマネージャーの、マネジメントのね、近藤さんにご挨拶したら久しぶりですねー!みたいな話をして。で、その後ね、岡村さんのパフォーマンスと言うかね、2時間半あまりのライブを観ましたけど。うん、いち岡村ちゃんファンとしての自分みたいな感じで今まで岡村さんのミュージックを楽しんでたんだなーと思うんだけど、その世界への岡村さんの貢献っていう目線で見てるというか、その目線を僕の中に付加した上でライブ観てたら、その岡村さんの一挙手一投足がむしろ何かすごい感じ入ったんですよね。そうか!この歌は…、たくさんキスをバーッっとこうやってやったりするんですよ、岡村さんってね。キレキレのダンス踊ったりとか。この歌の次にはこの歌なんだなーみたいな。そういうことって自分が楽しいからやってるってことも当然あるんでしょうけど、こうやるとたぶんお客さんは喜ぶだろうなーとか。そういう様な目線も考えてるんだなーってこととかがいちいちビュンビュンくるんですよね。そのビュンビュン来るってことが、一方的にじゃあ他者から自分への愛情を感じるわけですよ。今までは一方的に僕が岡村さんを愛してるとか、僕がムーンライダーズを愛してるとか、僕がオザケンを愛してるとか、山下達郎さんを愛してるとか、ガガガSPを愛してるとか、アジアン・カンフー・ジェネレーションを愛してるとか、サンボマスターを愛してるとか、一方的にこうやって自分が投げかけてたんですね、自分勝手にね。それってだから当然相手側の方もその作品を通じて僕に投げかけてるっていうのは、その中でのメッセージ性をすごい…、メッセージと言うかね、伝わるものをある意味ピュアに受け入れてたんだとは思うんだけど。そこにそういう表現をしているってのはその僕の外側にいる表現者達が、僕も含めたあらゆる他者について、他者のことを考えているからこういう表現なんだな、こういうパフォーマンスなんだな、こういう行動をしてるんだな、こういう言動をしてるんだなってことが分かるんだなーってことに、やっと分かったってことかも知れないですね。
うん、だからね、そのアーティストの音楽とか作品、今日観た映画、エルビスという映画を観たとか、そういうものの中での感じ方みたいなものは…うん、なんかその作品に付随するその人の愛情みたいなものがむしろ感じられたんですね。感じられるようになったんですね、うん。
僕が落ち込む必要はない
今彩さんからメッセージが。「第一章では作品に飲まれてしまったけど、第二章では作品に乗れてる感じがする。」はい、まだ第二章になってから作品作ってないんですけどね。作ってないんだけど、なんかそんな風に思えてる感じがします。うん。で、僕の中でこれからそういう風に作り方が変わるのか変わらないのかは正直分かんないです。分かんないけど、でも少なくとも、何ていうんだろう、僕自体が何か他者に…じゃあ疎外感を感じた時に、よく感じる男なんだけど、”ああ、これ気のせいなんだな”ってちょっと思える気がするというか。気のせいっていうか少なくとも僕のことを疎外してるというより、その人が僕へ愛の矢印を出してないというか。だから岡村さんは川崎のライブ、コンサート会場で観たんだけど、岡村さんのファンはベイベって言うんですけど、ベイベ達に投げキッスと共に愛情を振り撒いてるわけですよね。でもじゃあ周りの人に何か僕は疎外感を感じた時に、疎外してるというマイナス面と言うよりは単純にその人から愛の矢印が出てないだけなんだよな、出す必要もないしねっていうか。だってその人達はエンターテイナーじゃないし、クリエイターじゃないからっていうことを何か普通に理解出来る様になると、なんか僕がその疎外感を感じたからって僕が落ち込む必要はないんだなっていう風に。
なんか他者に期待する・期待しないとか、人間関係で悩む・悩まないみたいな話も──じゃあ別に会社でもいいんだけど、なんかもうちょっとフラットにその事実を普通に受け止められる様になったなー、なるんだなーってことが今は感じてます、うん。まあ第二章始まったばっかなので、まだ第二章始まって3日間、3日目くらいだから…間違えてました!みたいな(笑) 第二章ナシ!ナシ!ってなるかも知れないけどね、分かんないけど。なんかそんな風に思います。
あ、今質問。「角田さんのAtoByoCシリーズは第二章に入るのですか?」うん、すごいありがとうございます、観ていただいて。コメントも頂きまして。あれとかってだからAtoByoCで今、塚越健司さんって社会学者とトークしてますけど、あれなんかも”塚越さんの面白い話を俺が聞きたいからやってる”だったんですよね、あの収録したのは5月の末だったんで。なので、あれを収録して今作ってる時にはまだその感性はなかったです。無いけどプロとしてこういう風に編集したら面白く見えるよなとかは当然あるんですよ。でもそれはそういう風にスタイリッシュに作ったらかっこいいよなとか、こういう風にやったらもっと面白いよなとか、こういう風にやればトークが相手に伝わりやすいよなーみたいなことを自分が好きだからやってるわけで。本当に相手のことを、観る人のことを思ってたか?というと、実は思ってないんじゃ無いかなって意味では、第二章に入るのですか?というと、…これから入れます!んふふふふ!これから第二弾、第三弾って続くんですけどね。
うん、まあそういう意味で言うともう最後本当に告知になっちゃうんだけど。今度の月曜日、だから7月4日の日に代官山蔦屋書店で斎藤幸平さんっていう東大の准教授、経済思想家の。今、人新生の本でね、40万部のベストセラーの斎藤幸平さんとAtoBtoCということでトークします。だから人新生のエンターテイメントってのはどういう風にやっていけばいいのかな?ってのがあるんで、それ、もし宜しければ来ていただきたいですし。来るのが難しければオンラインで観られますんで、観ていただけると。AtoBtoC第三弾でございます。で、一方で水曜日、7月6日は今度大阪の天王寺にあるスタンダード・ブックストアってところで浄土真宗の釈徹宗さんっていうお坊さんでいながら相愛大学の学長っていう、アカデミックでありながら宗教家である釈徹宗さんと6日の日にまたイベントやります。7時半からかな。オンラインでも観られるんで、もし宜しければ観ていただければと思っております。なので、来週の月曜日、水曜日は第二章の角田が…んっふっふっふっふっふ!トークしますんで(笑) どの様になるかってのを楽しんで頂ければと思います。ということで、また来週よろしくお願いしまーす。おやすみなさい。

文字起こし後の文字寝かし
(好き勝手に思った感想を書き残しておくことを文字寝かしと言うことにしました)
夜更けのICUC。ツイキャスでも日を跨いだことはなかったから、今までで一番遅い配信だったはず。第二章がヨウイチロウ改名事件みたいにナシ!ナシ!になってもそれはそれで一つのイベントみたいに楽しめるかも。角田さんみたいな可愛さで今のナシ!と言える様になりたい。
自分が好き・良いと思うものを作って世に出す。それが受け入れられないと疎外感を感じる。例えばそれが1対1なら恋愛と似てる。
テレビとか物づくりの場合は相手が多数=世間になるから、世に受け入れられないなら疎外された気分になるのも当然かも知れない。世の中には僕の作品が好きな人も嫌いな人も両方必ずいて、テレビは昔から嫌いな人の声が届きやすい。今はSNSがあるから、世に出した作品に一定の認知度があればテレビ以外でも嫌いな人の声が拾えてしまう。疎外感は常に身勝手な感覚だと信じてもいいかも。
好きがどれだけあっても嫌いが無いことにはならない…と私は感じる。だから嫌いの存在に傷ついたり疎外感を感じてしまう。1対多数には1対1とは違う振る舞いが必要なんだ。例えば「仕事人生あんちょこ辞典」に載ってるサードネームとか、ネガティブな部分を他人事として処理してくれるマネージャーの存在とか。サラリーマンという組織のうちの1人なることなんかもそうかも。
ちょっと横道。よく”悲しみは半分に 喜びは倍に”と言うけど、そんな都合よく悲しい方だけ半分にならんだろ?と思ってたけど、最近は「1人で対応してるわけじゃない」という心強さによる”半分マジック”なんだと思う様になった。心強さにはネガティブなことを上手く他人事に捉える効果がある。
角田さんが以前、仕事仲間はたくさんいるけどその中に友達はいないとか、社会人になってから出来た友達はいないと思うけど、マメヒコで会う方々やコトブキさんが友達かも…と言っていた。それが、サラリーマン時代に友達はできなかったけど、フリーになってからはフリーだからこそ必要になる友達(悲しみ半分マジック要員)を得て、高校からの友達も巻き込んで。それからフリーランスとして世に向き直し、友達と一緒に進もうって感じがする。1段上るのに6年の仕込み。
フリーランスは自分が好きで良いと思うもので活動していることは大事な基礎。第二章の角田さんの様にその上で他者を思いやれるようになってからが本番じゃないか?という気もする。で、多くの人に届いたら、次は届いた人を思って、岡村ちゃんでいうところの投げキッスを作品に含めていく。そういう雪だるま方式がいい生き方、いい活き方なんだろうな。難しいけど目指すべき。
たかだか50年しか生きてない。織田信長の人間50年を思い出した。ずっと人生50年だと覚えてた…。ついでに「六欲天の最下層、四大王衆天での1日が人間の時間の50年であり、そんな悠久の世界から見れば人間界の50年など夢か幻、あっという間のことなので、精一杯生きねばならない。」という意味らしいと知る。昔の人の享年が80歳とか案外長生きの人多くない?という疑問が解けてよかった。
”人生第二章は他者のために何かを生み出してみる”と聞いて、思い出したのが映画「人生フルーツ」。人生の三章ぐらいに当たるだろうか?出演している津端修一さんは無償で建築設計を請け負うけど、確か”この世へ恩返しする時になったから無償で”みたいなシーンがある。最近、私が毎月出展させて頂いてる鎌倉のカフェでは91歳のお婆さんが帯で作ったバッグの販売をしていらっしゃる。これがかなり安くて、聞けば多くの方に使って頂きたいのだと言うから、おそらく津端さんと同じ思いなんだと思う。
私はこれがこの世への恩返しとか、いい人生の締めくくり方の手本なんだと感じている。ぶっちゃけ安くていいモノの隣で時間がかかった分だけ高いモノを並べるというのは商売のハードルとしては高い。だけどこうして人生の何かを教えてくれる人は大事だし、助けてもくれる。今はそう言ったハードルを越えられるモノづくりが出来るように精進すべきなんだと思う。
検索ついでに見つけた。いつか行ってみたい映画にも登場する津端修一さんが最後に手がけた建物。
クール・ド・ナチュール
佐賀県伊万里市二里町八谷搦1179
私の言葉が足りなかった。「第一章では作品に飲まれ、第二章では作品に乗る感じ」は、角田さんが他者の作品に対して…だった。だけど結果AtoBtoCが一章と二章を跨いでいるという見どころがはっきりした。二章の角田さんは映画の悲しい内容に打ちのめされなかった。それはなんだか大人な映画の見方だなと思った。
私は子供の頃、他人の話を我が身に置き換えることが出来なかった。映画や本で感動することが分からない。今でもよく思い出すのは、母と映画館でハチ公物語を観た時、母はハチが亡くなるシーンで泣いてたことが不思議で仕方なかった。1987年公開らしいので私は10歳、そんなに小さい子供じゃない。あの頃の鈍感さは、何だか経験不足や知識不足では説明出来ないと感じていて。凹みやすい子はある程度凹み対策が整うまで超鈍感でいるという自己防衛本能というのが今の所の持論。それって出役として前に出ないこともちょっと似てると思ってみたり。
角田さんは昔からピュアだったんだろうし、それを自分の良さとして自信を持ってるし、誇ってるし大事にしている。だから作品にはどっぷり浸かって世界観の中を漂うことが大事だったんだろう。だから客観的な視線は拒否ってたんだろうと思う。
世界観に浸かりながら客観的な視点も同時に持ってる人ならコトブキさんだ。コトブキさんが映画を観ながら「ここ紹介したい」と思うことだ。視線に主観と客観を同時に持つことは可能だし、悪いことじゃないし、物事の見え方は深くなるんだ。でも難しいんだよなー。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
