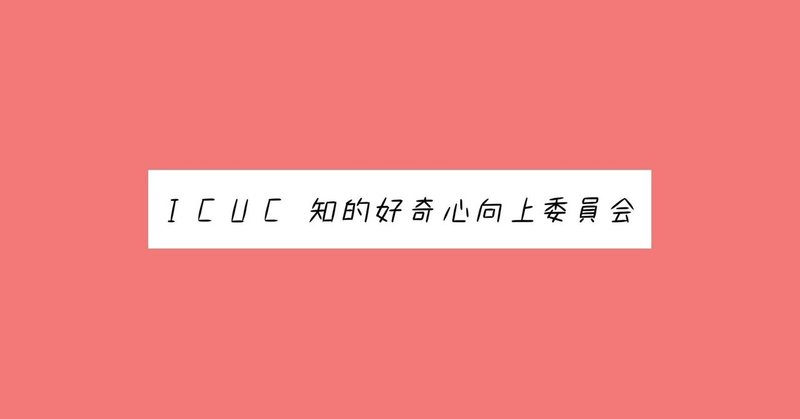
ICUC-076_2021.9.5【想いを横に置く:『ムサシ』を観て井上ひさしに教わる】
【ICUC知的好奇心向上委員会】の知的好奇心の向上&趣味の文字起こし。I see, You see ! Intellectual Curiosity Update Committee
新刊図書
『AP アシスタントプロデューサー』角田陽一郎著エパブリック
『仕事人生あんちょこ辞典』角田陽一郎/加藤昌治(ベストセラーズ刊)
角田陽一郎76「想いを横に置く:『ムサシ』を観て井上ひさしに教わる」ICUC知的好奇心向上委員会
「怨みの鎖を断ち切る」
井上ひさし作『ムサシ』を観て、やっと自分がわかった想いがあります!
動画の内容(+文字起こしメモ&感想)
面白いは自分が上手くいってないと外からやって来る
おはようございます。バラエティプロデューサーの角田陽一郎でございます。知的好奇心向上委員会でございます。えー…9月の5日。今日4日?…5日分でございます。よろしくお願いいたします。雨が続きますがいつの間にか9月になってしまい、9月になるとね、もうなんか暑くても秋だなーなんて思いますし。9月というとなんかもう年末も差し迫ってきたよなー(笑)なんて思ってしまうのが…すごいですね。なんか先週のICUC撮ってから1週間経ったんだけなぁ?とかって思っちゃったりしますよね。すーごい1週間が早く感じるなーなんて。で、1週間って4回来るとひと月ですからねぇ。またそれも早いなーなんて思っております、と。
で、あのー…小説『AP』が出まして。お陰様で好調で重版がかかりましてですね、先週の火曜日に。そう、で、火曜日はちょっと重版がかかったってのと、ちょうどTBSのドラマの植田博樹プロデューサーとトークイベントだったんですけどね。その際にドラマ化一緒にやれたらいいなーなんて愛の告白をしようかなーと思ってたら、ぜひ一緒にやろうよと言って下さったので、なんかちょっと開けたなーなんて感じもしてですね。
で、なおかつある番組からその日にちょうどオファーを頂いたりして。うん、出演の。だからなんかね、今までビジネス書とかね、歴史本みたいなものを出しりしてましたけども、それとはやっぱり…小説を書くとお声をかけて頂く感じがちょっとだけ変わるんだなーなんてことを肌で感じたりしてですね。それはそれでなんか素晴らしいなーなんて思っております。
で、それが火曜日でしょ?で、水曜日にちょっとこう…それも火曜日だ!火曜日にちょっとリモートミーティング、ある企業の方としてたらね。そこの社長さんと意気投合しましてですね。ちょっとそこのPRというか、そういうのとかをちょっと一緒にやれたらいいよなーみたいな話がまとまったりしてですね。それはそれでちょっと…すごいお洒落なプロダクツを作られている会社なので、そこの方々と一緒にやれると面白いなーとか。うん、なんか上手く行かないこともたくさんありますけど、面白い話てってのはなんか自分が…自分のところで上手く行ってないと外からやってくるものなんだよなーなんてことを実感する週でございました。うん。
で、上手く行かないって今いいましたけど。本当に上手く行ってないのかなー?ってこともなんかよく…冷静に考えたら分からんなーなんてちょっと思ったりもしてですね。うん、だからどこかのとこに書きましたけど、それを上手く言ってると思うか?あるいはダメダメだと思うかは自分の取り方次第ですもんね。だからどう自分が取るか?ってことを…なんて言うんでしょう?どう取るかということを考えるというかね。どう捉えるか?ってことを考えると、その捉え方をポジティブに捉えようかなって思うと、ただポジティブになろうぜって言うよりはポジティブになりやすいのじゃないかなーなんて思ったりとかしてたんです。うん。
で、そんなことを思っていながら…水、木…木曜日何やってたかな?なんかいいや。で、金曜日。金曜日はまさに昨日なんですけど。舞台の「ムサシ」藤原竜也さんがね、主演の。「ムサシ」を観に行ってきたんです。だから今日はちょっとそのメインはね、「ムサシ」の話をさせて頂こうかなーなんて思ってるんですけど。
2009年に観たムサシ
「ムサシ」って井上ひさしさん演出…じゃない、ごめんなさい、井上ひさしさん脚本・作、蜷川幸雄さんが演出で2009年かな?に初演をやってるんですね。で、ボク初演観に行ってるんです、2009年に。で、今回は蜷川さんが亡くなって7周忌っていう舞台。シアターコクーンに写真が飾られておりましたけども。出演されてる吉田鋼太郎さんが演出も兼ねてやって。
で、「ムサシ」を演ってたんですけど。あのですね、何が言いたいかと言うとですね。面白かったんですよ「ムサシ」。なるほどなーって言うことを分かったんです。で、だってあれって何回も、結構…2009年から再演されてるんですよね。だからやっぱり人気の戯曲なんだと思うんですけど。ところが。ボク2009年に観に行ったとき、ぶっちゃけ面白くなかったんですよね…。なーんか面白くなかったんです。その後、井上ひさしさんがお亡くなりになっちゃいますけどね。
ボクちょうどその頃、2007年、2008年くらいに井上ひさしに1回お会いしたことあるんですけど。ちょうどそういうこともあって、2005年、6・7・8年くらいに井上ひさしさん作の演劇を蜷川さんが演出するっていう蜷川×井上という、井上×蜷川みたいな演劇を毎年演られてたんですよね。で、2005年かなんかだったかなぁ?「天保12年のシェイクスピア」観に行って、もう、すーんごい面白くて。ボクたぶん今まで観た芝居の中でのベスト1は「天保12年のシェイクスピア」なんですね。すんごい良かった。うん。で、すげぇな!井上ひさし!って思ったっていうところもあり。で、翌年かなんかが確か「藪原検校 」だったのかな。「藪原検校」も面白かったですね。うん、すっごい面白かった。すごい長いセリフがあるんですけど、それを古田新太さんがセリフを言い切る!みたいな。そうすると拍手が上がるみたいなね。「藪原検校」、すごい面白かったです。で、翌年かなんかが「道元の冒険」だったと思うんですけど、「道元の冒険」も面白かったです。
うん、だからそういうちょっと歴史的なもので、井上ひさしさんが書かれたものをそれこそ蜷川さんが演出するというシリーズを観ててすごい面白いなーと思ってて、それで2009年、ついに…。──今まで言った作品はね、過去に井上さんが書かれたものを蜷川さんが演出で再定義するみたいなシリーズだったと思うんですけども、ついに新作をやる、「ムサシ」!宮本武蔵でか?!みたいな。だからボク新聞の全面広告が…朝日新聞かなんかが協賛だったと思うんで、なんか新聞に「ムサシ」ってでっかく出てたのとかすごい記憶に残ってて。うわぁー!面白そう!って思って。チケット取れないかなーなんて思って。チケットどうやって取ったのか覚えてないですけど取って。「ムサシ」を楽しみに観に行ったわけです。そしたらね、なーんか面白くなかったんですよ。なーんか面白くなかったって印象しか残ってなくて。だから正直昨日「ムサシ」の再演を観るまではどんな話だったか覚えてないです、正直。それぐらいボクの中では印象がなかったんですよね。
2021年に観たムサシ、つまらなかったと面白いの理由
ところが昨日は、というような井上ひさしファンの私としては「ムサシ」をもう1回観てみたいなーなんて思ってるところに今年コロナの中でね、吉田鋼太郎さんが演出でやるって言うんだったら、こりゃ観に行かなきゃと思って。それこそ藤原竜也さん、溝端淳平さんが武蔵を演るっていう…武蔵じゃないや!なんか今日間違えるな!小次郎を演るっていうね。というやつで観にいったんです。そしたらね、なんて言うかね、その時つまらないと思った理由と、今回面白いと思った理由も分かりました。
で、まずつまらないと思った理由って、なんか「ムサシ」ってそれこそバカボンドの武蔵をイメージするから、なんかこう日本全国を剣客として飛び回って、色んな方と戦うたいなイメージがある中、ワン・シチュエーションなんですね、基本ね。鎌倉のお寺っていう。そこで3日間禅の修行が行われる中で、武蔵とひょんなことから小次郎が一緒にいるという3日間みたいな話なわけで。なんかそれがボクの当時の…十何年前のボクには面白く見えなかったんだと思うんです。「ええ?なんか色々目眩かないの?」みたいな。
ところが今回面白いなと思ったのは、むしろそのワン・シチュエーションの3日間で武蔵と小次郎を演るというところというのは、極めて舞台的ですよね。だってセット変えなくていいわけですから。まあちょっとだけ変わるんですけど。そのセットが変わらなくていい、そのワン・シチュエーションの中で武蔵と小次郎を描くって、まさに芝居の醍醐味、それこそ井上ひさしさんじゃなきゃ描けないのではないかなと思うくらいの素晴らしさがあったわけです。
それに…だから気づいてなかったわけじゃなくて、分かってなかったのかなーなんて思うと、自分は芝居、今まで何観てきたのかなー?なんて思いました。すげぇ面白ぇじゃねぇか!と。その一つのシチュエーションの中で描くっていうのが。うん。そんなことをね、気づきもしなかったんだなー…その13年前は?12年前は?って思ったりもしました。
あともう1個ね、面白かったのはですね。巌流島の後なんですよね。だからオレね、そのことも忘れてました。だから何観てたのかなーなんて思うんですけど。巌流島で武蔵と小次郎が戦って、武蔵が勝ちますよね。小次郎はそのまま死んじゃう…本当は史実的にどうだったか分かってないらしいんですけど、死んじゃうところを、息があるから助けた方がいいぞと立ち会いしていた医者に武蔵は伝えて、そのままその場を去るんですよ。で、武蔵はそのまま生き返ったというか、復活した…その6年後という設定なんですね。で、武蔵はもう1回…あ、いや、小次郎はもう1回武蔵を果たし合いを行うと。じゃあ3日後にやろう──というようなお話しな訳です。
だから、なんて言うんでしょうね、戦いの後の仮定の話、架空の話なんだけど。その部分の「ムサシ」だってことって、すごい設定として面白いですよね。もう1回戦うのか?という。その面白さに2009年に気づいてなかった…なんで気づかなかったんだろうなーなんてのを思います。
で、3点目。芝居を観られる方もいるからネタバレにならないように詳しく説明しますが。結局、果たし合いをするってことは戦うってことじゃないですか、何かの想いがあって。怨みがあって。でね、そうするとそのセリフの中でね、武蔵でも小次郎でもない方が言うセリフがあるんですけど。「怨みの鎖を断ち切る」っていう言葉があるんです。怨みの鎖を断ち切るという言葉がそのメッセージなんだなっていうことを思った時に…。そっか、井上さんがね、井上ひさしさんがずーっと描いてる世界平和というか、なぜ人は戦うのか?なぜ戦ねばならないのか?戦わないでいられないのか?戦いを止められないのか?ていうことをずーっと描いて来たことを、この「ムサシ」でも描いてるんですね。だから戦いにどう勝てば…とか、戦いの中で研ぎ澄まされていく人間というものを武蔵という──、今までの武蔵像とか、格闘技ってのもそうかも知れないし、だけど戦わなくていいじゃないかっていう。それを説いていたっていうことがまさに井上ひさしさんだからこそ説いてたわけですね。そこにもボク気づいてなかったですね。気づいてたのかも知れないけど、当時そこまで深く思えなかったんだけど…。
怨みの鎖を断ち切る
そう。だからその3日間で武蔵と小次郎は戦わないでいるためにはどうすればいいか?ということを描いている。…描いてるんですよね。もうそれ以上言うとネタバレになっちゃうから言わないですけど。そうかー。だから怨みの鎖を断ち切る、思いの鎖を断ち切るっていうことっていうことって、戦わなくていいじゃんってなるためには、その怨みの鎖を断ち切らなきゃいけないんだって…。それってたぶんあらゆるね、太平洋戦争だろうが、広島の原爆だろうがね、中近東の争いだろうがね、アフガンだろうがね、あらゆることって怨みの鎖がずーっと繋がって繋がって、繋がって繋がって、起こってるわけじゃないですか。争いというか。それってもしかしたらね、人が好き嫌いとか、憎むとか、憎悪とか、復習とか、そういうものってのはあらゆる怨み、怨念、思いみたいなものがそういう行動を起こしてるとすると、仮にそういう思いがあったとしても、どこかで誰かが断ち切らない限り争いは消えないんだぜっていうことを井上ひさしさんは「ムサシ」で描いてたんだなっていう。みなさん気づいてると思いますよ。ボクがあまりにもバカで2009年の時にはそれに…気づかなかったというか、そこに着眼点が行かなかったんでしょうね、うん。
だからそのことで色んなことが思えます。1つは──知的好奇心向上委員会的に言うとって意味ですけど。1つは自分がそのとき出会った作品とか、出会った行動とか、出会った人とかに、なんかネガティブなものを感じたとして。あいつつまらないなーとか、あの作品はどうもおもろくないなーとか、色んな思いってあると思うんだけど。それはその作品自体が面白くないのか?つまらないのか?ってことじゃないんじゃないかな?って、前からボクそのことは主張してたんだけど、今回思いました。今回の「ムサシ」の2009年にはつまらないと思って2021年には面白いと思ったボクのその思いはひとえに”ボク”の責任ですね。井上ひさしさんは2009年にもそれを描いていたし、2021年にはそれを吉田鋼太郎さんが描き直してわけですけど、ずーっと描いてますよ。ところが2009年のボク、39歳のボクにはそれが分からなくて、51歳のボクにはそれが分かったと。で、それにはもしかしたら震災だとかね、その後のボクのバラエティプロデューサーの経歴とかね、TBSを辞めるとかね、色んな出会いと別れがありね、親父が死にね…とかね。なおかつコロナがありとかね。なんかそう言う様な、そう言う様なこともあって。その想いの鎖は断ち切らなければいけないっていうことを、怨みの鎖は断ち切らなければいけないってことを、井上ひさしさんが描いたことを、やっと、やっと理解出来る度量、器になったのかなーとも思います。
でもそれって別に39歳だから分からないってことじゃなくて。そんなこと19歳だって分かる人もいれば79歳だって分からない人がいるわけで。そうするともうその作品が分かる分からないみたいなことも含めて、もうあらゆるものはその人の度量なのではないかなーなんて思いました。だからそう言う意味で誰かがこの作品のことを、ある作品のことをくさしてても、全然意味がないことだし。意味がないというかその人にとっては意味がありますよ。ただそれを鵜呑みにしてその作品をつまらないとか思うことは全く意味がないことだし、だからって自分がすげぇ面白いと思ったからって他の人には刺さらないものかも知れない。で、それは人間関係だってそうだし、あらゆることってそうなんだなーってことになんかこう…再認識させられたって言うか。当たり前のことなんだけどねって言うのが1つです。
あともう1個は、その怨みの鎖を断ち切るっていう言葉が今のボク、今の私、角田陽一郎に、自分にも言われてるのかなーなんて思いました。それが怨みなのか…分かんない、憐憫なのかね、愛情なのかね、あるいは怒りなのかね、そういう感情、ある感情が在るとして、みなさんにも在ると思うんですけど、ボクにも在ると思うんですけど。その感情に縛られてると、その感情で人は行動してしまうじゃないですか。
で、それは感情こそが論理だってボクはいつも主張してるという意味で言うと、そんなことは全くその通りなんだけど、その感情に左右され続けると結局やっぱりこの活動みたいなものも、その感情の色に染まっていくんですよね。だから怨みで行為をしてしまうとやっぱり怨み色でその活動は行ってしまうし。悲しさで活動してしまうとやっぱり悲しい色で包まれてしまう。
それはもうしょうがないと言うか仕方ないし、むしろだからいいんだとも言える。うん、だからいいんだとも言える中で、ボクに今、怨みの鎖を断ち切れって舞台上でセリフとして在り、それがボクの観客としてボクの耳目に触れてる時に、そうか、断ち切ればいいんだって思った時にね、なんかね、すーっとまた感情がね、ボクの中の…ボクの中の戸愚呂を巻いていた感情がね、なんかすーっと消えたんですよね。
想いを横に置く
そう思った時に、ボクよく悩みというものはずっと無くならないんじゃないかって、このICUCではよく言ってるんですね。どう言うことかと言うと、ある悩みがあって、それが解消すると悩みが消えたんじゃなくて、その悩みの空域にまた違う悩みが入ってきませんかね?って。だからボクはなんか頭が痛いなーと思ってて、頭が痛いなーが治るとお腹が痛いなーになり…とか。で、お腹が痛いなーが治るとなんか今度は人間関係で悩み…みたいな。で、人間関係で悩みがやっと治るとお金で悩みとか。なんか悩みって常に常に順繰りやってくる、と。だからつまり自分の脳内に悩みという部位が何割かあって、その何割のところに入るとそれが悩みになり、その悩みが消えるとまた違うものが悩みになるというか。自分の頭の中に悩みという一定領域があるのではないかなっていう風なことをよく思ってます。
それは今でも思ってます。それが何割あるか?半分くらい悩みの人もいれば1割くらいしか悩みがない人とかがいて、人それぞれでその悩みへの対処方法が変わるのではないかな?という、あくまでボクが非科学的かも知れないけど、ボクが思っていることをよく言ってるんですけど。その怨みの鎖を断ち切るって言葉と聞いた時にすーっと消えた時に、悩みというものは自分の頭の領域にあるんだけど、なんかそれを…その想いを横に置くという…置いとけばいいんじゃん、別個にというか。だからそれがあるからもう自分の悩みの領域があるから消えないものなんだよと思うんじゃなくて、あるんだけどその想いの部分に目を行かせない、想いの部分に思いを馳せないというか。そういうことも可能なんだなって、ちょっと思ったんです。
だから怨みの鎖を断ち切るってのはまさにそういうことで、怨みという自分の想いはやっぱり無くならないですよね。無くならない、うん。じゃあどう断ち切るのか?と言った時に、その怨みというものが…感情なのかね、頭の中なのか、情報として残ってると思うんですけど、その情報にアクセスしないってことが鎖を断ち切ることなんだなーって思って。
その怨みというかある想いに、情報にアクセスしないっていうのはどういうことか?というと、つまり…つまり、つまり、その思いを横に置く。置いといてってよく言いますけど、置いといてって…置けないじゃん!とか思ってたんですけど、なんかボクは「ムサシ」を観てたらちょっと置けたんですね。横に。うん、それで観終わったあとね、なんかこう、ちょっとこう、晴れ晴れとした気持ちで演劇、シアターコクーンの外に出ました。
なんかその怨み、辛み、妬み、嫉み、みたいなもののある想い、もしかしたら愛かも知れないし、憎しみかも知れない…みたいなものは、どうせ自分の中では消えないわけで。ただその部位を横に置く。その想いを横に置くということが…うん、いいのかなーと思いました。
それってそう考えると、よく瞑想とか座禅の時にね、呼吸というものに一点に集中して悟るというかね、そういうことって言ってて。そういうことって…ね、そういうことを思ってると違うことに雑念に想いがいくじゃないですか…みたいなことだけど。そういうのをちゃんとやれると、瞑想をやるとすごい想いがスッキリするみたいなことを言われてて。ボクも瞑想やってみたいなーと。で、時々やってみるけども、なかなか雑念、バラエティプロデューサーだけに雑念を生産し続ける脳内なので、なかなか瞑想状態にはなれないよなーなんて、座禅状態にはなれないよなーなんて思っていたんだけども。なんかその想いを横に置くって思ったことで、なんかその座禅とか瞑想に通じるものがあるのではないかなっていう、またボクの中でのちょっとした仮説ができました。だからちょっと瞑想やってみようかなーと思いました。
そういう風に思うえばいいのだということをやってみるということは、なんか次のボクの中での思考のパターンというか、行動になるのではないかなってことをね、昨日はすごい感じさせてくれたんですよね。それがなんかすごくボクの中では救われましたね。やっぱりそういう意味で井上ひさしさんってすげぇなー。うん。その舞台を観させて頂くことでそういうことが分かるっていうね、つまりあの頃の分かってなかった自分ってことも分かるし、あの自分には自分が分かってなかったってことなんですけど…ということも分かるし。
そういう様な想いみたいなものが頭にたくさん詰まっていて自分というものが出来てるんだけど、その中でのあるにょろ、ぐにゅっとした、にゅろっとした、嫌な想いみたいなものが、なんか自分の中ではどうやれば消えるのかなー…、よく川の様に流す、川の様に流すって言ってましたけど、どう流すのかなーと思った時に、なかなか流せないなーと思うと、やっぱりそれが自分の中で澱んでいくよなーなんて思ったんだけど。もう澱んでる部分はあるんだと。最初にたかを括ってしまってね、その在るものにアクセスしないっていうようなことを意図的に思える──そうすとね、武蔵と小次郎は果たし合いをしなくていいのではないか?っていう、つまり争いを産まなくなるのではないか?っていう、そういうことをね、思わせてくれるというか。まあこれ以上言うとホント、ネタバレにになるから言わないけども。うん。それを知った…、うん、経験でしたね。
自分に対する作品の存在意義
なんか素晴らしい経験をさせていただいたなーなんて思います。うん、なんか色々ね、難しいことやね、解決しないことだってたくさんあるじゃないですか。それはね、首相も辞めることだしねーとかね、あらゆる、あらゆることでそういうことはあるんだろうなーとは思うんだけども。でもそれで嘆いていてもね、始まらないじゃんかーとはやっぱり一方では思うわけです。
じゃあどうすればいいんだ?みたいなことも当然るんだけども。そう思うからこそね、そこに想いを馳せないって言うか(笑) うん、その想いを横に置くということをやってみた上で、で、なんて言うんでしょうね、次の…次のというか、違う想いを形にするというか、違う想いで生きていくということがやれれば、なんか抜け出せる──うん、その…その考えなきゃいけないってものから抜け出せる。
だからなんか今までボクはそれを解決するためにはそのことを突き詰めて考えなければそのことを処理できないと思ってたんだけど。たぶんそれって処理出来ないんですよね…っていうか。処理できないまま在ると。その処理できないまま在るものをある意味もう在るということを肯定…というか、肯定も否定も在るから(笑) 在るから、うん。で、その在るものを在ると受け止めてそれを横に置いておく。うん。…そういうことか、という様なことがなんとなく理解できた…ということかなーなんて思います。
「ムサシ」、うん、すごいなー。蜷川幸雄さんのね、7年、亡くなって7周忌だっていうようなことが舞台のロビーのところに写真が飾られておりましたけども。やっぱりすごい演出家だったんだなーと思うなー。なんかね、色々観ました。身毒丸とかも観たし、シェイクスピアのも何作か…本当は全部観たかったんだけど全部観てない、埼玉の彩の国のやつとかもね…とかも思ったんだけども。
うん、あの、なんて言うかね、その作品自体を面白いとかつまらないって思うっていうことも当然あるし、その作品の世界についてどう思うか?ってこともあるんだけど、今回の「ムサシ」の話で言えば、「ムサシ」の作品が面白い・つまらないって話をしてますけど、えっとー、(後部座席へ手を伸ばして)ちょっと待ってくださいね、あったあった、ちょうどパンフレットがあった。じゃーん!「ムサシ」。うん、これ、いやぁー、すごい良かったですね。──あ、そうそう。だからね、その作品自体の良い悪いみたいな話にいつもなってしまうんだけども。その作品自体の良い悪いということもあるけども、それが自分の人生というか自分の想いにどう投射されるか?みたいなことが実はやっぱりその作品を自分がどう…なんて言うのかな、その作品の存在意義であるかも知れないですよね。だからその作品自体が良い悪いじゃなくて、その作品を受け入れる自分がどう感じたかっていうことがなんか全てなのかなーなんて思います。うん。
いやぁ。想いを横に置く。先週で言うと今週のテーマ何て書くかなーって。タイトルね。先週は電気グルーヴへのことを書いて。結局電気グルーヴって書きましたけども。うん、今回で言うと「ムサシ」…で、学ぶ。「ムサシ」で思ったこと。うん、「ムサシ」が教えてくれたこと。…かも知れないですけどね。うん。
井上ひさしさんってボローニャが好きでね。ボローニャ、イタリアの。で、ボク、ボローニャ大学留学したいなーなんて思ってます。うん、まあ今この歳で留学してどうなるかってことは分かんないけど、井上ひさしさんって本当に尊敬してるので、なんかそいういう想いみたいなものを知れたって意味でもすごい大きかったし。自分の小説を『AP』書きましたけど、次の小説を今書こうとしてるんですけども。すごいすごいインスピレーションを頂いたなーなんて思いました。
はい。そんな感じで知的好奇心向上委員会ICUC、今週はこんな感じで終わりにしようと思います。みなさんもまた来週お聞きいただけると幸いでございます。バラエティプロデューサー角田陽一郎でございましたー。はい。

文字起こし後の文字寝かし
(好き勝手に思った感想を書き残しておくことを文字寝かしと言うことにしました)
代官山蔦谷のトークイベント、ハンパない面白さだった。私が初めて角田さんを知った2年前のトークイベントでは同じ会場で、田中泰延さんが短パンで「虫取りのスタイル」と仰ってたけど、今回は虫取りのスタイルよりラフな短パンの植田さん。なんだか座った感じがバカボンのパパみたいで愛嬌抜群だし、お互い信頼してる感じがよく伝わるいい雰囲気。頂いたコメントにお礼を言う時は二人とも手元のタブレットに向かってお辞儀して、それがお二人のタイミングがぴったり一緒で。お互いずーっと視線がお相手から外れず。ああいった良い雰囲気って本当に気持ちがいい。いつ頃『AP』ドラマPやって!と言うのかなと思ったら、初っ端からドラマ化する仮定で話が進む。進む時のあの誰かが私のアドレナリンの蛇口を急に開けた感じ、それを目の当たりにしたのもまた気持ちが良かった。何度でも観たい!ただ今回のICUC、それに続く「木曜日何やってたかな?なんかいいや。」。”木曜日は寿司特”を忘れないでーっ(泣)
「目眩かない(めくるめかない)」って言い方、面白い。39歳の角田さんにとって、人間が戦うとはなんだ?という問いより、劇を劇として、ただの客として、目眩く物語を楽しみたかったのかな。ムサシ初演の2009年は角田さんがgoomoでサービスを開始した年。自分に目を向けるより外を見て楽しむ機運が高かったのかも知れない。今だって劇を劇として観てるだろうけど、今ボクに届いたこの出会いの意味を探すことが、好きというか探しがちと言うか、そこがバラエティなのかも知れないけど…って感じだ。
機運も運気も体調も、上がれば下がり、下がれば上がるを繰り返す。1タームを人生とした大きな上下に、日々のタームや秒タームでの細かい上下が重なっていると私は思っている。連鎖って単語はそもそも環状の部品の連続である鎖が連なるという、二重に連なってる言葉だと思うと、私の思う上下のことを言ってるんじゃないかとも思ったり。
そういう意味で1年の流れの中で、想いに思いを馳せがちなんじゃないかと思う8月。8月は下がる、故に9月からは上がるがセットになっていて、今、わだかまりが溶けた様な消えた様な感覚があるのは、上がり始めかも知れない。気球や潜水、凧のように、錘を外して浮き具合を調整していく。月の満ち欠けも同じか。違うのは体重だ。健康的には上下しない方がいいけど、下がったら上がらないで欲しい。そしてまず下がって欲しい。
想いを横に置く。そして横に置いた想いに思いを馳せない。それが難しい。一昨年か?私はネタのつもりで話していることがあっんだけど、開口一番言われたのが「怒りは手放すんだよ」で、正直ムカッとしたことがあった。怒ってたわけじゃないし、まだこの件について考えたいのに…そんな思いだった。
怒りというのは5秒で終わり、あとは悔しさや恐怖など他の感情が怒りという見た目で居座っているだけだという。居座りを許したり、そこに留めているのは自分の意思なので、その居座りをさせないようにすることが感情を手放すことなのだという。辛い感情を手放す手順というか動作もいくつかは知ってるし、本当に辛い時はそれを使えばスッと楽になることも知ってる。でも怒りたいなら気が済むまで怒ってることにしてる。ただ、辛くなるなら丸ごと横に置いて思いを馳せないようにするしかない。
思いを馳せない方法の一つが瞑想。バラエティ頭脳の角田さんに瞑想は合ってるだろうな。瞑想と似てる集中。古代中国の麻酔法は痛みを忘れるほど碁に熱中させるんだそうだけど、体の不調も同じこと。一番辛い症状に意識は集中するため、その不調がなくなると不調2位が繰り上がり1位になる。悩みがなくならないというのはそういうことだし、暇だと良くない考えばかりが頭を占めていくのも同じこと。
角田さんのような頭は一度に一つを高速で行うか並列処理が可能だろうから、集中しても集中しても思いを馳せることが出来てしまうかも知れない。だから瞑想がいいんだと思う。電気グルーヴとムサシ、もしかしたらその世界にどっぷり浸かることで集中や瞑想の状態だった可能性もある。痛みを忘れるほど集中するか?ひと目を気にせず踊り出すか?
角田さんの言う感情こそ論理、確か「本音で話すは武器になる」に書いてあったと思う。今回は活動の原動力は感情だからと解釈してみた。だからその活動は感情の色に染まっていく。それは体験したことがある。サークル活動が始まった時、自分が幸になることは結果世のためになるみたいなスローガン(?)だったものが、途中で主催者があることに気づく。この活動のきっかけは人に対する怨み、打倒〇〇、あいつより幸せになってやる!だったと。活動開始後に気づいたことは嘘ではなかったけど、この気づきをきっかけに活動全体の雰囲気が変わった。活動には嘘がない、というか嘘がなくなるんだ。一人で活動を客観視することも大変、複数人の感情の方向性を整えることも大変。
想いを横に置く。綺麗な文だ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
