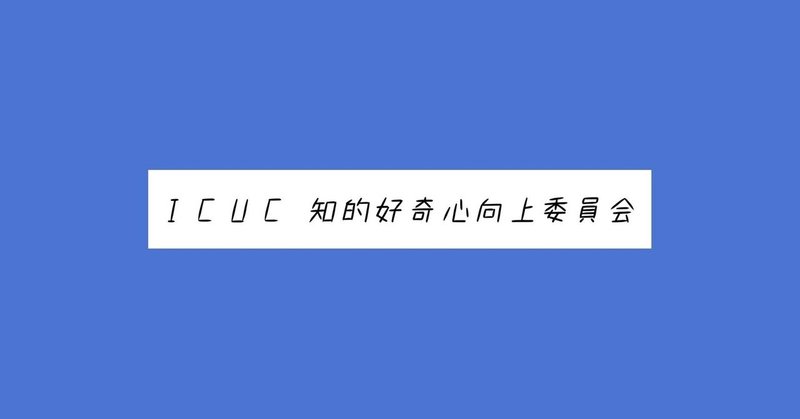
ICUC-081_2021.10.10【いる、なる、する】
【ICUC知的好奇心向上委員会】の知的好奇心の向上&趣味の文字起こし。I see, You see ! Intellectual Curiosity Update Committee
新刊図書
『AP アシスタントプロデューサー』角田陽一郎著エパブリック
『仕事人生あんちょこ辞典』角田陽一郎/加藤昌治(ベストセラーズ刊)
角田陽一郎81「いる、なる、する」ICUC知的好奇心向上委員会
「本当はそこに“いる”ことこそが大切で、そして場を共有するから何者かに“なる”、その後に何かを皆で“する”ようになる。でもこの資本主義の現代社会では職場でも学校でも何を“する”かばかり、その成果ばかりが最初に求められてしまう」佐渡島庸平・井川啓央
beとdo、自分の存在と行動について話しました。
動画の内容(+文字起こしメモ&感想)
ICUC初YouTube-Live-
おはようございまーす。ICUC知的好奇心向上委員会でございます。えーと、聞こえてんのかな?聞こえてますかね?バラエティプロデューサー角田陽一郎でございますが、今日はICUCをYouTubeLiveで初めてやってみようかなーとちょっと思いました。
なんかね、最近ツイキャスやってるんですよね。で、ツイキャスやってて、今日もずっと作業してたんですけどツイキャスをやっておりました。で、なんかそれをどうせやってるんだったらば生配信でもいいかなーなんて思って、やっております。
いつもね、30分ぐらい喋ってそれを…なんて言うんでしょうね、1回編集…編集してないんですよね、どうせね。編集しないでやってるだけだから一緒なんですよ、どうせ。なのでまあやってみようかなと思ったって言う感じではあります。それで、でもそっか、これ告知してないから全然見る方いないんだな。でも後で見る方もいる…だからまあ、そんな見る見ないとか気にせず喋ってみようかなーなんて思ってます。
”いる” ことが大事
でね、今日話そうと思ったことは、そもそもで言うと水曜日にカフエ マメヒコでですね、マメヒコの井川さんっていうオーナーと、コルクの編集者の佐渡島庸平さんと、いつもトークライブというかイベントみたいなものをやってて。「ここ何」って言うんですけど、「ここ何」が3ヶ月ぶりにあったんですよ。で、あったんで、そこでトークをしました。
その時にね、佐渡島さんが「カフエ マメヒコの素晴らしいところは何か?」って話をするわけですよ。で、何だ?みたいな話になったときに、それはつまり今の教育現場での良くない点をむしろカバーしているのがマメヒコなんですけど──まず人間がいるじゃないですか。いる。で、いて、そこの場を共有するから何者かになるわけですよ。で、なる。なってそこから何か始める。何か行う。つまりする。──つまり、まずいて、それから何かになって、そこから何かをする。「いる、なる、する」という順番が本当は教育としては正しいのに、それこそ教育って今やまず”する”ことから始めるじゃないですか。これやりましょう、あれやりましょう、宿題やりましょう、授業やりましょう、クラブ活動やりましょうみたいな。”する”からやりますよね、と。”する”からやって、その後”する”ことで”なる”、”いる”、というか。つまり”なる”か、”いる”か、とかを置いといて、本当は人間ってただ”いれ”ばいい。そうじゃなくて何か”する”ために生きてるという感じになっちゃってて。それってそもそも動物なんて生きるために生きてるというか、生きるために何かをするわけで。本当は”いる”ということの方が大事なのではないか?っていう。その時に佐渡島さんがね、カフエ マメヒコってただいりゃいいんだっていう、そこに”いる”っていうことに意味があるじゃんみたいなことを言ってて。それがマメヒコの魅力なんだと。
で、実際カフエ マメヒコでは今連続ドラマを井川さんが監督で作ってる…脚本・監督・撮影で作ってるんですよね、お客様たちと。その時ってお客様たちが音声さんやったり、まかない弁当を作ったりとか、色々要件というか仕事というかをやることがあるんですけど。それってボクら、ボクらテレビマンですけど、テレビマンが撮影する時と根本的に違うんですよね。テレビマンの僕らが撮影する時は何かというと、撮影するときに美術品があったら美術さんに発注するし、その美術さんに発注するときもメイクさんが必要ならメイクさんを呼ぶし、衣装さんが必要なら衣装さんにものごとを頼むし、大道具が必要なら大道具さんだし、小道具だったら小道具さんとか。つまり逆に言うと、大道具がないロケだったら大道具さん呼ばないんですよね。つまりそれって同じ撮影でもするってことがある意味100%、その”する”ことのために必要な人を呼ぶというのがボクが撮影している現場なわけですよ。
ところがカフエ マメヒコで撮影を”する”ことは、”いる”人の中でやっていくみたいな。でもそっちの方が人間的ではないか?っていうことを井川さんに佐渡島さんが言って、まあそうだねって話になり。だからその今の教育現場って話をしましたけど、それが究極的にいうと仕事の現場、会社って”する”ためにいますよね?ただいればいいって会社はまあないですよね。だからたぶんボクたちが仕事現場で疲れてしまうというか、その”する”ことを常に求められるからであって、ただいればいいっていうのはなかなか無いわけだし。その”する”ということがもし無くなっちゃたら会社辞めてねって言われてしまうと言うか。だからその社会に”いる”ということと社会で何かを”する”ということって、本当は人間というか動物というか…植物もそうかも知れないけど、”いればいい”だけなのに”する”ことが先に求められてしまうっていう。それがたぶん窮屈だし疲れてしまうんだよねっていうことだとは思うんです。
なので、その水曜日にマメヒコで「ここ何」って言うイベントをやってて。カフエ マメヒコの井川さんと、コルクの佐渡島さんと、あとCXのG2って言う人、あとボクがフリートークをするだけなんですけど。「ここ何」って元々は「ここから何か生まれるかも会議」の略で「ここ何」だったんですけど。まあ色んなものは生まれてるとは言えね。佐渡島さんが俳優やってみたりとか、井川さんが小説書いてみたりとか。もともと井川さんを小説家にしようみたいなことから始まった会議なんですけどね。もう2年前…3年前か。コロナで休んでたりしてて。最近やっと復活、最近というか今年になってまた復活して今やってる感じなんですけど。なのでそんな感じでカフエ マメヒコってのはいるという存在が大事だっていうのってすごく分かります。なのでその話を聞いて、ボクもすごい得心したと言うか、うん、なるほどなーとは思いました。
”いる”だけでは不安になる
でね。なるほどなーって思ったっていうのが前提な上で。じゃあ一方でさっき言いましたけど、ボクが何かを撮影する時って基本は”する”の行為しかないんですよね。つまり商業的に番組を作るし、このYouTube、ICUC知的好奇心向上委員会だって、YouTubeで映画パーソナリティーのコドブキツカサとやっている寿司特だって、山本豊津さんという東京画廊のギャラリーのオーナーとやってる豊津徳だって、それで収益を生んでるかはともかく、やっぱり喋るという行為を”する”ためにこの配信をやってるわけです。うん。
でね。”いる”方がいいんだって言う佐渡島さんの意見はもう本当に最もだし。井川さんのやってるカフエ マメヒコでも”いる”という場を作るっていうことって素晴らしいし。つまりその人間が存在する、existすること、英語で言うとbeでしょうね、”いる”って。”する”ってdoじゃないですか。つまりdoしなくてもbeしてることに価値があるっていう考え方って素晴らしいなと思うんだけど、じゃあこと角田陽一郎個人、ボクはどう思うかと言うと、”いる”だけだとね…物足りないんですよ。物足りないって言うか不安になっちゃう。ここにいていいのかな?って思っちゃう。それってずーっとサラリーマンやってたからかも知れないし、職業病と言えるかも知れないし。寂しい男なのかも知れないけど、その場合にただいてくれたらいいよって言われてしまうと何やればいいんだろうって、すごい疑問に思っちゃうんですよね。昔から。うん。
だからボクが早口ですごいわーっと喋っちゃうのってその瞬間瞬間の時間というか場を──場と言ったってこれはオンラインかも知れないけど──そういうのを共有している時に、共有して頂いてるから、何かやっぱりそこに有益なdo、”する”をしないといけないんだろうなっていう思いがやっぱりボクの中ではあるんだろうなーとは思うわけです。
うん。なので水曜日にね、佐渡島さんと井川さんとG2と話した後ね。なんかそのことばっかりずーっと考えてるんですけど。なんかね、あの時のトーク、すごい疲れたんですよね。っふっふっふっふっふ。うん。自分という人間が存在している意味って果たして何なのかなーって思っちゃったっていうか。やっぱりするということをボクはしないと実は存在してちゃいけないんじゃないかなーなんて、ちょっと思っちゃったりもしちゃうんですよね。そんなことないよって言って欲しいという甘えん坊なだけかも知れないんだけども。
何かをしなくてもそこにいてって…いていいだけの人間であってほしいなーとは思うんだけど、自分なんていう存在はそんなものではないんじゃないかなっていう…。別に謙遜とかじゃなくて、本当にそう思っちゃったりすると、じゃあ何も…”する”ことが仮に有益じゃなかったりとかね、したことが価値がないことだなーと思っちゃった時に、そもそもexistしてない方が、存在してない方がいいんじゃないかなーってちょっと思っちゃったりするというか。なんかそんなことをね、考えたりしてるわけです。
期せずして ”いる” をしたツイキャス
一方で、──そう言う感じで自分がね、文章を書いたりとか、こう言う風に動画で喋ったりとかしてるわけですけど──、一方でツイキャスを3週間前から初めてみた…2週間前かな?初めてみたのは、実はその”ここ何”の前からなんですけど。それはきっかけで言うと早口で喋るのが…それ、この前のICUCで話したっけな?寿司特、コトブキツカサのでは話してますけど、自分が早口で喋りすぎてるのは、ラジオにゲストで出た時にこれ早口過ぎるだろう!っていう、自分の作り手としての、プロデューサー的に出役としての角田陽一郎、これ出役NGじゃないかなと思っちゃったりもしたわけです。なので、ちょっとこう早口じゃない感じで喋ることって出来るのかな?ボクは…なんて思ったりなんかしたりして。それで、じゃあツイキャスをやってみようかなと思った時に、むしろ喋らない。ダラダラ喋る。早口にしない。情報量がない。ってことをちょっと試しにやってみたわけです。
そうするとね、期せずしてね、それって今話してた”いる”と”する”の違いになったわけですよ。だからボクが何かをやる時に何かしないとダメだなーとずーっと思ってるから何かをしてるわけで。それがクリエイティブ作業としても、大したクリエイティブかどうかは置いといて。で、そうじゃないものをやってたいなーって思ったわけじゃ無いんだけど、期せずして、じゃあダラダラ喋る、あるいは早口で情報を入れない、みたいな感じでツイキャスをやるってことは、つまりそれって自分という存在がいるだけでも良しとしてくれるか?自分はただ”いる”のを配信してるというか、存在してるのだけをただ流しているだけで果たして成立するのか?みたいなことを、なんかただ感じているだけなのかも知れないですね。…感じているだけというか、感じてみたいと思ってやってるんですね。
で、だからなんか、そしたらその何名かですけど見て下さってる方とかがいると、自分が”する”というのをしていないのに、”する”というのをしていない状態、ただ”いる”だけでも何人かの人が見て下さってるということって、「あ、”する”をしなくてもいいんだな」という意味で、ちょっとホッとできる、安心できる、「ああ、自分ってこの世界に存在しててもいいんだな」って思えるっていう。
これってね。よく若者の自己承認要求とかよく言われたりするし、学校でいじめられるか、いじめられないか、みたいなものまで行かなかったとしても、自分というのの社会での立ち位置みたなことをみんな気にしてると思うけど、なんかそういうことをこの50過ぎの男でもやっぱり気にしてるんだなっていう現れなんだなーとか自分でも思いつつ。でもこれって別に60歳でも、70歳でも、80歳でも、40歳でも、男でも、女でも、トランスジェンダーでも、色んなことを感じる時にやっぱいり自分というのがexistしててもいいのかな?という、どこかで証が欲しくなるんだろうなーなんて思ったりするわけですよね。
それをね、別にツイキャスをやってるからその証になるかどうかは別として、自分の中での思考実験っていう意味で、このICUCみたいな感じで”する”をなるべく心がけて、一応”知的好奇心向上委員会”って名前を付けてるわけですから、見ている方に少しでも知的な好奇心を向上する何かのヒントになるような話をしたいなーという意味では、ダラダラ喋ってるだけなんだけども、”する”という行為を頑張ってきてるとは思ってます。で、一方でツイキャスとかはむしろ”する”をなるべくしないでやってみようみたいなことでいる、みたいな感じでやってます。
で、今日なんかもね。だからこれを撮影で、ライブでやろうと思ったのは、全く同じiPadでやってんですけど。これを今…ツイキャスをそれまでやってて、やってたと言ってもダラダラ2〜3時間やってたのは、自分がここで作業してたので…。プリンターが動かないとか(笑) なんか印刷するとか、そんなことをやってたんで、別に何も喋ってるわけでもなく、ただダラダラだらだら流してただけなんですけど、だったらその感じで一緒にICUC、ちょっとライブでやってみようかなーなんて思って、1回ツイキャス止めて、今ライブでICUCをやってるみたいな感じです。
移動中のexistはホッとする
で、なんでじゃあやってみようかなーって思ったかって言うと。そのツイキャスでここ1週間ぐらいずーっとダラダラ喋ってる時に、ツイキャス…結構ね、車で運転しながら、移動中にやってたわけです。移動中にやってるって、ONにしてから車動かして。そのままずーっと放置してるだけだから、やってると言うよりは定点で──。だからつまりやって…そっかそっか、ツイキャスはやてないので、ドライブ、運転だけはしてますけども、操作はしてないというか、つまりやってない。ただ監視カメラとして、定点カメラとして、ボクが運転してる、角田陽一郎という存在をただ流してるだけで、こんな感じでわーっと喋ったり…いや、なるべく喋らないようにはしてますけどね、喋らないようにはしてますけども、そんな感じでずーっとやってる時に、なんでツイキャスを移動中にやりたくなるのかなって、ちょっと思ったことがあるんです。
それは何かというと、つまりさっきの「いる、なる、する」って話で言うと、ボクは”いる”ということに価値があるという佐渡島さんとか井川さんの言ってることはすごい納得しつつ、こと角田陽一郎個人としては”いる”だけだとやっぱり存在してなくてもいいんじゃないかなって言うか。ボクなんかの存在要らないんじゃないかなってやっぱり思ってしまうんですよね。だから、だた”いる”という事でそこから…じゃあ仮にツイキャスという配信を出来るか?と言うとそれじゃ悪いんじゃないかなって、やっぱり思ってしまうところがある。だから出来ないんです。その場に”いる”だけで、”いる”というのを観察して下さいって言うんだと、ボクがね、すごいイケメンだったりとか、あるいは美女だったりとか、あるいはすごい有名人だとか、何かそういう”いる”という事に耐えうるだけの個人だったらその場にいて、ただキャストしててもいけるのかなーなんて思うんだけども。自分はそれほどでもないよなーって…厳密に言うとそれほどでも有るか無いかということじゃなく、自分がそれほどでもないよなーと思ってること…ということかも知れないですけどね。と思ってると、やっぱりなんか申し訳ないなと思っちゃうんだと思うんです。
で、申し訳ないなーって思ってる中で、移動中って厳密に言うとA地点からB地点に移動してるじゃないですか。で、A地点からB地点に移動している中で、A地点に”いる”、あるいはB地点にいる、で、A地点の”いる”というところでのツイキャスは今の話では出来ない。まあB地点で出来るかどうかは分かんないけど、B地点も同じ意味では出来ない。ただ、AからBに移動してる間はドライブという行為をしてるんだけど、ドライブ以外の行為はしてないわけで。つまりボクの中で行為はしてるわけですよ、するという。するという行為をしてるんだけど、逆に言うと、その状態の”いる”という状態だったら…なんか見せてもいいんじゃないかなって思えるんですよね。
つまりA地点にいないから。移動というのはその場にいないってことじゃないですか、移動している。移動中は移動しているという”する”という行為はしてるんだけども…まあそれ以外してない行為を、移動中のexistはボクとしてキャストしていいのではないかって思えるっていう。
なんかすごい複雑なことを言ってるようだけど、全然複雑なこと言ってないんだと思うんですけど。それを思った時に、移動っていう、moveするって言うか、移動するというか…うん、移動しているのであるならば、その移動中は見せられるなと思った時に、ロードムービーというか、定点観測の定点がムービングしていればボクはそれを見せてもいいんだなって何か思える、ホッとする感じって、なんかすごく面白いんですよね。
移動先は本質的に同じでも移動中は…
この説明で皆さんに伝わってるかどうかは分からないんだけど、ボクがやっぱりバラエティ番組をずーっと作ってきて…と思った時に、だからボクが定住できるかノマドなのかみたいなことって生き方でもあるじゃないですか。で、定住してるの嫌だなーって思ってるわけですよ。どこかに移動したいなと思ってる。ヨーロッパに住んでみたいなーとか、京都に住んでみたいなーとか、色々思うんだけど、いざ住むってなると、やっぱりなんかボクの中でその住んだ街で結局、今…じゃあ東京とか、ここは海の街ですけど、そういう所にいることと大して変わらないんじゃないかなー…。大して変わらないってのはネガティブな意味で。その街が素晴らしいとか、その都市が素晴らしいみたいな話は置いといて、なんか意味がない。結局どこにいても一緒なんじゃないかなって本質的には思っちゃうわけですよね。
ところがそのA地点からB地点に移動してるというプロセスの時はワクワク感があると言うか。そのワクワク感があれば、そのワクワク感を感じているボクという存在、existしている、”いる”というボクは見せられるものなのではないかなーなんて思ったりもするし。と言う時に、じゃあどういうことを思ったとか考えたみたいなことって、なんか言葉として表すこともいいんだろうなーなんて思ったりもします。
それがだから、ねぇ、旅のエッセイみたいなものってあるじゃないですか。うん、だからその街、その場所に定点でいるからこそ分かることってのもありますけど、ボクはむしろそこにずーっと定点でいるってことは──何回か前のICUCで「カメラを動かしたい」って回があるんで、そこでそういうことを喋ってるんで、もしこの話にちょっとでもなんか知的好奇心が揺らいだ人がいたら見て欲しいなーと思うんだけど──ボクはやっぱり定点でいることって苦手なんだなーと思ったことと、ボクがただ”いる”ってことだけだとやっぱりボクという人間が生きられないんだなってことを、それこそ水曜日にマメヒコでね、カフエ マメヒコで思った事というのと、すごいリンクしてるなーって思うわけです。
角田陽一郎67「ボクはカメラを動かしたい:自分ができないことに気づくこと」
YouTube / note(文字起こし)
最近、挫折しました。つまり自分は研究者にはなれないんだってことに気づいた、ってことです。
でも自分がいろんなできないことに気づくと、自分ができることが築ける、っていう前向きな話でもあります!ぜひご覧ください!
皆さんはどうなんでしょうね。この世界に”いる”ということを考えれば考えるほど、いた方がいいかなって思います?あるいは自分なんかいなくてもいいかなって思ったりします?ただネガティブ・ポジティブみたいなことを超えて、いなくてもいいんじゃないかなってやっぱり思う自分が一方でいるんですよね、ボクとしては。いや、いなくてもいいと言うほどポジティブにいないことを言ってるんじゃなくて。いてもいなくても一緒じゃないかなって思ったりもするというか。
遅れて来た自我
だから”いる”ことに価値があるんだって言う佐渡島さんの言葉とか井川さんの言葉ってすごい優しい言葉なんだと思うんですね。いや、だからこんなボクでも角田さん”いて”いいんだよって言われると嬉しいと言うかね。
だから最近すごく思うんですよね。なんか人の欲望の目的でありたいみたいなこと。これってね、すごいジェンダー論で言うとね、例えば若い女の子が男性の性の対象として存在しているって、すごい自分としては嫌じゃないですか。気持ちは超分かります。ところが愛されている人間として存在してるってのはすごい嬉しいですよね。でも愛というのも人の欲望だし、じゃあ性的な対象ってのも欲望だとすると、性的な対象だと嫌で愛だといいっていうのは気持ちは超分かります。ボクもそのことを否定もしてないし、むしろ肯定的に捉えてるけども、ボクはむしろ今、仮にその欲望が薄汚れた欲望だとしても…、いやだから極論すると、この角田ってのと付き合ってると仕事が来るのかなーとか、プロデューサーだからもしかしたらデビューできるかも知れないなーとか、…ボクに性的欲望を感じる人がいるかどうかは置いといてですけど(笑)、まあそういうことで、つまり邪な欲望の対象としてのボクみたいなものがexist、いるとしてても、仮にそれだとしても「角田陽一郎さん、あなたはこの世界にexistしてもいいんだよ。」って言ってくれるだけでなんかホッとするみたなことってありますよね。
それってやっぱり年々自分が歳取ってくるとそういう…仮にその気持ちが邪な気持ちだとしても、そういう気持ちを自分に持ってもらえるという…なんて言うんだろうなぁ、だからやっぱり自己承認要求みたいなことかも知れないけども、なんかそう言うものがどんどん、なんか、自分の中で必要になって来てるような気がするんです。だからそんなものが無い時に”する”という行為をたくさんすることで、もしかしたら自分って言うのはこの世界に生きていいですかって訴えてるのかも知れないですよね。そのために本を書いたりしてるのかも知れないし。うん、本を書いてるのかも知れないし、こういう感じでYouTubeで配信したりしてるのかも知れないですよね。うん。なんか、遅れて来た自我とも言えるかも知れないですね。今まではそんな自我とかもそんなに考えずに、ただクリエイティブという行為をするというだけで、なんか大丈夫だったんだけど。
ま、色々あります。この1年間の色んな人間関係のね、移り変わりみたいなことも大きい。ってか多分それがほとんどの原因だと思いますけども。そんな中でやっぱり『AP』という小説を自分で書いた、うん、その中でフィクションとノンフィクションって話もね、ICUCで先週したかな?先週したんだっけな?最近ツイキャスばっかやってるから(笑)、どこで話したか忘れちゃいましたけど。うん。フィクションとリアルみたいな話をしましたけども。そういうもので、全てはフィクションなんじゃないかなーなんて思ってるわけです。あらゆる人の考えがこの世界を作ってるという意味で、この世界は全部フィクションなんだなと思った時に、そんなフィクションの世界の中で自分という存在があってもいいって思えるって、じゃあAさん、Bさん、Cさん、Dさん、Eさん…みたいな感じのボクじゃない他者の中で、角田という、角田陽一郎という人間がフィクション、その人の、Aさん、Bさん、Cさん、Dさん、Eさん、Fさんとかの頭の中でのフィクションの中で、ボクという存在がexistしててもいいと、許容してくれる、あるいはぜひ存在して下さいって思ってもらえる。むしろ消えてしまえばいいのにって思われたとしても、それってすごい言えば憎悪だし、この人嫌いだなみたいなことかも知れないけど、それでもなんか存在しなくてもいいやって思われるよりは…あ、存在しなくというか、存在してたんだっけ?って思われるよりはいいのではないかなーと、そんな風に思ってしまう。
うん、だから仮に自分というのがこの世界の薄汚れた対象だとしても、existしていいんだよって言われることを何か求めているみたいなのがあるなーって。それって人間50年ぐらい生きてると存在自体が薄汚れてくるからかなー(笑) なんて思いますね。うん、良くも悪くも。それはあらゆる人がその対象なんじゃないかなーって思いますね。だからよく、あるタレントさんとかってオワコンだーとか言われて、ひどいなーなんて思うんだけど。仮にその人、アーティスト、文化人、タレントさんがオワコンだとしても存在してていいわけじゃないですかってなった時に、存在してやるぜ!みたいなね、させてくれよ!みたいなね、そういうような思いみたいなものが”いる”っていう所には大事なんだなーって思えるというか。
はい。そんなことを思いました。今日はライブで話してみましたけど、いかがでしたでしょうか?あの、なんかコメント頂いた方、ありがとうございます。嬉しいですね。と言うことで…なんかね、この感じで良ければICUCもなんかライブでやってみるのも悪くないなーなんて思っております。うん。一応30分たくさん喋ってみました(^^) ツイキャスでは全然喋ってないから。だからやっぱりするという行為をやるために、いるということで、自分の中での安心感って言うか、そういうものがたぶん、あらゆる人間は必要で、それを提示して行くっていうのがこの世界ではこれからも大事になっていくのではないかなーなんて思っております。ICしゅ、(笑) ICしゅって言っちゃった!ICUC知的好奇心向上委員会でした。(この配信を)止めてみたいと思います。

文字起こし後の文字寝かし
(好き勝手に思った感想を書き残しておくことを文字寝かしと言うことにしました)
「自分という存在がいるだけでも良しとしてくれるか?」当たり前だ。角田さんがこの世に居てくれなきゃ泣く。角田さんはこの世に居ていい。どこで何をしててもいい。ご機嫌に暮らしていてくれればなお嬉しい。この世は人の思考で出来上がったフィクションな世界なんだから、邪な欲望の対象になんてならなくていい。
最近もし角田さんが亡くなってしまったらと考えていた。たぶん私の父の亡くなった年齢が52で、その父から「人というのは50くらいが節目なんだ。50代で亡くなる人って案外多いんだよ。」と聞いていたから。父が余命宣告を受けるよりもずっと前にそれを聞いていて「何だい、あんたがそっち行くの?!」と思ったから。──もし角田さんが亡くなっても、私はSNS等でお知らせがあれば知ることは出来る。でもそれがなかったら気が気じゃないけど、どうにも出来ない。耐えきれなくなったとして、おそらくコトブキさんにご存知ないか聞くと思う。それでダメなら自分が会いに行ける確率がある井川さんに聞くのかな?
私がこの世界にいた方がいいか?私はそれほど世界の何かに貢献してないから、猫と一緒に暮らす以外の点において自分が ”いた方が” いいとは思えない。だって私が居ても居なくても世界は変わらない。だから居ていいと思う。命あるものはすべからく、ただ生きてていい。それが生物の尊厳だし、お固く言えばそれが人なら人権なわけだし。その上でいいと言える佐渡島さんや井川さんは優しい。角田さんはその優しさをありがたく頂いていい。
「いる、なる、する」昔なら子供が家に生まれる=いる、成長して○歳に”なる”と、仕事を”する”。”なる”と”する”は成長と共に増え、”する”は徐々に家庭の外にも波及し、地域に”いる”、地域で仕事を持つように”なる”、仕事を”する”、若い者に様々な”なる”と”する”という役割を引き継ぎながら、全ての役割を引き継ぎ終えて人生を全うする──という想像をしてみた。昔は今のような可愛がる愛情の与え方はしなかったかも知れないけど、今より”いる”ことがもっと当たり前だったんじゃないかと思う。家族、親戚、仕事、地域、場は入れ子になっていて、互助的な役割も強かったろう。
それは言い換えれば場への帰属度合いが強くて自由がない。場という群れを離れる代償が不安なんだと思う。20~30年前に職業選択の自由ってフレーズが繰り返しCMで流れていたけど、現代は…家族と親戚は入れ子になってると思うけど、それらは仕事や地域の入れ子からは外れた。入れ子の外でそれぞれの場に帰属される。この2つは場としては広いけど脆い。だから簡単に離れられるけど、脆い分だけ恒常的に不安と引き換えにしてる気がする。互助の希薄さに気づいちゃったなーという感じ。
「出世のススメ」P.47の糸の切れた凧の話もそう。今の若い子は家族大好きな子が多いと聞く。お母さんのご飯が一番美味しい!と答えるのも当たり前、友人みたいな母娘も多い。それって帰属先が浅いわ少ないわで不安いっぱいの中年世代の親が、つまり職業選択の自由と共に就職した世代が、今度は子供と共に場を確立させようとしてるようにも見える。さらに若い子は若い子同士でシェアハウスやサードプレイスの活用をしっかりやってる子も多い印象。親の不安を感じ取って先手を取ってるようにも見える。
角田さんは移動することが性に合うとして、じゃあ遊牧民なら生きやすかったか?と考えると、場=群れで一緒に移動しているから、そういうことにはならない。角田さんの帰る場は角田家で、サードプレイスが苦手で、仕事上で友達になった人はいなくて、それらが前回のファミコンの終わりに繋がると思う。角田家がなくなったと言うと語弊があるけど、つまりあちこち旅をする角田陽一郎が帰る場の変容という喪失。角田さんがリツイートしてたのかな?スナフキンは旅をしているけど、ムーミン谷とムーミンという帰る場があるから旅人でいられるんだと。心の拠り所があるから旅が出来る。
浮気性の人はこの人と別れてしまったら僕は独りだ、それは嫌だ!という思いが強くて、保険的に二股、三股…となる症状なんだそうだ。例えが悪いけど、角田さんの言う人が苦手は、つまり人が嫌いなのではなくて、群れる・つるむが嫌いで、好きな人は大好き。甘えん坊の寂しがりだから、その人からここに”いる”だけでいいと言って貰えないかも知れない不安が先立ってるが故のサードプレイス苦手、仕事上の友達なし…という面もあるかも知れない。
その場にただ居るだけは申し訳ないと感じるのは、成るのひとつの始まり方だと思う。外部からの要請ではなくて、自分で成れそうなものを探す。成れるの漢字変換に慣れると鳴れるが出てきたけど、doを始めて慣れてくる=習熟してくるということと、それが特徴となって広く知れ渡る=鳴るなんだなと。「いる、なる、する」の”なる”がなんとなく”する”と重なってるように感じてたのはこういうことかも。
最近よく出る「『AP』という小説を書いた」という話は、子供が産まれてから変わったと言う人の話と似てる。愛情を貰う方から掛ける方になり、別の形の愛情を貰う。「なる⇆する」の回転の中心に場を作ったのが井川さんというか。
日曜の夜、あと少しで文字起こし完了というところでツイキャス開始。同時に行うという謎のハードルを設け、見事クリアした(笑) ICUC1回をどのくらい頭の中で反芻し続けるか、話が繋がってるから明確に分からないけど、最新の回は1週間は反芻してる気がする。特に3日は味が濃い。私の変な感想文で角田さんを含め、誰かが不快に思ってないことを祈るばかり。そんな私が言えるのは、カフエ マメヒコの「エ」は実は大きい。カフェじゃなくてカフエなんだ(^^)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
