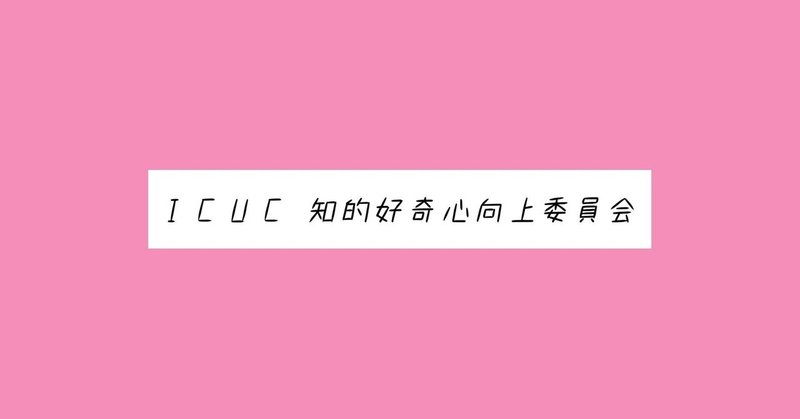
ICUC-101_2022.2.27【城崎にて】
【ICUC知的好奇心向上委員会】の私の知的好奇心の向上&趣味の文字起こし。I see, You see ! Intellectual Curiosity Update Committee
城崎温泉から配信しております。
文化資源学のゼミ合宿。
動画の内容(+文字起こしメモ&感想)
城崎温泉
おはようございまーす。知的好奇心向上委員会でございます。えーーと聞こえてるかな?ICUC知的好奇心向上委員会でございます。2回言ってみました。バラエティプロデューサー角田陽一郎でございます。なんかすごいですよ。今日はですね、今、布団の上に寝っ転がってやっております。照明も大丈夫かな?まあ大丈…大丈夫か。はい。今日はですね、…なんか照明が──ま、いっか。はい。えー、すごいですね、寝っ転がって。でも寝っ転がってやってるって言ってるけど、こう顔がアップになってれば別に寝っ転がってようが、寝っ転がってなかろうが、対して変わらないなーとも言えるんではないのかなー?と思いながら。寝っ転がってやってみようかなーなんて思ってたり…思っていたりもします。
今日のタイトルはですね、ICUC知的好奇心向上委員会102回目でございますが。志賀直哉の小説「城崎にて」ではないのですが、「城崎にて」というタイトル…ああ、どうもコウキさん、こんばんは。ありがとうございます。「城崎にて」というタイトルでやっておりますが。つまり私は今、城崎温泉の旅館いてね(笑) ね!旅館にいてもこうやって生配信できちゃうんだから時代でございますよね。はい、そういうものをやっております。城崎温泉の…で、今ですね、城崎温泉行かれた方います?兵庫県のね、豊岡市になるのかな?になるんですけど。外湯めぐりみたいなのが。めぐるんですけど、さっき本当に10時ぐらいにこのホテルに着いて、で、外湯が20──9時半くらいに着いたのか、で、23時までとか書いてあったんで、もうICUC撮る前にせっかく城崎に来たんだから温泉入ってこようと思って、いま温泉入ってきて。で、入ってきて、急いで帰ってきて、こんな感じでICUC知的好奇心向上委員会をやってるとなるとですね、…何が言いたいかというと、眠いですね。んっふっふっふっふっふ!眠い感じでございますね。まあ眠い感じでもいいかなと思いながらやっております。なので何か質問とかあったらば下さい。何でも答えますが。ない、まあそんな感じでやっております。
で、なぜ城崎にいるかって言うとですね。それこそ金曜日から関西方面に来てるんですけども。仕事というよりはどちらかというと私がいま東大の大学院の博士課程1年なんですけども、ゼミ合宿というものがありまして、そのゼミ合宿で。文化資源学っていうところに私は在籍しているものですから、まあ色んな文化政策的な、文化資源的なところを見学したり、そこの関連する方にお話を聞いたりというのを金曜日からやっていて。本当はね、違う…何ヶ月前かに行こうと思ってたんですけど。そもそも夏に行こうとか言ってたんですよね。秋というか。そしたらやっぱりちょっとコロナの馬鹿がね、はびこっているせいで無理だから12月にしましょう…あ、1月にしましょうってなってたのか。そしたら1月がねえ、オミクロの馬鹿が何か出てますから1月無理ですねなんて言いながら。そうすると卒業する方もいらっ”ちゃ”る…いらっしゃるので、じゃあもう3月のこの時期みたいな話になり。それもね、決行するかしないかみたいな話になったんですけれども。
そういう意味で言うと普通合宿ってね、みんなで泊まって、同じお部屋に泊まりましょうみたいな感じになるんですけど、それだとちょっとコロナの中いかがなものか?みたくなったので、基本はもう泊まるところは勝手にみんな決めなさいと。うん、任せますと。ただそのポイント、ポイントで行く場所はあるので、そのポイント、ポイントで行く場所に集合して、お話し聞いたり見学したりして。で、次の場所に各自い行くみたいな感じに。ちょっと異例のゼミ合宿になっていますと。はい。なので(金)(土)(日)ってことで今日3日目なんですけど、城崎に居る、と。はい、そんな感じでございます。
ゼミ合宿(竹田城、立雲峡、皿蕎麦)
でね。インスタとかにもあげましたけど。金曜日はね、京都国立博物館に行ってですね。ボクは琳派展見に行ったことがありますけど。その京都国立博物館のバックヤードをね、副館長の方に解説してもらって。うん、なかなか勉強になったというか、やっぱりね、バックヤードみたいなのを見れるって面白いじゃないですか。そういうのを見させて頂いてね、なんかすごい勉強になりましたね。
で、土曜日はそのまま兵庫県に移動しましてですね。朝来市…朝来市かな?に行ってですね、芸術の森美術館っていうのがあるんですね。その芸術の森美術館っていうのを見学して、またお話を伺ったりとか、それこそ朝来市のホール、文化施設の担当者の方にいろんな問題点とか未来展望とか、そういうのをお聞きするっていうのをやり。で、…土曜日でしょ?それがその日のうちにあの、ほら、マチュピチュと言われてる竹田城。竹田城跡に一泊して。やっぱり竹田に泊まったからには竹田城跡を見た方がいいよねって話になったんですけども。ボク数年前に竹田城趾に行ったことあるんで、皆さんは行くって言うんですけど、ボクはむしろ竹田城のこっち側の山から竹田城を見る、と。だから皆さんが竹田城で想像するようなマチュピチュみたいな写真はこっちの、反対側の立雲峡というところから見れるんですね。なので、立雲峡から見てみようということで。で、どうせ見るなら雲海はこの時期には見れるかどうかわかんないけども、絶対見れないわけでもないのでってことで。で、見れるんでしたら朝の6時半、日の出が6時半近くだったんで、6時半から7時半くらいの間が見られますよって言うんで。なるほど!と。で、宿から車で10分くらいだって言うんで、ああ、じゃあ6時過ぎに出ればいいんですね〜みたいな話をしたところ、その立雲峡の駐車場のところから展望台までは第二展望台は歩いて5分くらいですけど、第1展望台は歩いて20分くらいですって言われたら…、まあ、どうせなら第1の方がいいかなと思うじゃないですか──ってことで!今朝は5時半くらいに起きて、見れるかなーなんて思いながら。まあちょっと行ってみようと思ったわけですよ。
で、5時40分ぐらいに旅館を出たら…雪(笑) 雪降ってるんですよね、雪。雲海とかそういうことより…でも雪かい?!みたいな。でもなんか天気予報を見ると晴れるとも出てるし。あれ?ということはむしろ雪の雲から晴れ間が出たりすると見られるのではないか?みたいな一縷の期待を、希みを背負ってですね、ボクは5時45分に宿を出発して、6時前には立雲峡の駐車場に着き、そこから20分の展望台を目指したわけですよね。
そうするとですね。つまり、ボク、インスタに上げてるんで興味ある方は見て頂ければいいんですけど。
もう、ちょー雪山なんですよね。雪降ってるから。もう雪山を…普通に歩いて20分の上りなんですけど、結構急なね、20分なんですけど、雪山の20分は30分ですよねーみたいな感じなんで、結構久しぶりにザクザクですね、雪を掻き分けながら展望台まで行ったわけです。で、なんとか6時半、6時40分くらいにですね、展望台には着いたんですけど、まさに五里霧中ってやつですかね。もう、ほんとにもう雲に、ってか目の前が雲みたいな感じで。ま、結局見れなかった、見られなかったっていうのが今日の朝。
疲れましたね。朝…うん、久しぶりに…。でもね、ボク、今日…、いつもおはようございますメッセージ送ってますけどね。今日送ったのはまさにその雪で、展望で雪の映像で。
おはようございます。3月6日です。
一年のうちで何回か、自分の中で自然の量が足りないなと感じる時がある。
そういう時は、海に行く、森に行く、雪道を歩く。風を感じる、匂いを感じる
つまり、身体が自然を求めているのだ。
身体が旅を求めているのだ。
人は篭っては生きていけないのだと想う。
ってことを書かせて頂きましたが。本当にね、なんか久しぶりに、何かこう…でも雪とかもすごい多いと大変だったりするんですけど、なんかね、雪にまみれながら、で、ちょっとこうなるんじゃないかなと思ってスノトレみたいなものを履いてきたんで良かったなと思うんですけど。
なんか雪道をザクザク歩くみたいなのって、やっぱりあれ年に1回…1回でいいのか2回…だから雪国の方は日常なのかも知れないんですけど、そんな日常じゃないボクとしては…。でも昔だったらね、スキー行ったりとかした時に思ってました。雪が足りないなーみたいな。なんかこう雪のところを歩くと体がすごい、芯から冷えるみたいな。でもあの感じってすごく、なんか、身体が自然を求めてる、自然を注入する感じっていうのをすごい感じるなーと思いながらね。まあ、景色は見れなかったんですけど。雪道を歩く、と。
で、その後ね、学生とか先生と、皆さんと合流して。そしたらボク以外の人たちは皆んな竹田城に登ったみたいなんですけど。そしたら雪の竹田城に登ったからすんごい綺麗で最高でした!みたいな。角田君もこっちくれば良かったのにみたいな。はい。まあ若干そう思いながらね。こんな雪の竹田城なんてなかなか見られないわよ〜みたいなこととか言われながら。まあ…そんな感じで皆さんと合流し。結局まあ車で次の場所に行くみたいな。そんなことをやってました。
ゼミ合宿(江原河畔劇場、歌舞伎座、芸術文化観光専門職大学)
でね、江原河畔劇場って平田オリザさんのやってる青年団がね、運営してる劇場場あるんですよね。民間の劇場なんですけどね。そう、豊岡市の。で、そこを見学させて頂いたりとかね。そうするとね、なんかこう青年団って駒場東大前のアゴラ劇場っていうのが青年団の劇場だと思うんですけど、今は青年団ってこの豊岡に移動されてるんですね。で、そこでワークショップとか。そう、(チャット欄)「インスタの写真、確かに絶景です」綺麗ですよね。…大変でしたけど、うん。それでワークショップとかやってるって言うんですけど、地元のね、小学生とかが演劇の練習とかしててなんか良かったです。すごく。
で、そこからね、出る石と書いて出石(いずし)。出石蕎麦ってのが有名で。小っちゃい、皿そばって言うんです。本当に小っちゃい餃子を入れるぐらいの、タレを入れるぐらいの、小っちゃい蕎麦をね、何枚も頼むんですよ。だから7人いたのかな?7人いたんで1人10枚食べるって言ったから70枚頼みますか?って話になって。70枚とか頼むんですね。だけどボクは食いしん坊だと15枚ぐらい行きますよってんで、じゃあボクは15枚食べたいなーと思ったんで、じゃあ75枚みんなで頼んで。これもインスタに上げてますけど。で、まあ7人で75枚の蕎麦を食べるみたいな。
出石って行かれたことある方はいらっしゃるかは知んないけど、結構昔の街並みが残ってて。城下町なんですけど、なんかすごいいい場所でした。で、そこにね、歌舞伎座の、歌舞伎をやってる永楽館という。もう100余年経っている建物があったんで、この永楽館ってところに行って。そこの館長さんにね、またお話を。なんかすごい面白いお話をされるので、2時間ぐらいお話を聞くみたいな。はい。
で、聞いてね、いま豊岡にあれなんですね、大学があるんです。新しく出来たんですよね、専門職大学が。アート・文化・観光だったかな…ちゃんと正式に言わなきゃいけないですね。えーっと…その大学があって、その先生方とね、歓談をするっていう。会食というか。そういうものをね。──芸術文化観光専門職大学ってのが数年前に出来てるんですね。で、そこの方のお話を聞いて。芸術と文化と観光についての専門職大学なんですって。うん。まあそういうのをやってみたり。で、明日はこうして、明後日はこうして…みたいなのがあるんですけど。まあどこまでボクが居るかはまだ考えてないんですけど。まあそんな感じでですね。まあ簡単に言うとこんないい歳したおっさんなんですけど、学生を満喫してるとも言えますかね。
自然と制約のある楽しい旅
でね。これ、やってみて…面白いなと言うか、いいなと思ったのって、旅って自由な方がいいじゃないですか。ところがねぇ、自由じゃないからいいなと思うときが合宿みたいなのってありますね。だからこうしたい、ああしたいみたいな、それぞれの意見がありつつ。こうすべきだ、ああすべきだみたいなのもあるし。当然予定の変更があった方がいいし。竹田城登るんだったら登って帰って1時間じゃ無理だから2時間、2時間にすると次のスケジュールが合いませんねーみたいな。そういう様々な…ねえ、スケジュールの変更みたいなものがあったときに──だから、もう、昨日、昨日の夜とか結構喧々囂々となってですね。だから…じゃあこの時間だったら間に合わないから予定を何分遅らせて。でも先方が待ってるからじゃあこのBパターンを作ってみたいなこととかを色々やったりするじゃないですか。それってボクなんかもね、仕事でテレビとかのロケハンとかロケとかの時に撮影の香盤表じゃないですけど結構やったりしますけど。明らかにそういうことが無くて、なんか好きなとこをぼーっと行くって旅より、ボクが仕事でロケとかロケハンで行っている旅ってそういうようなスケジューリングを組むじゃないですか…とか。今回のゼミ合宿みたいにある意味、束縛があるみたいなことの方がボク、はっきり言うと旅って楽しいんじゃないかなーっていう風に薄々感じてましたけど、今回久しぶりにそういうゼミ合宿みたいなのに参加して。
去年はだからコロナでなかったんですよ。去年度は。で、一昨年がボクが大学修士一年だったんで、それこそ2年前には長崎に行ったんですけど。それもね、ボクなんか普通なるべく段取りがいいコースで行っちゃったりするから、離れたところだとバスとかだとなかなか待たなきゃいけないからね、レンタカーとか借りちゃうんですよね。ところが3年前とか…だからまだ1年生だしね、皆さんに合わせなきゃと思って鈍行に乗ってったりとか。運行してる数時間に1本しかないバスみたいなのを待ったりするとかすると、バス停で1時間半ぐらい夏の暑い時に待ってなきゃいけないなーみたいな。それがまたなんか良かったりするんですよね。待たなきゃいけないじゃんみたいな。鈍行だからゆっくりだなーみたいな。ついバスでうとうとしちゃうなーとか。なんか皆さんと色々お話ししたりとか。それがなんかすごい楽しいなーなんて。うん。修学旅行っていうのとまたちょっと違うんですよね。うん。幾分みんな大人だからと言うか。この感じがすごいなんか楽しいなーなんて思った記憶があって。
だから去年はね、コロナで皆んな行けなかったみたいだから、今年はと思って。うん、ボクなんかむしろ積極参加で。うん、面白いですね。うん、だからこう…束縛というか制約みたいなものってのがある中でどうやるか?みたいなのって一つの…うん、面白さの要因なんだよなって。それってね、ほら、ゲームとかやる時も…ゲームって将棋でもいいですよ?歩は後ろに戻れないとかあるじゃないですか。という制約があるから成立するわけで。どの駒も縦横斜め、全部行けますよみたいなのだったらやっぱり将棋が成立しないじゃないですか…みたいに。だからあるルールの中で制約があるってことの方が実は楽しいんだよなーって思ったりするってことを今回再実感しましたね。
うん。なんかね、そういうことが知れるっていうのが一方で…だから、何て言うんですか?今回の旅で学んだ知ったことを”城崎に”て語るうちすると、やっぱりある一定の自然みたいなものを体内に、身体に入れないと人はやっぱりダメなんだなということ思ったっていうのが一つと。つまりそれっての旅を欲してるんだなっていう。うん。だから旅というのはした方がいいんだなと思う。で、もう一方で旅ってのは本当に自由な旅でもいいのかも知れないんだけど、束縛がある、なんか制約がある旅っていうにはそれ相応の意味があるんだよなーみたいな。ことを思いますね。強いて3つ目と言えば。…という合宿とか研修旅行みたいなことだから、先方にこういう感じで話を聞きたいっていう、つまりインタビューのアポを取ってるわけですよね。そうするとただの観光をしているとやっぱりただの観光だけだと、ただのゲストというか、ただ客観的にしか街を楽しめてないよなー…、まあ、体験するとか色々あるとは思うんですけど。ところがある…じゃあ文化施設とか、そこの担当者の方と1時間2時間お話しする機会があるって、客観的と言うよりむしろその方の主観みたいなものがすごい伝わってくるという意味で──それがね、普段の本当に観光だと話を伺いさせてくださいよと言ってもなんでお話ししなきゃいけないんですか?みたくやっぱりなるところが、やっぱり大学の研究、学習、教育の一環なんでってことで皆さん快くお話をして頂けるっていうね。それって素晴らしいプライオリティーだなとは思います。で、その素晴らしいプライオリティーだなってのは別に学生だから出来るわけじゃなくて、ボクもテレビ局にいた時とかはどっかに取材した時とかに普通ならカメラが中に入れないようなところも今回カメラがあるからOKですよみたいな特別な許可が下りたりして行けたり。ボクだから本当に…前も喋ったかも知んないけど、テレビ局入ったばっかの時に京都のあるお寺…竜安寺だ、竜安寺に取材に行ったら、石庭で有名な庭とは違う庭みたいな、今は公開してるか分かんないですけど当時はまだ公開してない庭があって。その庭とか案内して頂いたりとかね。これが普通に観光なら入れない場所にいるんだなって、これがテレビ局にいることの価値だなーなんて思ったんですけどね。別に今回も関係ないけどもやっぱり教育ってことでお話が聞ける。うん、そのライブ感みたいなのが感じられたのがなんか勉強にもなるし、普通に楽しいなーって思うみたいなね。うん、そんなことを感じた旅でした。
今書いて頂いてますけどね。「制約の中で思考錯誤するのも楽しいかもしれませんね」うん、そうなんですよね。だからトラベルはトレーニングだって言ってる方がいらっしゃって。ああそうなんだ、と。だからトラベルするというのはすごい快楽を追求するというよりは、…だって海外とか行ったら本当にそうじゃないですか。なんか盗まれるかも知れないみたいな危険な所は回避しようみたいなこととか。チケット買いたいけど言葉が読めないとか。結構トレーニングになるようなよね、だからそういうような意味がすごくあるんだなっていう。うん…そもそも思ってるんだけど。そんな感じってのが今回、教育の一環というのトレーニングっていうことだからすごく実感した旅だなーなんて思います。
死を記憶させる
うん、まあそんな感じなんですけど。それこそね、それがつまり4日からゼミ合宿に行ってますけど、行きの新幹線、京都まで行く新幹線ね、乗ってたらですね、パッとTwitter見たらね、ロシアがウクライナの原発を攻撃したってニュースになっててね。それはすごく色んな事を感じられたなって話を最後にしたいんですけど。で、ボクはそれを思った時に──ちょうどその時か…、その前日が新月だったんで、3月3日ね、ボクは色々思いが変わったのって東日本大震災の時だって話を書いたんですけど。その東日本大震災の地震と言うよりは原発の事故、爆破されている、原発のメルトダウンっていうか、あの映像みたいなものにすごいすごい衝撃受けた。死のリアルを感じだっていうことを書いたんですね。面白いですよね。原発の映像は映像っていう意味ではリアルじゃないんだけど、その映像というものでリアルな死を感じたっていう記憶があるっていうことを文章で書いたんですけど。ボク実は…だからこの4日の翌日のね、4日の新幹線に乗っている時に原発を攻撃するって言うニュースが流れた時に、またちょっとこの世が終わるというか、自分の身体の死みたいなものすごい感じたなあって思った時に、プーチンっていうのは、それはラテン語でメメントモリ、死を記憶せよみたいなね、言葉があるんですけど。メメントモリさせてんじゃねーかなプーチンは、と。この世界のあらゆる人間にって。…ちょっと思ったっていうことがあって。それをボクは文章で書いたので最後に読みたいんですけど。
memento mori 死を記憶せよ
今回のロシアの暴挙、プーチンの狂気、今朝の原発攻撃のニュース、この1週間のウクライナの状況で、個人的にはいろいろ気付かされた。
目が醒めた、目を醒まされたような感覚。
強くなければならないということを。
今を存分に生きるということを。
そして、memento mori 死を記憶せよ
ということを。
今までは、いい意味でも悪い意味でも、人生なんてぬるま湯に浸かっていればいいんだと(ちょっと)想ってた。
この世界はぬるま湯の世界でいい湯加減なのだと。
楽しければいいのだと。
でもそうしているうちに、狂気の施政者どもに煮え殺されてしまう。
memento mori 死を記憶せよ
あらゆる世界の困難さが自分自身に襲って来たとしても、
それを受け容れるだけの勇気を持つ必要があるということを。
memento mori 死を記憶せよ
っていう文章をね、書いたんですけど。うん。なんかね、ボクなんてすごい弱い人間なんで、何かあると落ち込んだりとか、大丈夫かなーみたく、まあ…分かんない、ボクだけじゃないかも知れないですけど、思った中で、もう圧倒的に大丈夫じゃないことが起こるとすると、もう圧倒的に大丈夫じゃない世界の中で些細なことで落ち込んだりしてる場合じゃないなっていう。うん、なんかいい意味にも…悪い意味と言うか、悪いことが起こって──(音声不良)──ってことかなと言うか。うん、なんかちょっと強く生きた方がいいなってね、あのプーチンの狂気の行動を…、うん。原発を攻撃?!みたいなのを聞いたときにね、じゃないと本当に殺されてしまうんだなって。それってだから自分が武力をつけて対決しましょうみたいなことでもないんですけど。なんか自分が日々のこととか、プライベートなのか仕事なのかでいちいちガチャガチャ落ち込んでる場合じゃないなっていう。世界が襲ってくる。そうするとこの話だって自分たちが核で死ぬかどうかってこともあるけど、単純に食べるものがなくなるみたいなことなんて本当にすぐ、数カ月後に襲ってくる可能性だってあるみたいな時に、うん…。という、絶対的な死の恐怖というのは常に持つべきだっていうメメントモリ的な事を感じたっていうか。感じられたというか。悪い意味でも良い意味でもと言うか。悪いことで良い…良いのか分かんないけど。その気概みたいなものを持つ必要があるんだなって思わされたと言うか。そんな1週間でございました。
「城崎にて」ってことで、今週のICUCを終わりにしたいと思います。また来週よろしくお願い致しまーす。おやすみなさーい(^^)

文字起こし後の文字寝かし
(好き勝手に思った感想を書き残しておくことを文字寝かしと言うことにしました)
いつも通り座っていても、寝っ転がっても、机に頬杖してるくらいかな。確かにあんなり変わらないけど、寝転がってるということは分かるから、なんとなく修学旅行の夜みたいな。同室の人と寝るまでお喋りする時間みたいな気がしてくる。
京都の琳派展って、確か警備の方が電話に出るご老人等々に注意してまわるんだけど、それが仕事なのは分かるけれども、もうちょっと言い方というか、周りの人が気持ちよく観覧できるような伝え方って出来ないものか?と抗議した…みたいな話が記憶にある。
去年だか一昨年だかに美術館を女性アイドルが紹介して来場者を増やそうとしたものの、すぐ中止になったことがあったと思うけど、撮影OKが定番になったのも、つまりはSNS拡散による来場者増加を狙ったものだと聞いたことがある。博物館や美術館によく行く人には当たり前なことなんだろうけど、美術館などは暗黙の了解が割とある。そこへ客足を増やすための策が重なり混乱を招いてる気がする。子供の頃によくわからない大人の集まり、大抵は親戚の冠婚葬祭だけど、そういう場で大人から何かを習うように、美術館や博物館の使い方も習えるようになるといいのにな。来場者増加のための妥協案を増やすのではなく。
合宿で喧々囂々…したことないな。合宿らしい合宿は小学生の時に通ってた水泳教室と、高校の授業でのスキー合宿のみ。大学時代はサークルの合宿はあったはたったけど、誰も行く気がないなら中止でいいだろうに開催だけは決定事項で、なあなあに進め、嫌々行ったり、なあなあの部分全てが悪い方向に行くばかりで泣いたり。今思い出すのも嫌なくらいだ。
でも今、行きたいと思う人と集まって行くのであれば嫌な思い出にはならないと思う。角田さんの言うように行き先で喧々囂々し、行き方でも喧々囂々し、それでも楽しくやれる気しかしない。少々嫌でもとにかく行くというのは高校までだったのかな、社会勉強的な意味で。大学生になったら行かないものは行かないと言うべきだった。辞めてしまったらサークルがなくなるんだとしても、それが申し訳ないと思うのだとしても、結局は自分が悪く思われたくないだけの見栄なんだから、そこで毅然とする練習…それが大学生のうちに出来ればよかったな。
撮影の香盤表。香盤表という単語を初めて聞いたし、なぜ香という字を使うのか気になりすぎた。つまり香炉の格子と表の格子が似ているからそう呼ばれるらしい。常香盤、香時計とも言うようで、香が燃えることで時間を測るもの。香道みたいなものの中に時間に関わる作法があるのかも知れないけど、骨董市などで常香盤を見かけたらお値段次第では買ってみたい。
3年前の長崎のゼミ合宿。そうか、あれはゼミ合宿だったのか。私はどうしてICUCに参加したのか本人もよく分かってない状況で、インスタで見て、なぜか里帰り的なものだと思い込み、最初のICUCの時に九州出身なのかと聞いた。そうか、ゼミ合宿だったのか…。
みんなで鈍行。自由な旅といいつつも、自分が行きたい場所があり、その目的地に行くには当然自分の使いやすい手段を使うわけで。それが複数人の、それがまた友人というわけでもない人たちとの集まり。だから考えたようなことがない目的地とか、使ったことがないルートを体験する機会になる。束縛というか制約みたいなものがある旅は、旅の美意識みたいなものな気がする。こうすれば簡単で早いんだけど、この仕上がりはどうしてもダメというか。例えば他人の価値観を作品を通して見ると、何重にもフィルターが入って、どこか自分の中にある価値観をベースに作品を見てる気がするけど、一緒に旅するのであれば、他人の旅の美意識を体験することになる気がする。理解しきれない部分も含めた美意識体験は自分の美意識の確認かも知れない。
今朝、漫画のセリフに「自然は芸術を模倣する」という台詞が出てきた。「芸術は自然を」ではないのはどういうことか?考えてみましょうという話で、つまり漫画の中では解答は出てこないので検索してみたところ…、面白い回答があった。
自然という計り知れない謎の多いものに対して、芸術が一つの見方を教えてくれる。芸術とは色んな役割?効能?があるけど、その中にそうした視点を示すことで日常を刷新することがある。そう考えてる方がいた。そうすると、旅は芸術風に考えると合作なんだろうな。
原発の映像はリアルじゃないけど、映像でリアルを感じる。こちらは「芸術は自然を模倣する」に近いかも知れない、芸術と言うより技術か。テレビを遡って行くとラジオ、電話、印刷、手書き、文字になるかと思うけど、人が人に伝えることが大元にあって、印刷が出来ることで手書き手紙の方向性の一部が断たれ、テレビが出来たことでラジオの方向性の一部が断たれ、一瞬で世界中に同質の情報を届けることはネットのものとなったから、テレビからはその方向性が断たれ、断たれると個性が濃くなる。合宿にも通ずる。転換点に来たので良い機会だから自分を見つめ直しましょうと言うか。人のフィルターを潰すほど大きな事件だったりすることも含め、出来るだけ人のフィルターを通さない素の情報の提供がテレビらしさの一部になっていくんだろうか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
