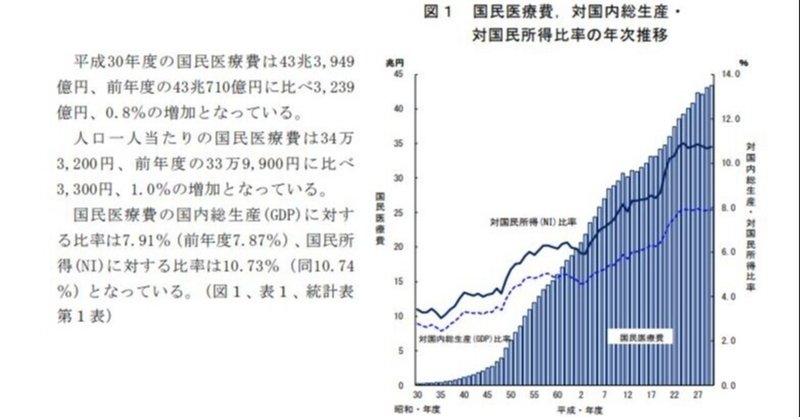
初めての 診療報酬改定レポート8 番外編 財政審より その2
*財政制度分科会資料一覧より 前回からの続き抜粋
こんにちは!須藤です。今回は前回に引き続き財務省の財政制度分科会資料抜粋となります。医療機関においてはコロナウイルスへの対応と全世代型社会保障改革の残された課題、製薬企業にとっては社会保障改革の課題と薬剤費の適正化が気になる所ですね!薬剤費適正化は厳しい内容が続くように思いました。
〇新型コロナウイルス感染症への対応
・医療提供体制強化のために8兆円弱の国債による支援を行った。
・R2年医療機関全体の減収見込み1.7兆に対し補助金措置額1.6兆とマクロ的には減収を補い得る額が措置された。→診療報酬不足は診療報酬で補う手法が自然であり、支援成果やコストが見える化できる。具体的には支援交付金に代え前年/前前年同月の診療報酬額を支払う手法を検討する。
・新型コロナに対応しない医療機関への支援は見直しが必要。
・コロナ感染症の医療法人の経営状況への影響把握→医療法人においても事業報告書等につきアップロードによる公表を可能とし、データベース整理を行うことで見える化を推進する。

〇全世代型社会保障改革の残された課題
・一定所得以上の後期高齢者の2割の患者負担→「所得基準」課税所得28万円以上かつ年収200万以上(施行日は令和4年度後半から) ・施行後3年間は3000円の上限措置。
・後期高齢者医療制度は広域連合が設置され責任主体が曖昧→ガバナンスを効かすため財政運営主体を都道府県とすることを検討する。 (国保では都道府県化を実施し医療費適正化が実効あるものと期待 下図)

・従来の医療費適正化はミクロ施策の積み上げ方式で住民健康保持を重視→医療費見込みが計画期間中更新されずPDCA管理が出来ない。
・データ分析業務の目的に医療費適正化を明示しデータ分析と活用を推進すべき。
・生活保護受給者を国保被保険者へ加入を検討する。生活保護受給者の平均通院日数の長い診療科の適正化や通院日数の長い地域の偏りがある。 ・精神病床の生活保護受給者長期入院も地域による偏りは8倍となり都道府県のガバナンスが医療扶助費の適正化になる可能性。

〇薬剤費の適正化
・新規医薬品の保険収載による財政影響は勘案されず予算統制の埒外となっている。→財政の予見可能性を損なう。

新規医薬品の薬価算定方式等
①類似薬効比較方式(Ⅱ)の新規性に乏しい新薬の薬価算定は、類似品に後発品が上市されている場合はその価格をと勘案する。
②原価計算方式の営業利益水準14.8%を適正化して薬価に反映させる。
(製造業平均の営業利益は4%台)
③有用性加算Ⅱから「製剤における工夫」などの加算からの除外。

既収載医薬品の薬価改定
・市場実勢価格を適時に薬価に反映させるため毎年薬価改定は完全実施を早期に実現する。
・加重平均調整幅2%についても合理的にあり方を見直す。

既存医薬品の保険給付範囲の見直し
・保険給付範囲を縮小する→既存薬の種類に応じた患者負担の設定、薬剤費の一定額までの全額患者負担等の手法を検討すべき。
・とりわけOTC類似薬の保険給付からの除外/縮小などを検討すべき。

後発医薬品の更なる使用促進
・バイオシミラーの使用を促す数量目標の設定やフォーミュラリの後発医薬品の選定基準設定などを検討すべき。

・大学の奨学寄附金と薬剤の適正使用の関係が注目され、疑念が生じないようにする必要がある。奨学寄附金については廃止含めたあり方を見直し、製薬会社からの資金提供の透明性を高める。
多剤・重複投与、長期処方への対応
・オンライン資格確認システムによる薬剤情報の活用から、診療報酬における多剤・重複処方について減算等の措置を拡充する。
・一定期間内の処方箋繰り返し利用制度(リフィル制度)の導入を図る。

・自殺対策は大きな課題であり、向精神薬の過量処方を問題視してきたが取り組みを強化すべきではないか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
