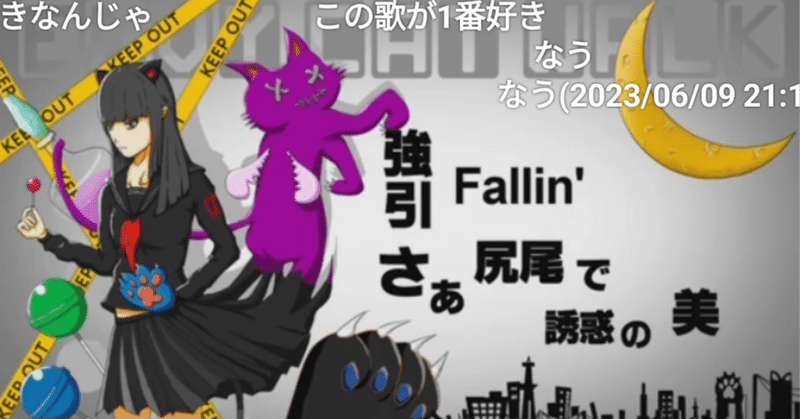
【歌い手史2011〜13】歌い手”第2の意味”の成立 りぶのヒット 「俺達の文化」の消滅【歌い手史を作るプロジェクト】
アンダーバーの「パンダヒーロー」騒動などで露わになった歌い手観の対立は、時を経るにつれて、徐々にその趨勢が明らかになっていく。
対立が顕在化し始めた2010、11年は、まだ両者は拮抗していた。ボカロ楽曲をシンプルに歌うばかりの歌い手もいれば、ネタ的な歌ってみたばかりを投稿する歌い手もいた。
両者が共存し、ある種の多様性があった。
しかし2013年ごろから、目に見えて均衡が崩れ始めた。
優勢となったのは——「ボカロ曲をいわゆるJ-POPのように歌うユーザー」の歌い手観だった。
◆新規層が求めたもの
10年、11年にはまだせめぎ合っていた両者だったが、13年にはボカロ楽曲をシンプルに歌った歌ってみたのヒットの方が増え始める。

「【ガチでFULL歌ってみた】紅蓮の弓矢 -進撃の巨人【あるふぁきゅん。】」など、「ガチ」を謳う歌ってみたのヒットも目立ち始めた。
こうした歌ってみたが優勢になる事情はいくつもあった。が、何より大きかったのは至極単純に、それを求める新規の聴き手の増加だった。
歌ってみたの人気はその誕生以後、右肩上がりに人気を伸ばした。時間が経つにつれて新たにネットに参入し始めた10代後半を中心に聴き手を増やし、2007、8年とは比べ物にならないほどの活況を呈していた。
従来から歌ってみたの界隈にいたユーザーたちは、その盛り上がりを喜んだ。「俺たちの文化」である歌ってみたがますます盛り上がってきた、と自信を深めた。
しかし、こうして新たに参入した若い聴き手が求めていたのは、かつての歌い手とは違った。ニッセイ基礎研究所の廣瀬涼はこう指摘する。
「CD音源などをそのままアップロードすることは著作権の侵害となり投稿が削除されることが一般的であるが、カバーソング(歌ってみた)としてアップロードされた曲は二次創作として認められ、投稿削除がされにくい。そのため、本家が歌った曲の代わりに歌い手が歌ったバージョンが聞かれることも多かった。併せてニコニコ動画の音源だけをMP3データとしてダウンロードし、スマートフォンで聞くと言う行為も横行していた。音楽コンテンツという位置づけであった「歌ってみた」においては、好きな歌い手の音楽をダウンロードし、ニコニコ動画を開かなくとも(インターネットがない環境でも)楽曲を楽しむユーザーも多数いた」
新たに参入した聴き手たちが求めたのは、従来のアレンジ過多な歌い手ではなく、一般的なアーティストの代替としての歌い手だった。
当時、新たに歌ってみたの聴き手として参入したとされる10代後半の若い層は、音楽の過疎のもとに生きていた。
10代後半では金銭的余裕も無く、音楽を購入する機会は限られる。ネットで音楽を聴こうにも、レコード会社がネットに否定的な立場をとっていたため有名楽曲は配信されていない。
彼らが歌ってみたを求めたのは、その代替としてだった。
歌い手たちの人気の伸びを支えたのは、一般的なアーティストに触れることが出来ない層の、その代わりとしての需要だった。
一般的なアーティストの代替である以上、彼らが求めるのは「楽曲を2ちゃんねる的価値観に沿うように歌うユーザー」か「ボカロ曲をJ-POPのように歌うユーザー」か。
——当然、一般アーティストに近い歌い方の歌い手、つまり、ボカロ側が求める歌い手像と共通した歌い手を彼らは求めた。
ネタ的なものなんてお呼びじゃない。
もっと音楽プレーヤーで普段から聴けるようなものを。
そういう感覚で、彼らは歌ってみたを聴いていた。
それはボカロ側が求めた歌い手像——シンプルにボカロ曲を歌う歌い手と合致していたし、その人気を押し上げる主要因になった。
もちろんのこと、従来からの歌い手観を持つ層は、この傾向に反発した。
こんなのは俺たちの歌い手ではない。
アイドルみたいなもんじゃないか。
自分たちが考える歌い手観に合致する歌い手を称揚し、これこそが本流だと主張した。あのときの祭りのような感覚こそが歌ってみたにとって大切なんだと、彼らは口にした。
自分たちの文化だと思っていたものが塗り替えられていく様に、彼らは我慢がならなかった。「俺たちの文化」が簒奪されることが、許せなかった。
だが、抵抗は無力だった。
かつてのような歌い手を求めるユーザーは、2012、3年には、既に少数派に転落していた。ファンの入れ替わりが激しいネットコンテンツの例にもれず、最初期からのファンより新たな歌い手ファンの方が、圧倒的に数が多かった。
多数派の声の前に、彼らの声はかき消された。
そして、こうした新旧の価値観の対立は、新たな歌い手観に沿った存在——“りぶ”のようなユーザーたちの台頭によって終止符が打たれるに至る。
◆りぶの台頭
りぶはまさに“アーティスト然”とした歌い手だった。

2010年にデビューしてヒットを連発し、2015年に唐突に活動頻度を落とす。
投稿する歌ってみたには、ネタ的な要素を入れない。「彗星のような——」という二つ名を送りたくなるほど鮮烈で、ミステリアスで、アーティスト然としていた。
彼が歌ってみたに出会ったのは、2007、8年頃のことだった。
「『動画に文字が流れる面白いサイト』というような認識でした。“歌ってみた”に出会ったきっかけは、halyosyさんの『メルト』でした」
だが、この時すぐさま歌い手として活動しようとは思わなかった。当時の彼が中高生だったという事情もあるだろうが、歌ってみたが彼の期待に沿うような空間ではなかったことも関係しているのだろう。
ニコニコ動画に出会う前から、りぶは音楽に触れて育った。
幼少期にはピアノを習っていたという。一度は辞めてしまったものの、高校入学と同時にバンドを結成し、今度はギターをやり始めた。
とくにいわゆる一般的なバンド然としたものが好きで、Bump Of ChickenやUnison Square Gardenなどをよく聴いていたという。
そういう彼にとって、当時の界隈は期待に沿うものではなかったはずだ。
07、8年ごろの歌ってみたのヒット作では、「2ちゃんねる的価値観」に沿うネタ的な歌ってみたが主流で、シンプルな歌ってみたは少数派だった。
だからこそ、すぐさま飛び込みたいという気持ちにはならなかったのかもしれない。
しかし、数年が経つと、心境が変化し始める。
「高校くらいから、歌というのは僕にとって一番の趣味でした。その歌がもっと上手くなったらもっと楽しいんじゃないか、じゃあ上手くなるにはどうしたらいいんだろう? そのためのツールとして始めたのが“歌ってみた”でした」
彼が歌い手として活動を始めた2010年は、シンプルな歌ってみたが大きく大きく人気を博し始めていた時期に当たる。
ボカロ側が望むような歌い手が増え始め、メジャーデビューを果たし始めてもいた。
りぶの眼には、その光景が魅力的に映ったに違いない。
以前に比べ、もっとシンプルな歌ってみた、自分がやりたいような歌ってみたが人気な場所。それは、自分の修練のために適した空間に映っていた。
2010年5月23日、りぶは「Marygold 歌ってみた【りぶ】」を投稿して歌い手としてデビューを果たす。
そして月に2、3本アップしたりもしながら、歌ってみたを投稿し続けた。
シンプルな歌い方は目立つものではないため、「いきなり大人気!」とはなりにくい。だが着実に、人気を積み重ねていった。
そして約1年後、彼は飛躍を果たす。
2011年10月24日。りぶは自身21作目の歌ってみたとして、ボカロ楽曲『エンヴィキャットウォーク』の歌ってみたを投稿する。

原曲はボカロPトーマが10月24日に投稿したボカロ楽曲で、原曲投稿からわずか2日での投稿だった。
これが記録的なヒットになった。
まずは当日のカテゴリランキングで12位にランクイン。翌日のランキングではランキング3位&1万マイリストを達成。
その後も伸びを維持し続け、翌12年の7月、投稿から1年を待たずして100万再生を達成。
ニコニコ動画の歌ってみたとしては、異例のハイペースだった。
これを機に、りぶは一気に飛躍を果たす。これ以降、りぶの歌ってみたはミリオンヒットを連発するようになり、2012~14年にはもっとも人気の歌い手の一人に数えられるようになる。
のちのライブ時のインタビューで、りぶはこう述懐している。
「いちばん大きな変化をもたらしてくれたのがこの曲で。多くの人に自分のことを知っていただけたり、大きな会場でライブをさせていただけるきっかけになったのは、やっぱり『エンヴィキャットウォーク』だった気がする」
◆「俺たちの文化」を愛した者たち
りぶのような歌い手が人気を集めるさまは、時代の変化を映し出していた。
それが大勢に影響を与えたわけではないが、ボカロ側が求める歌い手像「ボカロ楽曲をいわゆるJ-POPのようにに歌うユーザー」に沿った歌い手が圧倒的な人気を集めるさまは、時代の変化を表していた。
当然ながら、かつての歌い手観——2ちゃんねる的価値観に沿った歌い手を求めるユーザーたちは反発した。
何もわかっていないくせに。こんなのは歌い手じゃないんだ。
彼らは反発するしかなかった。あのときの祭りのような、俺たちの歌い手が変わっていくさまが、どうしても許せなかった。
しかし徐々に、否が応でも敗北を認めざるを得なくなる。
りぶをはじめとした新世代の歌い手の活躍を目にして、もう時代は変わったのだと認識させられる。
もう俺たちは少数派なのだと悟り、彼らは失望した。それほど明白に、時代は移り変わっていた。
もう「俺たちの文化」である歌い手が返ってこないと悟り、彼らは嘆いた。
「昔は、何やっているんだかわからないクオリティーの低い動画でも、おもしろさを見つけ出して、コメント職人が動画に落書きしたり、その動画をネタにして他の動画がつくられたり、みんな盛り上げていこうとする感覚があったと思うんですよ。だけど今は、最初からおもしろいもん持ってこい! っていう状況になっている。それが、なんだか悲しいというか、辛い感じがしています。みんな見ていて楽しいのかな、と」(歌い手・アンダーバー)
「プロに近づき過ぎていて、そもそもの魅力だった“いい意味での素人っぽさを形にする場”ではなくなってきている。完成された綺麗な動画しか観ない世界になってしまって、ふざけた動画は投稿しにくくなったなって」(歌い手・ぽこた)
ある者は界隈から離れ、歌い手のファンを辞めた。
07、8年ごろが全盛期だったな
今はつまらなくなった
またある者は憎しみを募らせ、歌い手のアンチとして活動し始めた。
あんなのアイドル(笑)じゃん
歌い手が歌い手さまになったから叩くんだよ
残ったわずかな者も態度を硬化させ、過激派のごとく「歌い手の伝統に敬意を払え」と主張するようになった。
過激な人間の言うことなど誰も聞くはずなく、ますます孤立を深めていった。
かくてかつての歌い手観を持つ者たちは次々と歌ってみたの界隈を後にし、歌い手という肩書の第2の意味「ボカロ曲をいわゆるJ-POPのように歌うユーザー」が成立するに至る。
当時の記事では、こんな風に書かれている。
「生身の人間がボカロ用の曲を歌い演奏する『歌ってみた』『演奏してみた』というジャンルも人気で、彼らがステージに上がるイベントも生まれた」
もっとも、こうした認識が成立することは、当時の大多数の歌い手たちにとって悪いことではなかった。
ボカロ文化の一端として自らの人気も高めることが出来るし、音楽レーベルの注目も集められる。2010年代初頭はボカロブームが起こっていたから、なおのことその効果は高かった。
大多数の歌い手には積極的に反発する理由は無かったし、そもそも当の歌い手たち自身にも「ボカロ曲をいわゆるJ-POPのように歌うユーザー」という認識が共有されていた。
それを嘆いたのは、ごくわずかな人間だけだったのだった。
そしてボカロ曲を歌わない歌い手なんていくらでもいた、という事実は忘れ去られるに至る。
歌い手の新たな意味が誕生した瞬間であり、かつての歌い手が失われた瞬間だった。
次回→【歌い手史2011〜13】歌い手はボカロと手を取り合った ”兼業クリエーター”の時代【歌い手史をつくるプロジェクト】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
