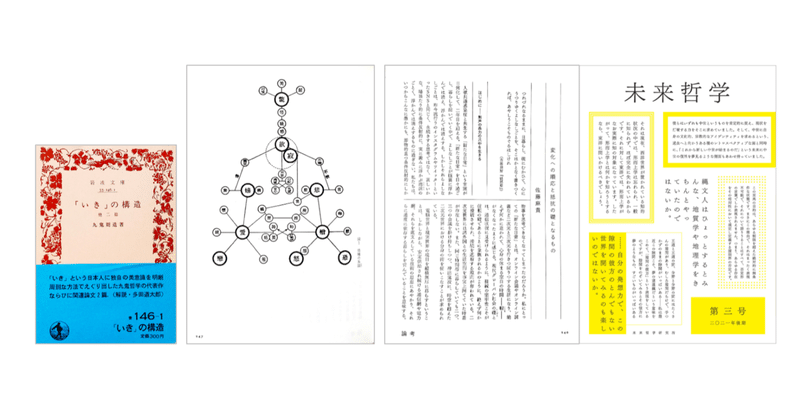
佐藤麻貴「変化への順応と抵抗の礎となるもの」((『未来哲学・第三号』)・九鬼周造「情緒の系図」
☆mediopos2653 2022.2.20
現代社会のシステムは
「無声の暴力」に満ちている
その暴力とは「正しさ」であり
その「正しさ」によって人は縛られ
管理社会化が進んでいる
もちろんその「正しさ」なるものは
管理に都合の良い「正しさ」であって
公の見解として「正しい」とされているがゆえに
それに「抵抗」することは難しくなる
そんなとき
声高に唱えられる「正しさ」に対して
そのアンチとしての別の「正しさ」を対置しても
善悪の二項対立構造を強めるばかりだ
いま必要なのはそうした「正しさ」の
「根底にある源泉を捉え」
そこで生まれている「無声の暴力」に
耳をすませてみることだろう
「正しさ」は理性的な論理によって
支えられているように見えながら
その実その根底にあるのは人間の情緒に他ならない
しかもその情緒は自覚的でないが故に多くの問題がある
『未来哲学』の第三号に収められている論考
佐藤麻貴の「変化への順応と抵抗の礎となるもの」では
「人間性の人間らしい振る舞いの根源」は
「理性よりも感情や情動に由来する」という視点から
九鬼周造の「情緒の系図」がとりあげられている
(岩波文庫に『「いき」の構造』とあわせて収められている)
「情緒の系図」は「喜怒哀楽欲」という五情を土台に
歌を手引きとした人間の情緒について論じられているが
佐藤麻貴はその「情緒の系図」を参考にしながら
「友情」という「他者への関与の在り方の形態」を
「無声の暴力」に対する「小さな抵抗」として論じている
九鬼周造の「情緒の系図」はたいへん興味深く
九鬼周造による「図」とともに
それについての簡単な説明を引用してあるが
ここでは九鬼の「情動を通した、関わり方の論理」を
「友情」に当てはめて論じられている
それは自己と他者との間に芽生えてくる
能動的でありまた受動的でもある関係性である
「友情という情動に根差した情愛を通した
関与の在り方が拡大されていけば」
「人間と人間、また人間と人間以外の他者との
共生の模索可能性への道のりが、
関与の在り方を通して開いていく」のではないかという
「正しさ」からは「友情」は開かれない
「「愛」に付随する楽、喜、懐、親、恩の情」もなく
もちろん「自由」の可能性もそこにはない
「無声の暴力」としての「正しさ」に
「抵抗」して生きるために必要なのは「友情」であり
ともに生きともに関わりともに喜ぶ「情緒」なのだ
数学者の岡潔のいう「情緒」も
おそらくどこかでそこにつながっている
■佐藤麻貴「変化への順応と抵抗の礎となるもの」
(『未来哲学 第三号 二〇二一年後期』
未来哲学研究所 ぷねうま舎 2021/12 所収)
■九鬼周造「情緒の系図」
(九鬼周造『「いき」の構造 他二篇』岩波文庫 1979.9所収)
(佐藤麻貴「変化への順応と抵抗の礎となるもの」〜「はじめに−−無声の暴力の只中を生きる」より)
「無声の暴力とは、現代の社会システムそのものである。現代社会は倫理や道徳が声高に唱えられ、人権に代表される権利、気候変動やプラスチックごみなどの環境問題や持続可能性をはじめ、さまざまな分野に亘る問題が露呈され、問題提起されている。それらは、みな、一般的に正義論と言われるように、ある意味で「正しい」論理なのだ。しかし、未来哲学が捉え、論じるべきは、そうした表象に現れている問題一つ一つと、それら問題を捉える正しい論理の「正しさ」を吟味することではないはずだ。私たちに課されているのは、その「正しい」とされる「正しさ」を生み出す、表象として現れる諸問題の反転作用の向こう側、すなわち「正しさ」の根底にある源泉を捉えることではないだろうか。つまり、私たちの課題とは、捉えどころのない、現代の社会システムそのものの、無声の暴力の聞こえぬ「声」に耳を澄ませ、捉えどころなく、捉えどころが無いからこそ「見えない」問題の本質を見定めて、身を潜めて隠れているビヒモスを焙り出し続けていくことにあるはずだ。それは、従来通用していた方法論のように、安直に善悪という二項対立構造を作って分類したかのように錯覚し、悪と見定めたものを糾弾し排除しようと試み、また糾弾された対象が排除されてゆくような安易なものではない。脱構築という哲学的手法ですら、脱構築したにもかかわらずバラバラに解体したリバイアサンの影に怯えている。永遠と繰り返し脱構築を強い続ける哲学的方法論は、もはや届かない。
資本主義システムという、人間の欲望の肥大化を留まることを知らずに助長するシステムを糾弾したり、民主主義システムに隠された功利主義的な最大多数の最大幸福の追求という問題の根底として見定めたりしても、容易に届かない何ものかに、いよいよ私たちは対峙し、根底から問い直していかなくてはならない。では、そのビヒモスやリバイアサンを生み出す正体とは何か。それはやはり、人間、そのものであると、私は思う。人間の生まれ持った性(サガ)を見極め、見定めた上で、社会システムの舵取りをどうするかが問われている現代ほど、人間性が躍動する時代は無い。理念をお題目や念仏のように唱える時代は終了し、いよいよ、論ずるだけではなく、関与し行動する哲学が求められている。」
(佐藤麻貴「変化への順応と抵抗の礎となるもの」〜「3 友情という関与について/敵を探すよりも、情動を発揮せよ」より)
「国際社会における問題の対処法につき、我々は新しい対処の仕方、あるいは新しい回路を発明しなくてはならない。グローバルからローカルまで重層的に連関するネットワークが構築してきた堅牢さがほころびる時、私たちは何を意識している必要があるだろうか。トマス・カスリス氏は、日本哲学の本質を「関与する哲学」であると指摘している。形而上学的、観念的な考察を深める西洋哲学に比し、日本哲学は空海や道元に見られるように、形而下、すなわち身体を通した実践哲学であり、そうした点において切り離された知(detached knowing)ではなく、関与する知(engaged knowing)を通した哲学ではないだろうか、という指摘である。」
「関与の仕方を考察するに当たり、人間性の人間らしい振る舞いの根源となるものは、一般的に理性よりも感情や情動に由来すると思われる。人間の情緒を五情として喜怒哀楽欲が挙げられる。九鬼周造は、人間の人間性を考えるに当たり、五情を土台に歌を手引きとした人間の情緒について「情緒の系図」を図示している。九鬼は「欲」と「寂」を個的存在としての人間の中核に据え、その上部には、「嬉悲愛憎」を四つの中心として、快不快の感情を展開している。九鬼は、感情を快不快という対立構造において分類するが、最も主要な情緒は「嬉しい」と「悲しい」であるとしている。「善」という意識は「嬉しさ」を起こすのに対し、「悪」という意識は「悲しさ」を起こす。人間性を考察するにあたり九鬼の示した「情緒の系図」を参考に、快に分類される「嬉」と「愛」に付随する楽、喜、懐、親、恩の情から、他者への関与の在り方の形態として、(・・・)私自身の経験から友情について考えてみたい。」
「九鬼はスピノザを引きながら、「嬉しさ」とは精神が一層小さい完全性から、一層大きい完全性に移ることと分析し、「悲しみ」はその反対で、一層大きい完全から一層小さい完全に移ることを指すとする。また、「〔嬉しい〕とか〔悲しい〕とかいう情緒は、心の内奥に深く感じられる感情」であるとし、それらが「外部へ向かって方向を指示された場合に、〔喜び〕とか〔嘆き〕という様相を取ってくる」としている。一方、「嬉しさ」は受動的であり、「喜び」とは能動的であるが、「嬉しさ」とはもともと興奮的な情緒であるから「喜び」に展開しやすいとも指摘する。(・・・)
九鬼は情緒の重層構造のみならず、時間的、空間的契機についても考察を加えている。「嬉しい」ことの末梢形態は「楽しみ」であるが、九鬼によると「たのし」とは天照大神が天岩戸から出た時に諸神が「手伸(たの)て」喜び歌ったところから由来するため、「手を伸ばす」という空間的な意味と、未来に向かって手を伸ばす時間的な意味あいを持つと分析する。「楽しい」とは、未来げの展望を内包しているものでもあるらしい。「嬉しさ」とは発散すると、「笑み」や「笑い」へと爆発していく。また「うれし」とは「心(うら) - 愛(は)し」から転じたものであり、時間的性格が含意されているものに「親しみ」が発露する。つまり、対象と過ごした時間が、ある一定期間を超えると情の濃度が高まり「親しい」という感情が生じてくる。それに従って、対象の時間的非存在に対して「惜しい」という感情が生まれる。九鬼によると「愛」はその背景に消滅を予見する限り「嬉しい」感情だけではなく、「悲しい」感情が含まれるため、全体としては「愛(かな)し」という全体感情の中に「悲しみ」という部分感情が含まれているものだと分析する。時間的契機を中心に考えると「親しさ」は現在的感情であるが、「親しさ」が過去を回顧する時「懐かしい」となり、未来性を帯びて未来に「親しさ」を求める時には「恋しい」となる。」
「上に見てきた愛憎の時間的、空間的規定のみならず、九鬼は更に次の三つの項目についても、愛憎につき、それぞれ検討を加えている−−−−対象そのものの一般的存在性格に規定されているもの、対象の特殊的作用に規定されているもの、対象の所有性格に規定されているもの。「愛」の様相で見ると、対象の存在性格が自己と比較して大きい場合には「畏れ」、自己と比較して小さい場合には「労わり」や「憐れみ」という「優しさ」の主観的感情が芽生える。これに対し、「憎」の様相の場合、対象が自己よりも小さい場合には「蔑み」になるし、自己よりも大きい場合には「諦め」の感情が起こる。他方で、特殊的作用に注目する場合、愛が与えられた場合に愛を以て反応するのが感謝の情である「恩」であるし、憎が与えられた場合に憎を以て反応するのが「怒り」である。最後に、対象の所有性格に規定されたものとして、自己の所有物が愛すべきものであれば「誇り」の感情が起こるし、「誇り」が持続し変質すると「高慢」となると分析されている。」
「九鬼が示していたのは、情動を通した、関わり方の論理である。九鬼の考察を友情に特化し当てはめてみると、友情とは、手で触れ合えるという身体性とこころの働きである情動の双方が、相互作用的に空間と時間という所与の偶然性の只中において、自己と他者との間に能動的、受動的に芽生えてくる関係性なのであろう。友情には、その人と出会うという偶然性に加え、情動に根ざした因果的な関係性が含意される。因果的な関係性とは、互いに関与し、互いに影響を与え合う、九鬼によると、それが「愛」から始まるものであれば「愛」によって返礼されるが、「憎」を契機としたものの場合には「憎」や「憎」の派生感情によってしか反応されないということだ。何故なら、九鬼の分析ではそれら「愛憎」の情動は表裏一体の構造を有しているからだ。
(・・・)九鬼の情緒の系図によると、「愛憎」とは確かに表裏一体の感情ではあるものの、「愛」をもって汝に接することに徹すれば、「愛」か「愛」の派生感情がブーメランのように我には再帰するはずである。「愛」の派生感情を送ったにも拘わらず、何らかの論理構造の歪みに起因した「憎」の派生感情が返礼されない限り、所与の空間と時間という偶然性の中で、国境や性別、年齢などの差異を超えて、友情は生まれるはずである。(・・・)
見えない仮想敵であるコロナウイルスや、人間の行為の結実である気候変動に対し、対立構造を基底とした上で、不用意にも仮想的な開戦を一方的に宣告し、「人類が一丸となって闘いを挑みましょう」というプロパガンダを提示せずとも、また、差別や差異に注目して新たな仮想敵を敢えて探さなくとも、友情という情動に根差した情愛を通した関与の在り方が拡大されていけば、人権の拡大解釈の史実が示すように、人間と人間、また人間と人間以外の他者との共生の模索可能性への道のりが、関与の在り方を通して開いていくのではないだろうか。そうした新たな道のりが開かれる時、人類は複数の尺度と価値の重層性を、隣人への関与の在り方を通して、諸問題への新しい関わり方の論理と倫理を手に入れることができるはずだ。つれづれなるままに思う時、無声の暴力と変化の只中を生きる私たちが再認識すべきなのは、友情という関与的な在り方を通した、闘争への小さな抵抗である。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
