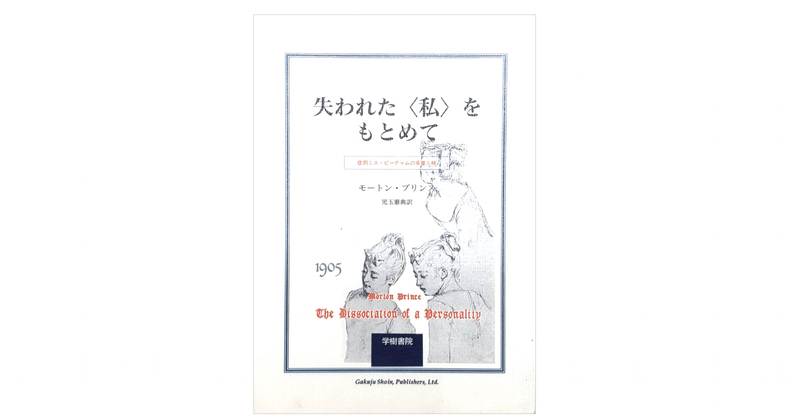
モートン・プリンス『失われた〈私〉をもとめて―症例ミス・ビーチャムの多重人格』
☆mediopos2752 2022.5.31
テレビドラマ化された田村由美原作の漫画
『ミステリと言う勿れ』には
解離性同一性障害の人物「千夜子」が登場し
その千夜子が生み出した別人格
「ライカ」を演じる門脇麦の演技は
いまも印象に残っている
あくまでも創られたキャラクターなので
実際の解離性同一性障害の現象とは
ずいぶん異なった演出がなされてはいるだろうが
わたしたちはふつう
じぶんはじぶんだと疑わないで生きているものの
じっさいのところ
そうした人格の統一性というのは
極めて疑わしいところがあり
多重人格的な現象の実際の症例などを知ると
知らないだけでじぶんのなかにも
いろんな人格が隠れているのではないか
そんなことを考えざるをえなくなる
本書は一九〇五年に初版が刊行された
多重人格に関する研究書で
一八九八年に神経衰弱の症状を訴えて
精神科医である著者の診療所を訪れた
二三歳のカレッジの女子学生ビーチャムの
六年間(一八九八−一九〇四年)にわたる記録である
著者が催眠を用いた治療を開始すると
ビーチャムとはまったく別のタイプの人格があらわれ
独立した個性を主張するようになり
「自分はサリーである」という
ビーチャムは信心深く真面目で良心的な性格だが
サリーは陽気で活発で悪戯好きな「小悪魔」であって
ビーチャムを苦しめるようになる
ビーチャムはサリーについて何も知らないが
サリーはビーチャムのことなら心の隅々まで知っている
著者はサリーを再び意識下へ戻す治療を開始するが
今度はビーチャムでもサリーでもない
情感豊かで健康的な第三の人格が登場してくることになる
そして著者はこの第三の女性こそが
真のビーチャムだったのではないかと考えはじめる…
じぶんの知らないじぶんというのは
だれにでもある程度は存在しているが
じぶんがじぶんだと思っているじぶんは
じぶんだとは認めたくないじぶんを
見ないようにして生きているところがある
そしてその見ないようにしているじぶんを
統合しようとする第三のじぶんというのがいて
そこで魂の葛藤が多かれ少なかれ起こってくる
じぶんとは認めたくないじぶんが
たくさんいればそれだけ多重人格が隠されていることになる
そしてひとつに統合することもそれなりにむずかしくなる…
『ミステリと言う勿れ』の「ライカ」の話を読んで以来
多重人格の研究で有名な本書を読んでみようと思っていたところ
古書店に寄ったときにちょうど入荷したばかりだった
こうしたことはわりとよくあるけれど
ある種のシンクロニシティにしても
それは魂の統合のためのひとつの働きでもあるのだろう
魂はじぶんの内的な働きだけではなく
偶然のように外から働きかけられるものでもあるのだから
■モートン・プリンス(児玉 憲典 訳)
『失われた〈私〉をもとめて―症例ミス・ビーチャムの多重人格』
(学樹書院 1994/9)
(訳者による「序」より)
「この本は私にとってなにやら一生涯の課題と成った思い出の本である。(…)一人の女性が、体は一つで、それがある時はクリスティン・ビーチャムであり、ある時はサリーに成る。そのうちに三人目のビーチャムが登場し、同じ一つの体を三人がとりっこする。人格分裂とか自我分裂とかいわれている異常の、生きた実例である。」
(本文より)
「本研究の被験者ミス・クリスティーン・ビーチャムは、自分のなかにいくつかの人格が発達した女性である。ときおり彼女の人格は変化するのであり、しかも短時間のうちに変化することもよくあり、おのおのの変化とともに性格が入れ替わり、記憶が交代するのである。彼女は、真の自己あるいは本来の正常な自己、つまり生まれついての自己、彼女の本質とされる自己のほかに、三人の異なる人物のいずれになることもできた。三人の異なるというのは、身体はおなじでも、おのおのがはっきりと異なる性格をもっているからである。その違いは、異なる思考、異なる見方や信念、理想、気質、また異なる学習や趣味、習慣、経験、記憶によって示される。おのおのはこれらの点で他の二人と、また本来のミス・ビーチャムとも異なっている。これらの人格のうちの二人は、互いについて、あるいはもうひとりの者について、推測するか間接的にえる知識以外はなにも知らない。したがって、これら二人のおのおのの記憶には、他の者が生きている時間に相応して空白がある。ふいに二人のどちらかが目覚めてわれに返ると、その人物は、自分が一瞬どこで何をしたか言ったかを知らない。三人のうちのひとりだけが他の二人の生活について知っており、またこのひとりは特別変わった性格を示し、個性という点で他の二人とはかけ離れているため、他の人格からこの人物への変化は、この症例の最も驚くべき劇的な特徴のひとつとなっている。それぞれの人格は万華鏡を見るかのように入れ替わり、しばしばその変化は一日のうちに生じる。こうして、つぎのようなことが起こる。つまり、ビーチャムは、もしもこの名で何人かの別個の人を指すとすれば、あるときはわずかまえには最も強く反対したことを主張し、行い、計画し、手配し、一瞬前にはみずからの理想にとり厭わしいっものだった趣味にひたり、また、ついいましがた熱心に計画し整えたものを取り壊すのである。
(…)
ビーチャムは、スティーブンソンの想像の所産の、実人生の一例である。ただこういえるんは嬉しいことであるが、ハイド氏のごとき人間の本性の邪悪な側面は、彼女の性格にそれに相当するものがみられない。この人格の分裂は倫理面のものではなく、知的、気質的な面でのものである。それぞれの人格の性格は著しく異なるが、その違いは気分や気質や趣味の面でのものなのだ。おのおのの人格は他の人格に対して悪をなすことができない。
一般にこの種の症例は、出現する人物の数によって「二重人格」とか「多重人格」として知られるが、もっと正確な術語は、解体された (disintegrated)人格である。なぜなら、おのおのの副人格(secondary personality)は正常な自己全体の一部でしかないからである。どの副人格も、その個人の精神生活の全体を保持してはいない。その人の自我として知られる本来の意識の統合(integration)はいわば崩壊し、その記憶や知覚や獲得や環境への反応様式などをいくぶんなりとも失っている。それでもまだ存続する諸意識状態が、それら自体のあいだで統合されて、独立した活動が可能な新たな一人格を形成する。この第二の人格は、その本来の解体されていない人格と、ときおり交代するかもしれない。その本来の人格のさまざまな裂開線にそう解体(disintegration)によって、いくつかの異なる副人格が形成され、それらが互い交代するかもしれない。また、その崩壊において、その新たな人格の統合の際に退けられるいくつかの意識状態がその新たな人格の外側に、それ自体が統合されて残存し、こうして第二の、同時に機能する意識を形成するかもしれない。これが潜(在)意識(subconsciousnss)と呼ばれるものである。こうして、さまざまな副人格が、本来の正常な人格の解体によって形成されることがわかるだろう。こうしたかたちで使われる解体という言葉は、ときに変性(degenetaion)という意味で用いられる解体と混同してはならない。後者は、破壊された心もしくは気質的な障害のある脳を意味している。変性は正常な精神過程の破壊を意味しており、狂気と等しいといってよいだろう。他方、多重人格をもたらす解体は、正常な自己を構成する複雑な構成体の、ひとつの機能的な乖離(dissociation)であるにすぎない。その基本的な精神の諸過程は、それ自体は正常なものであり、ふたたび正常な全体へと連合されうるのである。
解体された人格もしくは多重人格の症例はずいぶん報告されており、真実そのような現象があることも、それが生じるその基礎にある一般的な原理も、疑問の余地なく確かなものになった。これまで研究され報告された例では、それぞれの精神状態の複雑性やそれぞれの人格の独立性はさまざまである。単純なかたちでは、副人格は、高度に統合された「自動症」現象もしくは催眠現象によって示され、また、いわゆる自動書記や類似の現象をとおしての潜意識の状態としてのみ、あるいは他には催眠状態としてのみ認められる。筆者が報告した症例R夫人の「マニー」と呼ばれる状態、またピェール・ジャネが記載した症例B夫人のレオンティーヌとレオーレの状態が、このような単純なかたちの例である。
もっと完全に発達したかたちでは、副人格は霊媒のトランス状態とおなじである。(…)この種の人格の外的生活は、それが主意識とは独立に営まれるかぎり、極度に規制されたものであり、いわゆる「降霊術の会」の経験にかぎられる。そのような人格は、通常の人間の能力をもつ点では完全であるが、どの人間ともおなじく仕事をし、行為し、遊ぶ人という点では、自律性は甚だ乏しい。そのような人格がどれほど社会生活のあらゆる機能を営み、みずからを環境に適応させうるかは、疑問である。催眠状態、つまり人為的に誘導されたタイプの解体は、かりにあるとしてもじゅうぶん完全なことは稀であり、真正な人格を構成する、環境へのじゅうぶんな自発的順応性をもたない。」
「ビーチャムは、多くの歳月さまざまなかたちで観察されたため、友人やとりわけ彼女に関心をもつ者たちに、よく知られるようになった。彼女は、七年以上、つまり一八九八年の初期以来、著者の専門的な保護化にあった。彼女は、この間のほとんどにおいてたえず観察されたのであり、長期間毎日観察されることもあった。
(…)
わたしが最初に知ったビーチャムだけが、少人数ではあるが教養ある人たちのサークルで知られた女性であり、その人たちを彼女は心配させるにいたったのである。(…)ビーチャムを語る際には、あるいは彼女のことにふれるときには、いつもこの名は、他に修飾がなければ、この最初のビーチャム、最初に観察された人物を指すことにしよう。のちには、簡単にするために、また他の者と区別すために、彼女にBⅠとも名づけた。他の人格や催眠下の自己は、それぞれが出現したときに、BⅡ、BⅢ、BⅣなどとした。このようなあまりスマートでない名称を用いたのは、さまざまな現象が完全に研究されるまで、どんな仮説にも肩入れするのを避けるためである。
(…)
過去六年間(一八九八−一九〇四年)、この三人の人格が「間違い続き」を演じたのであり、それは、喜劇のときもあれば悲劇のときもあった。彼女たちは、観客を混乱させるようなかたちで舞台に上がり降りし、つぎつぎと入れ替わり、そしておのおのが、ほんの一瞬前には自分が見知らぬ存在だったような場面において他の二人の役を演じたのであり、サリーを除いておのおのは、そのまえに起きたことをなにも知らないのである。これらの歳月、筆者はビーチャムの生活について膨大な記録をとり、しかもしばしば毎日記録をとった。三つの人格すべてからえた証拠、またもちろん催眠下の自己からえた証拠を、苦心して記録した。何らかの申したてられた出来事あるいは精神的現象を解明し、実証し、あるいは疑わせる証拠は、ことごとく取り上げた。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
