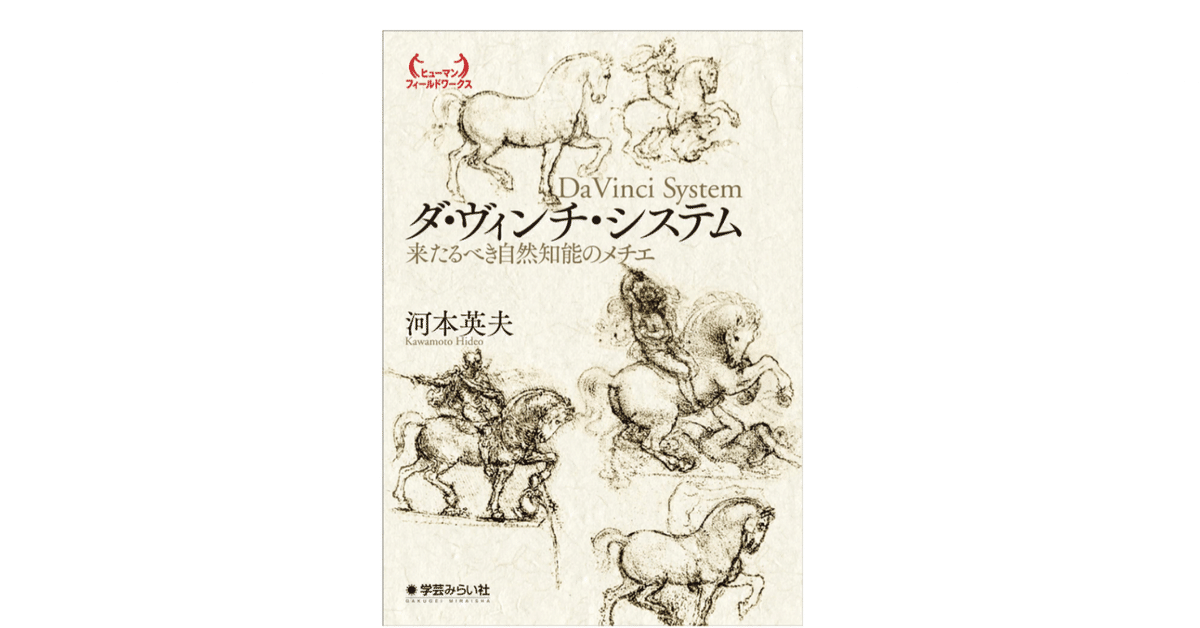
河本 英夫『ダ・ヴィンチ・システム/来たるべき自然知能のメチエ』
☆mediopos2712 2022.4.20
レオナルド・ダ・ヴィンチのデッサン(素描)
とくに水のように動きを表現しているものは
見飽きるということがない
ポール・ヴァレリーの
『レオナルド・ダ・ヴィンチ論』をきっかけに
ここ7年ほどのあいだ
じぶんでもなぜなのだろうと思いながらも
水にこわだりつづけている
ずっとphotoposで使っている写真は
水と光と風とが織りなす
不思議の動きに魅せられながら
ことあるごとに撮り続けているものだ
その水の姿は機械的に抽象化しては
決してとらえられることができない
そのことに驚かされ続けている
オートポイエーシス・システム論の河本英夫の
『ダ・ヴィンチ・システム/来たるべき自然知能のメチエ』は
ダ・ヴィンチの「自然知能の構想」に迫った
きわめて刺激的な著作である
ダ・ヴィンチは「私は自然から学ぶ」と言い
飛翔する鳥・洪水・回転式飛行機・人体解剖図など
さまざまなテーマのデッサンと観察記録を残しているが
もっともその関心を向けていたのが「動き」「運動」である
ダ・ヴィンチはそうした変化のなかに
その物の「個体性(そのものらしさ)」を探ろうとした
科学や哲学がもっとも苦手としているのが
おそらくはその「個体性」である
それは「統一性」や「体系性」に基づく
単純な規則性に還元できないからだ
河本英夫は「デュアル・リサーチ」によって
ダ・ヴィンチの視点に迫ろうとしている
「デュアル・リサーチ」とは
「究極のものを一元的な位置から解き明かすのではなく、
複合的な仕方で浮かび上がらせることであり、
これこそが事態の究極の姿だと考えていく」在り方である
一元的な視点というのは
ある意味で「神学」にほかならない
その意味では科学も哲学も「神学」のひとつである
そしてダ・ヴィンチ的な「デュアル・リサーチ」は
そうした「神学」を去ることのできるアプローチなのだ
それは「かたちと動き」というプロセスを
「変化」のなかでそのままとらえようとすること
それはまさに「個物の個体性を捉えることと同じ」であり
科学的な視点ではとらえそこなってしまうものなのだ
ポエジーのない言葉
個体性をとらえ得ない論理
そうしたものにたいして
常に感じざるをえない苛立ちも
まさにそこにあったのかもしれない
ノヴァーリスが構想していた「来るべき自然学」もまた
そうした「来たるべき自然知能のメチエ」を
必要としていたはずだ
■河本 英夫『ダ・ヴィンチ・システム/来たるべき自然知能のメチエ』
(ヒューマンフィールドワークス 学芸みらい社 2022/4)
(「はじめに」より)
「知識の多くは言葉をつうじて習得される。そしてさらに習得した言葉を捨てることによってしか到達することのできない体験的領域は、おそらく無数に存在する。手垢の付きすぎた既存の言葉を捨て、新たに言葉を紡ぎ直し、再度、言葉に体験の重さと命を回復させるのが、「詩人」である。
ダ・ヴィンチは、言葉とは異なる体験の仕組みを解明し、自分自身の最もすぐれた能力である「デッサン(素描)」を全面的に活用する方向に進んだ。それは単に「絵が途方もなく上手い」という範囲の出来事ではない。むしろダ・ヴィンチは、「デッサンの詩人」であろうとしたのである。それとともにデッサンと言語との新たな関係を作り出そうとしている。これが人間の言語を超えていくための最も有効な踏み出しの一つである。そうした確信と覚悟が、ダ・ヴィンチにはあった。こうした作業が、おそらく現在の主流の科学研究とは異なる、ダ・ヴィンチ的科学を出現させたのである。」
(「第Ⅲ章 ダ・ヴィンチ的科学/人類史の不連続点」〜「3 デュアル・サーチへ/「最後の神学」を捨て、世界の現実の姿に迫る」より)
「科学や学問にこれまで暗黙であるにしろ要求されてきた規範は、「統一性」や「体系性」であった。これらはあらゆる事柄や事象が、一貫した一つの糸や視野の中に配置されることだった。一つの原理のもとに万象を配置するという科学や学問の規範的な要求は、どこかに「神学」の名残を残している。それはダ・ヴィンチからすれば、人間の側の認識や知識の要求であって、自然界の本性ではない。
運動という現象は、誰にとってもやっかいな問題である。運動しているものを座標軸上の位置に変化で記述すれば、運動についての一面的切り取りにすぎなくなる。植物の成長も、微生物の動きも、動物のささやかな動きも、いずれもそれじたいで行っている運動であり、座標軸上の一変化では、ほとんどそれらの自己運動するものには届かない。
さらに言葉で、現にある自分の状態から自分自身で「自己差異化」すると語っても、そう言いたくなる気持ちはわかるのだが、自己差異化から多くの運動のモードを取り出すことはできない。植物は多くの場合、双葉を出し、そこから茎を伸ばしてさらに体を作り替えていき、昆虫は時に応じて幼虫から成虫へ変態を遂げる。
自己差異化には多くのモードがありすぎて、人間の言葉から追跡できるモードはごくわずかなものである。運動が何であるかを問い詰めて、究極の事態を取り出す試みは、運動に対して「筋の通った」やり方なのだろうか。それをやろうとすれば、究極の事態に迫るある種の「哲学」となり、言葉による届かなさにどこかで自己満足し、場合によっては自己陶酔することにもなる。
そんなときには、「運動」を一つの観点で捉えることは、そもそも筋が違うと考えていくことができる。哲学の試みは、筋違いの必死のあがきだったと考えることができる。特定の視点から捉えることで限界が生じるのであれば、その限界を解こうとしたり、限界の意義を語ったり、限界に直面している自分自身に自己陶酔すること以外にも、いくつもやり方がある。究極の事態や原理的な事態は、複数個の視点から二重化したり、場合によっては多重化したりして捉えることが基本となる。
たとえば運動するものを、一方ではデッサンで描き、数学的表記をその運動するものの「影」のように配置して、さらに不足している事態を人間の言葉で表現することができる。こうした複合的に二重化した考察こそが、究極のものの本来の姿だと考えていくことができる。
これを「デュアル・リサーチ」と呼ぶことにする。これは究極のものを一元的な位置から解き明かすのではなく、複合的な仕方で浮かび上がらせることであり、これこそが事態の究極の姿だと考えていくのである。こうして運動や現実性についての「最後の神学」を捨てることができる。」
「究極のものは、最低限いつも二重性を帯び、二重の仕方で成立する。
(…)
これは出発点に特定の原理を設定し、そこから世界の多様性に到達することが困難であることへの別の解答の仕方でもある。究極のものは一つであるというのは、人間が人間であることに付き纏う根本的な思い込みであった。もはやそれを捨てることができる。世界の究極の姿は、根源的な二重性であり、質の異なる原理が二重性のまま運動して作動することが、世界の最初の姿である。
そこからも少なくない帰結を導くことができる。
たとえば解けない問題に直面したとき、解けない箇所を突破するような試みは、すでに筋が違うと考えていくことができる。世界が最基層で二重化しているのであれば、解けない箇所を突破する以外に、さまざまなやり方があるに違いない。壁に当たればそこを突破するのではなく、二重化したもう一方の要素に変化をあたえ、局面を変えていくことができる。場合によっては、二重化している要素の隙間に開きをあたえたり、密接に連動させたりすることもできる。ダ・ヴィンチ的科学は、こうしたデュアル・リサーチの典型例を示していたのである。
ダ・ヴィンチの描こうとしたデッサンは、「動きのデッサン」であり、精確には「動きの継続のデッサン」である。
このデッサンには、二つの基本的な要素が含まれる。動きの継続にかかわる要素と、そのつどの変化にかかわる要素である。加速しようとする身体体勢と減速しようとする身体体勢は、まるで別ものであるが、いずれも動きの継続は含まれている。動きの継続の中で、ただ回転数を上げたり、回転数を下げたりしているのではない。こうした仕組みで成立しているのは、自動車である。馬の加速の場合、歩幅を大きくし、回転数を上げる場面もあるが、加速そのものが開始されるまさにそのときの身体体勢の変化が問われる。一定の加速状態になれば、それを繰り返せばよい。
近代科学的に言えば、ここには変化という変数と、変化率という変数が含まれていることになる。この二つを同時に指定しないと、ダ・ヴィンチのデッサンの図柄は出てこない。
だがこの二つの変数の値を指定しても、なお動作の現実の姿は決まらない。というのも同じ値をもつ動作の姿は、実はたくさんあるからである。たとえば足の短い馬と、サラブレッドの馬の動作の姿が同じであることはそもそも無理である。(…)ここに美的な要素がからみ、物理的身体の固有性が絡んでくる。」
「ダ・ヴィンチは、水の動き、たとえば渦巻きのような動きのモードに繰り返し記述を向けている。そこでは渦巻を描き、その力学的な仕組みを考え、それによって明らかになったことを導入しながら、再度、水の動きを描き、それからさらに水の動きの仕組みを考えようとしている。視点を二重化したために、考察が循環的に形成されていくのである。」
「最難関は、近代科学のいたるところで発見され、解明されてきた規則性である。こうした規則性と別のタイプの規則性の解明や設定が見出されれば、ダ・ヴィンチ的科学は成立すると思われる。(…)
ところがダ・ヴィンチのやり方だと、プロセスを捉えるために、その一つの局面がプロセスの在り方を総体として、内的に感じ取ることができるように切り取られなければならない。個々の局面は変化し続ける。この変化とともにプロセスの総体は分岐したり、別様に進み始めるように連動していなければならばい。これは個物の個体性を捉えることと同じである。そして個別がそれとしてあるという「個体性」は、科学的な仕組みではどのようにしても届かなかったことである。」
「謎は均衡点を少しずらしてみれば、別様に見えてくる。均衡点をずらした微笑みは、たとえそれが技巧に満ちたものであっても、二番煎じ以下にしかならない。そうした均衡点が、おそらく「モナ・リザ」において出現したのである。言葉を替えれば、別様に分岐していく可能性に満ちたまま、分岐することの予感をそのまま描いたのである。
こうしてダ・ヴィンチ的科学の可能性の広がりがどのようなものであるのかが、うっらとわかってくる。世界の二重化が起きる場所を見定め、二重化の可能性をそのまま感じさせることのできる二重の現実、すなわち「かたちと動き」を現実化させたのである。」
《目次》より
■第I章 見果てぬ構想──ダ・ヴィンチ・システム
1 同時代的な問いのウイング
2 思考・作業・経験──ダ・ヴィンチ・システム 1
3 ダ・ヴィンチの「注意能力」は何に向かっていたか──ダ・ヴィンチ・システム 2
4 エクササイズとしての経験──探求の方法論的な原理
■第II章 生成するダ・ヴィンチ──主要草稿(1475~1519年)から
1 『トリヴルツィオ手稿』(1487~1491年、35~39歳)
2 『パリ手稿B』[アッシュバーナム手稿Iを含む](1487~1491年、35~39歳)
3 『パリ手稿A』[アッシュバーナム手稿IIを含む](1492年、40歳)
4 『マドリッド手稿I』(1493~1500年、41~48歳)
5 『鳥の飛翔に関する手稿』(1506年、54歳)
6 『パリ手稿F』(1508年、56歳)
7 『ウィンザー手稿』(1475~1518年)
8 『水の研究』[素描集、第一篇、風景・植物・水の習作](1509~1513年、57~61歳)
9 『解剖手稿A』(1510年、58歳)
10 『絵画の書』(メルツィ編)
■第III章 ダ・ヴィンチ的科学──人類史の不連続点
1 ダ・ヴィンチ的科学の特質
2 近代科学の前線
3 デュアル・リサーチへ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
