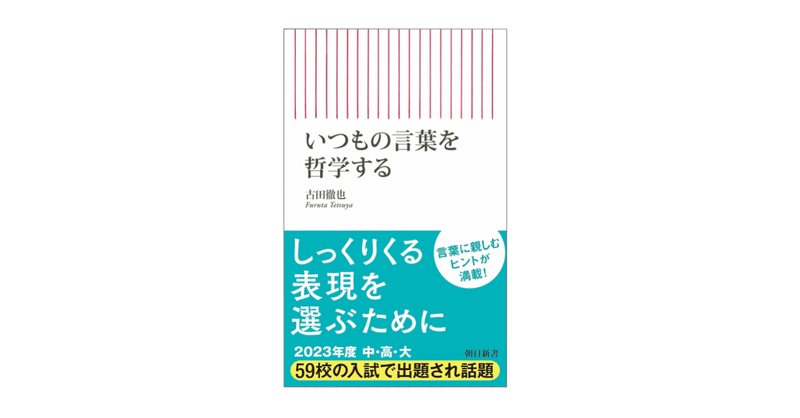
古田徹也『いつもの言葉を哲学する』
☆mediopos3437 2024.4.15
たかが言葉
されど言葉である
とくに私たちが
日常的に使っている「いつもの言葉」の
「ありようや、その重要性、面白さ、そして危うさ」
といったことを意識しておくことは
言葉の表現というだけではなく
私たちの「生」そのもののありようを
見直すことにもつながっていく
本書にはさまざまな事例が挙げられ
大切な視点を与えてくれるものばかりだが
そのなかからいくつかをピックアップしながら
「されど言葉」を再確認しておきたい
まず「先生」
これについて言挙げされることはよくあるのだが
確認の意味で
「先生」という言葉は
じぶんのことを「先生」と呼ぶにせよ
ひとから「先生」と呼ばれるにせよ
「先生」が成立している場以外においては
ほんらいどちらもエラーになるはずだが
「どこでも先生」的になることが多いようである
学校の先生にせよ
公に偉いとされる人にせよ
「どこでも先生」が求められていたりする
「○○さん」と呼ぶと失礼になるのだ
「社会に出る」という言葉も
よくわからずに使われている言葉である
学校を出て働くようになることや
「ひとり立ちする」ことが
「社会に出る」ということではない
子どもでもすでに社会にでているといえる
もしあえて「「社会人」という、
ある者を別の者と区別する言葉を使うのであれば、
社会の偏った厳しさを和らげようと努め、
相互依存の網の目からこぼれ落ちる人々に手を伸ばす者を、
「社会人」と私は呼びたい」
そう著者はいう
その意味ではぼくなどは
学生の頃からいわば「ひとり立ち」せざるをえず
その後の四〇年以上働き続けてきたけれど
いまだじぶんを「社会人」などとは言えない
そして「炎上」
なぜ「炎上」するのか
それは「人々がともに問題を整理し、吟味し、
理解を深め合っている」
そんな「本来の意味で「批判」が行われている、
建設的な議論の場が存在」していないがゆえに起こる
繰り返しになるが
ここでいう「批判」とは「同調と攻撃」ではない
「内容の吟味」「物事に対する批評や判断」
「良し悪しや可否をめぐる議論と評価」のことである
個人的にはあまり「社会的」なことはふれたくはないが
さすがにとりわけコロナ禍現象以降の
言論に関する過度の劣化には目を覆うばかりなので
それに関することを以下にいつくか
特に政治やマスメディアの世界において
「「なぜそれをしたのか」という質問に答える責任」が
あまりにも果たされていない
「応答を拒否したりはぐらかしたりし続ける」だけでなく
それを逆撫でするような政策や報道が
なされるようになっているのが現状である
「○○感」という言葉も常套句と化していて
「明言を避けてぼやか」し
「言質を与えず責任を回避する」ために使われる
また説明し難いあるいはしたくないときには
カタカナ語などの「新語」が使われたりもする
そして「他人だけではなく自分自身も
その言葉によって振り回され、煙に巻かれてしま」う
新型コロナウイルス感染症や
コロナワクチンの問題については
ひとつひとつ挙げていけば切りがないほどの惨状だ
「新しい生活様式」という言葉もそのひとつ
この言葉は「内容と言葉が食い違っている」にもかかわらず
むしろ意図的に社会を隅々にまで管理することになった
「自粛を解禁」「要請に従う」
といった歪曲された言葉も同様である
ここでいう「自粛」とはいうまでもなく「禁止」であり
「要請」というのは「命令」である
それを外的に強制するというのではなく
じぶんからその責任において行うようにという
いってみれば恐ろしいまでの言葉の刷り込みである
ある意味で外的に起こっている戦争以上に
実質的な意味での戦争状態と
人口減を起こしているコロナワクチン騒動は
これまでそうしたことを意識しないでいた人たちにも
「されど言葉」ということを意識化するための機会を
切実なまでに与えてくれているともいえるが
この4月13日に池袋で行われた数万人規模の
外国のメディアさえも大きく報道しているような
抗議デモの模様でさえ
自国の大手マスメディアはまったく報道しないでいる
言葉の歪曲・破壊以前の「言論封鎖」の世界が
いままさにわたしたちのまわりで大規模展開されている
そうした閉塞状態を打開していくためにも
「いつもの言葉」を「たかが」ではなく
「されど」として見直していく必要がある
そしてそれがどこまで意識化されるかが
「戦後」の私たちの生を大きく規定していくことになる
■古田徹也『いつもの言葉を哲学する』(朝日新聞出版 2021/12)
**(「序章」より)
*「本書は、私たちの生活のなかで息づく言葉のありようや、その重要性、面白さ、そして危うさというものを、多様な観点から辿っていくものだ。」
*「本書に登場する言葉には、現実をぼやかす言葉、責任を回避する言葉、人を傷つけ排除する言葉、対話を拒絶する言葉などもあれば、これまで注意を向けられなかったものを見事に捉える言葉、文化の奥行きを反映する趣きある言葉、人生と生活の瞬間を切り取る愉しい言葉や美しい言葉などもある。
本書は、そうした多様な言葉を鉄ガクする。「哲学」とはこの場合、「批判(クリティーク)」の営みのことであり、そして「批判」とは本来(・・・)「非難」や「攻撃」のことではなく、対象をよく吟味し、その問題や可能性を明確にする営みのことを指す。
かつて哲学者のウィトゲンシュタインは、「すべての哲学は「言語批判」である」と語った。本書もまた「言語批判」を行うものだが、扱うのはいつもの言葉たちだ。すなわち、私たちの生活の中に織り込まれてきた言葉、そして、私たちがいまよく見かける言葉、いま繰り返し用いている言葉を哲学する。
多様な言葉のもつ多様な側面を見渡し、「批判」しつつ、全体として本書が探求するのは、言葉を大切にするとは実際のところ何をすることなのか、という問いである。その過程で、〈言葉は生活ととともにあり、生活の流れの中ではじめて意味をもつ〉という事実を、私たちは何度も確認できるだろう。そしてまた、〈しっくりくる言葉を慎重に探し、言葉の訪れを待つ〉という仕方で自分自身の表現を選び取り、他者と対話を重ねていく実践が、いまの私たちにこそ与える重要性も、次第に浮かび上がってくるだろう。」
**(「第一章 言葉とともにある生活」〜「8 「お父さん」「先生」―役割を自称する意味と危うさ」より)
*「この頃、娘と会話したときに、自分自身のことを自然に「お父さん」と呼んでいることに気付いた。これは自分には驚きだった。」
*「人は、固有名詞や人称代名詞の担い手であるだけではなく、何らかの社会的役割を代表する普通名詞の担い手でもある。「先輩」、「後輩」、「生徒」、「学生」、「社員」、「運転手」、「スタッフ」、等々。ただし、自分自身に対する呼称として用いられるものは少ない。(・・・)
その例外として、「お父さん」、「お母さん」、「おじいちゃん」、「おばあちゃん」などのほかのすぐ思いつくのは、「先生」だ。大学の教員の場合は「先生」と自称することはまずないが、幼稚園や小中高の教喩が自分のことを「先生」と呼ぶのは特に不自然ではない。」
*「学校における「先生」という呼称をめぐっては、『オトナ語の謎。』の冒頭に、糸井重里さんが高校時代に体験した興味深いエピソードが紹介されている。
ある日、定年退職を翌年に控えた先生と生意気な生徒が言い争っていた。とはいえ、先生の方は余裕な様子で、口元に軽い笑みさえ浮かべていた。しかし、生徒がある一言を発したことで、先生は突如として烈火のごとく怒り出し、「なんだ! 貴様は!」と怒鳴りつけたという。なにも生徒は、「バカ」だの「アホ」だのといった悪罵を投げつけたわけではない。ただ、生成に向かった「あなたは」と言ったのだ。
おそらくその先生は、「お前」とか「てめえ」などと言われても怒らなかっただろう。「あなた」という、むしろ丁寧とも蹴る二人称で呼ばれたことによって、理性では抑えられないほどに感情を逆撫でされたわけである。つまり、そこでの「あなた」という呼称は、自分がその生徒にとっての保護者や恩師ではなく、議論の対等な相手として位置づけられたことを示すものであり、それが何よりも無礼に感じたのだろう。その先生は、まさに「先生」というアイデンティティを————生徒を一方敵に指導する立場に身を置く視覚ないし権力を————脅かされたのである。」
**(「第一章 言葉とともにある生活」〜「9 「社会に出る」とは何をすることか」より)
*「「社会に出る」とは何をすることを意味するのだろう。「社会人」とは誰のことを指すのだろうか。」
*「「社会」とは、決して一枚岩ではない、多様な人々が直接的・間接的にかかわり合いながら生きる場だ。その意味では、子どももすでに社会に出ている。そして、彼らにとって社会は決して楽なものではないし、大して守られているわけでもない。日々膨大な務めを果たし、大人と同様のシビアな人間関係————しかも、大人よりも遙かに露骨な人間関係————と、直接的な暴力の危険に曝されている。」
*「では、「ひとり立ちする」ことが、「社会に出る」ことなのだろうか。いや、文字通りの意味で自立している大人など誰もいない。その仕事や生活が、どれほど多様な人々に依存していることか。」
*「誰でも、否が応でも、すでに社会に出ている。にもかかわらず、敢えて「社会に出る」と言うのであれば、それは社会の多様な場所、多様な側面にかかわるようになることを指す————そう私は理解したい。ひとつの場所の方法や慣習にただ順応するのではなく、むしろそれを相対的に見て、別の可能性を想像できる場に立つことを意味する、と考えたい。
繰り返すように、社会は一枚岩ではない。「社会は厳しい」のではなく、社会は特定の人々に厳しい。敢えて「社会人」という、ある者を別の者と区別する言葉を使うのであれば、社会の偏った厳しさを和らげようと努め、相互依存の網の目からこぼれ落ちる人々に手を伸ばす者を、「社会人」と私は呼びたい。」
**(「第二章 規格化とお約束に抗して」〜「5 「批判」なき社会で起こる「炎上」」より)
*「同調と攻撃の間の中間領域が確保されにくく、「批判」という言葉が本来含んでいた「内容の吟味」、「物事に対する批評や判断」、「良し悪しや可否をめぐる議論と評価」といったものがおそろかになりがちな現状は、「炎上」という言葉の現在の用法にも通じている。」
*「「炎上している」とか「賛否の声が上がっている」といった言葉によって物事をひとまとめにしてしまうのではなく、具体的な内容を「批判」する行為が、メディアでもそれ以外の場でも、もっと後半になされる必要がある。そして繰り返すならば、それは必ずしも否定的な行為だとは限らない。賛意を示すのであれ、あるいは難点を指摘するのであれ、人々がともに問題を整理し、吟味し、理解を深め合っている場こそ、本来の意味で「批判」が行われている、建設的な議論の場なのである。」
**(「第二章 規格化とお約束に抗して」〜「6 「なぜそれをしたのか」という質問に答える責任」より)
*「少なくとも自由で民主的な社会において、人が為政者として責任をもって行うべき意図的行為(政治的決定など)に関しては、応答可能性だけではなく、実際に応答する義務が必ず伴われる。すなわち、「なぜそれをしたのか」————あるいは、「なぜそれをするのか」————と聞かれたら、それに対してまともなかたちで答えられるのでなければ、その行為に関して自分が負うべき責任のないようも、責任の有無自体も明らかにできず、それゆえその行為は社会において正当化されない。もっとも、応答には「理由は説明できない」というものも含まれうるが、その場合、理由を説明できないことの理由をまともに説明できなけば、やはり当該の行為は正当性を失う。」
*「たとえば、為政者に「なぜ?」と直接問うことができる政治家やジャーナリストなどは、為政者から理由の説明が返ってこない場合、そのことを批判しなければならない。また、応答がまともな理由の説明になっていない場合にも、やはりそのつど批判しなければならない。応答を拒否したりはぐらかしたりし続ける為政者に対して、執拗に理由の説明を求めて、何度でも聞き返し続ける者が現れれば、私たちはその者を支えなければならない。たとえ私たちが「その者」自身にはなれないとしても、そうしたやりとりに飽きてはいけない。為政者から説明が与えられないことに慣れてはいけない。それは、私たちが自由で民主的な社会を望むかぎり果たすべき最低限の責任である。」
**(「第三章 新しい言葉の奔流のなかで」〜「1 「○○感」という言葉がぼやかすもの」より)
*「「○○感」という言葉が、いつから猛威を振るうようになったのだろう。」
*「「スピード感をもって進めていく」という言い回しも、最近は各所でよく聞かれるものであり、もはうや常套句と化している。しかし、これもなぜ「感」なのだろうか。なぜシンプルに「素早く」「迅速に」と云わないのだろうか。」
*「このように、どこか明言を避けてぼやかす姿勢、言質を与えず責任を回避する姿勢こそが、「○○感」という言葉がいま氾濫を起こしている大きな要因だろう。」
**(「「第三章 新しい言葉の奔流のなかで」〜「8 「チェアリング」と「イス吞み」―ものの新しい呼び名が立ち現せるもの」より)
*「新語の導入が常に物事の特定の見え方を明確にしたり、新しい見方を開いてくれたりするわけではない。それこそ、ある種のカタカナ語や業界用語のように、視界をぼやかし、物事の輪郭を見えにくくさせるものもある。
新しい言葉を無闇に振り回しているときには、他人だけではなく自分自身もその言葉によって振り回され、煙に巻かれてしまっているケースが大半だ。新しい言葉の奔流のなかで溺れないためには、その言葉によって物事の何か重要な輪郭が本当に見えてくるのか、世界をより豊かに色づけるものであるかを、そのつどよく見極めていくことが欠かせない。」
**(「第四章 変わる意味、崩れる言葉」〜「3 「新しい生活様式」―専門家の言葉が孕む問題」より)
*「二〇二〇年五月四日の新型コロナウイルス感染症対策専門家の提言以降、そこで発信された「新しい生活様式」という言葉が、社会のありとあらゆる場所に広まった。
(・・・)
当時もいまも、私はこの言葉の用い方にはきわめて批判的だ。
(・・・)
「新しい生活様式」という言葉は、「今後のあるべき望ましい生活のかたち」という意味合いで受け取るのが自然だ。しかし実際のところ、件の専門家会議が「新しい生活様式」の名で提示したのは。長くとも数年後には終息することを想定した(あるいは、それを目指した)中長期的な感染対策に過ぎない。つまり、内容と言葉が食い違っているのだ。」
*「この食いちがいは、おそらく意図されたものだろう。
(・・・)
もしそうであれば、この意図は成功を収めた。「新しい生活様式」という言葉は確かに社会の隅々に行き渡った。そして、なぜそのように成功し、この言葉が目立ったかといえば、ひとつには、言うまでもなくメディアで繰り返し使われたということもあるが、もうひとつには、この言葉が人々にショックを与えたとうことがあるだろう。それは、大抵の人々が恒久的な生活様式になるとは想定していなかったものが「新しい生活様式」と呼ばれた、というショックである。」
*「こうした社会のあり方が常態化すれば。それは私たちの間に深い分断と禍根と傷を残す。仮に感染症拡大防止に多少の効果があったとしても、そのような状況は恥ずべきであり、避けるべくものだ。」
**(「第四章 変わる意味、崩れる言葉」〜「4 「自粛を解禁」「要請に従う」―言葉の歪曲が損なうもの」より)
*「新型コロナ禍の前後で大きく意味合いを変えた言葉には、この「三密」や、あるいは「濃厚接触」などのほかに、「緊急」や「緊急事態」という言葉も含まれるだろう。
(・・・)
新型コロナ禍という世界規模の災厄の渦中で私たちは、既存の言葉をこれまでとは異なる意味で理解して使用することを急に迫られている。しかし、これは危険な傾向だ。大抵の言葉は、長い歴史や多様な生活の文脈を背景に成り立っており、関連するさまざまな言葉と連関しながら、私たちの生活自体を根底で支えている。にもかかわらず、あたかも自分たちの意のままにできる道具のように言葉を扱い、その意味を好き勝手にころころ変えてしまえば、私たちは自分の拠って立つ基盤を自ら損なうことになる。」
*「たとえば、一回目の緊急事態宣言が解除される頃から、多くのマスメディアで「自粛を解禁」という見出しや文言が踊るようになった。これは二重の意味で奇妙な言葉だ。
まず、「解禁」とは文字通り〈禁止が解かれること〉を指す言葉だ。(・・・)それゆえ、「自粛を解禁」だと、自粛の禁止が解かれること————つまり、自粛が許されること————を意味することになってしまう。
そして、さらに奇妙なのは、自粛とは、これも文字通り〈自ら進んで行動を粛むこと〉を意味するということだ。つまり、自粛している事柄は、そもそも禁止が解かれる対象ではないのである。
(・・・)
いま政治や行政の場では「自粛」という言葉が「禁止」の意味にねじ曲げられ、「要請」という言葉が「命令」の意味にねじ曲げられている、ということだ。自粛しているはずの事柄に対する「解禁」という誤用は、こうした歪曲がもたらしたひとつの結果として捉えうる。」
*「言葉の意味や用法というのは、私たちの社会や生活にとって些末なものでは全くない。むしろ、その生命線であり、急所でもある。新型コロナ禍における言葉の歪曲はこのことをはっきりと私たちに示すものだが、それ以前から、言葉の意味の恣意的な「変更」は、政治をはじめとする公共的な空間で常態化していた。」
*「言葉がねじ曲がり、壊れることは、そのまま、言語的なコミュニケーションが不全になることを意味する。言葉を雑に扱わず、その意味や用法に心を配り、自分の言葉に責任をもとうと務めることは、言葉とともにある私たちの社会や生活を支える基礎でもあるのだ。」
【目次】
第一章 言葉とともにある生活
1 「丸い」、「四角い」。では「三角い」は?
2 きれいごとを突き放す若者言葉「ガチャ
3 「お手洗い」「成金」「土足」―生ける文化遺産としての言葉
4 深淵を望む言葉―哲学が始まることの必然と不思議
5 オノマトペは幼稚な表現か
6 「はやす」「料る」「ばさける」―見慣れぬ言葉が開く新しい見方
7 「かわいい」に隠れた苦味
8 「お父さん」「先生」―役割を自称する意味と危うさ
9 「社会に出る」とは何をすることか
10 「またひとつおねえさんになった」―大人への日々の一風景
11 「豆腐」という漢字がしっくりくるとき―言葉をめぐる個人の生活の歴史
第二章 規格化とお約束に抗して
1 「だから」ではなく「それゆえ」が適切?―「作法」に頼ることの弊害
2 「まん延」という表記がなぜ蔓延するのか―常用漢字表をめぐる問題
3 「駆ける」と「走る」はどちらかでよい?―日本語の「やさしさ」と「豊かさ」の緊張関係
4 対話は流暢でなければならないか
5 「批判」なき社会で起こる「炎上」
6 「なぜそれをしたのか」という質問に答える責任
7 「すみません」ではすまない―認識の表明と約束としての謝罪
第三章 新しい言葉の奔流のなかで
1 「○○感」という言葉がぼやかすもの
2 「抜け感」「温度感」「規模感」―「○○感」の独特の面白さと危うさ
3 「メリット」にあって「利点」にないもの―生活に浸透するカタカナ語
4 カタカナ語は(どこまで)避けるべきか
5 「ロックダウン」「クラスター」―新語の導入がもたらす副作用
6 「コロナのせいで」「コロナが憎い」―呼び名が生む理不尽
7 「水俣病」「インド株」―病気や病原体の名となり傷つく土地と人
8 「チェアリング」と「イス吞み」―ものの新しい呼び名が立ち現せるもの
第四章 変わる意味、崩れる言葉
1 「母」にまつわる言葉の用法―性差や性認識にかかわる言葉をめぐって1
2 「ご主人」「女々しい」「彼ら」―性差や性認識にかかわる言葉をめぐって2
3 「新しい生活様式」―専門家の言葉が孕む問題
4 「自粛を解禁」「要請に従う」―言葉の歪曲が損なうもの
5 「発言を撤回する」ことはできるか
6 型崩れした見出しが示唆する現代的課題
7 ニュースの見出しから言葉を実習する
8 「なでる」と「さする」はどう違う?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
