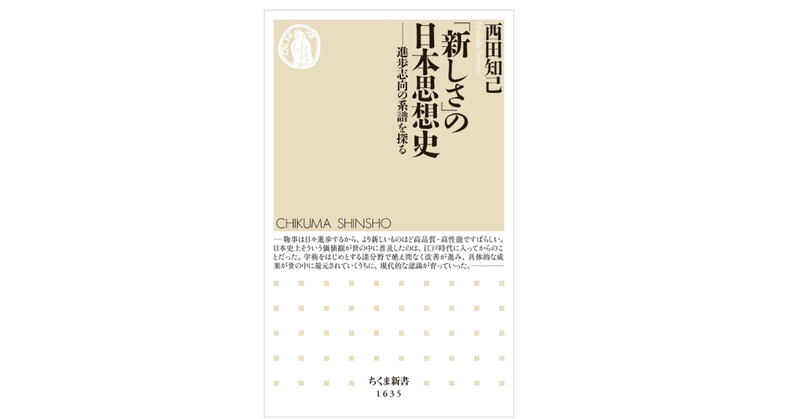
西田 知己 『「新しさ」の日本思想史/進歩志向の系譜を探る』
☆mediopos2650 2022.2.17
言葉は変わる
現在使っている言葉の多くには
それなりの歴史的な奥行きがあり
言葉を変化の相のもとに置き
それが成立してきた背景を知ることで
言葉を生きた働きとして理解することができる
本書では日本思想における
「新」「新しさ」という言葉について
たくさんの事例も含め
その歴史が豊かに興味深くたどられている
現在「新しい」という言葉は
「進歩的だ」「新鮮である」という意味で
使われることが多いが
古代や中世では
過去をあらわす「古」や「旧」などと組み合わされ
単に「現在」を示すものであり
当時現在のように目新しさを意味していたのは
「珍(めづら)し」や「鮮(あざらけ)し」だった
また古語では「新し」は「アラタシ」
つまりアラタ(新)はアラタ(改)ムと同一とみなされていた
古代や中世社会では
古いほど理想的ですばらしいという観念があり
「本」の字がつく言葉が主要なもののひとつだった
「本」は物事の始点や起源をあらわし
最初に成立したものこそ
根源的で重要だとみなされていたので
「改める」という「新たむ」は
あくまでも「本」があってこその「新」だったのだ
しかも「改む」ことを好ましく思わない政権にとっては
法政に関して使われていた中世語の「新儀」は
反社会的な行為の象徴的な表現でさえあった
「新しい」が現在のような意味になってきたのは
近世とくに江戸時代になってからである
かつては否定的にも使われてきた「新しい」が
次第に肯定的に用いられるようになり
幕末維新期には大衆をリードする
キャッチフレーズにさえなり
明治以降の西欧文化・文明を
受容する下地ともなり現在に至っている
こうして「新」という言葉の歴史を踏まえることで
その「新」という言葉が現在もっている
可能性とあわせてその陥穽もとらえることができる
現代の「新」は
ほんらい前提とすべき「本」を失っているのではないか
もちろんそのときの「本」は
単に過去を求めるがゆえのものではなく
本来の根源的なものへの探求を怠らない
という意味での「本」を意味するのだが
■西田 知己
『「新しさ」の日本思想史/進歩志向の系譜を探る』
(ちくま新書 筑摩書房 2022/2)
「「言葉は生き物だ」といわれる。世の中の移り変わりや、流行り廃りに連動して新語が誕生したり、従来からある言葉が不意に脚光を浴びたりする。(・・・)
「新」の語は、流行に振り回されやすい素地があったわけではなかった。現に古代や中世社会では、取り立てて語義変化を起こさなかった。それが江戸時代から明治時代にかけて、意味するところが百年単位でじわじわと推移し、従来よりも好意的に受け止められるようになった。結果的には思いのほか大きな変貌を遂げた末に、現代語の「新」が醸成されている。その過程で産み落とされる「新」関連語彙の量は、二十一世紀の今も衰える気配がなく、巨大な流行り言葉のようでもある。」
「古語の「新」は通例、過去をあらわす「古」や「旧」などと組み合わされて、現在を意味した。対する現代語の「新」は今だけでなく、今後にも意識が及んでいる。今後出る新製品や新情報に期待を寄せるのは、この先の改善や進歩を見越しているからなのだろう。逆に今後の劣化、いわば未来の「古」が思い描かれると、今の新鮮味を実感できる。古代から中世にかけての「新」は、まだその域に達していなかった。「新(あたら)し」のかわりに目新しさや瑞々しさを伝えてきたのは、「珍(めづら)し」や「鮮(あざらけ)し」などの語だった。
よって「新」の字を含む中世語の場合も、今と同じ言葉でも意味まで同じではなかった。(・・・)
戦国期をへて平穏な江戸時代が訪れると、学術や文芸が小刻みに更新されながら発達し、「新」の変化をうながす原動力になった。そろばん書の『塵劫記』は、たびたび「新編」を出しながら階梯を重ねていった。俳人の松尾芭蕉は、つぎつぎに新作を発表しながら俳句の「新しみ」を説き続けた。『解体新書』という名の「新書」は、西洋医学の評価を大いに高めた。こうして社会全体で、継続的に「新」なるものが生み出されていった。従来型の「古」と「新」の構図が崩れ、「新」に次ぐ「新」の展開が可能になった。そこから今後の向上や飛躍が思い描かれ、その予感が「新」の字に見出されるようになったと考えられる。
一方では「新」に次ぐ「新」を懸念する声も高まってきた。声を発したのは、荻生徂徠の門流や本居宣長などの、伝統思想を重んじる学者たちだった。目先の「新」がもたらす利益にとらわれず、「根本」の精神や「本(もと)」の社会に立ち返るよう主張している。彼らこそ、「新」に牽引された世の中の進歩を肌で感じていた人たちだった。「本(ホン・もと)」は「古」や「旧」と並ぶ「新」の対義語で、今でも「新館」に対して「本館」という。この「本」関連の語彙も江戸時代に語義が変化し、「新」の推移とリンクしている部分がある。
江戸時代に評価を高めた「新」は、幕末維新期に大衆をリードするキャッチフレーズ的な役割を果たした。明治「維新」の幕が開け、政府は「御一新」の旗印のもとで政権の運営に乗り出した。民間では何々「新聞」や何々「新報」などの創刊ラッシュが起こり、国際社会を取り巻く先取り情報の提供をめぐって競い合った。明治時代の政治や社会を伝える用語に「新」が多いのは、決して偶然ではない。徐々に進歩していく今後に対する人々の期待や願いを、この字に託せるようになった結果でもあった。
それに比べると、古代や中世の歴史的な変革などでは、変えようとする側の本人が「新」を名乗るケースは少なかった。まだ「新」の価値が後世ほど高くなく、そもそも言葉として用途が広くなかった。明治以降の学者たちが「新」によって過去を位置付けた事例ならいくつもあり、「大化の改新」「鎌倉新仏教」「建武の新政」あたりがよく知られている。これらはみな、明治時代の価値観が過去の歴史的な事象に投影された具体例だった。
世界史的に見れば、進歩思想は十八世紀のヨーロッパ社会で発達した。日本では幕末維新期の翻訳文化を介して、欧米社会に見習うべき「進歩」が各方面で主張された。とはいえ、かけ声だけで文明開化が実現されるはずもない。高度な外来の文化を受け入れるための、下地となる学術や思想といったものが、あらかじめ国内で育っていなければならない。「新」や「本」の字義の変化をだどる試みは、その点に迫る一助よなるように思われる。」
「古代や中世社会にあっては、古いほど理想的ですばらしいという受け止め方が広く通用していた。むろんその度合いは分野しだいであり、同じ分野でも個々人の思想的な立ち位置などにも左右された。カギとなる言葉にも多様性があり、「本」の字がつく言葉はもっとも主要なひとつだった。
(・・・)
「本」は、物事の始点や起源をあらわした。その原義をふまえながら、テーマによっては、最初に成立したものこそ根源的で重要度が高いとみなされていた。特定の「本」などのものに、大いなる付加価値が与えられていたのである。たとえば仏教語には「本願」「本尊」「本仏」などがあり、本来あるべき「本」が理想に掲げられていた。
仏教では「正(しょう)」もまた最初の姿をあらわし、仏法は「正法」でもあった。
(・・・)
最初のことをあらわす「正」が、現代語にもいくらか残っている。たとえば一月のことを「正月」ともいう。由来については諸説があり、最初の月こそ一年のお手本とすべき月だったとする見方がある。
(・・・)
伝統的な「本」や「正」の解釈は、「善」にも押し広げることができる。つまり「善」「悪」の関係も、本来は先と後の関係にあった。典型例が『孟子』に代表される儒教の性善説で、逆に「悪」を先に持ってきたのが荀子の性悪説だった。
(・・・)
最初が理想的で、後世になるほど理想から逸脱していく。そういう価値観のもとでは、現状に対する評価が辛口になりやすい。ましてや、今後の進歩によってもろもろの事態が改善され、より良き未来が訪れるとする考え方も、容易には育ちにくい。今後の新製品や新情報に期待を寄せる、現代語的な「新」が成り立ちにくかったことも、想像に難くない。現に古代や中世社会には、古代語や中世語ならではの「新」が成り立っていた。」
「当時は「本」の存在があってこそ「新」も成り立った。もし先に「本」が廃れたら、おのずと「新」の存在価値も薄れた。」
「院政のもとで「新院」から「新」の字が外れるのは、先達の「本院」ないし「一院」が世を去ったときだった。そのとこいは、単に「院」の一字を名乗ることになる。」
「法政に関する中世語の「新」のうち、おそらくもっとも否定的に解釈されていたのが「新儀」だった。あらゆる反社会的な行為の、象徴的な表現でさえあった。「儀」は事柄や案件の意で、何々の「儀」といえば、何々の件に関して、といった程度の意で使われた。よって「新儀」と書いた場合には、「新」に良からぬ含みが持たされていた。
『御成敗式目』を生んだ武家法の世界では、「新儀」が違法行為の「非法」と結びついて「新儀非法」とも称した。」
「歴史の推移をたどっていくと、新たな画期となる「新」の側に目を奪われやすい。そういう内容が教科書にも年表にも載りやすい。それでも政権の安定や永続性を願う為政者にしてみれば、現状維持がベストだった。新興勢力に対しては、しばしば不信感が先立った。(・・・)その一点を取り上げても、現在ほど「新」を歓迎する時代ではなかった。」
「『新古今集』は当初「続古今」と命名される可能性があった。「新」で決定する前に、「続」が提案されていたのである。(・・・)
その「新」なるものが、時として批判的に受け取られていた点は、和歌の世界でも同様だ。平安から鎌倉にかけての動乱期を生きた定家は、若い頃に前衛的な作風の歌を詠み、当時の歌壇から「新儀」と酷評されていた。(・・・)
それでも定家は、一貫して「新」なる詠歌を目指した。
(・・・)
「あたらしき」ことの是非をめぐる議論が成り立ったのも、もとになる「本歌」つまり「本」なる存在があってこその話だった。そこには伝統的な「本」と「新」の構図が成り立ち、「本」から離れて「新」に次ぐ「新」といった今後の展望は意識されていない。というよりも、今後の展望は必要なかった。創作活動としての詠歌は、今を生きる歌人によって生み出されていく。その立ち位置を強調し、ある種の使命感を自負したのが定家による歌論の「新」だった。」
「古語辞典で「新し」を引くと、元来はアラタシと読まれていたことが補足されている。
(・・・)
古語のアラタ(新)については、語源的にアラタ(改)ムと同一とみなされている。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
