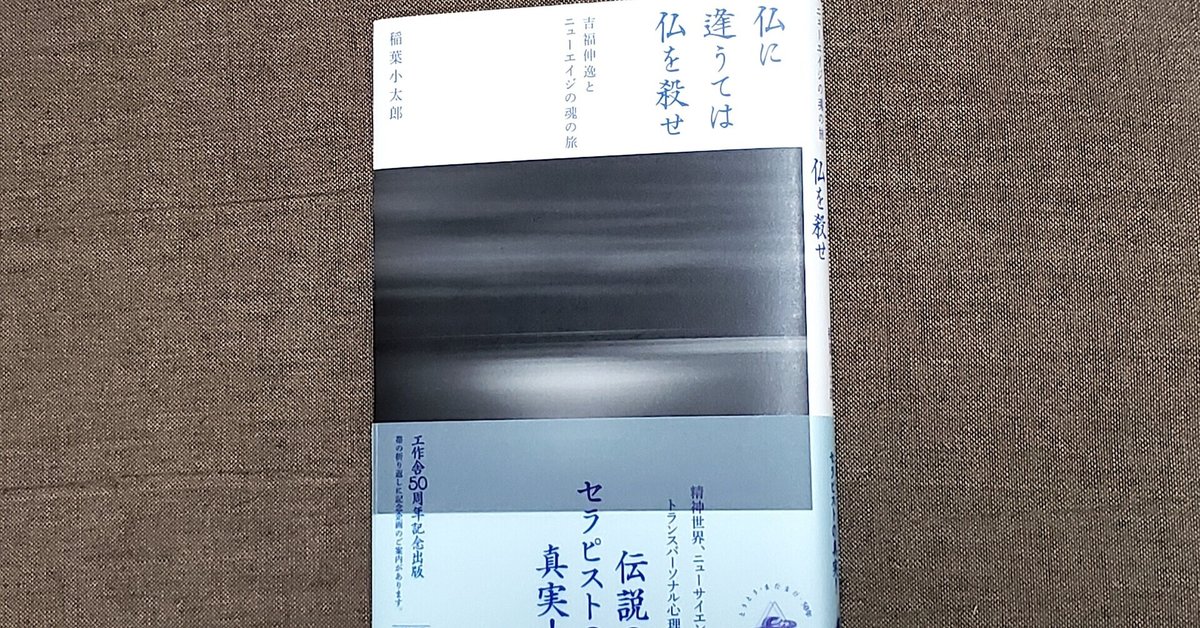
稲葉小太郎 『仏に逢うては仏を殺せ/吉福伸逸とニューエイジの魂の旅』
☆mediopos-2371 2021.5.14
吉福伸逸といえば
ぼくにはまずケン・ウィルバーをはじめとした
トランスパーソナル心理学の紹介者で
一九八〇年代の終わり頃から九〇年代のはじめ頃
その関係の訳書や対談をずいぶん読んだ記憶がある
その後いきなりハワイに移住して
サーフィンをしていたり
二〇一三年に亡くなったことは知っていたが
この本に目を通すまで
その生涯についてはほとんど知らずにいた
著者の稲葉小太郎は
ぼくよりも数年若いくらいだけれど
トランスパーソナルや精神世界
ニューエイジなどから受けた影響としては
ほぼ同世代に属するといっていいかもしれない
とはいえそれらに対するスタンスは
ずいぶん異なっているようだ
「カウンターカルチャー」の受け止め方といってもいい
稲葉小太郎はそれに対してずいぶん郷愁があるようだ
カウンターカルチャー(対抗文化)とは
サブカルチャー(下位文化)の一部で
メインカルチャー(主流文化)に反する文化だといえるが
ぼくにはメインカルチャーへの思い入れもなければ
それに対抗したカウンターカルチャーへの思い入れもない
サブカルチャーという位置づけにも特に関心はない
どちらもある意味で「信仰」的になってしまうからだ
カウンターカルチャーは
メインカルチャーのシャドー(影)のようなもので
メインの「信仰」に「夢やぶれた」者が
カウンターというところに新たな「信仰」を求めている
そんな位置づけもできるのかもしれないが
どちらにしても人はそこで「群れ」ようとするのだ
メインカルチャーでは
学校や文化機関などに関連した場で群れ
カウンターカルチャーでは
ワークショップやセラピーなどで群れ
ときに「グル」のようなものを求めて群れてしまう
メインカルチャーにせよカウンターカルチャーにせよ
人はそれに応じた「権威」(仏)を求めて彷徨っている
その意味でいえば
本書のタイトル
「仏に逢うては仏を殺せ」は
言い得て妙だといえる
本書を読んだ限りでは
吉福伸逸という人物はおそらく
じぶんのなかの「仏」と「仏を殺」すことのあいだで
ほんとうは激しく葛藤していたのではないだろうか
そして外的には「仏を殺」すことを意志しようとした
そしてそのことにその場その場で正直だった・・・
現代のスピリチュアルな世界やマインドフルネスへの傾斜は
姿を変えたカウンターカルチャーを
商品化したようなものかもしれない
それらの世界もまたさまざまな「群れ」のなかで現れる
そしてそれらは管理社会を背景にした消費社会の影として
成功という名の承認や「私を見て!」という類いの承認欲求を
さまざまなかたちで増殖させているように見える
そしてそこでの原則は
「仏に逢うては仏を殺せ」ではなく
自分を探して仏(という投影)に出逢おうとする
とでもいえるだろうか
ひとは自由であることに耐えられらず
さまざまな「群れ」のなかで承認されたいと願うからだ
■稲葉小太郎
『仏に逢うては仏を殺せ/吉福伸逸とニューエイジの魂の旅』
(工作舎 2021.4)
「本書は生前の吉福を知る人々を訪ね歩き、証言をつなぎ合わせて、この謎多き人物の足跡をたどる試みである。世間的にはまったく無名の男である。本にするほどの材料が出てくるのか、不安もあった。ところが吉福の歩みを追うことは、図らずも昭和史の失われた一側面に光を当てることになった。
七〇年代の終わりから九〇年代にかけて、「精神世界」ブームというものがあった。大型書店には「精神世界」コーナーが設置され、若者たちの実存的な探究心を刺激した。「自分探し」の源流がそこにあり、底流にはオウム真理教を生み出した精神風土が横たわっている。ところがいま、この時代のことは封印されたごとく語られず、知る者は減るばかりだ。
吉福の人生をたどることは、この「精神世界」ブームとはなんだったのか。、ふり返ってもう一度考えることでもある。
近年、仏教の瞑想に由来するマインドフルネスが注目され、書店には専門コーナーもできている。自己探求は人間にとって永遠のテーマだ。しかしこの道は果てしなく、曲がりくねっている。
宗教、心の成長、意識の変容、スピリチュアリティ、救い、癒しといったものと私たちはどう向き合っていけばいいのか。」
「私がこの人物に興味をもったきっかけは、一九八〇年代に数多く出版された「トランスパーソナル心理学」の翻訳や入門書だった。大学で印度哲学を専攻したものの、もっと実践的な部分を知りたいと思っていた私にとって、吉福が日本に紹介した新しい心理学の流れは魅力的なものだった。
自己とはなにか。心は成長するのか。<悟り>とは?
人生のなかで誰もがぶつかるであろう難問に、セラピーの手法をもちいてアプローチする姿勢は、研究室でテキストに向き合うよりエキサイティングで、禅寺で壁に向き合うよりスマートなものに見えた。大学を卒業した私は出版社に就職、取材の名目で吉福の弟子によるワークショップに参加するうち、吉福伸逸その人に対する興味がつのっていった。
そのころ、吉福はすでに伝説の人物だった。ボストンのバークリー音楽院でジャズを学び、帰国後は翻訳家としてニューエイジやトランスパーソナル心理学の文献を日本に紹介、セラピストとしてワークショップをリードした。だが、その実像は謎のベールに包まれていた。顔写真もなかったし、ある日忽然と表舞台から姿を消し、その後はハワイでサーフィンと畑仕事の日々というのもできすぎたストーリーに思えた。」
「「仏に逢うては仏を殺せ」
中国臨済宗の宗祖・臨済義玄の言葉である。仏とは仏道を学ぶ者にとっての理想、到達点であるはずだ。そんな相手をも「殺せ」とは物騒な話だが、要は、自分にとっていちばん大切なものにも執着するな、ということだ。
吉福伸逸は、この言葉のとおりに生きたと思う。肩書きを持たず、権威を離れ、せっかく産み落としたトランスパーソナルという赤子をたらいの水ごと流すようなことを平気でした。ものごとの本質にしか興味を示さず、今日打ち立てたセオリーを次の日には捨てた。」
「だがこの男が、ただ刹那を生きるだけのニヒリストだったとしたら、あれほど大勢の人が慕い、集まることはなかっただろう。多くの人は「吉福さんはやさしかった」、「愛があった」という。北山耕平は吉福が死んだとき、「宇宙がなくなったように感じた」とまでいう。そのやさしさはどこからきていたのか。
表向きは「セラピーは自分のため」、「ぼくはぼくのためにやっている」と、心のおもむくままに生きたように見える吉福だが、その心の奥には深い「悲しみ」があった。ジャズをあきらめ、すべてを失った「悲しみ」が、自己のルーツを見失い、生き方に迷った者たちと共振した。二〇〇一年アメリカ同時多発テロ、二〇一一年の東日本大震災のときも同じである。そう考えるとようやく、「悲しみの共同体」という言葉がしっくりと腑に落ちるのである。
ひとりの人間のなかで、愛と執着、やさしさと厳しさ、創造と破壊が同居していた。自ら迷い、答えを求めた「傷ついたヒーラー」。矛盾を抱えながら、矛盾のままに生きた。それを包み隠すことなく、人間というものトータルに丸ごと生きた。それが吉福伸逸だった。」
「本書の執筆中、久しぶりにトランスパーソナルやマインドフルネスの集まりに出てみたが、トランスパーソナルはもはやスピリチュアルと同義語のようだし、仏教からスタートしたはずのマインドフルネスも、読者にとっては「自己啓発」のひとつ。<悟り>を求めるより、仕事のストレスを軽減し、自分の能力を高め、もっと成功し、もっと「稼ぐ」ことに主眼が置かれているように見える。
「精神世界」もニューエイジも、しょせんドロップアウトした人々の夢だったのか。カウンターカルチャーは、結局カウンターのまま終わるのか。
そうなのかもしれない。
だが、そうだとしても、カウンターはカウンターとして存在することに意味があるのではないか。
「自己探求」が夢だったとしても、先の見えない時代のなかで絶望しそうになったとき、生きづらさに押しつぶされそうになったとき、吉福伸逸の生き方が助けになるのではないか。
自分はなぜここにいるのか?
ほんとうの願いはなんなのか?
答えのない問いを深めるヒントが、この稀有な男の人生のなかに散りばめられている。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
